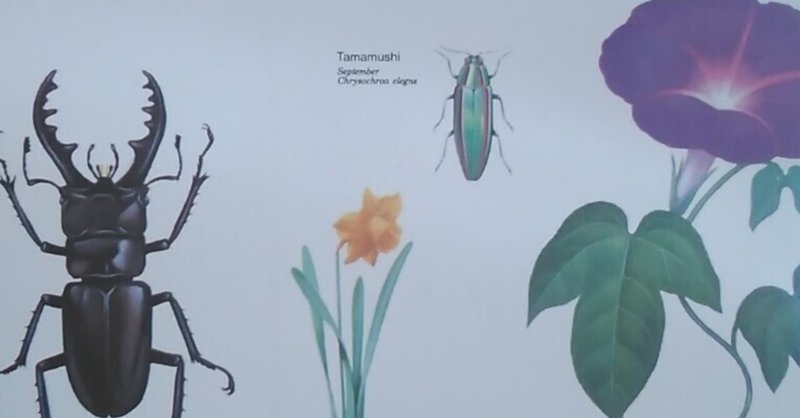
いいかげんで偽りのない僕のすべて ⑧
夜は家族で焼き肉を食べに行った。初音ちゃんは相変わらずよく食べた。
肉はもちろん、白米に冷麺、ビビンバ、サムゲタンスープもたいらげ、デザートの杏仁豆腐とマンゴープリンも残さなかった。僕も少食ではない方だが、初音ちゃんを見てるだけでお腹いっぱいになった。
「いやあ、見ていて気持ちいいよ。おいしそうに、食べるねえ」
父は珍しく笑いながら、初音ちゃんの底なしの食欲に感心していた。もうすごいねえ以外の言葉、発動しなかった。それぐらい圧倒されていた。
帰りも雨は降り続けていた。車で帰宅する途中に初音ちゃんはコンビニに寄ってほしいと言い、店内で買い物をしてから戻ってきた。
「叔母ちゃんごめんね。小さいのしかなかった」
母に手渡した袋にはマヨネーズが入っていた。やだあ、いいのに。母は笑い「ありがとね」と初音ちゃんの頭を抱き寄せた。こういうことを当たり前にできる。素がいい子だから、僕もみんなもなんとなく許してしまうのだ。
早寝の我が家は帰宅してからもあまりゆっくり寛がない。父はすぐにお風呂。母は明日の準備。初音ちゃんと僕は居間で携帯のオンラインゲームをやっていた。初音ちゃんは負けると叫んで叩いてきて「もう一回やる」と何度も対戦を挑んできた。僕は画面を見てるふりをしながら一秒ごとにくるくる変化する表情を観察していた。素直な女の子は素直に可愛いと思う。全部計算で無邪気スイッチを自在にオンオフできる機能が備わっているとしても、
男は結局これにやられる。欺いと言われる女性タレントも欺いと分かっていて、上手だなと可愛く思うのだ。だから騙されたって傷付かないし、バカだねと言われてもなんにも感じない。文句を言う子より、けらけらと笑ってる子の方が可愛いと思うに決まってるんだから仕方ないのだ。
毎回最後の僕が風呂から出ると、初音ちゃんはまだ居間にいた。テレビも消えたちゃぶ台に肘を付け、産婦人科からもらってきた手術の注意書を読んでいた。とうとう明日かと僕にもちょっと緊張した。
「もう寝た方がいいんじゃない?早めに休んでおきなよ」
声を掛けると「うん」と深く頷いた。
「明日、ホントにいいの?付き合ってもらって」
「それはもう気にしないでいいから。それより何もないことを祈るよ。無事に終わればそれが一番だから」
自然と優しくなっていた。少しでも初音ちゃんの気持ちを和らげたかった。僕は付き添うことしかできない。今さら倫理的なことや心情に訴えることを話すより、課された仕事をひとつ終わらせるみたいに、明日はそれを済ませればいいだけだよと、押し寄せる迷いや罪悪感を差し止めたかった。
「健太郎君、あたしが起きるまでどこにいるの?」
「まだ決めてない。初音ちゃんが病院で待っててほしいならそうするし、どっか行っててほしいなら適当にどこかで時間潰すよ」
初音ちゃんは、うーんと首を傾げて「明日になってから決める」と立ち上がると「風邪ひくよ」と、僕の濡れた髪を肩のタオルで背伸びして拭いた。
さすがに今日は来ないだろうと、部屋で昨日買ってきた文庫本を読みながら、明日の段取りをなんとなく辿っていると、廊下から足音が聞こえてノックされた。おい嘘だろと時計を見ると、今日はまだ一時にもなっていなかった。今夜こそ本当に眠れないのかもしれないが、それでも休んでおいた方がいい。僕は追い返すつもりで扉を開き「バア!」と顔を突き出した。わあっ、あははははと初音ちゃんは笑いながら部屋に入ってきた。だが寝室には行かず、僕がさっきまで本を読んでいた勉強机の椅子に座り「ほんとはね…」と、背凭れに顔を乗せた。
「ずっと健太郎君を待ってたんだ。寝たふりしながら、こっち来ないかなって思ってた。本なんか読んでないであたしのこと見てって念力送ってた。健太郎君は知らないと思うけど、まだこっちに住んでた頃、寝てる健太郎君にキスしたことあるんだ。知らないでしょ」
初音ちゃんはうふふと笑い「好きだったの。ずっと」と口唇を噛んだ。僕は半分ぽかんとしながら聞いていた。彼女はいたずらそうに笑っていた。
「なにもされてないと思ってたでしょ」
僕は机に寄りかかって、うんと髪を掻いた。初耳だった。
「無防備で寝ちゃいけないのよ。男の子だってなにされるか分からないんだから」
四日前に僕が注意したのと同じフレーズ。初音ちゃんは勝ち誇ったようににんまりしていた。笑いが込み上げた。やられたぜとおかしくなった。
「ちなみにだけど、キスだけ?」 僕は尋ねた。「あとはしてない?」
「してない。キスだけ。でも二回ぐらいしたかな。だって先に他の人としてほしくなかったんだもん。怒った?」
「いや別に。ああじゃあファーストキスって初音ちゃんだったんだ。自分のことなのに初めて知った。はは、そうだったんだ」
「ごめんね。あたしが奪っちゃった。平気で寝てるからさ。なんにも知らないで」
初音ちゃんは僕の手を掴み、幼稚園児のお遊戯みたいに前後に揺らした。
なにが嬉しいのかずっとニコニコしていた。
「いとこ同士って結婚できるんでしょ?」
水面から顔を出してるイルカみたいな黒い目が見つめていた。
「そうだね。法律上は」
「じゃあ、こうしてても罪じゃないのよね。誰にも咎められないのよね。悪いことしてるわけじゃないのよね」
そうだね。僕も微笑んだ。けど僕は昨夜のことがあっても初音ちゃんをいとことしてしか認識しておらず、恋愛感情は全く湧かない。だからといっていざとなれば結婚できる大義名分で寝たわけでもない。けど好きではあるし大事でもある。いいわけをひとつさせてくれるならそれだけだった。放っておいたら傷付くと思ったんだ。ずるいかもしれないけど、僕はどこかでずっとそう思っていた。初音ちゃんに応えたと唱えていた。
「もっと早く気持ちを伝えられてたら、こんなことにならなかったのにな。
ほんとばかだよね。けどこんなことがなければここに来てないんだよね。どちらにしても健太郎君を困らせてたんだけど」
「でもなんにもなく初音ちゃんに言われてたら、びっくりしてスルーしてたよ。なに言ってんの?とか笑い飛ばしてたと思う」
「それでもよかったの。自分の中ではひとつのけじめが着いたから。でもやっぱり普通じゃないか。いとこに告白されたらおかしいと思うよね」
「おかしいっていうか、初音ちゃんなんて、普通に可愛い女の子じゃん。いい所に暮らしててさ。なのになんでこんなつまんない田舎者のいとこがいいのか、単純に不思議だよ」
「あたしは健太郎君を田舎者なんて思ったことないよ。いとこって悩んだことはあるけどさ。健太郎君すごく頭いいし、本もたくさん読んで物知りなのに、どうしてそんなに卑下するの?ここだって自然がいっぱいで、景色も綺麗で、すごくいい所なのに、なんでそんなに見下すの?」
「ここにいて物事が解決したことがないからだよ。それに、僕の頭いいは勉強ができるだけで、生活には反映しないんだ。中身は空っぽなんだよ。今も昔も。だから本なんか読むんだよ。少しでも隙間埋めたくて。ひとりじゃなにも決められないんだ」
「じゃああたしのことも頼まれたからやるだけ?」
「だっていとこだもの。困ってたら助けるよ」
「それだけ?」
「それだけじゃだめ?いとこだからこそなんでもやってやろうと思ったんだよ。この部屋だって初音ちゃんしか入れてないし、初音ちゃんの前でしか煙草を吸わない。そうでしょ」
まあね。そうね。初音ちゃんは僕の腹を軽くパンチしてから椅子から立ち上がった。そして「あー煙草くさい部屋」と言いながら、おやすみと手を振って出ていった。
次第に消えてゆく足音を聞きながら、僕はベッドに倒れた。もっとマシな答えがあったはず。もっと気の利いた文句があったはず。いつまで経っても僕は上手な嘘が付けない。優しくなれないし、優しさが分からない。不安でいっぱいの初音ちゃんの心の負担を軽くしてあげるべきなのに、まさになんも言えねえ。まだまだガキだぜと自己嫌悪に髪をぐちゃぐちゃかき混ぜた。
手術は午後の一時からだった。当日は食事を抜くようにと言われていたので、初音ちゃんは水だけを飲んでしのいでいた。土曜日は仕事が休みの母も家にいて、僕の友人と初音ちゃんの元同級生で出掛けるということにした。
病院は電車とバスで90分の所にある。逆算で十一時には家を出る予定だった。初音ちゃんは黒のノースリーブに、マスタードカラーのフレアスカート。服のレパートリーのない僕はブルーグリーンのポロシャツと、あまり
皺のないベージュのチノパンで、少しでも大人っぽく見えるようにした。
初音ちゃんが持ち物の確認をしていた時だった。家の電話が鳴り、近くにいた母が受話器を取り「はい」と出た。
「まあ、こんにちは。いえいえこちらこそいつもお世話になっております」
母はやたら丁寧に挨拶しながら目で僕を呼んだ。こっち来いと大きく手招きした。僕?と自分を指差すと、母は頷き「ええ、おります。今代わります。お待ち下さい」と話口を押さえて僕に受話器を差し出した。
「星野さんのお母様。娘さんのことで話があるって」
え?と思いながら受け取った。もうそろそろ出掛けなくてはならない時間で、僕はちらと初音ちゃんに目をやった。心配そうな表情でこっちを見ていた。ちょっと待ってと合図を送ってから「はい」と電話を代わった。
先輩の母親はひどく取り乱していた。わめくように話してるので、なにを言ってるのかさっぱり分からず、何度も聞き返した。あーちゃんがね、あーちゃんがね…と繰り返しながら、彼女が今病院にいると声を震わせた。
今朝起きて来なかったので部屋を見に行ったら倒れていた。睡眠薬を大量に飲んで緊急搬送されたのだと電話口で泣きながら話した。
「今から来てくれない?」
洟を啜りつつ僕に言った。
「あの子にとって健太郎君だけが心の支えなのよ。元気づけてあげてちょうだい。もう少ししたら意識が戻りそうだから」
僕は母親の頼みに逡巡した。彼女の自殺未遂の知らせにひどく動揺し、何から考えればいいのか全く分からなくなっていた。昨夜食事の誘いを断り、
別れのメールを送ったせいなのかと頭が真っ白になった。体が冷えてゆく。背中から四肢へと感覚がどんどんなくなっていった。
来てちょうだいね。待ってますからね。
母親は何度も告げて電話を切った。僕は曖昧な返事しかできないまま受話器を置いた。しばらく世界から物音が消えた。
「ーどうしたの?娘さん、何かあったの?」
声を潜めた母が僕を覗き込んだ。ああ…うん…。なんとか頭を整理させた。
「ーちょっと、入院したらしくて…」
ええ?と母は目をしかめたが、すぐに事情を察したように「無事なの?」と小声で尋ねた。多分…。答えながらも僕は完全に混乱していた。
もしこのまま彼女が目を覚まさなかったらどうしよう。話せないままになったらどうしよう。思うだけで手足や喉が勝手に震えてきた。
縁側の前でバックを膝に置いてる初音ちゃんと目が合った。じっとしたまま、悲しげな目で僕を見つめていた。そうだ。僕はこれから初音ちゃんに付き添わなければならない。産婦人科に行かなきゃならないんだ。だが先輩が白いベッドに横たわってる姿が頭から離れず、恐怖で動けなくなった。
「健太郎君、あたし、先に行くね」
初音ちゃんは明るい声で言い、にっこり笑った。
「もし来れたら連絡して。そしたら向こうで合流しよう。じゃあ叔母ちゃん、行ってくるね」
そうして母に手を振り、居間を出て玄関でサンダルを履くと、早々に出ていってしまった。待ってくれ。心で背中に呼び掛けた。僕は答えを出せぬまま「行ってくる」と靴も履ききらずに駆けていった。
「初音ちゃん!」
前を急ぐ初音ちゃんを呼んだが、トートバッグの紐を握りしめて走る彼女は止まってくれなかった。そんなに走って転んだりしたら危ない。僕は加速した。元陸上部なので足は速い。すぐに追い付いて腕を取った。初音ちゃんは口唇をぐっと噤んだまま「行って」と僕を見上げた。
「ー電話、健太郎君の彼女のお母さんからでしょ。あたしは大丈夫だから、そっち行って。もう十分やってもらったから、ひとりでも平気。気にしないで」
そしてバックから同意書の入ったクリアファイルを取り出した。
「これもらった時ね、もう連絡付かない人だからサイン無理だと思うって話しておいたんだ。そしたら保護者のだけでもいいからって言われて、昨日お母さんにFAXで署名してもらったんだ。だからこれだけあれば大丈夫だと思う。自分のことだから、あとは自分でやる。だからもう気にしないで。やっぱり、健太郎君を巻き込みたくないし、決心ついてるから」
僕はなんにも言葉が出なかった。初音ちゃんとの約束を反古にしたくないのに、やはり星野先輩のことが気になって仕方ない。いいや、行くよと、口にできなかった。あちこちから色んな感情が吹き出して、どうするべきかの判断できない。だから初音ちゃんに行ってと言われてホッとしている自分がいた。ごめん、ごめんと思いながらも、うまく返せなかった。
「健太郎君のおかげで勇気出たんだよ。もう迷いない。明日になったら全部終わってると思えば、そっちのが気が楽だから怖くない」
初音ちゃんにリスの歯をにょきりと見せ、僕の手を取り「ありがと」と包み込むように撫でた。優しい手触りなのに力があった。僕など敵わないぐらいの強さが込められていて、気付けば縋るようにぎゅっと握り返していた。
何かあったらすぐに連絡してほしいと初音ちゃんと約束し、僕は先輩のいる病院に向かった。バスの時間が待てずにタクシーを使った。移動中、ずっと祈り続けていた。無事でいてほしい。左足以外、もう彼女からなにも奪わないでほしいと、初めて本気で神に祈りを乞うた。
到着した病院の面会受付で彼女の名前を言うと、ついさっきICUから一般病棟に移ったと聞いて、命は助かったんだと安堵した。ここは昨年の事故の時も入院していた所なので、大体の場所は把握できている。教えられた病棟には迷わずに行き着いた。
南館の五階。オフホワイトの壁と、等間隔に並ぶ病室。センターに始終忙しそうなナースステーション。どの部屋も扉は開いていて、大部屋のベッドをクリーム色のカーテンがくるりと囲んでいた。
ひとつずつ病室の名前を確認しながら探した。端から端まで通路を歩くと、一番奥にある茶色い扉の特別室に「星野朱里様」の名前があった。ようやく見つけたが、扉の前に立つと、ノックする手が躊躇した。去来する思いが気持ちを鈍らせていた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

