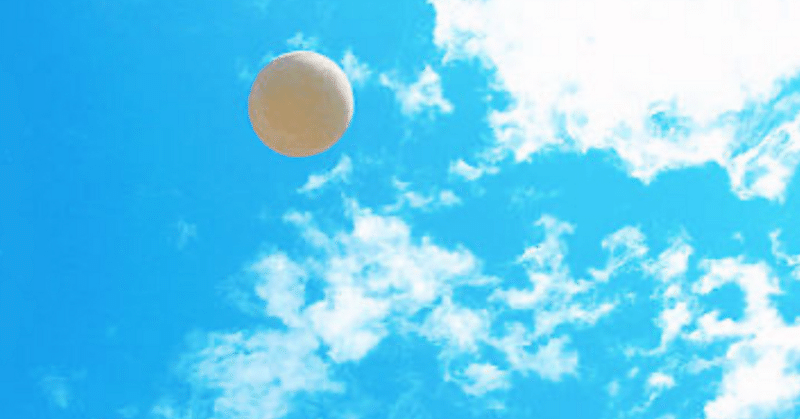
【短編小説】スローボール
もう少し曇り空がよかったが、盛岡は晴れ渡っていた。
「山ってさ、天気がいいと、遠ければ遠いほど青いんだね」
盛岡駅近くのレンタカー屋で借りた白い小型車の助手席で真(ま)紘(ひろ)が言った。
「そうか?」
「そんなこと知らないで生きてきたよ」
車窓から吹き込む空気は、四時間前までいた東京の朝のそれよりも涼やかだ。遠く見える岩手山の青は、空の青とほぼ同じ色で、中腹付近まで残っている残雪が、その境界線を引いている。新幹線からはところどころに見えた、田植えを終えたばかりの水田のきらめきは見えなくなった。見えるのは、背の高い道路脇の松並木と、その向こうの牧草地、さらに遠くの青い山々だ。
「確かに青いな」
「そうでしょ」
「でも、スカイツリーから見た遠くの山だって同じだろ」
「そうかも知れないけど、とにかく今気付いたの」
多少、不満そうな声で真紘は言ったが、僕達の会話はいつもこんな感じだ。むしろ、今日の真紘は朝から機嫌がいい。
真紘は、ごく軽度の鉄道オタクで、盛岡駅で東北新幹線の車両と秋田新幹線の車両とが切り離されるのを見て、一段とテンションが上がっている。さらに、駅前で朝食と昼食兼用の盛岡冷麺を食べると、「美味しい」を連発していた。ただ、ここから先は、車でなければ不便なのだと言い聞かせても、行き先と同じ方向に向かうローカル線に乗りたかったと不満を漏らしていた。まあ、この日帰り旅行の目的が目的なだけに、あまりテンションを上げられても困る。
僕の気持ちは正直重い。だから、この五月(ごがつ)晴(ば)れの眩しさが結構きつい。だが、帰路は気が楽になっているはずだ。
おおよそ正午に盛岡を出発して二十分ほど経った。国道4号線は、北へ進むごとに急に平地が狭くなるから、あっという間に山が近付く。初夏の陽光が輝かせている新緑の黄緑の中に、ぽつぽつと見えるピンクは野生の山桜だろうか。
僕は東京では嗅げない草と土の混じったような匂いを嗅ぎながら、岩手に帰って来たのが五年ぶり、盛岡より北に行くのは十三年ぶりだということに思い耽っていた。
髪の乱れを気にしたのか、真紘が窓を閉めて、薄いピンクのブラウスの袖を少しだけまくった。それに合わせて僕も窓を閉めた。車内はエアコンを使わなくてもちょうどいい温度だ。それまで、あまり聴こえなかったローカルFMから、のどかな風景にそぐわない、ハードな邦ロックが聴こえてきた。
「しかし、本当に田舎だね」
楽し気に真紘が言った。
「悪かったな」
「いい意味で、だよ」
「いい意味で田舎って俺には理解不能。田舎は田舎だよ」
「人の話を素直に受け取りなさいよ」
真紘は東京生まれの東京育ち。僕達は東京の大学で知り合った。真紘は教育学部で国語科を専攻し、大学院に進んでいる。僕も同じ教育学部で、入学時は公民科専攻だったが、在京の食品メーカーに就職した。あちこちの大学に潜り込んでは、学食のメニューを食べあさり、それを評価し合う、「学食研究会」というふざけたサークルで知り合った。付き合い始めて五年が経つ。一応、真紘の親からは公認の仲だ。
明日は東京で大学時代の仲間の結婚式がある。新郎新婦共に同じサークルの出身で、僕も真紘も出席するから、今日は目的を果たしたら、ほぼとんぼ返りなのだ。
「あれが岩手山」、「これが姫神山」、なんてことを僕は教えながら運転していたのだが、「ここが石川啄木の故郷の渋民」を教えたあたりから何も教えることが無くなってきた。名も知らぬ低い山がだらだらと続くだけだからだ。
「帰りに啄木記念館に寄れるかな?」
国語専攻の真紘としては、どうしても寄りたいのだろう。
「たぶん寄れるよ」
「帰りの新幹線の切符は買ってないんだよね」
「ああ、特に混んでないようだったし」
「宮沢賢治記念館は無理だよね?」
「花巻か。泊りなら行けたけど、今日は無理だな。また今度来よう」
「うん」
無理、と言われたのに真紘は満足そうな声で言った。「また今度来よう」が気に入ったのだろう。
目的地までのちょうど中間地点あたりにあった道の駅で小休憩し、また車を北へ走らせた。とうとう通り過ぎる場所についての僕の知識は皆無になってしまい、僕達はFMのパーソナリティーが話すローカルな話題に仕方なく耳を傾けながら、さっきの道の駅で買ったペットボトルのミネラルウォーターを交互に飲んでいた。
しばらくすると、登坂斜線がある急な坂道に入った。ようやく見覚えがある道だ。それを登りきったところで、目的の一戸町(いちのへまち)に入ったことを標識が示した。
「圭(けい)君、ここにいつまで住んでたんだっけ?」
「小五まで。そのあと盛岡に引っ越した」
「どっちが楽しかった?」
「断トツでこっち」
「なんで?」
「友達がいっぱいいたし、親もまだ優しかった」
「ふうん」
真紘が空気を読んで質問をやめた。真紘のこういうところが好きだ。
一戸町の町なかに入った。
駅を通り過ぎて、古びた商店街に入ると、真紘は周囲を見回しながら、「なんか昭和の町っていう感じ」と言った。
東京育ちにはそんな風に見えるのかなと思いつつ、「ここら辺はあまり変わってない。でも、土曜日なのにシャッターが閉まっている店が多いな」と僕が言った。
町は慎ましく緩やかに動いていた。干物を並べ替えている鮮魚店の中年の男性。もう午後だというのに店先を箒で掃除している衣料品店の老人の女性。目的地は特になさそうに見えるシルバーカーを押しながら歩いているかなり高齢の女性。郵便局の前では老人の男女が立ち話をしている。車の往来は数えるほどだ。子供の姿も数人見られたが、ほとんどが老人。
それを見ながら真紘が言った。
「でも、寂しい感じはしないよ。なんか温かい感じ」
「どこが?ほとんど年寄りしか歩いてないのに?」
「逆に、そのせいかも知れない。みんなのんびりしてる」
「当たり前だろ。年寄りは暇なんだから。若い人は忙しいし、車で移動する」
「なんか、さっきからつまんないことばっかり返すね、圭君。嫌いなの?この町」
「好きだよ」
間もなく、僕達は大きな寺に到着した。
*
『昨日、明(あき)範(のり)君、亡くなったらしいよ』
二月に妹の文(ふみ)香(か)から届いたLINEには、リンクが貼ってあって、それを開くと岩手の新聞社のニュース記事が出てきた。
―――大型トラックと軽自動車が正面衝突 若い男女が死傷
新聞記事を読んだには読んだが、呆然としていてよく理解できなかった僕は文香に電話した。
「大学の友達が一戸の出身で、詳しく教えてくれた」
文香は盛岡の大学の教育学部三年生だ。僕と違って今のところ親の希望通りの道を歩んでいる。
「彼女を連れて一戸に帰省した帰りだったみたいだよ。弘前に。国道でセンターラインをはみ出して大型トラックとガッシャーン。車が燃えたんだって」
幼い頃の明範君ではなく、想像上の漠然とした二十四歳の明範君の顔と、記事に写真は無かったのに、恐ろしい事故現場が脳裏に浮かんだ。
「弘前?」
「弘前の大学の理工学部を卒業して、そのまま弘前の建設会社に就職したんだって」
「彼女は?」
「火が出る直前に、通りかかった車の人達に助け出されたんだって。足に大怪我したらしいけど。明範君にとっても、明範君のお母さんにとっても唯一の救いだよ」
「明範君のお父さんは?」
「だいぶ前に亡くなったって」
「そっか」
「お母さんは気が変になっちゃったらしい」
「そりゃそうかもな」
「火葬が明日、お葬式は明後日だって。行く?」
「平日だから難しいな。後で墓参りに行くよ」
「行くなら、ついでにうちにも帰って来てよ。父さんと母さんが…」
「無理」
虫のいい話だが、文香には教師になってもらいたい。親の期待を裏切るのは僕だけで十分だ。
*
文香に調べてもらった明範君の菩提寺は、一戸町の中心の高台にあった。長い石の階段を登ったところにあり、周囲には杉が林立していて、その間にたくさんの墓が並んでいる。
僕達は駐車場に車を停め、階段を登った。樹々の影になっているせいで、車中よりはいくらか涼しく感じたが、二人ともかなり息を切らしながら登った。
「スカートじゃなくジーンズにして正解だった」
手すりに頼りながら、真紘が言った。僕もグリーンの長袖Tシャツにジーンズという涼しくて動きやすい恰好だったが、額にうっすらと汗が浮いてきた。僕は、さっきの道の駅の産直で買った、小菊やカーネーションの生花の束を右手に持ち、一緒に売店で買った墓参りセットを左手に持っていたから、手すりに掴まれなかった。
そもそも真紘は明範君を知らない。僕の幼馴染という知識しかない。「幼馴染の墓参りに岩手に行ってくる」と言ったら、「私も行く」と真紘は言った。僕が育った町を見てみたいと言われ、少しだけ戸惑ったが、了承した。
寺の山門をくぐると、手入れされた庭木の間を縫って舗装された細い通路があった。右に釣鐘堂があり、正面に大きな本堂があった。本堂からは鏧子(けいす)の音と読経が聞こえていたから、何かしらの法事が行われている様子だった。
僕は本堂の右側に繋がっている庫裏(くり)の玄関にあった呼び鈴を少々緊張しながら鳴らした。間もなく割烹着姿の中年の女性が出て来て、丁寧な言葉で何の用件かを訊いてきた。「高田明範さんのお墓を知りたいのですが」と僕が言うと、女性は意外なほどにすんなりと、分かりやすく教えてくれた。さらに、貸し出し用の手桶と柄杓、加えて水道がある場所も教えてくれた。
僕達は、また山門をくぐると、横に伸びる通路を数えながら階段を下りて行った。教えられた数の通路を右に入っていくと、一番奥の杉の木の隣に明範君の墓はあった。墓地の高い位置にあり、見渡す限り他の墓参者はいない。あまりに山が近く、ここから見える山々は青くなく全て緑だ。その狭間に真紘の言う「昭和の町」が見える。
大きく息を吸ってから、「やっぱりなんかいいな、この町」と真紘が言った。
「こんな風景が珍しいからだろ」と言いながらも、僕は結構うれしかった。
墓と向き合う。
一つの約束が蘇り、一転して心に鈍痛が走った。
―――県営球場で会おう
*
僕は高校の体育教師の親父が赴任していた関係で、一戸町で小学校三年生から五年生までの三年間を過ごした。お袋は専業主婦で、ずっと親父の転勤に付いてきた。もちろん僕と文香も。
親父は大学まで野球をしていた経歴から、転勤する先々の高校で野球部の監督をしていた。甲子園には手が届かなかったが、親父が監督した高校の野球部はたいてい強かったし、一戸桜陵高校でもそうだった。
冬場以外は、毎日、ナイター練習まで指導してきて、帰宅するのは早くても午後九時頃だった。土日も練習や練習試合、大会でほとんど休みの日が無かったが、僕は寂しくなかったし、不満もなかった。それは高校野球の監督をしている親父をカッコいいと思っていたし、自慢に思っていたからだ。
特に試合のときはカッコよかった。試合前のシートノック。正確なノックを連打し、それを選手達がまるで機械のようにきびきびと処理していく。そして、最後にキャッチャーにノックをする。これがノッカーの腕の見せどころなのだ。親父は一発で高々とフライを打ち上げる。ボールは綺麗に筆記体のℓの字を描いて、バッターボックス付近に戻ってくる。キャッチャーが捕ったのを合図に、整列していた選手が親父とグラウンドに礼をし、自陣のベンチに走って引き上げる。スタンドから見ていた僕には熟練されたショー、または、少々大袈裟だが、神々しい儀式にすら見えたものだ。
もちろん親父は僕にも野球を教えてくれた。
僕が五歳ぐらいのときには、小さいが本革のグローブを買ってくれた。一戸町に行ってからも、忙しい中、日曜日の午後なんかに、よく小学校の校庭でキャッチボールをしてくれた。僕の家は小学校のすぐ近くだった。
「大きく振りかぶる」とか、「左足はゆっくり高く上げる」とか、ピッチングフォームを丁寧に教えてくれた。大きく外れたボール以外はだいたい、「ストライク!」とか、「ナイスボール!」と言って褒めてくれた。さすがに教えるのが上手く、自分で言うのもなんだが、僕は同い年の友達よりも、はるかに基本に忠実で綺麗なフォームと、正確なコントロールを身に付けた。もちろんバッティングも教えてくれた。
ただ、僕が四年生で少年野球チームに入ってからは、ほとんど教えてくれなくなり、「チームの監督やコーチに教えてもらえ」と言うようになった。それが指導者同士の礼儀なのだそうだ。ちょっと寂しかったが、それはそれで僕は親父をカッコいいと思った。
*
読経は聞こえなかったが、鏧子の音が聞こえていたから、まだ法事は続いているようだった。
墓は、とても綺麗だった。「高田家代々之墓」と刻まれた黒御影石の墓石には汚れ一つ無かったし、敷かれた玉砂利には一本も雑草が生えていなかった。
供えられていた花がまだ綺麗だったから、それはそのままにして、真紘が花立ての水を取り替え、持ってきた生花を供えた。僕は蝋燭を燭台に立ててライターで火を点け、焼香し、手を合わせた。
「明範君、安らかにお眠りください」とだけ僕は祈った。それが精いっぱいだった。真紘も続いて、見ず知らずの故人に焼香した。
*
転校してきた当初、僕と明範君はなかなか仲良くなれなかった。
真新しい立派な校舎だったが、各学年に一つしかクラスがない小学校だった。だから、当然同じクラスになったが、クラス内の違うグループにいて接点がなかった。社交的なグループの人達は、転校生の僕をちやほやしてくれ、すぐに仲間に入れてくれた。明範君は、どちらかというとおとなしい、真面目な二、三人の友達といつも一緒にいた。
そんな僕らを引き合わせたのは野球だったし、親父でもあった。
転校してきて、一か月ほど経った頃、やはり日曜日の午後だったと思う。僕が親父と校庭でキャッチボールをしていると、ブランコの横で自転車に跨ったままの明範君が、じっとこっちを見ているのに気付いた。僕が手を止め、そちらを見ていると、親父が手招きをしながら明範君に、「おいで!一緒にやろう!」と声を掛けた。
もじもじした感じの明範君だったが、初めから一緒にやりたかったのだ。その証拠に、自転車のかごには、グローブと軟式ボールが入っていた。
親父が一戸桜陵高校の野球部の監督だということは、友達の間で有名だったから、明範君は僕のことが羨ましかったし、親父から野球を教わりたいと思っていたのだ。僕ら親子のキャッチボールも何度か見ていたのだろう。
「お前は、どこがやりたい?」と親父が明範君に訊いた。小学生までは好きなポジションをやって、野球を好きになることが大事、というのが親父の持論だった。
「キャッチャー」と明範君は緊張した顔のまま即答した。
学生時代の親父はキャッチャーだったから、特に専門分野だった。
親父は、その日のうちに、キャッチャーの基本を明範君に教えた。グローブでだったが、キャッチャーミットの構え方、ショートバウンドの処理の仕方、捕球してからの素早い送球動作。そのときの明範君の真剣で生き生きとした目が忘れられない。親父も明範君を気に入ったようだった。その後、数日のうちに明範君はキャッチャーミットを親から買ってもらった。
親父は、それからも何度か明範君に指導したが、キャッチャーに一番大事なこととして何度もこう教えた。
「ピッチャーと仲良くなること。そして知ること」
こうして、僕と明範君は親友になり、平日も休日も朝から日が暮れるまで一緒に過ごした。二人ともイチローのファンで、シアトルマリナーズの帽子を被っていたし、背丈も似ていたから、よく双子のようだと言われた。僕らは成績もまあまあで似通っていたし、教室で目立つのを嫌がるタイプだった。ただ、僕は、いい加減で周囲に流されやすい性格だったのに対して、明範君は頑なで責任感が強い性格だった。だから、僕のほうが友達が多かったが、明範君は周囲からの信頼が厚く、先生から薦められて学級委員なんかをやっていた。そして、「野球をする時間が減る」とよく不満を漏らしていた。
明範君は旅館の一人息子で、お父さんは旅館業の傍ら町議会議員をしていた。忙しい人で、日中あまり家にいなかった。お母さんは商売柄、いつも化粧を欠かさず、身なりがきちんとしている印象だった。痩せていて綺麗な人だったし、僕はお母さんの笑っている顔しか覚えていない。
旅館は大きくはないが、文化財になってもいいのではないかと思うほどに古くて立派な木造の建物だった。お母さんが一人で切り盛りしていたが、当時からあまりお客さんがいなかった。だから、と言っては何だが、僕らは、雪深い冬や、野球ができない日に、旅館のたくさんある部屋や、小さな池がある和風の庭で、かくれんぼなんかをして思う存分遊んだ。もちろんゲームもしたけど、ほとんどが野球ゲームだった。お客さんの邪魔にならない限りは、僕らがどんなに騒いでもお母さんは許してくれた。
四年生になった僕らは、一緒に少年野球チームに入団した。週に四回、小学校の校庭で練習があった。年に何回か大会があって、町営の野球場で試合をした。
僕らは何人かの六年生を差し置いて、五年生からレギュラーになった。僕はライトで、明範君はキャッチャーだった。弱い相手との試合では、六年生のエースピッチャーに代わって、僕がピッチャーをすることもあった。
僕らバッテリーは息の合ったコンビネーションで、直球にスローボールを織り交ぜながら、格下の相手チームのバッターを面白いように打ち取った。少年野球は変化球が禁止されていたから、僕らは球速を五段階に分けて、それを組み合わせていた。サインは、一番速い球が人差し指一本で、一番効果的だった山なりの超スローボールが指五本といった具合だった。そんなことができたのは、三年生の時からのキャッチボールの積み重ねと、チームの練習が無い日に二人だけで練習をしていた賜物だった。何より僕らは、お互いを知り尽くしていた。明範君は僕が投げたい球を知っていたし、僕は明範君が出すサインのだいたいの予想がついた。
*
墓誌を見ると、明範君のお父さんが亡くなったのは十年前で、享年は四十五歳とあった。「若いな」という単純な気持ちと同時に、僕が知っている、姿勢が良く、貫禄がありながらも柔和な顔をしたお父さんの面影がぼんやりと浮かんだ。
そろそろ帰ろうとして、蝋燭の火を消し、真紘に無言で促した時だった。左手に花束を入れた手桶を、右手に小さな竹籠を持った女性が歩いて来た。柄が大きな紫を基調としたブラウスを着て、グレーのスラックスを履いている。一目で判った。明範君のお母さんだった。それは僕にとって、懐かしい顔であり、歳月を感じる顔であり、痛ましい顔でもあった。
お母さんが五メートルほどのところまで近付いた。最初、僕を他の友達だと思ったようで、軽く会釈しながら、「ありがとうね。わざわざ…」と言いかけたが、ふいに驚いたような表情に変わった。
*
親父の転勤が決まり、盛岡の小学校に転校することになった時は、本当に辛かった。明範君以外の友達もたくさんできていたし、緑豊かな一戸町が大好きになっていた。野球は新チームになり、強いチームじゃなかったが、いよいよ四月から僕がエースピッチャー、明範君がキャプテンでキャッチャーとして、一番大きな大会に出られると張り切っていた矢先のことだった。
三月の中頃、先生がクラスのみんなに紹介するより前に、僕は明範君に転校することを告げた。明範君は悲しそうな顔をしなかった。平気な顔をして、残りの数日を一緒に過ごした。まだ、風は冷たく、チームの練習は始まっていなかった。雪解けしたばかりで、校庭はところどころぐちゃぐちゃだったが、まるで四月からも同じチームでバッテリーを組むように僕らはキャッチボールをした。明範君が出すサイン通りに投げられる確率はさらに高まり、僕らのスローボールを中心としたコンビネーションは一段と向上していた。
いよいよ最後の夜、僕は明範君の家に招待されて泊まった。僕らは大きな風呂に一緒に入り、野球ゲームをした。そして、お父さん、お母さんと四人でお別れ会をした。お母さんが作ってくれた豪華な料理を四人で食べた。明範君は、いつも通りに楽しそうで、変わった様子はなかった。
だが、僕はお袋から聞いていた。「明範君のお母さんが言ってたよ。明範君、毎晩泣いてるんだって」と。
僕は明範君の前ではもちろん、家でも泣かなかった。何故だか解らない。そんなに遠くまで行くわけじゃないと思っていたからだろうか。新しい環境への不安のほうが強かったからだろうか。僕がまだ子供だったからだろうか。逆に大人になりかけていたからだろうか。
引っ越しの日、僕ら家族が親父の車で出発しようとしていた午後、僕と文香の友達がたくさん見送りに来てくれた。文香はプレゼントをたくさんもらっていた。僕には野球チームのみんなが寄せ書きをくれた。受け取ると、僕はすぐにその中に明範君の名前を探した。
―――県営球場で会おう。
そう書いてあった。それは高校野球の県予選でお互いに勝ち進み、岩手県営野球場で試合をしようという意味だった。
もうすぐ車に乗り込もうとしているときに明範君が近寄って来て、最初親父に、「ありがとうございました」と礼を言った。親父はその下げた頭をポンポンと叩いただけだった。
そして、明範君は僕のところに来た。笑ってもいないし、泣いてもいない。
「県営球場で会おう」
寄せ書きと同じことを明範君は言った。
「うん」
僕はそう言って、手を差し出し、明範君と握手をした。
*
「圭ちゃん?」
お袋と同じ年代だから、まだ五十歳前後だろうが、明らかにそれよりも老けて見えた。昔の印象とは大きく異なり、全く化粧っ気がなく、白髪を染めて隠す様子もない。顔や首にも明らかにたるみが見られる。痩せているというよりやつれているといった印象。加えて表情がどことなくおかしかった。瞬きが多く、若干しかめるような顔をし、探るような眼で僕を見ている。
「はい。ご無沙汰しています」
そう答えつつ、僕は意外だった。明範君のお母さんが僕を覚えているとは思わなかった。僕が一戸町を離れて、十三年が経っているのだ。しかも、成長期という外見が一番変化する十三年だ。忘れている、若しくは判らないと思うのが普通だろう。
「本当に圭ちゃんなの?」
まだ疑っているような目つきをしている。僕はわずかな怖れすら感じた。
「はい。藤村圭(けい)太(た)です」
不意にお母さんは泣き始めた。声を上げて。手桶を下に落とし、上着のポケットからハンカチを出して顔に当てた。手桶は横倒しになり、水は零れ、花束は土に転がった。
*
親父が変わったのは、いや、僕から見た親父の印象が大きく変わったのは、親父が次の高校に赴任してからだった。親父は四十代に入っていたし、僕は思春期を迎えていた。
盛岡の高校に赴任した親父は野球の指導を辞めた。
大人の事情というやつは、なかなか子供に理解しがたいものだが、親父とお袋の会話を聞いていると、何となく解った。野球の指導者として脂がのった一番いい年代だったはずの親父に、周囲からの要請はあったらしかったが、親父が固辞したようだった。
親父は高校球児の指導でも、ましてや甲子園でもない、違うものを目指し始めたのだ。
*
寺から鏧子の音は聞こえなくなり、一羽のカラスの声だけが聞こえた。僕と真紘が焼香した線香は、もうすぐ燃え尽きそうだった。
お母さんの嗚咽が鎮まってきたのを見て、真紘が花束を拾い、僕に渡した。そして、「水、汲んできますね」と言い、手桶を持って、また寺の方へ上がって行った。
お母さんがハンカチをしまった。瞬きは減ったが、まだ目に険しさのようなものが残っている。
「圭ちゃん、今日はどこから?」
お母さんの声は上ずっている。
「東京に就職したんで、東京からです」
「このためにわざわざ?」
「はい。都合がつかなくて葬儀に出られなかったので」
「ありがとうね」
聞き取れるが、声は揺れていた。
「いえ」
「お父さんと、お母さんは元気?」
「はい。妹も元気です。今も盛岡に住んでいます」
「いいね。私はもう独りぼっち」
「はい…」
「あの娘(こ)は彼女?」
「まあ、そんなところです」
「そっかあ…」
お母さんの声は明らかにくぐもり、またしかめるような顔をした。
一命を取り留めたという明範君の彼女のことを考えたのだろうと僕は思った。さらに、その彼女が治らない傷を負っていたとしたら、お母さんの心の傷も想像できないほどに深いだろうと思った。
*
親父は今、盛岡の高校の副校長をしている。親父は、野球を辞めて、管理職を目指し始めた。酒を飲むと多少気が大きくなり、本音を話す癖があった親父が、よく話していたのは、概ねこんなことだった。
「体育教師が出世するためには、現場にばかりいたらだめだ。上に認められて教育委員会に行き、教師を指導する立場になる。そして、副校長になり、校長になる。野球の監督をしていると、現場から離せられない人間になる。それではだめだ。俺は甲子園より、校長を目指す」
その頃の親父に何があったのかは知らない。いや、何もなかったのだろう。もともと親父は、そういう価値観の持ち主だったのだ。
その証拠に、中学に入ってからの僕に親父は、やたらと勉強をしろと言い始めた。そして、教師になれと。それも主要五教科のどれかの教師になれと。僕には全く理解不能だったが、お袋も同じことを言うようになった。お袋は本来、大らかで優しい人だったが、専業主婦だったお袋が、親父の目指すものを支えることは当然のことだったのかも知れないし、安定した生活を送ってきた教師の妻が、子供にも教師になって欲しいと願うことも普通のことだったのかも知れない。
僕も一戸町で親父が野球の指導をしていた頃は、教師に憧れに近い気持ちを抱き、一番身近な職業だと思っていたが、盛岡の小学校に転校してから少しずつ変わった。
六年生という、思春期を迎え始めたクラスメイト達は、そうたやすく転校生に近寄って来てはくれず、なかなか教室に馴染めなかった。だから、簡単には友達ができなかった。
やはり少年野球チームに入団したが、チーム作りが出来上がっていたところに急に入ってきた新入団選手という立場。練習でキャッチボールの相手を見つけるのにも苦労をした。
表面上の友達はできたが、自分をさらけ出すことはできなかった。もともと目立つことが苦手だった僕の性格に拍車がかかった。人前で発表すると緊張で声が震えるようになっていた。先生は最上級生の先生らしく、厳しい男の先生で正直好きになれなかった。
何より、理想の教師像だった親父の変化。そんな僕が、教師を志さなくなっていったのは、僕にとって当然の成り行きだった。
それなのに、僕は大学の教育学部に進んだ。僕は親に自己主張したり、ましてや反抗したりする術を知らなかった。学校生活と同様、流れに任せた。そもそも、確固たる自分の意見というものを持ち合わせていない人間だったのだ。だから、「教師にはなりたくない」気持ちは、「教師にはならない」に繋がらず、心の奥底に留まったまま、僕は大学生になってしまったのだ。
だが、結局教師にはならなかった。大学は、多少の温度差はあるものの、周囲のほとんどが教師を目指し、情熱に溢れている学生ばかりだった。彼らは、「子供が好きだ」、「数学の面白さを伝えたい」、「サッカーの指導がしたい」などと、教室で、学食で、飲み会で熱く話した。そこで、ようやく僕は自覚した。大学に入ってすぐのことだ。
僕は教わるのが嫌いではないが、人前に立って教えるのは好きじゃないし、得意でもない。自分が成長したいとは思うが、人を成長させることに興味はない。僕は教師に向いていないし、なりたくない。もし、教師になどなったら、生徒が可哀そうだし、僕自身も追い詰められる。絶対に。
僕は教師になることを辞めた教育学部の学生になった。親の忠告を無視して、教員免許も取らず、民間会社に就職しようと決めた。
それ以来、盛岡には帰らなくなった。そして就職した。
それでも、親父とお袋は、通信教育で教員免許を取り、会社を辞めて、岩手で教師になれと言う。いまだに。
*
水を汲みに行っていた真紘が戻ってきて、あらためてお母さんにあいさつし、簡単に自己紹介をした。
お母さんは、「私は独りぼっちで何もすることがないから雨が降っても雪が降っても毎日来てるんだ」と言いながら、手際よく墓参りを済ませた。
「うちに寄っていってちょうだい」とお母さんが言った。
僕は、お母さんの様子が普通ではないように感じたし、真紘も一緒だったこともあり、戸惑った。だが、お母さんの言葉には行く手を遮るような強さが感じられて、断ることが難しいように感じたし、せっかく来たのだから、仏壇にも焼香していったほうがいいのではないかと思った。そして、真紘に同意してもらってから言った。
「寄らせていただきます」
「ありがとう。本当にありがとう」
お母さんはまた泣きそうな声で言った。お母さんの情緒は明らかに不安定だったし、僕は、お母さんの僕に対する「こだわり」のようなものを感じ、また怖れのようなものも感じた。
*
盛岡の中学校の野球部で、僕は野球に限界を感じていた。
僕の身長はあまり伸びなかった。中学二年の段階で、一六二センチ、五十五キロ。一八〇センチ近いチームメイトもいる中、コントロールが良くてもピッチャーなどできない。非力で肩が弱い僕に、監督が命じたのはセカンドだった。もちろん試合に出られればセカンドでも仕方がないと思っていたが、三年生になっても僕はレギュラーになれなかった。僕が入った中学校の野球部は、県大会上位の常連校だったのだ。
高校を選ぶとき、僕は迷いに迷った。僕レベルでもレギュラーになれそうな高校が盛岡地区に無いことはなかった。ただ、学力との兼ね合いで上手く選べなかった。僕の学力にちょうど良く、親が薦める高校の野球部は強かった。もちろんレギュラーになれなくてもその野球部で野球を続けることは可能だった。だが、親が薦めない高校に行ってまで野球を続ける気概も、レギュラーになれないことを知りながら野球を続ける情熱も、もう僕には無かった。
つまり、僕を迷わせていたものは、ただ一つだけだった。
結局、僕は親が薦める高校を選んで野球部には入らなかった。
親父は僕が野球を辞めても全く残念がらなかった。僕の野球のレベルを知っていたから。そして、さらに「勉強をしろ」ばかり言った。お袋も。実際、僕は勉強をした。勉強をするためにこの高校に入ったのだと思いたかった。
高校に入ってからの明範君の様子を僕は全く知らなかった。野球を続けているのかさえも。高校野球の情報を僕は遮断していたのだ。まあ、親父は野球を辞めていたし、強豪チーム以外の報道など、ほぼされないのだから、簡単なことだった。
僕は内心、明範君も野球を辞めていることを望んでいたのだと思う。
*
一キロほどの距離を歩いて来たというお母さんを後部座席に乗せて移動した。
商店街の枝道にある高田旅館はもう閉めていた。お母さんの話では、お父さんが亡くなった十年前に閉じたのだという。それ以前から、ほとんどお客さんもいなかったし、と付け加えた。
広い土間がある玄関に入り、思わず建物の中を見回す。太い柱や梁、漆喰の壁。僕にとっては、どこもかしこも懐かしかった。匂いさえも。だが、違和感があった。どこか艶というものが見当たらなかった。建物が息をしていないような感じがしたのだ。
真紘は、「素敵な建物」と見とれながら言った。
使うところだけ掃除しているのだとお母さんは言い、僕達を仏壇がある居間に通した。
仏壇の横の小机に置かれた葬儀用の大きな写真の明範君の顔は、僕が知っている明範君、ほぼそのままだった。鮮やかな黄色と水色のグラデーションのバックに囲まれた明範君は血色が良く、わずかに笑っている。短めで前髪が少しだけ額にかかっている髪型も昔とさほど変わっていない。僕が知っている明範君が単純に十三年分大人の顔になっただけのように見えた。ついさっきまで長く感じていた十三年が、「たった十三年」に感じられた。
焼香し、鈴(りん)を鳴らして、手を合わせる。鈴の透明な残響の中、僕はまた、「安らかにお眠りください」とだけ祈った。
*
高校三年の夏だった。地元新聞の社会面に大きな記事が載った。お袋が見つけたのだ。夏の高校野球県予選の裏話を取り上げた記事だった。
―――背番号がない『主将』の夏終る
「精神面でチームを支えた背番号がない主将が、相手校の校歌を聞きながら号泣した。一戸桜陵の佐々木孝之監督から「事実上の主将」と信頼された高田明範記録員(3年)。昨秋の新チーム始動時は主将に指名されたが、後輩の台頭もあり、春の大会でレギュラーから外れ、今夏から登録メンバー二十人からも外れた。ただ、野球への情熱は人一倍で、チームの精神的柱であることから、佐々木監督が記録員としてベンチに入れた。ルール上、記録員は主将になれず、副主将だった三上康平選手(3年)が主将になったが、高田記録員が実質の主将であることは三上主将をはじめとしたチームの誰もが認めている。高田記録員は『背番号は無かったが、みんなと同じユニフォームを着て、監督に与えられた僕にできる限りの野球を、憧れだった県営球場でできて幸せだった。これからの人生に生かしたい』とアンダーシャツで涙を拭いながら話した…」。
記事には大きな写真も載っていた。明範君は、県営球場のベンチ前に整列したチームメイトの端に立ち、顔を上に向けながら泣いていた。チームメイトと比べて明らかに小さな背丈で。
*
お母さんが座卓を囲んだ座布団に僕達を座らせ、お茶を出してくれた。
「葬儀に来られなくて本当にすみませんでした」
僕は居住まいを正し、あらためて謝った。
「いいのよ。どうせ明範に会えなかったし」
僕には意味がわからなかった。
「酷かったのよ。焼けちゃったから」
今度は目を必要以上に見開き、何かに耐えるようにお母さんは言った。
「警察の安置室に行ったらね、見ないほうがいいって警察の人に言われたの」
背筋が寒くなった。漠然としながらも黒焦げの死体がイメージされた。思わず顔をしかめてしまった。真紘は俯いていた。
「でもね、もちろん私は見たわよ」
「…」
「明範だって判らなかった。体に貼り付いてた燃え残った服の一部が辛うじて明範だってことを証明してくれてた」
僕は恐ろしいイメージを振り払うために頭を振りたかったが、必死で我慢した。同時にやはりお母さんはおかしいと思った。事故死、焼死した息子の無残な遺体の様子を、十三年ぶりに合った息子の幼馴染に話そうとしているのだ。初対面の真紘にも。
「警察の人から紹介された、その町の葬儀会社に霊柩車を頼んだけど、断られたの。霊柩車にもイメージダウンっていうものがある、焼死体はだめだって暗に言うのよ。びっくりした。霊柩車が遺体を運ぶのを断るなんてことがある?仕方がないから、そこから紹介された全国チェーンの葬儀会社に頼んだ。そこなら納棺もちゃんとしてくれるって」
お母さんの顔には、嘲りの薄笑いが浮かんでいるように見えた。
僕に何かを話す余裕は微塵もなかった。とにかく怖かった。一つは明範君の無残な遺体のイメージが。もう一つは、それを話し続けるお母さんが。真紘を気遣う余裕すらなかった。ただ、明範君を知らないのだから受ける度合いに違いはあるだろうが、恐怖に耐えてくれているだろう真紘に一段と、いとおしさを感じた。
「親戚にも誰にも遺体は見せなかった。もちろん誰も見ようとしなかったし。火葬の前もね、私だけが棺桶の扉を開けて、お別れを言った。見かけは誰だか判らない真っ黒な明範に」
そこでお母さんは意識的に間を置いたようだった。静かに深呼吸をしているようにも見えたし、何かを話し終え、これから新しい話をしようとしているようにも見えた。そして、一転して毅然として言った。
「当たり前なのよ。私の子供だもの。私が顔を見てちゃんとお別れを言わなきゃ、明範が可哀そうでしょ」
線香の匂いが一段と強く漂ったような気がした。
僕は、やはり何も言えなかったが、ああ、お母さんはまともなのだ、実に普通で、まともな一人の母親なのだと思った。
「ちょっと待っててね」
何かを伝え終えたというように、心なしか落ち着いた声で、そう言って立ち上がると、お母さんは仏壇の下の扉を開き、ビニール袋に入った何かを取り出した。
「これ」
お母さんはビニール袋から古い茶筒を取り出した。今度は口元に、かすかに明るさすら感じ取れた。
茶筒は銀色のブリキ製で、蓋が取れないように太いビニールテープが巻かれていた。あちこちが錆びている。僕が手に取る。それが何なのか、僕はぼんやりと思い出した。
タイムカプセル…。
僕が盛岡に引っ越す日の朝、僕らは二人で、ここの庭にこれを埋めたのだ。広い庭のどこに埋めたのかは忘れた。もちろん何を入れたのかも。
「どこに?」
僕は、ようやく口を開くことができた。
「四十九日が終わって、気持ちがいくらか落ち着いた頃に、明範のアルバムを開いたの。そしたら、圭ちゃんが引っ越しする前の日にうちでお別れ会をしたときの写真があって、その中に、にこにこした二人が、これを持ってるのがあった」
お母さんが続けた。
「二人のタイムカプセルだって思い出した。そして、探さなきゃって。圭ちゃんに渡さなくちゃって思った」
「よく見つかりましたね。こんなに広いお庭なのに」
「それが、簡単だったの」
「どうして?」
「庭の端っこ辺りだとは見当が付いていたから、塀の近くをちょっとだけ探したらね、割りばしが立ってたの」
「割りばし?」
僕は割りばしなんてものが、よくも腐らずに残っていたものだと思い、土で汚れ、カビが生えて、腐りかけた割りばしを想像した。
「それがね、綺麗な新しい割りばしだったの」
僕は思わず天井を見上げた。天井板の木目がすぐに歪んで揺れた。
「事故に遭う前、最後に帰省したときに取り換えて行ったんだと思う。多分、時々取り換えてたんじゃないかな」
いくつかの理由がある涙を僕は初めて流した。悲しかったし、うれしかったし、悔しかった。
僕はハンカチを持っていなかったから、Tシャツの袖で涙を拭った。真紘がすでに湿っているハンカチを貸してくれ、僕らの涙が混じった。
「よかった。母親の役目をまた一つ果たすことができた。あとは一周忌まですること無いかな」
僕らは、このタイムカプセルを、いつ二人で掘り起こし、開けようとしていたのだろう。あの「約束」を果たしたときだったのだろうか。だが、僕は「約束」を守らなかった。それなのに、どうして明範君は。
「開けてみてもいいですか」
「もちろん。私も見てみたい」
茶筒を振るとゴロゴロとした感触があった。僕は、ビニールテープを外し、渋くなっていた蓋を開けた。中から出てきたのは、窪みにわずかに土が付き、細かなひびがいくつも入った少年用の軟式ボールだけだった。白球とは呼べないほどに色褪せたボールが、僕に思い起こさせたのは、十三年前の少年の僕らではなく、大人になった僕らがこのボールでキャッチボールをしている光景だった。
「ごめんなさい!ごめんなさい!ごめんなさい!」
僕は土下座の姿勢のまま、写真にでも仏壇にでもお母さんにでもなく、右手に握ったボールに向かって、何度も何度も泣きながら謝った。
お母さんにその意味が解ったのかどうかは解らない。ただ、お母さんは僕に近寄り、ずっと背中をさすってくれた。
しばらくして、泣き続けながらも僕がようやく体を起こすことができたとき、お母さん以上に事情が解らないはずの真紘もまだ泣いていた。
「本当にありがとうね」
お母さんは駐車場まで見送りに出て来てくれて、運転席の僕に言った。ボールは茶筒に戻し、後部座席のリュックに仕舞った。
「また来てね」
「はい。お墓の場所も分かりましたし、ここにも必ず寄らせていただきます。お母さんもいろいろ大変でしょうけど、お体を大事にしてください」
お母さんは頷き、今度は助手席を覗き込んで言った。
「真紘さんも」
「はい。必ず来させていただきます。私、この町が好きになりましたから」
僕は、もう一度感謝を伝え、車を発車させた。僕はサイドミラーに映る、手を振るお母さんの笑顔が明範君に似ていると初めて思った。
午後三時を過ぎていた。車中で二人きりになっても、真紘は僕の「ごめんなさい」について訊いてこなかった。僕が話すまで訊いてこないだろう。そういうやつなんだ。
「ちょっと寄り道してくよ」
まだ陽は高かった。懐かしい小学校の駐車場に車を停め、僕達は車から降りた。青空に包まれた校庭に、少年野球チームの姿は無く、若い親子連れが一組いるだけだった。走り回っている三歳ぐらいの男の子に声を掛けながらお父さんが追いかけている。お母さんは赤ちゃんが乗っているらしいベビーカーを押しながら見守っている。
横に立って同じ光景を見ている真紘に僕は言った。
「啄木記念館のあと、もう一箇所寄り道していいか?」
「どこ?」
「盛岡」
「盛岡のどこ?」
「実家」
「え、こんな格好で大丈夫?」
「大丈夫さ」
僕は小さく土が盛られたマウンドに歩み入った。綺麗に整った土の上に小石がぽつんと一つだけあった。僕はそれを拾うと、大きく振りかぶり、左足をゆっくり高く上げ、基本に忠実なフォームで小石を投げた。
右手から放たれたスローボールは大きく弧を描いて飛び、小石は校庭脇の草むらに消えた。 (了)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
