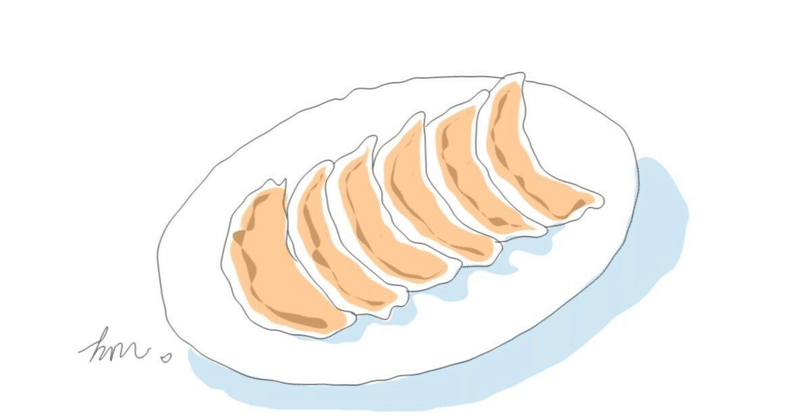
ぼろラーメン屋の、激うま餃子。
中学生の頃、図書館に通っていた。
平日も休日も、開館時間から閉館時間まで。
飽きもせず、ほかに居場所もなく、せっせと自転車を漕いで通った。
わりと新しかったので、勉強机や本には困らなかったが、なんせ建物の中には図書館以外何もない。
カフェも、コンビニも、パン売り場もなく、建物のロビーには自動販売機だけ。
徒歩圏内に、何もなかった。
だから、一日中そこで過ごすためには、パンなどを持参しておくか、一旦家に昼食をとりに帰る必要があった。
これがけっこう、めんどくさかった。
ある日、それを知った母が「近くに買い物に来てるから、いっしょにお昼を食べよう」と連絡してきた。
当時ガラケーの、メールの受信箱に母の名前があって、わたしはそのまま建物の外に出た。
駐車場に、母がいた。
手ぶらだ。
何か買ってきてくれているわけじゃないらしい。
このまま、どこかに連れてってくれるんだろうか。
無言で近づいていくと、母は「ねえねえ」と言いながら指差してきた。
「あんた、このへんほんまに何もないじゃないの」
「え?そうだよ、言ったじゃん。どっか食べに行くんやろ?」
わたしが不満そうな顔で言っても、母は顔色ひとつ変えない。
娘の理不尽な態度なんかで、動揺するような母ではない。
もう一度車出すのは面倒だわと、辺りをキョロキョロする母は、ふと真正面の店に目をとめた。
「あそこは?」
それは、古いラーメン屋だった。
営業しているかどうかもわからないくらい、小さくてボロい佇まい。
薄汚れた黄色いのれんに、赤っぽい字で「ラーメン」と書いてある、ように見える。
なんだ、ラーメン屋があるんじゃん、とはならなかった。
あるのは知っていた。
行くに値しないと思っていたのだ。
思春期の中学生だ。
もし友人に、母とふたりでオンボロラーメン屋に入るところなどみられたら?
むりむり、絶対次の日ネタにされる。
14歳のわたしは、それに耐えられるほど強メンタルじゃなかった。
あそこはいやだ、恥ずかしくて死ぬ。
「いやあ、あそこはないって。やってるかも分からんし」
ごにょごにょ反論すると、母はなぜかその言葉を無視して進み出した。
妙に張り切っている。
なんだ、意地か?
こういう入りにくい店にも、大人は難なく入れますというところを見せようとしてくれているのか?
それなら他でやってくれ、頼む。マジで。
そんなことは言えず、オロオロと不安な足取りでついていく。
近づけば近づくほど、おんぼろだ。
潔癖気味だったわたしは、ますます不安になっていく。
それに、まったく人気がない。
昼時だけど、閉店してる?
いやいい、むしろ閉店しててくれ!
しかしわたしの願いは届かず、母はその古い引き戸を勢いよく開いた。
ガタついた戸が、がらがらと大きな音を立てた。
中には、だあれもいなかった。
客はいない。が、電気はついている。
黙って戸の前に立っていると、右奥のカウンターから、フッと人影が現れた。
「いらっしゃい」
大きくも小さくもない声。
おじいさんの声だ。おばさんもいる。
湯気がもわもわと店内に漂っていて、表情はよく見えなかった。
二人の店員が見えたことで、母はそのまま敷居を跨いで、ずんずんと店内へ入っていった。
あわあわと続く。
母が黙ったままカウンターに腰掛けたので、隣の丸椅子にちょこんと座った。
そして、母がメニューを見る横で、俯いて制服のスカートを見つめた。
そもそも、この時のわたしは多分、カウンターに座るなんて初めてだった。
ラーメン屋には行ったことがあったが、いつもファミリー向けのお店ばかりで、お座敷にしか座らなかった。
客の出入りも多くって、店内はいつもわいわいにぎやか。
ところが、この店はどうだ。
だれひとりしゃべっちゃいない、静寂。
おじいさんも、おばさんも、ろくに会話はしてないし、テレビもラジオもついていなかった。
気まずいな。
なんだか、いたたまれない気持ちになって縮こまった。
そういえば母とも受験のことで揉めていたので、ふたりでの食事は余計気を揉んだ。
はあ。
なんでのこのこ来ちゃったんだろ。
お昼なんて抜いて、適当に飲み物でごまかして、そのまま図書館で過ごせばよかった。
くよくよとそんなことを考えながら、手元のスカートをいじっていると、母が「すみません」と声をあげた。
カウンター越しに、おばさんにいくつか注文をする。
何を頼んでもらったか覚えていない。
それぞれラーメンひとつずつと、あんた、餃子食べる?とか聞かれた気がして、うんともすんとも言えない返事をした。
餃子ひとつ、以上です。はい。
よく頼むわ、とおもった。
これで不味かったら、どうするんだろう。
おじいさんとおばさんが、私たちが食べるところをのぞき込んでくるのを想像して、うっとなる。
子どもの頃のわたしは、おとなの「失敗」を見るのが苦手だった。
立派なおとなが、自分の失敗を悲しそうにしていたり、残念な顔をしていると、自分事のように辛かった。
失敗するかもしれないことに、挑戦しようとするおとなも苦手だった。
なぜだろう。
父が昔、自分の会社で子ども向けの商品を展開したいと話してくれたときのことを思い出した。
精密な木のパーツを組み立てて、昆虫や乗り物がつくれるんだ、どう思う?
そのようなことを聞かれたとき、真っ先に「悲しい」とおもった。
お父さんが考えた商品が売れなくて、お父さんが悲しい気持ちになったらどうしよう。
そのことが不安でたまらなくて、「うーん、どうだろね」と曖昧に答えた。
父は、娘の手ごたえがないと思ったのか、その話はそれ以上しなかった。
数年後、別の店で木の組み立て式のおもちゃを見たとき、「これは、お父さんがやりたかったものなのに」と思った。
変な話だ。
わたしは、ただ応援してあげたらよかっただけなのに。
そうやって物思いにふけっていると、カウンター越しにラーメンがふたつ渡された。
母が受け取る。
これまた何年の前なので、どんなラーメンだったか覚えていない。
チャーシューとメンマとネギののった、すごく普通の醤油ラーメンだった気がする。
メンマが苦手なので、いやだなと思ったことだけ覚えている。
べつに、不味いとは思わなかった。
続いて、餃子だ。
楕円の白い皿に並んだ餃子がひとつ、渡された。
先に言うと、これが、タイトルの「激うま餃子」になる。
なんで、あんなに美味しかったんだろう。
今でもあの日の衝撃を覚えている。
母と同時に箸でつかんで、何も考えずにぱくっと食べた。
そして、衝撃。
「え!?」思って母を見ると、母もこっちを見返したところだった。
勢いよく顔を見合わせたわたしたちは、口の中の餃子を飲み込んですぐに叫んだ。
「めっちゃおいしい!」
母の目が、まんまるに開かれていた。
え!?
なにこれ、めっちゃ美味い!!
正直、ラーメンに大したインパクトがなかったので、餃子もまったく期待していなかった。
ふたりで思わず顔を見合わせるくらい、とても美味しい餃子だった。
かじった餃子の中をのぞく。
ひき肉とニラと、そして刻まれた透明の細いもの。
これは、「春雨」だ。
「春雨が入ってる!」
さっきは少し大きな声が出たので、今度は意図的に小声にしながら、しかし興奮気味に母をこづく。
「春雨、まあほんと」と母ものぞく。
ニラの風味と春雨の食感がとてもマッチして、ジューシーで、食べやすい味だった。
わたしたちは、ラーメンそっちのけでぱくぱくと餃子を食べた。
5,6個あった餃子だが、あっという間に、たいらげた。
おじいさんと、おばさんのことなんて、すっかりさっぱり忘れていた。
「きたなシュラン」なんて言葉があったけど。
この頃のわたしは、古くて汚い店ほど美味い、なんてツウな感覚は持っていなかったし、今のようにひとりでお店に入ることもできなかった。
でも、確かにこの時、このラーメン屋で、わたしはほんの少し成長した。
おんぼろラーメン屋で食べた春雨入りの餃子は、わたしの固定観念を少し払いのけ、母への尊敬度を少しだけ上げた。
それだけだ。でも忘れられない。
今思えば、ほんとうに美味しかったのか自信もない。
おんぼろの店構えのわりに、というフィルターがかかっていたのかもしれないし、母との気まずい空気を何とかしたいあまりに、味覚がおかしくなっていたのかもしれない。
あれから、このラーメン屋がどうなったのか知らない。
見てもいないし、行ってもいない。
それでも、ニラの隙間にのぞいた細切れの春雨を、わたしはずっと覚えているのだ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
