
知識と知恵
イノベーションを起こすためには
今までのやり方を変えよう、知恵を出そう、このままではだめだ、イノベーションを起こそうという時にさて何をしたらよいのでしょうか。
かなり以前、東北大学名誉教授の西澤 潤一さん(半導体デバイス、半導体プロセス、光通信の開発で独創的な業績を挙げた。半導体関連の特許保有件数は世界最多)が書いていらっしゃた新聞記事を読んで感銘を受けた事を覚えています。
内容をうろ覚えですが、次のような内容だったと思います。
「知識は必要だ。頭に入れた知識をベースにそれぞれがどう結び付くのか、ヒントがないか考えることで、個別の知識がネットワーク化されていくのが「学問」。
受験勉強のように知識を丸覚えすることを強化すると創造性は阻害される。」

新しい知を生み出す
イノベーションの父と呼ばれる経済学者ジョセフ・シュンペーターも「ニューコンビネーション(新結合)」として、「既存の知」と別の「既存の知」の新しい組み合わせが、「新しい知」を生み出すと提示していますし、著書『イノベーションのジレンマ』で有名なクレイトン・クリステンセンも、イノベーションを「一見 、関係なさそうな事柄を結びつける思考」と表現し、シュンペーターの概念を引き継いでいます。
このイノベーションの例としてよく上がるのが、トヨタのかんばん方式です。
これは、トヨタ生産システムの生みの親である大野耐一氏が、アメリカのスーパーマーケットの仕組みを人づてに聞き、それを自らが目指す「ジャスト・イン・タイム」の生産に応用できると考えたときからスタートします。
ヤマト運輸の「個人の宅配に絞り込む」という着想も、吉野家の「牛丼単品で勝負する」から得たことも有名な話です。
結局、全く何もないところから新しいものを生み出すのは一握りの天才であり、多くは知識の転用というのが知恵なのだと思います。
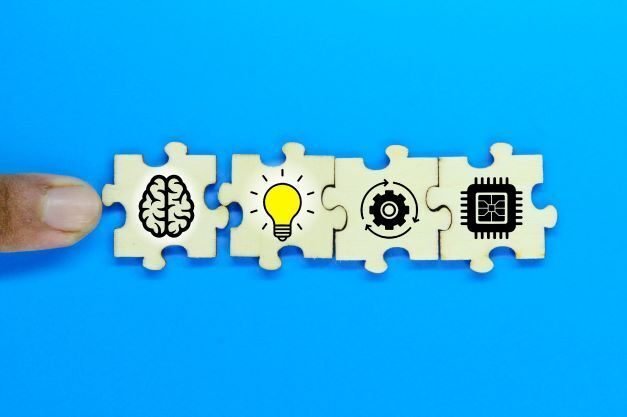
知の深化と知の探索
では、これを企業ではどうやって活かしたら良いのか。
経営学では「「知の深化」と「知の探索」をバランスよく行う企業の業績が良い。」とされています。
「知の深化」とは、今やっていることの知を継続して深めることであり、短期的に見れば効率性に繋がります。ノウハウの蓄積や改善活動がこれに該当するでしょうね。
一方、「知の探索」とは、「知の範囲」を広げることであり、一見無関係と思われる知識を収集しそれをイノベーションにつなげるものです。
しかし、これは即効性があるものではなく、しかもムダやロスが発生するというデメリットがあります。
従って、一般的には「知の深化」は熱心に行われるものの、「知の探索」をあまり行われません。せいぜい、行われているのは即効性を求めた「同一業界の先進的な取り組み」の収集ぐらいでしょうか。でもこれでは後追いでイノベーションとは言えないでしょう。
この「知の探索」とイノベーションの話は私が好きな話です。
結局重要なのは、好奇心だと思っています。
即効性になるものだけでなく、好奇心を持って知を探索する事、その上で何か自社の役に立つヒントはないかじっと考えることが必要だと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
