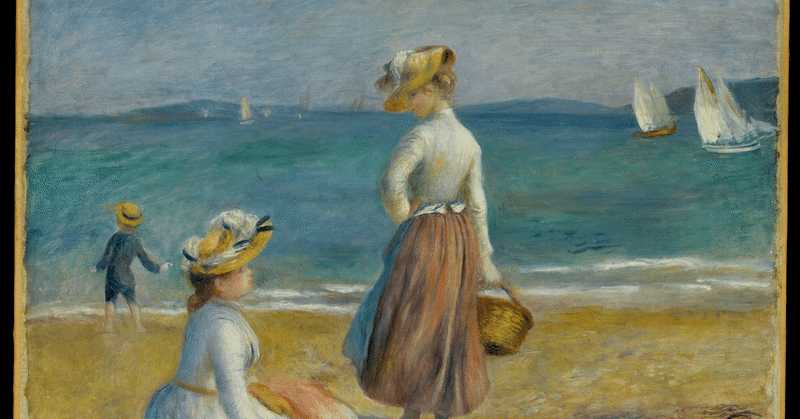
000:雨の日の朝食【ユーメと命がけの夢想家】
目次
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
寒いな、と、思うのだった。
そのあとで、自動車が水たまりを過ぎる音を耳にする。いや、逆か。この音を無意識のうちに聞くからこそ、世界は寒くつめたく冷ややかで、どうしようもないことを知るのだ。
うっすく目を開けてみると、再生を終えた動画のリンク欄があった。布団の脇に、仕事道具として手に入れたノートパソコン。それと半身をベッドから投げ出すような格好で放られているワイヤレスキーボード。ひっくり返ったマウスがひとつ。こめかみの痛みは、かけっぱなしの眼鏡のテンプルのおかげさまか。
今朝もまた、寝落ちをしたということか。小説を書くための資料あさりを日課とする僕の部屋は、ベッドで寝たきりでも機能するように設計してある。枕元には学習机に付属した椅子が置かれている。座るのは僕の尻ではなくて、原稿を印刷するためのプリンターだ。ノートパソコンはその上に置かれている。飲み物や保存食は窓の枠板に置く。この構成を発見したときは、それはそれは自らのことを天才だと思えた。
おかげで、休日は目覚めてから寝落ちするまでの時間を、余すことなく利用することが可能となった。
名作アニメを一気に観ることで、人物描写と作品構造の理解が深まる。学術的な解説動画に入り浸ることで、知識の裾野をひろげることができる。情熱の籠ったレビューが数多く書かれたゲームに没頭することで、プレイヤー……小説における読者の没入感を体験できる。机に山積みの本にまで手を伸ばすのは億劫であるけれど、床に置かれた本になら手を伸ばせる。当然、読書はなににも替えがたい最上の学びだ。
これらすべてを、文字通り一歩も動かずして可能なのだ。
三連休一日目の本日、閉めきられた戸の先から天気を窺い知ることはできないが、そんなことはどうでもいい。ただ、延々稼働をつづける暖房によって、部屋は極度に乾燥していた。ドライマウス気味で、なおかつドライアイがゆえに、飲み物を含んでも一向に回復の兆しはない。まばたきするのも、呼吸するのも苦痛であった。
これでは資料あさりもままならない。
あたたかいものでも、適当につくるか。
料理なんて呼べるような代物じゃない。僕が「適当につくる」ものといえば、以前は、味噌と鰹節とニンニクとショウガと、気分によっては卵を落とした混合物に、沸騰した湯を注いでかき混ぜたものが主だった。腹を満たしたい場合は、これに解凍した白米を投じる。うまい。
ただ、最近は別の味に浮気中だ。
きっかけは、noteで見知った梅干し燗だ。熱燗と梅干し。うまくないわけがない。
早速嗜もうと思ったのだが、窓枠の酒置き場にあるのはウィスキーだけであった。ものは試しだと、ウィスキーとお湯を1:1で割り、そこに梅を2つ入れたものを飲んでみた。ひどい味だった。
上記の反省を活かし、梅茶をつくりなおした。茶とはいうが、実際は梅にお湯を注ぐだけ。素朴な味わいに加え、上品な梅の香りをまとった湯気がたまらない。梅茶のとりこになった。
やがて今、素朴な味わいだった梅茶に、貝ひもとニンニクとショウガとビーフジャーキーを加えることで、濃厚なダシが全身をあたためる、究極の汁と相成ったわけである。
口も目もぱさぱさなまま一階へ降りた僕は、1リットルタッパーにブツを投入し、湯を注いだ。梅干しを見れば唾液が出るように、目も同時に潤ってくれればいいものを、なんてことを思いつつ、容器を持って二階へ戻った。ここ最近、階段を上り下りするだけでも一苦労なのは、寝たきり資料あさりの副作用だろうが、作品ができさえすれば、そんなもの、どうってことはないのだ。
早速布団に潜り、パソコン脇のワークチェアにタッパーを置く。かつてこれは執筆作業用の椅子であったが、机を使わなくなった今、これが我が部屋のダイニング・テーブルだ。水平にトレイを置けないのが玉に瑕だが、慣れてしまえばどうってことはない。
冷えた体をあたためるべく、梅茶といえなくもなくもない溶液を一口含んだ。湯気で眼鏡が曇り、貝ひもの旨味がきいた液が舌をひりつかせた。ジャーキーから溶けだしたこまやかな油によって唇はコーティングされ、ほう、と息をつくと、かすかなニンニクの香りが鼻から抜け、ショウガによって体温があがる実感がこみあげた。
角膜も潤う。マウスを握り、一日が始まる。
「さあ、あさるぞ」
「それは資料か? それとも死霊をあさるのか?」
中性的な声の問いかけは、ワークチェアの上端から聞こえた。
見上げると、椅子と天井のあいだにある空間に、人間のようなものが、あぐらを掻いて乗っかっていた。
「……つまらんシャレは、心のうちに留めておいたほうがいいぞ」
驚きの念は不思議と抱かなかった。普通、椅子の上方に鎮座する輩なんて不審者以外のなにものでもないか、あるいは自らの精神を疑うのものだが、僕にはどこか、この存在に覚えがあった。
物語を手掛けるにあたって、たびたび向こうから〈語りかけてくる〉ことがある。その影は様々で、ものごころついたころは、白い翼を生やした少女だった。小説を書きはじめてからは、その作品の主人公やヒロインや、様々な脇役たちが代弁者として姿を現した。もちろん、今回のように目の前に出没することなどあるはずもないが、それでも、なにかの拍子に現れることもあるだろうと、漠然と考えていたのだった。
つまり、僕の精神はおかしいのだ。疑うまでもない。自明だ。
「正論らしいことを言って逃げたつもりになっても、なんの意味もない」
ただ、今までの奴らとは、なにかが違う気がした。出没するだけでも充分〈違う〉のだが、本質はそこではなくて、嘲笑とかすかな敵意を感じるのだ。いや、奴らと意見が食い違うことはままあるわけで、それを〈敵意〉と呼べなくもない。
「わたしは、忠告をしに、君のところへ来たんだ」
忠告。物語から生まれたものが、そんなことを語りかけてくるだろうか。気迫というか、怨念というか、僕の外側のなにかが、これをつくりだしたのではないかと思ってしまうような、そんな〈異物〉感があるのだった。
「このままなにもせずにいるのなら、君は間違いなく死ぬ」
さらにそんなことを〈異物〉は言い放つのだった。
その表情は窺えない。髪が長いからとか、フードを目深にかぶってるとか、そういう話ではなくて、ぼんやりと輪郭が浮かぶだけの姿なのだ。まるで、人物設定を深めることなくボツにしたキャラクターみたいだ。
「死ぬってのはなんだ。物理的に死ぬっていうのか? それとも、作家生命的な意味でか?」
「作家生命!」
〈異物〉は手を叩いて笑い声をあげた。
「商業作家でもないのに。作家生命とくるか。それこそ心のうちに留めておいたほうがいいんじゃない?」
ひいひい腹を抱えている。ウケたようでなによりだ。
「でも……君さ、そんなことが愚問だってことは分かってるでしょ。作家生命だろうが、物理的だろうが、君にとってはイコールだ」
口にしたくなかったことを、平気で言葉にする。
小説を書けない自分なんて、生きてなどいない。死んでないだけなのだ。
「それと、『ウケたようでなにより』なんて思うのは、叱られた猫が顔を洗うようなもの。わたしの反応を受け流してるだけ。現在地点からの逃げグセがすっかりできあがってるってこと」
とにかく、その正論だらけの減らず口を閉じてやりたい気分になった。おとなげなくワークチェアを蹴飛ばしてそのまま椅子で殴り飛ばせば、少しは黙ってくれるだろうか。しかし梅茶をこぼしたくはないから、僕は黙って笑みを絶やさずにいた。
「このままなにもせずにいるのなら、僕は死ぬって言ったけど、不思議だな。確かに、少し前は本当になにもせずにいたよ。でも今はあらゆる資料を吸収している。書くことが怖いし、物語も人物も書けないでいる。でもだからこそ、学びの期間として貪欲になんでも手を出してるんじゃないか」
それとも出がらし状態のまま、空っぽの作品を乱発すればいいとでもいうのか。それこそムダなことじゃなかろうか。そんな作品にいったいなんの価値がある?
「その減らず口を閉じて、黙ってキーボードを叩けばいいものを」
マウスを握る右手が、汗で滲む。梅茶のショウガエキスのおかげだろう。
「よろしいかしら、君はそう言って、画面越しに砂金でもあるかのように熱が入ってるみたいだけど――」
「と、その前に」
〈異物〉の話が長くなりそうな気配を感じとったので、すかさず話を中断させた。
「君、なんて呼べばいい?」
「〈異物〉なんて仮称じゃ、わたしのことを誤解したまま話が進みそうだって、気付いたわけか。そうだろうねえ、わたしが〈異物〉なわけがないものねえ」
うんうん、と感慨深そうに頷いたあとで、奴は頬杖をしたまま唸った。
「どうせさしたる名なんてないけどね。そうだね、どうせ仮称を使うなら、このギトギト梅茶のなかで掻き消えてしまった梅のエッセンスから取りだそうか……。梅、うめ、UME、ゆーえむいー、ウメ……」
もごもごと口ずさむように、ウメと連呼したあとで、ひらめきを得たのか、合点をする。
「ユーメ。どう?」
世紀の大発見でもキメた教授の演技なのか、ユーメと自称するこれは、両手を腰に当ててえへんと胸を張った。
「UMEのユーメ、安直だな」
「このくらい安直なほうが、仮称っぽくていいでしょ。こういうのはシンプルなほうがいいんだよ」
名前はシンプルなほうがいい。その通りだ。特に長い作品を書くとしたら、ややこしい名前は覚えられない。人物の名前をタイピングする手前で、思い出す作業が生まれてしまう。覚えにくい名前は損失だ。自分なりの理由づけをしつつネーミングしたほうが覚えやすい。
で、だ。と、ユーメは本題へと戻る。
「君は画面の向こう側に、さも自分が求める理想郷があるかのように思ってる節がある」
ダンボール箱に詰めこまれた本や紙束の上に、ユーメは立った。ベッドにもぐる僕より、圧倒的高所から、ユーメは言い放つ。
「そんなの全部、ただの幻影だから」
幻影。まるで幻影のような輩から言われるのは、実に心外だった。
そんなもので僕を揺さぶろうと、変わる気なんて起きるはずもない。
「その証拠に、今、君が練ってる作品の状態、話してみ」
「新人賞用の原稿のことだな」
ユーメは頷く。
「魔力の源となる魔石が枯渇しかけた世界が舞台の、ファンタジー小説だ。主人公は採掘員か、あるいは運び屋の少年を考えている。そう遠くない未来に仕事もなくなるし、魔石も尽きることを悟っているから、主人公は厭世的なんだ。ただ、友人の誘いで鉱山に立ち入って、その最深部で物語は動きだす。主人公は、旧時代から眠りつづける少女と出会うことになるのだ……」
冒頭はベタな展開を念頭に、まずは読者の心をキャッチしたいと考えている。特殊な力を持つ少女は、鉱山の人々と交流をしつつも、やがてこの力をめぐり、対立が生まれてしまう。この作品を通して、僕はしっかりと見る、ということを描きたいのだ。目の前にいる、その人のことを、ちゃんと。
そして、そのためには、舞台に現実味を持たせたいと思っている。地球ではないまったく別の世界でも、僕や僕らと近しく思えるために、その世界の構造や歴史をひも解くところから始めていかねばならない気がしてならない。
「テーマと舞台設定先行。でも、肝心のストーリーと人物が手つかず、といったところか」
ユーメの分析は的確だった。「鉱山の人々と交流」とあるが、ではどんなエピソードがいいのか。なにも湧き出てこないのだ。
原因の一端は、ヒロインの少女の風貌も、性格も、ほとんどイメージできていないからだということは理解しているが、自分でも気味が悪いくらい、その掘り下げ作業ができない。どの地面もすべて岩盤で、いかほどに力をこめても、ツルハシが喰いこんでくれないような感覚なのだ。
おそらく今回の作品は、人物の性格や素性が物語の根幹にあると考えているからだろう。ストーリーがより具体性を帯びてくれば、自ずと的確な人物描写をすることができるだろうと思う。がしかし、ストーリーを描くには、登場人物に関する情報があまりにも少なすぎるわけであって、デッドロック状態に陥っているのだ。
だから、アニメを観、ゲームをプレイし、本を読むことで、様々な人物描写を学び、物語構造を叩きこみ、突破口を模索しているのだ。
「それ、本気で思ってる? このわたしと、こうして会話を試みておいて、まだそんな言い訳を続ける?」
腕組みしたユーメは、真剣そのものの口調でぼやいた。
「……まあ、だからわたしは来たんだけどね。君に、試練を」
ユーメは、人差し指をぴょんと立てた。
「毎週金曜夜10時に作品をひとつ公開する、これをつづけること。それができなければ、あなたは死ぬ」
「いや……待て」
あまりに一方的すぎる。冗談を聞いているみたいだった。僕は苦笑を浮かべてみたが、ユーメは腕組みを解くでもなく、じっと見つめてくるばかりだった。冗談でした、のドッキリネタばらしは、訪れる気配がない。
「毎週1本書きあげるだなんて……1週間なんて、舞台設定を考えるだけで終わっちまう」
「偉くなったものね。高校時代は、WEB上で毎週のように連載を更新してたくせに」
「あのときとは状況が違う。とにかく、1週間じゃ心弾むストーリーも、魅力的なキャラクターも作れやしない」
「今の君に、こだわりを持てるほどの猶予があると思ってる? つまらないプライドを守って、生命を終えた同好の士を、君はかつて鼻で嗤ったはず。今の君は、そのなかのひとり。違う?」
違う。
違う、と、言いたかった。
僕はちんけなプライドにしがみついて、現代の潮流を軽視して、世の中のなんでもに唾を吐いて自己満足する頭のかたいおじさんになんて、なってません。
そう、言ってやりたいのに。
「もの書きにとってなにより大切なのは、心弾む物語を書くことでも、魅力的な人物描写でもない。書きつづけるということ。君は最も大切なことを、4年前から……いや、10年前から、怠っている」
「あれはまだ未熟で、情熱にうなされてただけなんだ」
「今も未熟でしょ。あのころから商業作家を目指してるくせに。立場はなにひとつ変わってないくせに。現状でも仕方がないって口実だけ達者になってる自分自身が、惨めで仕方がないくせに。それでもなお、熟練者を自称する? 見苦しいったらない」
「それなら、出来の悪いストーリーに、魅力の欠片もないキャラクターを世の晒していいっていうのか?」
「いくらでも晒せるでしょ。君は小学時代に書いた処女作を世に晒せるだけの精神がある。それでも、『あれは昔の作品で、今は違います』ってフィルターをかけた人でなくちゃ読まないでくれって懇願でもする? 最新作がいいもので、次回作はそれをさらに上回る傑作で、それじゃあクオリティは右肩上がり、読者の期待も比例して増していく。そのプレッシャーに圧し潰されそうで、一歩が踏みだせない」
「僕はただ、いいものに仕上げたいんだ」
「いいえ、仕上がるはずがない。だって今の君、〈資料あさり〉と称して得てる物語のなかで、主人公が成長して、最後の試練にうち勝つシーンを見るたび、気味悪いと感じているでしょう? 成長の見込めない自分からしてみれば、成長する主人公なんて、異種族で異形で特異体以外のなにものでもないもの」
「気味が悪かろうが、書くしかないだろ」
「そう。書くしかない。書きつづけるしか、もうないの。で、君は書いてるの?」
「書けないから困ってるんだ」
「書けないんじゃない。書きつづけるの」
目の前の彼は、あるいは彼女は、きっぱりと言い放った。揺るぎない信念の濃縮されたもの言いのくせに、言葉のサラダみたいに、喉を通らない。
「ユーメ、お前の言ってること、めちゃくちゃなんだけど」
「いいえ、狂気でもなんでもなく、理路整然と伝えてるだけ。書きつづけないと書けなくなる。書けないのなら、書きつづけるしかない。他に方法があると信じて日々を過ごした君が、唯一していない、たった一つの修羅の道」
「それをしてしまったら、クオリティが――」
「君の言い訳に付き合うのも疲れてきた」
ユーメは、僕の言い分を却下した。
「いい? 週に1本、作品を完成させるだけなの。クオリティなんて求めない。長さだっていくらでもいい。テーマは『お題.com』から引っ張りだして、得意の天邪鬼で物語をこねくり回せば、できるでしょ?」「じゃあ駄作を量産するとして、いつまで続ければいい?」
「さあ? 書きつづけることが日課になるまでじゃない?」
そんな無茶な。こんなのを続けてたら、新人賞用の原稿に埃がたまる。
「これを日課にして、そのうえで新人賞作品も書けばいいでしょうに」
「よく言うよ!」
「無茶な注文だって思ってる? 嘘つき。書きあげた作品を題材にすることだってできることくらい、君なら知ってるはずだ。わたしと酌み交わす会話ですら、次の作品の伏線になりうる。村上春樹だって、短篇や中篇の作品のエッセンスをもとに長篇を書いている、みたいな話を聞いたことがあるはずじゃないの?」
もちろん、春樹の話は知っている。春樹好きの友人に直接問うたことはないし、文献で見つけたものではないと思うから、確証は持てずにいるけど。
「イチローって知ってるでしょ? イチローは天才だ、なんてもてはやされるけど、実際はたくさんの努力を重ねた結果だって話。そして、イチローはこう言った。『苦しいことでも、続けることが大事なんです。続けることで、いつかそれが苦しくなくなる。苦しくなくなってもなお続けるということが、日課なんです』って。君がこれから彩る〈日課〉を、新人賞にぶつければいい」
「……そのイチロー、出どころはどこだい」
「私が勝手に考えたことだって、分かってて言ってるでしょ。ドラマチックに明かす必要なんてないよね。わたしはあなたの分身なんだから」
あきれるひまもなく、ユーメは続ける。
「少し前にボツにしたネタがあったでしょ。あれはたしか、この夏、失意のどん底にいたときに書き記したネタ。イマジナリーフレンドと文通をするだけの、読者を想定しない物語。あれとおんなじようなものを、こうして再利用しようってわけ。突然思い出せてよかったじゃない」
そういえばそんなものもあった。しかし、設定を考えるだけでむなしさが増していき、結局2日で放りだしてしまった。
確か、放りだしてしまったはずだ。
無性に気になってGoogleドキュメントを開いてみると、思いのほか下のほうに『中年男子とイマジナリーフレンド』と銘打ったデータが眠っているのを見つけた。4500字程度で、冒頭の断片のみ。
今の今まで……ユーメが持ち出すまで、メモを残していたことすら忘れていた。
奴はいわばイマジナリーフレンドであり、自分自身であることは疑いようもない。ただ、ときどき僕の自意識の外側にあるものまで引っ張りだしてくる。それはまるで、執筆中の人物が、僕の想定外の行動をしはじめるのとよく似ている。自分の分身のようにも思えるし、他人のようにも思える。
意識と無意識を包括するもの。
君であり、僕でもある。
それはまさしく、ユメ、そのものじゃないか。
……僕の夢は、物語を書いて、それをひとりでも多くの人に伝えることだ。商業作家になることはその近道だ。でも、そこからずっと逃げつづけてきた。かつては、力が不足していたからだと考えた。でも今は、力が不足していると言い聞かせながら、その実、書きつづけることに自信が持てずにいるから、挑戦をおそれていた。
書きつづけるには、書きつづけるしかない。
10年逃げつづけてきた僕だから断言できる。A=A構文のなかに燦然とかがやく、たったひとつだけの、真理だ。
耳ざわりのいい他の理由を述べた文献があるとしたら、それはすべて逃げか、罠だ。
だから書きつづけることができなければ、死を選べと、ユーメは言うのだ。
「……分かった」
どのみち、言い訳なんて通用する相手ではない。生きるか、死ぬかだ。死んでないだけの状態なんて甘ったれたことは、少なくとも自称すべきではない。
すっかり放置された梅茶汁を飲んだ。冷えたからだろうか、他の味よりも、梅の酸味がよく出ているように思えた。
もぞりと布団から抜けた。文庫だらけの学習机の前に立ち、山積みになった資料を床へ押しやった。
「やってやる。本当は死んでないだけの自分に、嫌気がさしてたところなんだ」
こうして僕は、アマニュアで貧相なもの書き生命を賭して、物語を書きつづけることを決めた。
テーマ:雨の日の朝食
「お題.com」(https://xn--t8jz542a.com/)より
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
次回
目次
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
