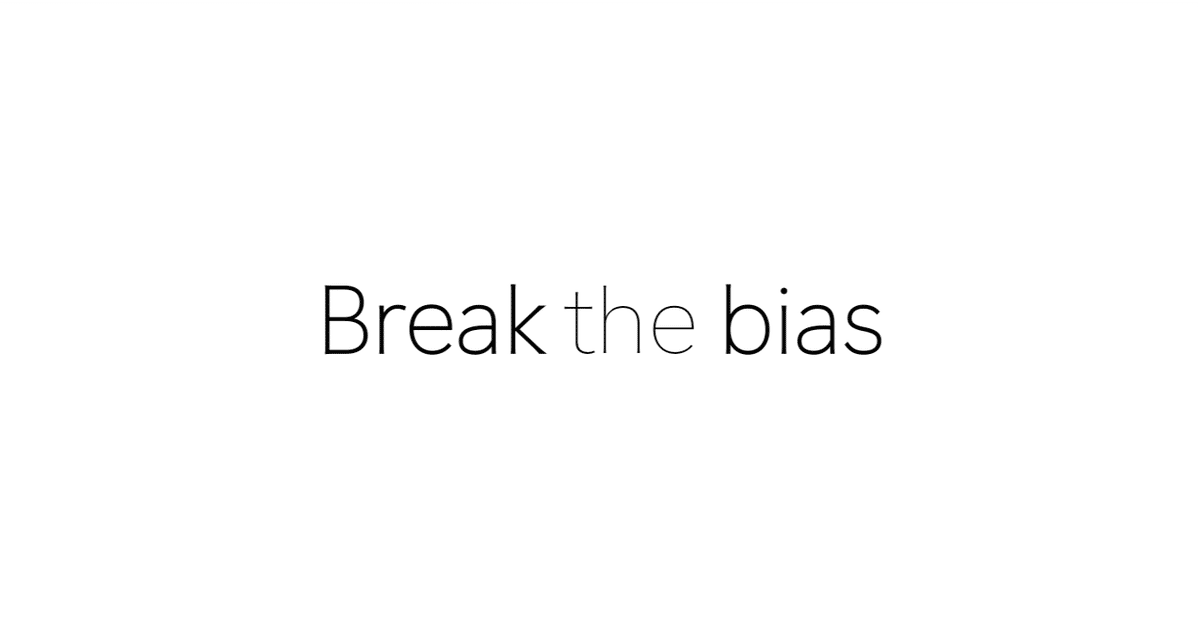
仕事でもプライベートでも影響を受ける!知っておきたい「バイアス」の話。
ある男が、自分の息子を「車」に乗せて、自ら運転をしていた。残念なことに、その「車」はダンプカーと激突して、大破してしまった。
救急車で搬送中に、運転していた父親は死亡。息子は意識不明の重体。あまりに悲惨な事故だった。
救急病院の手術室で、運びこまれてきた後者の顔を見た外科医は息を呑む。そして、つぎのような意味のことを口にした。
「自分はこの手術はできない、なぜならこの怪我人は自分の息子だから」
これはいったいどういうことか?
引用:なぜ「外科医」は手術ができなかったのか?
こんにちは!
今回は仕事をする上でもプライベートでも知っておきたい「バイアス」についてのお話です。
忙しい方のためにざっと内容をまとめておきます。
・バイアスっていうのは偏見のことで、だれもが絶対持ってるもの
・バイアスに影響を受けるのが普通だけど、影響を受けたままだと損する
・バイアスの種類を知っておくことで、バイアスの影響をギリギリまで下げる
バイアスはだれでも持っている
冒頭の問題、あなたは解けたでしょうか?
ぼくは最初にこの問題を見たとき、脳細胞が溶解する勢いで考えましたが、さっぱり意味がわかりませんでした。
さきに回答をお伝えすると、「外科医は母親だった」が答えです。
おそらく、わからなかった方の多くは「外科医 = 男性」と認識をしていたはずで、これこそまさに「バイアス」の影響を強く受けてしまっているよい例だったりします。
これまでの人生経験から、なんとなーく「外科医 = 男性」というイメージがついているわけですね。
ほかにも、たとえば「消防士」ときくと「筋肉がすごい」とか「男性」というイメージがありますし、「新体操」ときくと「体が柔らかい」とか「女性」みたいなイメージがあります。
「偏見」ともいえますが、べつに悪いことではありません。「バイアス」っていうのは誰もがかならず持っているものです。それがふつうで、むしろ完全に排除することはできません。
とはいえ、バイアスの影響を受けすぎてしまうと、仕事においてもプライベートにおいても自分が損をしちゃうので、注意が必要でもあります。
バイアスの影響でひとを見誤る
どんな損をしてしまうかひとことでまとめると、ひとを見誤ります。その人の本質が見えなくなっちゃうことが多いんですね。
例をあげてご説明します。
たとえば、「ハロー効果 / ホーン効果」というバイアスがあります。
・ホーン効果 / ハロー効果
物や人の悪い特徴が原因で、因果関係がないことにも否定的な評価をしてしまう認知バイアスのこと。
「第一印象でその後の判断を決めちゃう!」みたいなバイアスなんですけど、仕事でもプライベートでも影響を受けやすいです。
たとえば、ぼくがいま住んでいる物件への引っ越しを考えていたとき、物件紹介をしてくれていた不動産会社の人が、スーツ靴のかかと部分を踏み潰して歩いていたんですね。
で、靴のかかとを踏み潰して歩くような人は、紹介する物件も適当なんじゃ…?みたいな印象をぼくは受けます。
もちろん性格が見た目に現れることは多々あるのですが、「靴のかかと踏み潰す」と「紹介する物件」にはなんの関連性もないにも関わらず、「この人は靴のかかとを踏み潰して歩いているから適当な人だ!」と決めつけちゃうわけです。
話してみるともしかしたらすごく丁寧でちゃんとしてる人かもしれないのに…。
逆もまた然りで、すごく爽やかで好印象を持てるひとだったから「このひといい人!」って判断したけど、実は詐欺師だった…!! みたいなパターンもあり得ます。
これが「ハロー効果 / ホーン効果」の影響です。
こんな感じで、ひとを「決めつけ」で判断しがちになると、話してみるとすごくいい人で親友になれたかもしれないのにスルーしちゃったりとか、間違って騙されたりすることも出てきます。
ということで、人付き合いをする上ではなるべくバイアスの影響を下げた方がお得です。
さらにあと二つほど、知っておいた方がいいバイアスがあるのでご紹介しておきます。
「確証バイアス」と「親近感バイアス」
・確証バイアス
自分にとって都合のいい情報にのみフォーカスし、そうでない情報を軽視してしまう傾向のこと。
確証バイアスは、自分の判断を正当化したいときにとらわれがちなバイアスです。
たとえば仕事でいうと、Aというプロジェクトを進めるにあたって、「うまくいく派」と「うまくいかない派」に分かれたとします。
「うまくいく派」のひとは「うまくいく根拠」だけを集めがちですし、「うまくいかない派」のひとは「うまくいかない根拠」だけ集めがちです。
こうなると、問題に対して的確なアクションが打てなくなります。
Aというプロジェクトを進めること、否定すること自体が目的になっちゃうわけです。
本当に大事なのは、Aというプロジェクトがうまく作用するかどうかなので、これも本質を見失ってしまっているといえます。
本来の目的や問題点と照らし合わせて、Aというプロジェクトが的確なのかを、うまくいく、うまくいかないの両方の視点から見ていく方がいいですね。
・親近感バイアス
自分に似ている人を好意的に評価すること
自分と似ている人には好感を持ちます。
たとえば海外で日本人と会うと、謎の好印象をもったりしますし、県外で地元の方言をきくとなんだか嬉しくなります。
でも、その人の人間性とここで感じた好印象はまったく関係ありません。
「類は友を呼ぶ」とはいえども、自分と違うからこそ学べることは多いはずですし、自分の周りを自分と似た人だけで固めるのはちょっともったいない気がします。
こういうところでこそ「多様性」を重んじていきたいですね。
というわけで
・バイアスっていうのは偏見のことで、だれもが絶対持ってるもの
・バイアスに影響を受けるのが普通だけど、影響を受けたままだと損する
・バイアスの種類を知っておくことで、バイアスの影響をギリギリまで下げる
バイアスはうまく取り入れることで得することもできます。
「ハロー効果」を活用して、清潔感と笑顔を徹底すれば相手に好印象をもってもらうことができますし、「親近感バイアス」を利用して、相手と仲良くなることだって可能です。
何かしらの判断をするときにはバイアスの影響を下げる、判断してもらうときにはバイアスを活用する (もちろん悪用はダメ) ぐらいでいいかもしれないですね。
バイアスに振り回されないように気を付けていきましょー!
P.S.
バイアスについて調べていたら、メルカリさんで利用しているらしいバイアス資料が見つかりました。
すごい参考になったので、よければご覧になってみてください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
