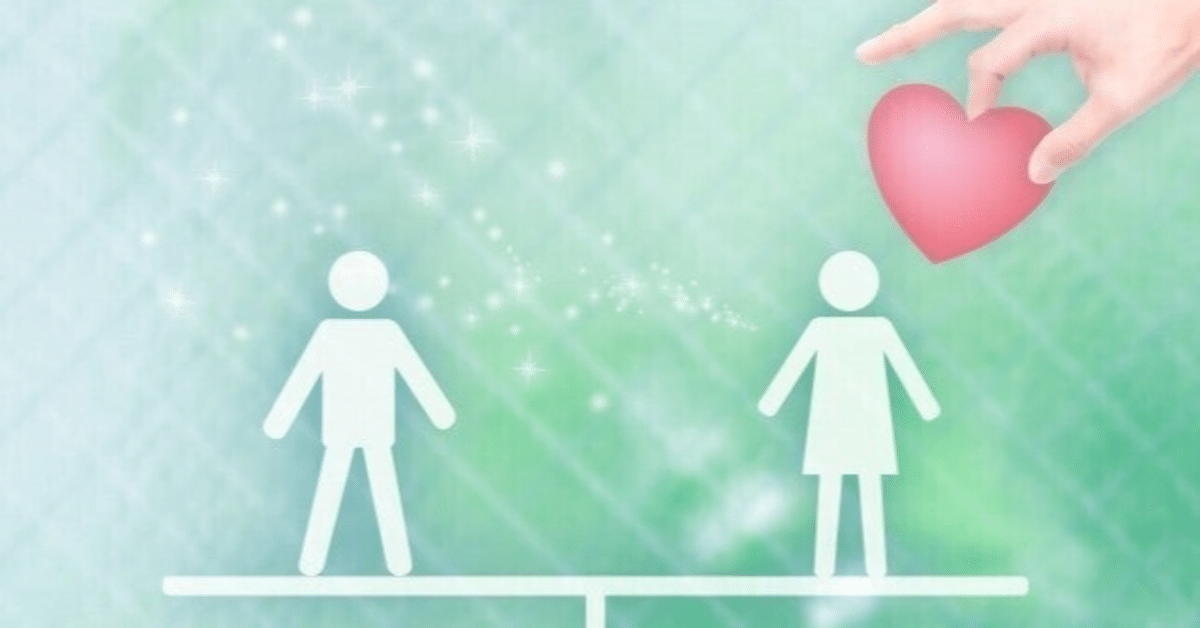
ただ知るだけで優しくなれることもあるかもしれない
☑︎ バランスよく食事を摂らない。食べるのはいつも卵焼きとウインナーだけ
☑︎ 買い物先のスーパーでは、落ち着きがなく、奇声をあげながら店内を走り回る。あげくには生鮮コーナーに売られている鮮魚を発泡スチロールごとひっくり返す
☑︎ すれ違った子の首を絞める、噛み付く
もし、こんな子どもさんを見かけたら、これまでのぼくは内心こんなふうに思っていたかもしれません。
「ぜんぜんバランスよく食事できてないじゃん。卵焼きとウインナーしか食べないとか栄養偏りすぎじゃない?親御さんはあまり子供の健康に気を使えないタイプなのかな。将来どうするつもりなの?」
「子供だからある程度落ち着きがないのはしょうがないけど、スーパーであれだけ暴れ倒すのはさすがにちょっとよくないでしょ。たぶん、普段からあまり叱ったりできてないからあんな感じになっちゃうんだろうな」
「人の子にわけもなく暴力振るうって、どこの組のもんじゃわれェェ!! 非魔倭離組だとコルぁぁあ!!」
そして今・・・。
ぼくは、そんなふうに考えていたかもしれない「おっせかい視野狭クソ野郎」な自分を、魔封波で電子ジャーに未来永劫とじこめてやりたくなっています。
なんなら魔封波かます前に、魔貫光殺砲で穴だらけにして、空中で爆発させ、「きたねぇ花火だ」なんてこの世の暴言という暴言をHPゼロになるまで吐き尽くしてやりたいとすら思っています。
きっかけは、ある友達に紹介してもらったこの本を読んだことです。
今回は、「知ることで優しくなれることもあるのかも」と思った話をしたいと思います。
自閉スペクトラム症の行動を見てどうするか
「ムーちゃんと手をつないで~自閉症の娘が教えてくれたこと~」は、自閉症のお子さんをお持ちの作者さんが書いている漫画です。
自閉症、という症状について、いまぼくがもつ知識はほとんどありません。
病気と呼んで良いのか、障害と呼んで良いのか、症状と呼んで良いのか、その呼び方すらわからない、というのが本音です。
なので、調べてみました。
自閉症は、正確には、アスペルガー障害・広汎性発達障害とともに「自閉スペクトラム症」と呼ばれる疾患概念らしいです。
自閉スペクトラム症は従来、自閉症、アスペルガー障害、広汎性発達障害などと呼ばれていた疾患を含む疾患概念になります。
対人関係が苦手だったり、特別強いこだわりを持っていたり、言葉の発達が遅れる、という特徴があるといわれています。
最近の調査では、20 ~ 50人に一人が自閉スペクトラム症と診断されるとのこと。
冒頭であげた 3つの例は、傾向として自閉症の可能性があるお子さんの行動、といえます。(もちろん違う可能性もありますが)
でも、そういうのって、知識として知っていない場合、多くの人は「しっかり教育がされていない」とか「変な子だ」みたいな捉え方をしてしまいそうです。
仮にですが、ぼくが実際に冒頭の例を目撃した場合、やっぱり「ちゃんと教育がされていないのかも・・・」みたいな捉え方をしてしまうと思います。
自己弁護するわけじゃなく、すこし冷たい言い方になってしまうんですが、これってある程度しょうがない部分もあるとは思っていて、たとえば、行きつけのスーパーで野菜や魚をしっちゃかめっちゃかにしている子供をみて、すぐにその子が「自閉症のような症状を持っているのかも」と背景事情を想像するって、なかなかハードルが高いと思うんですね。
多くの人が、その行動にネガティブなイメージを抱いてしまうのも理解はできますし、責めることはできません。
ただ、それってちょっと寂しいことだなとも思っていまして。。
というのも、知識さえ持っていればもっと優しい見方ができるようになるはずだ、と思うからです。
「知っている人」と「知らない人」では捉え方が変わる
「7つの習慣」という本に「パラダイムシフト」という考え方が紹介されています。
ある日曜日の朝、ニューヨークの地下鉄で体験した小さなパラダイムシフトを、私は今も覚えている。乗客は皆黙って座っていた。新聞を読む人、物思いにふける人、目を閉じて休んでいる人、車内は静かで平和そのものだった。
そこに突然、一人の男性が子供たちを連れて乗り込んできた。子供たちは大声で騒ぎだし、車内の平穏は一瞬にして破れた。男性は私の隣に座り、目を閉じていた。この状況に全く気付いていないようだ。子供たちは大声で言い争い、物を投げ、あげくに乗客の新聞まで奪いとるありさまだ。迷惑この上ない子供たちの振る舞いに、男性は何もしようとしない。
私は苛立ちを抑えようにも抑えられなかった。自分の子供たちの傍若無人ぶりを放っておき、親として何の責任も取ろうとしない彼の態度が信じられなかった。他の乗客たちもイライラしているようだった。私は精一杯穏やかに、「お子さんたちが皆さんの迷惑になっていますよ。少しおとなしくさせていただけませんか」と忠告した。
男性は目を開け、子供たちの様子に初めて気付いたかのような表情を浮かべ、そして、言った。「ああ、そうですね。どうにかしないといけませんね… 病院の帰りなんです。一時間ほど前、あの子たちの母親が亡くなって… これからどうしたらいいのか… あの子たちも動揺しているんでしょう…」
その瞬間の私の気持ちが、想像できるだろうか。私のパラダイムは一瞬にして転換してしまった。突然、その状況を全く違う目で見ることができた。違って見えたから違って考え、違って感じ、そして、違って行動した。今までのイライラした気持ちは一瞬にして消え去った。自分の取っていた行動や態度を無理に抑える必要はなくなった。私の心にその男性の痛みがいっぱいに広がり、同情や哀れみの感情が自然にあふれ出たのである。
冒頭の自閉スペクトラム症の子供の例も、この体験に少し近いものがある気がします。
同じ行動であっても、「事情を知るもの」と「事情を知らないもの」では捉え方が変わりますし、捉え方がかわれば、その出来事によって引き起こされる感情も変わります。
それは子供や両親を見る際の視線や、自分自身の行動にも影響を及ぼすはずです。
「ただ知る」だけでもきっと視線は優しくなるし、「何してるのあの子…」「親は何やってるの…」ではなく「大丈夫ですか?」といった言葉が出てくると思います。
別に自閉スペクトラム症に限らず、世の中にはたくさんの病気や障害がありますし、もっというと理解できないと思っていただれかの行動の裏側にも、隠されている事情があるのかもしれません。
表面の行動だけをみてそのひとを知った気になって話をするのは、避けた方がいいかもしれないですね。
というわけで
直近で自閉スペクトラム症関連の症状について考えさせられる機会があり、自分の思考をまとめるために書きました。
学生時代、勉強っていうのは「教科書を丸暗記することだ」的な認識を持っていたのですが、本当の勉強っていうのは「知識を得て、得た知識を活用し、Love & Peace な世界を広げていくこと」なのかもしれません。
結局、「知ったってなにもしないならおまえの自己満足じゃねーか!」という気もするし、「きれいな言葉を並べて人からよくみられたいだけじゃねーか!」という気もします。
知るだけでちょっとでも優しい捉え方ができるようになるなら、偽善丸出しシンドローム状態でも、もっとたくさんのことを勉強していきたいと思いました。
世の中のすべてではなく、身近で起きたことについてだけでも良いので、もっと勉強して、まずは身近なひとに優しくいられる自分を目指すことにします。
もし、ぼくが「おっせかい視野狭クソ野郎」になったときは、ぜひ魔貫光殺砲で貫いてください。
それではまた!
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
