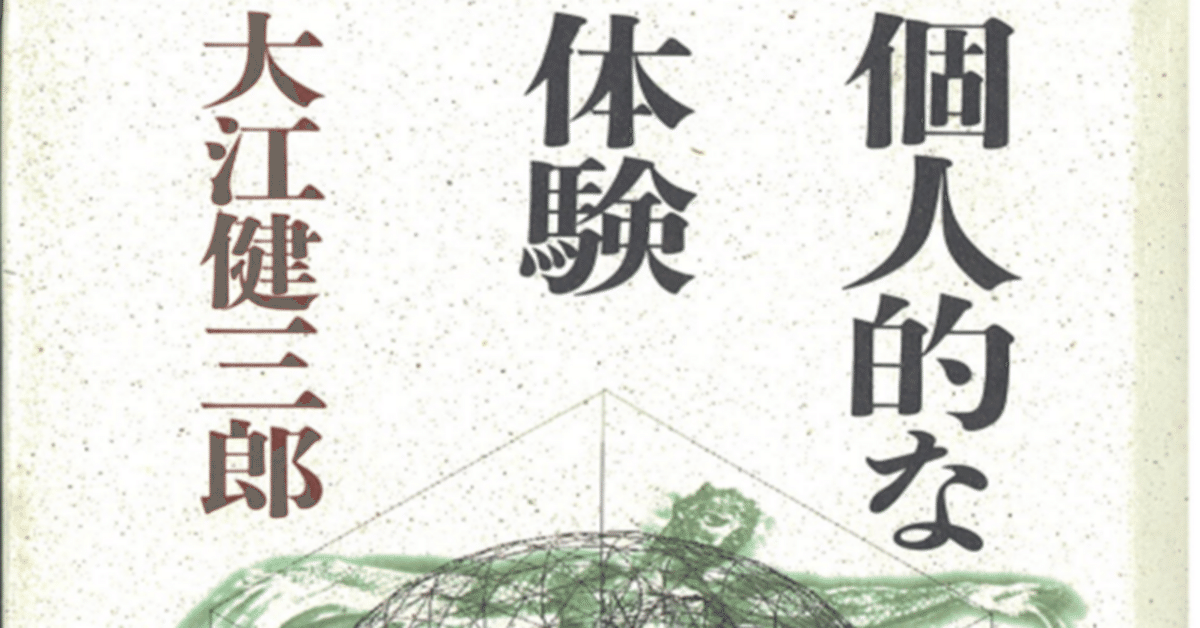
本の風景「個人的な体験」大江健三郎(1964年)
神話のはじまり

大江健三郎(1935~2023年)が旅立った。88歳だった。四国の谷間の村に生まれ、東亰大学時代に『飼育』(1958)で芥川賞を受賞。そして、文学的にも政治的、社会的にも戦後世代としての発言を強めていった。25歳で結婚。長男の誕生(1963年)。ここから大江文学の「神話」がはじまる。
現物
「まず、現物をみますか」・・・。「バード」というまだあだ名で呼ばれる主人公の初めての子供だった。「外観見たところ頭がふたつあるように見えますよ」。赤んぼうは「巨大な頭に包帯を巻いた怪物」だった。彼はやり場のない自身への「嫌悪感」に襲われる。状況を妻には知らせずそのまま病院を飛び出す。そして大学時代の友人の「火見子」のところに転がり込んで、泥酔する。翌日再び対面した赤んぼうは、「ほんとうに恐ろしい吐き気」をもたらした。次の日、脳外科へ搬送される救急車の中で、赤んぼうの「ミルクの量を減らして、砂糖水に変える」ことによって、赤んぼうの自然死を医師に依頼する。その時のバードは「赤っぽい暗闇」に包まれる。彼は思う。「女友達を殴りつけ、失神させて性交しよう」と。
バードは赤んぼうの死を待ち続ける。しかし待ち望んだ電話が伝えたのは、健やかに成長する赤んぼうの手術の予定だった。バードは慌てる。驚く医師団を前に、バードは赤んぼうを無理やり退院させ、二人は、火見子の知り合いの産科医に赤んぼうの死を依頼する。バードは自問する。「おれは…いったい何をまもろうとしたのか?」。自分の手で直接赤んぼうを殺さずに逃げ回る、自身の「欺瞞」に突き上げられる。バードはその場から立ち去り、赤んぼうと生きていくことを選ぶ。退院の日、義父は言う、「きみにはもう、バードという子供っぽい綽名は似合わない」と。
異世界

三島由紀夫は、『個人的な体験』を、「暗いシナリオは明るい結末をあたえなくちゃいかんよ、と命令する映画会社の重役みたい」と、ハッピーエンドの私小説と評する。しかし『個人的な体験』は彼の文学的スタイルの、まさに、その始まりであり、第1章であった。
「個人的」、「私小説的」物語でありながら、そこには異世界が容赦なく入り込む。たとえば火見子との執拗なセックスには、彼女の肉体の描写は無く、彼女の子宮とオーガニズム、僕のペニスが執拗に語られる。その宇宙は「死」につながり、「死」を望み、その「死」が僕の「欺瞞」を暴く。それは、その後の彼の小説の一貫したスタイルとなる。大江文学が私小説を超える、と語られ、「現代の人間の様相を衝撃的に描いた」と、ノーベル賞受賞につながる第一歩であった。
恩寵
赤んぼうは「光」(ひかり)と名付けられた。
「この小説を書いた時、私は実生活でも、知的な障害を持っている子供と生きてゆく事を決心していました。そのため必要な力が『忍耐』だとも感じていたわけです」。光が5歳の時、林の中の山小屋で、折から聞こえてきた鳥の声に「クイナです」と、突然語りだす。鳥の声を聞き分ける光に音楽の才能を発見する。その後、光は作曲家となる。そして、彼との共存は、「いま、希望がそれと一緒にあったことにも気付くのです」(『新しい人の方へ』)。それは大江文学が「希望の文学」と語られる、その始まりで、その後の彼の作品の本流となる。
彼は語る。「僕は信仰を持たない人間ですが・・・その背後にある、現世の自分たちを超えたものに耳を澄ませているのです。」(『恢復する家族』)と。
彼はそれを「恩寵」(Grace)と呼ぶ
(大石重範)
(地域情報誌cocogane 2023年11月号掲載)
[関連リンク]
地域情報誌cocogane(毎月25日発行、NPO法人クロスメディアしまだ発行)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
