
Love is PATIENT, love is kind.
米田淳一。この言葉でGoogle検索をすれば日本国内の一作家としての情報を得ることになる。しかし、それだけで済ませてはいけない。一作家として華々しく活躍した過去よりも、近過去に行われた月刊群雛とNovelJamという文芸イベントに深く関わっていたことを覚えている者は多い。今は時代が変わり、新しいインディーズの文芸活動が起こり世代交代が進む。それでも黎明期のインディーズ文芸に携わった米田氏の心意気を忘れることはできない。そんな彼の人間味の深さと、華々しく活躍した過去の証でもある一作家としての底力を、最新作『PATIENT ペイシェント』に収録された短編小説六作品を読むことで検証したい。
1: ネメシスの傭兵
「こんな大量の血が流れるなんて」
「犯人の撃った銃弾、鑑識が言うには『炸裂弾』じゃないかと」
「え、携帯火器でそんな炸裂弾って扱えましたっけ」
「ふつうはやらないよな。でもそれでボディーガードが使ったアタッシュケース型のケブラー製の盾がグズグズに撃ち抜かれ、ボディーガード2名が死亡、そしてその背後で守られていた国際通販大手・アメイジンの総帥ゼム・デファスに弾幕が命中、その射弾が炸裂し、体と脳を言葉のとおりに粉砕し、彼は即死した。犯人は至近距離から正体不明の小火器、判別不能のアサルトライフルの炸裂弾で3人を射殺、2名を負傷させたあと」
刑事たちは窓を見た。
「このホテル7階の吹き抜けに出て」
このホテルの吹き抜けの周りにはバルコニーがある。刑事たちが一斉にそこから下を見る。ホテルの瀟洒な内装を演出するフロントのデスクや、展望エレベーターの前に置かれたグランドピアノや、1階のカフェとその周りを囲む水盤が見える。そこに鑑識班員が集まって見上げているが、彼らは首を振っている。着地した痕跡がなさそうだ。
「そうです。犯人はここから降りて逃げたのではなく」
どこからか風が吹いた。
それに見上げると、照明で照らしあげられたこの吹き抜け直上の天窓が、窓フレームごと引きちぎられて無残に破れ、そこから夜の京都の風がねっとりと吹き込んでいる。
「この吹き抜けの上の天窓を突き破って脱出、行方不明です。この襲撃の様子はホテル内の警備カメラが撮影していました。現在その映像は鑑識の分析に回しています」
「現在所轄署の自署圏内配備を10キロ圏配備、広域配備に切り替え、NシステムやKシステムでの検索を実施中です」
「というか、その犯人、この7階から『飛び立っちゃった』のか?」
「そうなります」
(米田淳一『PATIENT ペイシェント』「ネメシスの傭兵」より引用)
https://bccks.jp/bcck/170341
華々しくもおどろおどろしい殺戮シーンで始まるこの小説は、まるで最近のハリウッド映画のような掴みはOK状態のインパクトを放っている。逆に言えば、ここまでフィクショナリティを貫きドライに冷徹にアクティヴなシーンを書き切ってしまう著者の筆力を、私は素直に評価したい。それでも物語は地味な警察刑事小説へと移行する。恐らくこの段階で地味で滋味なものを好む日本人は喜ぶだろう。ドライで冷徹なハリウッド・アクションと地味滋味な警察刑事小説の強度を比べれば、正直に言えば人間の会話はパワーが弱い。アクションの脂ぎった濃度が会話からは感じられない。そういう意味ではそれが著者の弱みになるのかもしれないが、寧ろそこを強化して、ある意味に於いて純文学的な発展を試みても面白いかもしれない。誤解を恐れずに言えば、埴谷雄高氏の『死霊』の域を目指し、特に人間の表裏を探求する思弁を、得意のハリウッド・アクションの横に並べてメリハリをつけてもいいだろう。もっとわかりやすく言えば押井守氏の『うる星やつら2ビューテイフル・ドリーマー』と『機動警察パトレイバー2 The Movie』のような感覚と強度を、この『ネメシスの傭兵』に求めたい。つまりこれは、化ける可能性がある、ということだ。喩えるならば作中に登場する中泉というキャラクターが自身の影、即ちドッペルゲンゲルと対峙する一場面がある。これも盛ることができたのではないか。ドッペルゲンゲルとオリジナルが触れることで物質と反物質の対消滅のような現象が起きてもいい。それこそ『新世紀エヴァンゲリオン』の人類補完計画で人間のATフィールドの箍が外れてオレンジ色のL.C.L状態と化してもいい。ドライで冷徹なアクションを書くように、ドッペルゲンゲルとオリジナルの差異をリアルな手触りで描く。そういう意味でもこれは、ダイヤモンドの原石のような可能性を秘めた短編小説である、と言えよう。
「無理だ。俺の命は消化試合に入ってる。俺がいくら考えてもいくらエレガントな解が出せても意味がない。頑張って好きな研究をして発表すれば評価されるなんて夢物語に過ぎないってことは思い知っている。どこで間違えたかもわからない俺はこうするしかない。どんなに理不尽な扱いをされて抗議しても、結局は俺の癇癪扱いにしかならない。でも、俺の研究はそんな連中のためにやってるんじゃないからな。俺は俺の研究とともに消えるよ。もう何も挽回の手段はない」
「梓川」
中泉は言った。
「それでも生きてくれ」
「もう御免こうむるよ」
「そうか。そうなら」
中泉は言葉を尖らせて言った。
「お前が死んだら俺も死ぬ」
梓川の顔がひきつった。
「そんな止め方があるか」
「おれは本気だ。お前がいなきゃ、おれたち業3の仕事も全滅だ。そのうえあれやこれやですでに睨まれてるから、理由には困らないでクビになっちまう。だから何でもいい。生きろ」
梓川は頭を振った。
「なりふりかまわないんだな」
中泉はそれに答えた。
「生きるって事の本質はそうだろ」
彼はその言葉にちょっと考え込んだ。
「……そうかもしれん」
(米田淳一『PATIENT ペイシェント』「ネメシスの傭兵」より引用)
https://bccks.jp/bcck/170341
この台詞はとてもいい。著者のリアルな生きざまが、フィクショナルな文章にまざまざと表れているのだろう。ブルーズを感じざるを得ない。
2: シャットダウン
朝テレビのスイッチを入れると、ニュースキャスターが「おはようございます。世界の終わりまであと七日になりました」と言う。
「火の7日間と古典アニメでいうが、この宇宙が真空崩壊するまでの時間はあと7日。正確には60万4000秒ちょっと。宇宙のあちこちに進出して生存圏を広げてきた人類の歴史もそれでプツンと終わってしまう。儚いものだが、なんにでも終わりはある」
彼はそういうと唇を噛んだ。
(米田淳一『PATIENT ペイシェント』「シャットダウン」より引用)
https://bccks.jp/bcck/170341
この書き出しの文章を見た瞬間に、日本SF作家クラブの小さなSFコンテスト(さなコン)に投稿したものだということがわかった。そして私は、この書き出しで縛るルールにダサさを感じていた。他の投稿作品も読んだが、殆どのものがこの書き出しに従順過ぎていて、この書き出しから更なる情景描写を展開させるものが多かった。つまり普通の感覚で読める、ごくありきたりの小説を思わせるものに仕上がっているものが多かった。小説を超えるような小説は存在しなかった。殆どの小説がこのダサい書き出しに潰されて、その後に続く文章の魅力を半減させていた。詩的な意味で潰されてしまったのだ。
朝テレビのスイッチを入れると、ニュースキャスターが「おはようございます。世界の終わりまであと七日になりました」と言う。ウイトタシマリナ、ニカノナトアデ。マリワオノカイセ、スマイザゴウ・ヨハオ。ガータス=ヤキスー・ユニトルレ。イヲチツイスノ――ビレテサア。
(Jihadi John Doeによる創作)
私が書くなら、このような文章を解体したものを出すだろう。恐らくそれだと審査員は通さないと思うが、私が言いたいのは、いい加減に審査員の顔色を伺い、審査に通る通らないの判断で文章を書くということを、作家(作家志望者)は止めて欲しい、ということだ。そういう意味では米田淳一氏が書いた『シャットダウン』は火の七日間というオタクカルチャーの視点を導入したことが、ある意味に於いて恥も外聞もかなぐり捨てているのが良かった。惜しむらくはそれが炸裂していたらもっと良かったのだが、それでも小説らしい描写に準じるよりも登場人物の会話を延々と書き続けるある種の異常さに、作家としての男気を感じた。デヴィッド・クローネンバーグ氏の『スキャナーズ』のワンシーンのような、脳内に周囲にいる人々の声が響き合うような会話が書かれていた。ウィリアム・バロウズ氏のカットアップ・メソッドのように会話文を細切れに解体して辻褄の合わないように再構築すれば、会話の異常な魅力はより際立つかもしれない。そういう意味に於いても、これもダイヤモンドの原石のような可能性に満ち溢れた小説である、ということを断言したい。
3: ペイシェント
対イクリール作戦ではイクリールのアルゴリズム解析が必須なのだが、まだそれは果たせていない。いずれ成功すると考えられているが、まだそれが成功していない。そのためにイクリールの増殖破壊アルゴリズムがわからないまま、マイクロ火器を使ってイクリールと戦わなくてはならない。増殖する相手にただの火器の火力で勝てるわけはない。与えられたMAMトルネードはもともとペイシェント・システムユニットの暴走増殖体を叩くために配備されたものだが、暴走増殖体とイクリールはあまりにも増殖速度が違いすぎる。
そのために今回トルネードには追加火器として最高段階に強化されたフォースシステムが搭載されたのだが、その程度でイクリールに勝てるとは思えない。増殖する戦闘無機生命体にはやはりアルゴリズムを解析してのクラック戦術が一番なのだ。それが今回使えないのはあまりにも不利だ。
どうしたらいいのか。砲兵の火力支援、航空火力支援を呼ぶにしても、その戦場にもなるペイシェントごと破壊してしまっては意味がない。システムのなかに巣食い、増殖する奴らを精密に排除し撃滅するのはどうすればいいのか。結局使えるのは炸裂弾頭ミサイルMPBM、戦術レーザーシステムTLSとその誘導破壊性能を強化してくれるフォースシステムだけが頼りだ。
蛇窪は思いを切った。行くしかない。できそうにないからといって投げ出して逃げるのは職業軍人ではない。それが使命というものだ。
(米田淳一『PATIENT ペイシェント』「ペイシェント」より引用)
https://bccks.jp/bcck/170341
ドライで冷徹なハリウッド・アクション文体が著者の米田淳一氏の売りであると前述で私は断言したが、この短編集の表題作でもある『ペイシェント』という短編小説は、そういう意味に於いても著者の良い面がてんこ盛りにされたハードコアな怪文書であると言えよう。ある意味、小説と言うよりもなにか映画の一部分を切り取り視覚も聴覚も嗅覚も全て文章化しているような、異形の趣すら感じられる。そこまで言うならば人間の五感の言語化、即ちロゴスの範疇にまで集約化するということは、人間そのものの退化と言われても仕方はないのだが、かろうじて物語を追えば『超時空要塞マクロス』に登場する巨大宇宙戦艦のようなグロテスクな生命体の体内に侵入した兵器の破壊活動を記録文書化したようにも見える。リアルな八十年代の記憶が甦る。センス・オブ・ワンダーの集積物を換骨奪胎してオリジナリティを生み出そうとした河森正治氏、板野一郎氏、美樹本晴彦氏、平野俊弘氏の先達の葛藤を思い出す。私も先達の傍にいたので苦労は骨身に染みている。しかしながら過去の浪漫など見向きもせずドライに冷徹に情景を切り取る行為を今もなお続ける姿勢こそが、『ペイシェント』が到達したハードコアな物語性と言うべきものだろう。
実を言えば、これに似た状況が既に起きている。今の時代のハリウッドで『モンスターヴァース』という映画シリーズがある。日本国内で昔撮られた怪獣映画がハリウッドに輸出されて換骨奪胎を施されたのが、それだ。そのモンスターヴァースのシナリオライターは、「人間の登場人物を最小限にして、クリーチャーのキャラクター性をしっかりと描くことは可能だ」という発言をした。つまり「怪獣が暴れるだけでも映画は成り立つ」と言い切ったのだ。このことを『ペイシェント』は逆輸入すればいい。正直に言おう。ここに描かれているハードコア描写を連ねるだけで立派な商品になる。『ペイシェント』にはそれだけの価値がある。
4: さよなら、私の戦争
その戦いのあと、普通であれば帰投のための飛行があるのだが、この無人ヘリは帰投操作はオーパイ、自動操縦で基地に帰るのでその操作もいらないのだった。任務終了のボタンを押してそのままデブリーフィングして私の仕事は終わりである。
終わって基地のなかで食事をして、そのあと家族のいる官舎へ帰宅する。途中コンビニによって買い物をする時、一瞬視野に戦闘中の照準サインが見えたような気がしてゾッとした。そのサインの向こうにいつものコンビニのバイトの女の子の明るい笑顔があったのだ。
それは任務を重ねるたびに続いた。ゾッとするだけではすまなくなってきた。メンタルに悪いと思ったら同僚も皆そうだったので、医官に相談して軽い向精神薬を処方してもらった。あまりいい方法ではないが、これも任務のためだ。
(米田淳一『PATIENT ペイシェント』「さよなら、私の戦争」より引用)
https://bccks.jp/bcck/170341
生きていくということ。いま生きていくということ。それはのどがかわいていても、のどを潤すことができない者がいるということを想像することができないことだ。喩え戦争の最中で相手を殺して相手の生を剥奪する生き方をしていても、それでも御前が生きているという事実は変わらない。互いに生きるか死ぬかを競い合う弱肉強食の摂理に従った瞬間に、フィクションの世界は古典的なヒューマニズムのドラマの色に染まっていく。そう思った瞬間に、生きることは普遍的なエンターテイメントを構成する部品の一つになる。この『さよなら、私の戦争』を読み終わった時に、真っ先にそのことを思い浮かべた。そして私の想像力は、この『さよなら、私の戦争』のフィクショナルな文章の裏面に、著者のリアルに食い込む非日常的な戦争の一部分が、ここに存在しているような気がした。更に私が思うことは、非日常的な戦争の同居が、人の生き死にに関わる医療従事者の人生に似ているということだ。似ていると言われたら、そうですかと軽く返事をして、あとは受け流せばいい。そして受け流すということは、それを受け止めてから違うところにそれを流す、という意味である。このことを忘れなければ、『さよなら、私の戦争』は純文学の域に達するだろう。喩え冗長と言われても、ネガティヴでもポジティヴでもない極限状態を文章で伝えることはできるのか。このことを喚起させるのもまた、著者の持つ強みだろう。
5: ジャムフォース
「ディスピアへの反撃に、役に立たないはずの物語が一番役に立つなんて」
「本当は、物語なんか役に立たない方が楽しいし、その方がずっと世の中が豊かで幸せなんだと思うぜ。物語を描き、それに人類が没頭することが、ディスピアに一番のダメージを与える可能性がある」
「でもいまじゃ、その物語を描ける人間は稀だ。このディスピア事態のせいで、人々はもう物語るには心にも金銭的にも余裕がなくなっている」
いくつもの小説投稿サイトが、運営資金も運営人員も不足している上に不謹慎だ、不要不急だという批判で閉鎖に追い込まれていた。
「書き手のほうが読み手より多いんじゃないかって言ってた時代が懐かしいよ。あれはどんなに炎上したとしても、今よりはずっと平和で豊かだった」
( 米田淳一『PATIENT ペイシェント』「ジャムフォース」より引用)
https://bccks.jp/bcck/170341
ハードコア・アクション、ハードボイルド・ライフ、溢れる思索、これらが私が分析した米田淳一氏の作家としての潜在的な武器になるが、これらとは違う意外な一面を隠し持っていることを見逃してはならない。それは、鉄道オタクの女性の語らいを父親が娘を見守る視点で描くことである。ある意味これは、著者のリラックスしている姿が文章の裏面から伝わってくるので、読者はやさしい気持ちになれる。常に目くじらを立てながら文学とはこうだと柄谷行人氏や蓮實重彦氏を手本にしながら論じ合った時代は、とうの昔に終わった。今は村上春樹氏を手本にするのか。違う。今はより混沌としていてアナーキックと化している。日本国内で言えば前述で挙げた月刊群雛とNovelJam、更にはブンゲイファイトクラブやVG+ (バゴプラ)などの正直に言えば有象無象のインディーズ文芸イベントが、ありし日の文学同人がインターネットとSNSを用いて強化した趣で、互いに存在を主張している。但し、これらが売れるのかどうかはわからない。そして、売れなければいけないのが小説という訳ではない。日本国内の商業小説全般が売れるという宿痾に縛られているのなら、それに囚われるのも逃げるのも、この『ジャムフォース』という小説を読んでから決めてもいいだろう。
この『ジャムフォース』はフィクショナルな物語の中に更に小さな物語を内包する、ある種のメタフィクショナルな感覚を読者に享受させる。喩えるならばそれは『ネヴァーエンディング・ストーリー』という映画に於いて、リアル世界で小説を読む読者が小説の中のフィクショナル世界に介入する感覚に似ている。原作小説の『はてしない物語』は映画とは異なり前編後編と分かれていて、後編ではフィクショナル世界からリアル世界への脱却が描かれている。『ジャムフォース』のフィクショナル世界は更に数多くのメタフィクショナル世界が内包されて、その濃度を増している。しかしながらこれらのメタフィクショナル世界の具体性は伏せられている為に、これらがリアル世界に対してどのような影響を与えたのかはエビデンスが不明だ。それ故にメタフィクショナル世界の細部を再調整することによって、『ジャムフォース』は『はてしない物語』を継ぐことになるかもしれない。嗚呼、ダイヤモンドよ。その原石は限られた鉱山でしか採掘できないものだから。
6: 方程式を壊す者
だが、その直後、シファの放つ光で宇宙の闇が切り裂かれた。
そこから、霜まみれになった血清輸送巡洋艦が飛び出した!
なんとシファは巡洋艦を自分の量子実装システムで別時空に格納し惑星ウォードンに進撃、そしてそこで格納した巡洋艦を取り出したのだ。
戦闘質量1万トンを、そのままシファは風呂敷に包んで運ぶかのように運んでしまったのだ。
(米田淳一『PATIENT ペイシェント』「方程式を壊す者」より引用)
https://bccks.jp/bcck/170341
この小説を読み、コロンブスの卵という慣用句を思い出した。今ではクリストファー・コロンブス氏は虐殺者と強姦者のレッテルが貼られてマイノリティ・グループから嫌われている。そういう意味では簡単には気づかないアイディアに気づくという状況に対して、もうコロンブスという言葉を使わなくてもいいのではないだろうか。
個人的にはX JAPANのYOSHIKI氏がカレーライスとオムライスしか置いていない喫茶店で、オムライスにカレーをかけて出してくれと言ったことのほうが、よっぽどコロンブスの卵していると思う。X JAPANのメンバーと私は同年代だ。横須賀のhideミュージアムに展示されたhide氏が思春期の頃に聴いたアナログレコードも、私が思春期の頃に聴いたものと同じだった。初期の彼らはモトリー・クルーのシャウト・アット・ザ・デヴィルのような鋲付きレザー・ファッションで、YOSHIKI氏は当時西ドイツから出たハロウィンというメロディック・スピード・メタル・バンドの音を傾聴していた。初期のX JAPANはハロウィンに似ていた。その後にX JAPANは自らのオリジナリティを模索していった。へヴィメタルとは違うヴィジュアル系というジャンルを作り、周りに広めていった。
ポスト・エヴァンゲリオン時代のラディカル・ハードSFと言われた若き日の米田淳一氏もこんな感じだったのではないかと思う。そして今、方程式は壊されようとしているのだろうか。私は興味津々の心持ちでいる。
ENDING: この道を行けばどうなるものか、危ぶむなかれ、危ぶめば道はなし
俺は小説を読むのも書くのも好きだ。たぶん世の高校生の平均的な好きさ加減よりは遥かに好きだ、と思う。けれど、文芸部に入部して以来、他の部員の作品をちゃんと最後まで読めたことがない。否定しているのではない。これは自分のための小説ではない、と思ってしまうのだ。義務のように読んでしまうのだ。それはどう考えたって、違う。
ひょっとしたら上手いのかもしれない。スゴイのかもしれない。でもそういう問題ではないんだ。ジャンルの問題でもない。だって梶井基次郎とかウラジミール・ナボコフとか好きだし。ラノベだって読めないやつは読めないし。
一方で俺は決して変わった人間じゃないと思っている。嗜好が偏っているつもりもない。
人間はいろんな好きと、いろんな嫌いと、いろんなどうでもいいもので出来ていて、その混ざり具合が他人とまるで違ったり似ていたりするのだ。そこに属性で境界線を引く意味なんてあるだろうか。あるのは「自分のためのものかどうか」という個人的な問題だけだろう。
だから俺は、どこかにいるであろう「もう一人の俺」のために書いている。あるいは、アイツなら読んでくれるはずだと思える「俺のような誰か」に向けて書いている。それは一人や二人であるはずがない。彼らの後ろには百人、千人、いやそれ以上の「俺」がいるはずなんだ。俺が読みたいと思うような話を待っている「俺」が。
きっといるはずなんだ。
(小林猫太『とらぬ狸の超電磁ヨーヨー(とらぬたぬきのハイパーウェポン)』より引用)
https://kakuyomu.jp/works/1177354055323577474
前述引用文の著書である小林猫太氏と、この書評元の著書を著した米田淳一氏は似ている。勿論、似ていると言われても、はいそうですかと軽く返事をするだけで、あとは受け流すことをしてもまったく構わない。似ているという事実にはなんの論理的な拘束力など働くことはないのだから。それでも似ているという言葉から醸し出される詩情というものが、知らぬ間にあなたの周りで影響力を行使しているかもしれない。この世界には自分に似た人間が三人いると言われている。何故、三人という数になっているのかは理由はわからない。それでも三人だと強く言い切るのなら、私は後述の件を思い出さざるを得ない。
『サイボーグ009』という漫画は昭和五十四年に二回目のテレビアニメ版が放映されたのだが、そこに登場する敵のブラックゴーストは三人の幹部の支配下にいて、その三人の名はブラフマー、ヴィシュヌ、シヴァであった。それは見ての通りにヒンドゥー教の三柱神の情報を換骨奪胎してエンターテイメントに展開した一例を示していた。そしてなによりも主題歌の『誰がために』を歌う成田賢氏の歌唱法が、「涙で渡る死の荒野」という歌詞を「しのこぉぉぉぉぉぉぉ、おっやー」と独特な歌い回しで歌うところが大人になった今でも強烈に記憶に残っている。
当時の日本国内は八十年代のバブル経済が始まる前で、六十年代の学生運動は落ち着いていたが、新左翼の過激派は活動を続けて新聞週刊誌を賑わせていた時代であった。その時代を生きた子どもは、テレビ番組や漫画やドーナツ盤のアナログレコードを、なんとなくつまらなく感じる日常を吹き飛ばす宝物として認識していた。今の時代の子どもなら、お気に入りユーチューバーの動画を観たりTikTokで踊るようなものだろう。もし私が今の時代の子どもなら、息を抜く手段がそれだけしかないのなら生きづらさを感じるだろう。
話がどんどん脱線していくので強引に戻す。前述引用で小林猫太氏が小説を信じると書いたことと、今もなお米田淳一氏が小説を書き続けることは、同じことであると私は言いたいのだ。勿論、売れたらいいだろう。それで食えたら、なおいいだろう。米田氏が過去にそれで食っていたことは承知している。それでも私はこのように言うだろう。小説を書くことと、小説でビジネスをすることは、違うことだ。後者は成功に導くには綿密なプランが必要になるが、前者はただシンプルであればいい。
「なりふりかまわないんだな」
「生きるって事の本質はそうだろ」
この台詞を信じたい。なりふりかまわず小説を書き続けていって、その上で生きるということが、やはり事の本質であるのだから。
Written by Jihadi John Doe.
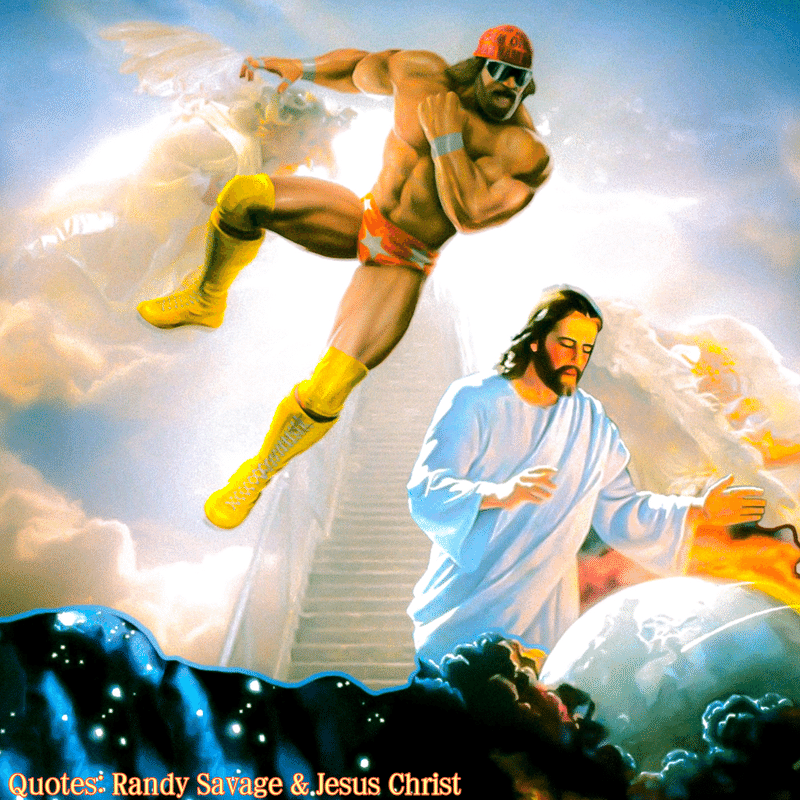
追記する。私は下記でも活躍している。興味を覚えた者は是非とも文闘士として闘って欲しい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
