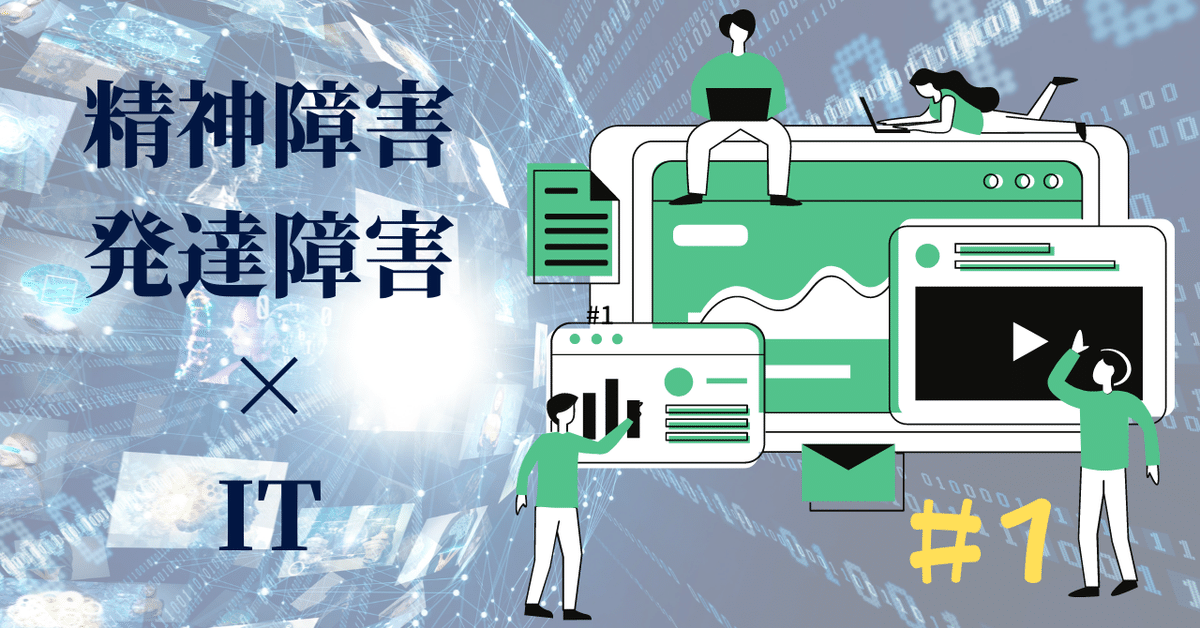
障害者雇用でDX推進って、どーゆーこと?
障害を抱える人たちが働くうえで、「やりがい」と「必要十分な給与」の2つの要素を満たすことは実は難しく、これまでも課題とされてきました。
JPTでは、これらの2つを満たす仕事の作り方を実践しています。
多くの企業が法定雇用率の達成に苦労する中、その一歩も二歩も先を行こうとしているJPTは、いったいどんな仕事の作り方をしているのか?
創業時の思い、1年を振り返ってどうだったか、これからどんなふうに進化していくのか。
社長の成川、副社長の阿渡にインタビューしてきました。
(執筆:ミッションパートナー ちひろ)
↓全4記事へのリンクはこちら(毎週更新)
・障害者雇用でDX推進って、どーゆーこと? 【社長×副社長対談】(第3弾・1/4) ※本記事
・重要度が高く、緊急度の低い仕事をやる。 【社長×副社長対談】(第3弾・2/4)
・ITシステム開発初期段階における上流工程の空白。 【社長×副社長対談】(第3弾・3/4)
・顧客のゴールそのものを受注すること。 【社長×副社長対談】(第3弾・4/4)
ー障害者は最低賃金で働くこと、就労継続支援の場合はそれ以下で働くことが当たり前というイメージがあります。どうしてなんでしょうか?
(阿渡)
身体障害、知的・精神障害にかかわらず、「障害を持っている=できないことが多い」と見なされる現実があります。
そのために、減点方式で仕事を評価されてしまいがちなことが大きな理由だと思います。
採用側は障害名や求職書類に書かれた文言だけでは何がどれぐらいできて、何ができないのかが想像できない。
たくさん採用するわけじゃないから”数打ちゃ当たる”的な採用も出来ない。
そのため、誰にでもできる単純作業で低賃金という図式ができあがってしまっているのではないでしょうか。
世の中の働き方がどんどん柔軟になり、いろんな立場の人が働きやすくなる一方で、障害者雇用の現場は取り残されているようにも見えますね。
(成川)
「障害者の法定雇用率」という言葉を知っていますか?
読んで字の如く、「社員の○%は障害者である必要がありますよ」という数字です。
2021年3月に2.3%に引き上げられています。
未達成企業は納付金を支払うことになりますが、企業が本当に恐れているのは企業名の公表です。
企業はまず、「法定雇用率を達成する」という目的のために障害者を雇用します。
人として、社員としてぜひ社に迎え入れたいという理由よりも前に、この数字が先に来てしまうのです。
そして雇用した以上は、彼らに仕事を用意する必要が出てきます。
本来ならデジタル化することでなくせる単純作業をいつまでも残したり、
外注することでコストを減らしていた業務を社内に戻してきたり、
社内福祉として、カフェ運営やマッサージ業務を作ったり。
会社としては法定雇用率達成という大目的があるので、運営では多少の赤字は目をつむる、もし赤字にならなければ御の字という認識が根強くあります。
単純作業を仕事として求めている人がいることは事実ですし、その人たちの雇用を支えることは社会的に意義のあることだとは思いますが、だからと言って生み出す価値がコストを下回る状況を良しとするのはお互いにとって良くない。
そこを抜け出さない限り、賃金は上がっていかないでしょう。
さまざまな業務をデジタル化することで生産性を上げるDX推進(※)というのがありますが、実は、障害者に仕事を残すためにこの動きが妨げられている側面があります。
ー合理的に利益を追求する営利企業の性質がそうさせているのですね。JPTの設立当時、自社の障害者雇用はどんな形にしようと思われていましたか?
(成川)
JPTのミッションは「障害の有無に関わらず、全ての人が対等(parallel)で、社会的意義を感じながら持てる技術(technologies)を発揮して働ける社会の実現」です。
その上で、障害者の仕事は単純作業で低賃金であるという現状を打ち破ることを大前提としました。
そのためには、彼らにしてもらう仕事そのものの価値を高める必要があります。
単純な入力作業や紙書類の整理など、障害者の仕事はDX(※)を妨げているイメージがどうしてもありました。それなら逆に、障害者たちの仕事でグループ全体のDXを推進できないだろうかと考えたのが始まりです。
※DXとは…
企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること。
(阿渡)
障害者雇用というと、僕のような身体の一部に障害のある人や、お菓子作りの作業所などで働く知的障害のある人をまずイメージすると思います。
実はそれ以外に精神障害というくくりがあって、これには統合失調症やうつ病、近年特に増えてきている発達障害も含まれます。
2018年の法改正で、この精神障害も法定雇用率の算出対象になったんです。しかし、精神障害は身体障害や知的障害と比較して、採用後の定着率が低いという現実があり、なかなか積極的に採用を進めるのが難しいのも事実です。
そんな中、JPTではまず、精神障害者(発達障害含む)をメインに採用していくことにしました。
ーそれはまた、どうしてですか? DX推進ということは、IT関連の業務がメインですよね? PC作業に支障のない身体障害を持つ人のほうが、高いパフォーマンスを出せるような気がしますが。
(成川)
おっしゃるとおり、そういった方もいますが、どの企業も考えることは同じ。特別な配慮なく優秀な障害者人材を雇える、と考え、獲得競争は熾烈です。
一方、発達障害を含む精神障害を抱える人たちの中には、高度なITスキルを持つ人たちが多くいるにも関わらず雇用は進んでいない。
企業で働く際のルールにうまく合わせられないかもしれないけれど、環境さえ整っていればすごく高い成果を出せる人たちが埋もれてしまっているんです。
精神障害×ITというのは、今の時代だからこそ実現していける形であると思います。
障害者と健常者、どちらも区別なく成果で評価されるあり方。
あとは、「難しいことだからやる」というのが理由かもしれません。
定着率が低いことなどが理由で他の企業があまり採用したがらないなら、JPTがやる。すると優秀な人がたくさん来てくれるはず。逆張りですね。
彼らが成果を出せる制度や環境を作ることができれば、どんな人でもそれぞれの能力を最大限発揮できる場所になるんじゃないか。
そんなふうに思うんです。
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
