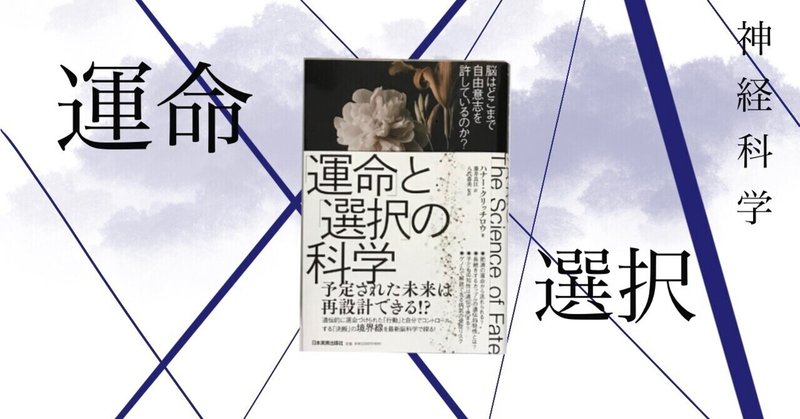
読書日記『「運命」と「選択」の科学』ハナー・クリッチロウ著
遺伝的に運命づけられた「行動」と自分でコントロールする「決断」の境界線を最新脳科学で探る
この本は、運命がどれほど遺伝子によって決定しているのか、自我との交絡によってどれほど変わるのかを知りたい著者が様々な専門家に聞いた体験を記したものである。
「運命」というと人間がコントロールできない全能の神がもたらすものというイメージがある。生まれか育ちか、といった問いには「両方」という著者も「運命」を生物学の言葉でどう言い表せるのかを探ることになる。
神経生物学的には、生命の発生とともに性格や信条、身体的な特徴などある程度の傾向は予測でき、これが「運命」なのではないか。とすると受け入れ難い「運命」であっても仕方がないのだろうか。
一方、私たちは自分の意思決定の下し方も「運命」づけられているのだろうか。この問いには、遺伝的な素因という意味でイエスとなるものもあるが、変えうるものであるという可能性には希望が持てる。
ただし、認知の不具合の大きさを忘れてはならない。
人間はとてつもない情報を処理するため、脳内ネットワークを駆使しても相当時間がかかる。そのため正確な現実ではなく近似値や錯覚で答えを出している。これは健康な人でも(むしろ頭がキレる人ほど)処理を早めるために備えているシステムなのだ。このとき認知の不具合を生むという欠陥に使われるのがその人独自の経験の単なる寄せ集めである。過去の経験がその人の意識を作っている、というのは悲しいかな、当たっている。特に神への信仰心というところではかなり際どい分析になっている。
どんなに洗練された信仰も、厳密な分析的思考が可能になる前に築かれた、脳の生得のメカニズムと無数の潜在意識が生んだものなのだ。だからといって、人生や信念について時間を割いて考えることを否定するわけでも、そのような行為が実用的・知的価値がないと主張しているわけでもない。ただ、意識的な思考はすべて、バイアスがかかり、不具合を起こしがちな認知と現実の構造に基づいていることは強調しておきたい大事な点だ。
神経科学的に「運命」を紐解こうとしたきっかけが息子の遺伝病の可能性を知るために検査を受けるかどうかという葛藤だったという。多くの研究者や専門家の意見を聞いてわかったことは、遺伝の可能性(そしてその後の運命)を知れるのはごくわずかであるということだった。それよりも予測可能なのは、行動を変えたり環境を変えたりであって、つまり行動して後天的な遺伝にも影響させていくことで「運命」は予測と近づいていく。
自由意志の大切さを感じた1冊だった。常に不満を抱えていながら自分で意思決定ができていない。それは判断を下すための経験が不足しているからなのかもしれない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
