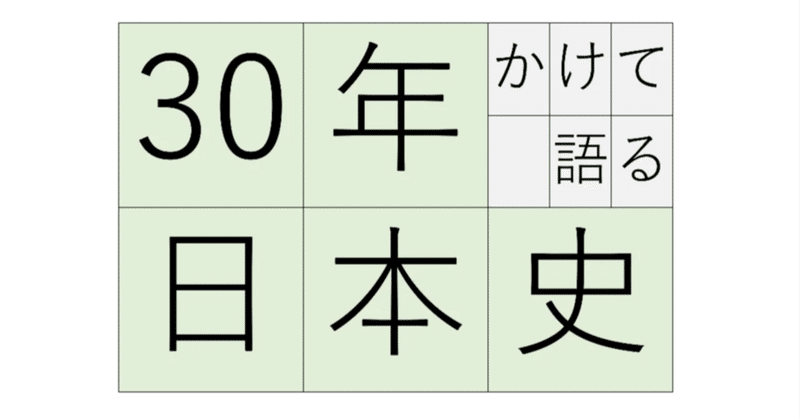
30年日本史00871【建武期】湊川の戦い 足利勢上陸
本間からの挑発を受けたものの、尊氏方からはなかなかその挑戦を受けようという者が現れません。やむなく尊氏方の佐々木顕信(ささきあきのぶ)がこれに応じようと、弓をきりきりと張りました。
ところがここで足利方のバカな武者が、鏑矢を一本放ってしまいます。それはほとんど飛ばずに落ち、後醍醐方の兵たちの嘲笑を浴びました。
「こうなってしまってはもはや射る意味もない」
と佐々木は矢を放つのをやめてしまいます。
この遠矢のエピソードは太平記の中でも有名なもので、現在、神戸市立和田岬小学校の校内には、「本間重氏遠射之跡」と記した碑が建てられています。
さて、矢を射損なって嘲笑を浴びた足利軍の中から200騎が、経ヶ島(神戸市兵庫区)から上陸して敵陣に斬りかかりました。しかし脇屋義助軍500騎に取り囲まれて全滅してしまいます。
足利方の細川定禅は
「後に続く者がいなかったから無駄に味方を討たれてしまった。足場のよさそうなところに上陸しなければ」
と言って、より広いところからの上陸を目指し、東へ進んでいきました。
一方の新田軍はというと、足利軍の本隊を上陸させまいと同様に東へ進んで行ったので、新田軍と楠木軍は大きく離れてしまい、その間の湊川(みなとがわ:神戸市兵庫区)に防備の軍勢がいない空洞が生まれました。そこに別の足利勢の軍船が横付けして、次々と上陸して行きました。
これは尊氏の陽動作戦に義貞がかかってしまったものなのか、はたまた偶然なのかは分かりません。しかし義貞が目の前の尊氏を討とうということで頭がいっぱいになって、楠木軍の存在を忘れていたことは間違いありません。楠木軍は僅か700騎という小勢で、他に味方のいない中、足利勢と向き合うことになってしまったのです。
正成は弟・正季に
「もはや逃れられぬ運命だ。さあ、敵を蹴散らそう」
と呼びかけ、目の前の敵に突撃して行きました。
楠木軍の間近に上陸していたのは足利直義軍でした。楠木兄弟はひたすら直義の首を狙って攻め寄せ、刀で敵を次々と斬り伏せていきます。直義は50万騎もの兵を率いていながら(太平記の誇張でしょう)、楠木軍のあまりの勢いに逃げ回ることしかできません。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
