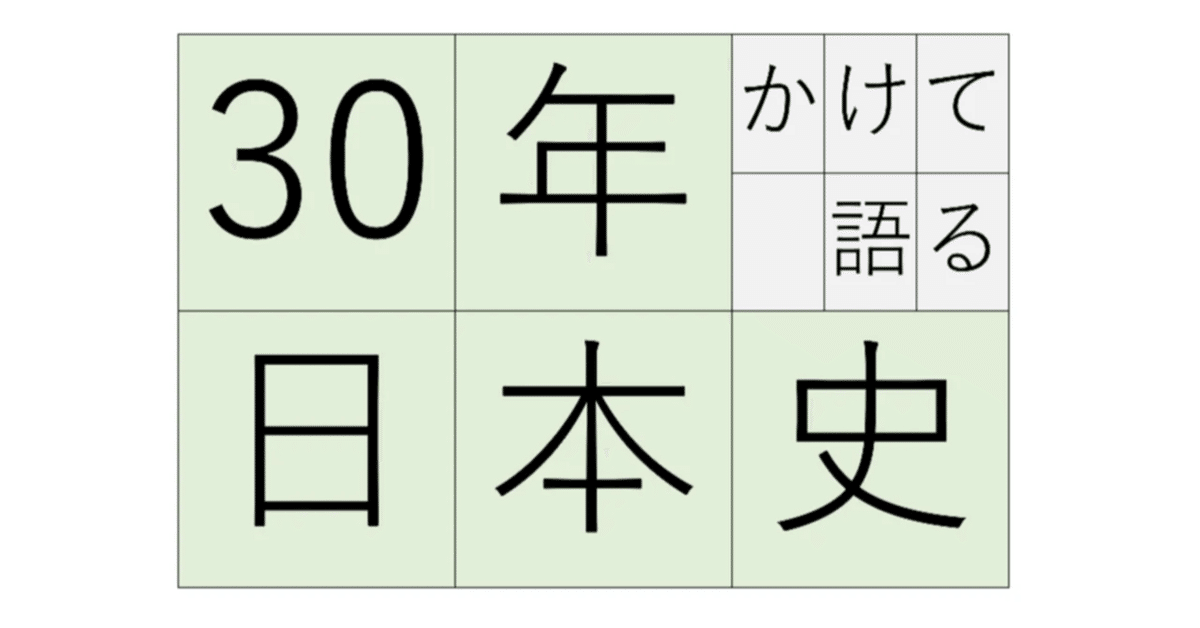
30年日本史00875【建武期】湊川の戦い 小山田高家と浄瑠璃姫
楠木軍が全滅した頃、新田義貞は足利勢を追って海岸線を東へ向かっていました。ところが行き過ぎてしまったらしく、西宮(兵庫県西宮市)から上陸した敵の旗の紋を見た義貞は
「小者ばかりではないか。足利尊氏・直義の軍勢はどこへ行ったのか」
と言って引き返し、生田(神戸市生田区)でやっと足利兄弟の軍と行き会うことができました。
対峙した両軍は1時間ばかり交戦しましたが、大勢の戦死者を出しただけで決着がつきません。義貞は
「私自ら戦うべきときが来たようだ」
と2万3千騎で敵陣に飛び込んでいきますが、尊氏軍は(太平記を鵜呑みにすると)30万騎の大軍勢です。新田軍は徐々に劣勢となり、やがて兵たちが逃げ始め、大将の義貞自身が殿(しんがり)となって味方を逃がすために踏みとどまって戦いました。
義貞の馬は矢を7本も受けて動けなくなりました。義貞は馬から降りますが、味方はこれに気づかず義貞に馬を譲る者すら現れません。そんな中、単騎の義貞に雨のごとく矢が降りかかります。義貞は名刀・鬼切で16本もの矢を切って落としました。
義貞の苦境を見た小山田高家(おやまだたかいえ:?~1336)は、自分の馬を義貞に譲って、追撃してくる敵を徒歩で防ぎますが、多数の敵に囲まれ遂に討ち死にしました。高家が時間を稼いでいる間に、義貞は危うく逃れることができました。
身を挺して義貞を救った小山田高家は、武蔵小山田城(東京都町田市)の城主です。この高家の妻・浄瑠璃姫(じょうるりひめ)について、こんな伝説が残されています。
聖武天皇の時代に、大磯(神奈川県大磯町)の海に三日三晩光り続ける不思議な場所がありました。漁師がその光る物を引き上げてみると、薬師如来像でした。
後世、平塚城(神奈川県平塚市)の城主・岡崎四郎(おかざきしろう)という人物がこの薬師如来像を譲り受け、子を授かりたいと拝み続けた結果、産まれてきたのが娘の浄瑠璃姫です。その後、浄瑠璃姫は小山田高家の側室となり、その薬師如来像を父から譲り受けて小山田城に祀っていました。
やがて湊川の戦いで小山田高家は戦死し、小山田一族は城を追われます。浄瑠璃姫は薬師如来像を背負って侍女13人と共に逃亡しますが、逃げきれず長池(東京都八王子市)に身を投げました。
それから時は流れ正平16/延文6(1361)年、蓮生寺(れんしょうじ:東京都八王子市)の住職・教山(きょうざん)が長池のほとりを歩いていると、池の中に光る薬師如来像を見つけます。住職は像を持ち帰り、堂を建てて供養しました。
現在、八王子市の長池公園には浄瑠璃姫を供養するための碑が置かれ、その近所の蓮生寺には件の薬師如来像が祀られています。
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
