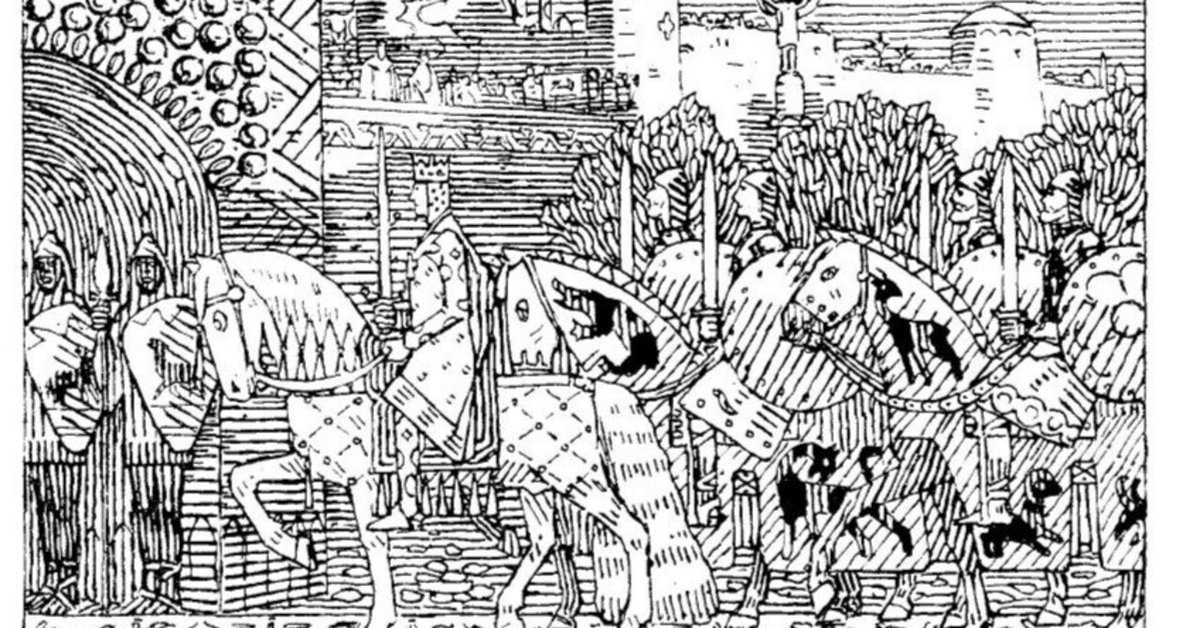
シグルズ王とエイステイン王
ノルウェー王朝史『ヘイムスクリングラ』収録「マグヌースソンのサガ」からのエピソードを取り上げた短編です。
第七回文学フリマ京都(2022年1月15日)で新刊として頒布したものですが、在庫がなくなり頒布終了したので note にて無料公開することにしました。
一一〇三年、ノルウェー王〈素足〉のマグヌースがアイルランドで戦死した後、三人の息子たちが王国の支配者となった。長男のエイステインは十四歳、次男のシグルズは十三歳、末っ子のオーラヴは四歳で、上の二人が幼い末弟の領地を管理することにした。彼らは異なる母親を持つ異母兄弟だったが、仲が良かった。オーラヴは早逝した為、統治者として後世に名が残るのはエイステインとシグルズのみである。
シグルズは八歳の頃、父王に連れられてオークニー諸島、ヘヴリディーズ諸島、アイルランドへの海外遠征に出て、父からオークニー侯に任ぜられた。しかし、正義感の強いシグルズは、兄弟とともにノルウェーの王位に就いた時、父が領地を取り上げたパール侯の息子に侯(ヤール)の称号とオークニーの支配権を返還した。
マグヌース王の息子たちが共同統治を開始して四年が経った頃。ヨールサラヘイム(イェルサレム)やミクラガルズ(コンスタンティノープル)に居たノルウェー人たちが帰国した。彼らは外国の様々な情報をもたらした。とりわけ人々の関心を集めたのは、ヴァリャーギ親衛隊の話だった。ミクラガルズでギリシア(ビザンツ)皇帝の傭兵になると莫大な富を手に入れることができるという。
ミクラガルズに行くことを望む者たちから「エイステイン王かシグルズ王に遠征の統率者になってほしい」と懇願され、二人の王は遠征費用を分担することを決め、準備に取り掛かった。
「我らのうち、どちらが航海を主導すべきであろうか」
シグルズの問いに、金髪のエイステインは笑って応じる。
「幼い頃から父上と遠征に出ていたそなたが相応しかろう、シグルズ。行きたくてたまらない……と、顔に書いてあるぞ。そなたは子供の頃から冒険好きだったな」
「さすが兄上。俺の性分をよくご存知だ」
赤髪を無造作にかき上げるシグルズの灰色の瞳が、きらりと光った。
エイステインも満足げに頷く。
「我らはそれぞれ得意とする分野が異なるゆえ、そなたが遠征や軍事を、余が内政を担当するのが良いだろう」
シグルズは海外遠征の経験が豊富でヴァリャーギ親衛隊にも属した曽祖父のハラルド苛烈王に、エイステインはビョルグン(ベルゲン)の町を築きノルウェーに平和をもたらした祖父オーラヴ王(オーラヴ三世)に似ているようだった。
シグルズ王は六十隻の船団で故郷を出立した。総勢五千人での大遠征である。
王の詩人(スカールド)〈短衣〉のソーラリンは出航の際、このように謡った。
鷹の如く勇壮な王のもとに
忠実で優れた軍勢が集結した
かつて王の身内が
賢明なるクラーキ(伝説の王)の仲間となったように
寛大で聡明な君(シグルズ)に
好意を寄せし精鋭らが集い
楯を備えた六十隻の船は
神の定めにて此処より海を滑りゆく
秋、シグルズ王の一行はイングランドを訪れて冬を過ごし、翌春にはヴァルランド(西フランス)に渡った。そして秋になるとガリスランド(スペインのガリシア)へ向かい、二年目の冬は其処に滞在した。
ガリスランドでは当地の領主がシグルズ王との取り決めにおいて冬の間ずっと市を開かせていた。一行の賄いの為である。しかし、シグルズ王の艦隊が大所帯であったことに加え、当地がさほど豊かな土地ではなかったせいもあり、物資はユール(クリスマス)まで保たなかった。
約束を違えるな、とばかりにシグルズ王が大軍を率いて領主の城に向かったところ、僅かな手勢しか持たない領主は恐れ慄いて城を明け渡し、逃走してしまった。
シグルズ王はかつて祖先たちがやったのと同様、そこで食糧や宝物を掠奪し、自分の船に運ばせた。部下たちを満足させると、王は出帆の指令を出し、イベリア半島の西岸を進んだ。
次に一行が出くわしたのは、異教徒(イスラム教徒)の海賊船団である。シグルズ王は彼らと戦い、八隻のガレー船を拿捕した。その後、キリスト教徒に掠奪行為を繰り返す異教徒らの根城となっているシントレの城塞(現在のポルトガル。リスボンの西)で再び異教徒と戦い、砦を占拠、キリスト教への改宗を迫った。シグルズ王は洗礼を拒否した者はすべて殺害し、大都市リズィボン(リスボン)とその南のアルカッセでも異教徒と戦って勝利すると、途方もない量の掠奪品を得た。
このように、ヴァイキングの子孫らしい行為を繰り返しながら船団はノルヴァスンド(ジブラルタル)海峡を通過してセルクランド(北アフリカ)沿岸部を航行、地中海の島々でも異教徒に勝利し、シキレイ(シチリア)島に到着。ロズゲイル侯ことロジェール二世の盛大な歓迎を受け英気を養った後、ついに聖地ヨールサラヘイム(イェルサレム)に至った。キリスト教の布教に尽力し、ノルウェーに大司教座を創設することを誓った見返りに得た聖遺物の一つ、削り取られたキリストの十字架の一部をシグルズ王はオーラヴ聖王の埋葬地ニダロスに奉納すべきと考えた。
ヨールサラヘイム滞在中にも異教徒との戦いに加わり、勝利に貢献したシグルズ王は北へ向かった。高貴な紫色に染めた布で飾り立てた旗艦を誇示するように船首に立ち、印象的な赤髪を風になびかせながら、意気揚々とギリシア(ビザンツ帝国)の都ミクラガルズ(コンスタンティノープル)を目指したのだった。
ギリシア皇帝キリアラックス(アレクシオス一世コムネノス)は若いノルウェー王とその一行を友好的に迎えた。帝都で競馬競技を観戦し、演劇や音楽を鑑賞して滞在を楽しんだシグルズ王は、帰国の際、自らの船団すべてを気前よく皇帝に寄贈した。皇帝は返礼として多数の駿馬をシグルズ王に贈り、帝国領内では案内人をつけてくれた。シグルズ王の部下の多くは、故郷を発つ時に望んだように、そのままミクラガルズに留まり、ヴァリャーギ親衛隊に服務したという。
出発時の十分の一に減ったシグルズ王の一行は、皇帝キリアラックスから贈られた馬で陸路ノルウェーを目指した。ボルガラランド(ブルガリア)、ウンガラリーキ(ハンガリー)、パンノウニア(パンノニア)、ビーヤラランド(バイエルン)、スヴァウヴァ(シュヴァーベン)。ビーヤラランドでは、のちに神聖ローマ皇帝となるロタール三世の歓待を受けた。そして、スレースヴィーク(シュレスヴィヒ)を経由してデンマークのヘーゼビューまで来ると、今度はデンマーク王ニールスが北ユランまで同行し、完全装備を施した船を用意してくれたので、シグルズ王は部下たちとともに安全にノルウェー帰国を果たすことができた。遠征は三年に及び、シグルズ王は二十歳になっていた。
シグルズ王が遠征に出ていた三年間、兄のエイステイン王は国内で様々な事業を進めていた。ニダロス(トロンハイム)やビョルグン(ベルゲン)に教会や修道院を建て、アグザネース(トロンハイムフィヨルドの河口にある町)に港を整備し、宮廷には木造の使徒教会を造らせた。また、スヴェア王国(スウェーデン)との国境に位置するヤムタランドの人々と親しく語り合い、かつて〈アザルステインの養子〉のホーコン王(善王)の支配下にあった時以来の友好関係を結んだ。シグルズは誰もがついて行きたくなる勇壮な戦士王として称賛されたが、エイステインは穏やかな日常を与えてくれる平和の王としての評価を受けたのである。
さらにエイステイン王はニダロスでかつてオーラヴ・トリュグヴァソン王が建造させた〈長蛇号〉を模した大船を造らせた。そして、ニダロスに造船所を建設した。
兄のエイステイン王は美男だが中背で、癖のある金髪と碧色の眼をしていた。聡明で法律に詳しく、弁舌に優れ、陽気な男だった。
弟のシグルズ王は身の丈高く、赤髪で、雄弁ではないが無愛想ではなく、礼儀正しくて風格があった。
外交が得意なシグルズと、内政に優れたエイステイン。正反対のような兄弟であるが、二人の治世はノルウェー史上最長の共同統治となった。
そんな二人が、ある宴の席で自分たちのどちらが優れているかを論ずる余興を行なったことがある。
ウップランドのエイステイン王の館で開かれた宴での出来事であった。初日の夜に出された麦酒(エール)が大層不味く、折角の饗宴が台無しになりそうだった。
どうにか場を盛り上げようとして、エイステイン王が口を開いた。
「今宵は皆、静かだな。何か面白いことをやろうではないか」
そして彼は弟のシグルズ王に提案を持ちかけた。
「弟よ、まずは我らから始めよう。皆の気持ちをほぐす為に」
陽気な笑みを浮かべる兄を一瞥して、シグルズはふっと息を吐き出した。兄に較べ口数の少ない彼は、余興で人々を笑わせることに関心が無かったのである。
「兄上が一人で好きなだけ喋ればいい」
「いや、このような時は誰かを相手に話すのがよいのだ。余とそなたとは身内で、財産も教養も差がない。そんな我らが比較に足るならば、どのようなものがあるだろう? そなたが余に勝ると思うことは何だ?」
エイステインは弟に問うた。
シグルズは、いかにも面倒くさそうに兄を見た。
「俺と兄上との違いを言うなら、膂力の差かな。実際にやるつもりはないが、俺は兄上の背骨を折ることだってできるだろう。だが、年齢は貴方のほうが一つ上だ」
「そなたのほうが余より上背があって体格も良いのは事実だ。しかし、そなたが何の競技に熟達していたか、思い出せないなあ。教えてくれぬか、シグルズよ」
こちらが余興に気乗りしないのをわかっていながら、兄はさらに話を振ってくる。舌打ちしたいところだったが、堪えてシグルズは答えた。
「例えば水泳とか。その気になれば、俺は貴方を沈めることもできる」
「泳ぎなら、そなたと同じくらい上手かったぞ。それに、スケートでは余のほうが上だ。そなたより速く滑れる」
「遊びの延長のような競技より、もっと実用的な技術を較べよう。弓は首長の心得として必要不可欠な技だが、両足で踏ん張っても兄上に俺の弓は使えないと思う」
「確かにそなたほど強い弓は扱えぬが、矢の命中率は大差なかろう」
「誰よりも強く、様々な武芸に長じていることこそ、首長の備えるべき特質。そうでなければ戦場(いくさば)で精鋭を率いることはできぬ」
「戦場ではそうかもしれぬが、平時においては智恵のある者が尊ばれる。そして美貌を兼ね備えていることも、人目を惹くには重要な特質だ。また、余は法律に関してそなたよりもずっとよく通じているし、審議の際には雄弁さがものを言う」
「ええ、確かに」
と、シグルズは言った。
「貴方の滑らかな弁舌は、誰にも真似できないだろう。だが、すべてを信用できるとは言い難い。兄上は口が軽すぎて、すぐに約束は反故にされてしまうのだから」
「おやおや、わが弟は思っていたよりも口が達者なようだ。余は相手にとって良かれと思うことを口にするまで。そうして皆が喜んで帰っていくのを見るのが好きなのだ」
「俺が遠征を率いたことは首長らしい行いであったと皆に言われるが、貴方は王女のように国内にとどまっておいでだった」
シグルズのその言葉には、さすがのエイステインも気を悪くしたようだ。
「それについては我らの間で取り決めたことだ。そなたが遠征に出るほうを選ぶことは最初から判っていたから、余は姉妹とともにそなたの旅立ちの準備をしてやったのだ」
「俺がセルクランド(サラセン人の国)で数多くの戦いを経験し、すべてに勝利したことは貴方の耳にも入っているはず。これまでに無かったほど沢山の宝物をこの国に運び込んだこともね。俺は外国で王侯や最高の名士に会い、最高の評価を得た。その間、貴方は故郷で出不精を決め込んでいたのでは?」
「そなたの外国での戦いぶりは勿論聞いておるさ。だが、余はもっとノルウェーの為になることを国内で行なってきた。教会を幾つも建造し、港を築き、ビョルグンの町に立派な広間を備えた屋敷を建てた。そなたがセルクランドで青い肌(黒人)の異教徒を殺している間にな。それがノルウェーの利益になったとはあまり思えぬが」
「此度の旅ではヨルダン川を泳いで渡ったよ。その岸辺にあった藪の針葉樹で結び目を作り、願をかけた。兄上にそれを解くことができるかな? できなければ、それにかけた呪いがかかるといい」
「そなたのかけた願を解くことは、余にはできぬだろうよ。だが、そなたが帰国し、一隻の船のみで余の艦隊に加わった時、そなたにはとても解けぬような結び目を余はつくっただろう」
そこで二人の王は口を噤んだ。どちらも相手に対し腹を立てており、決して良い気分ではなかったが、言葉の応酬には互いの様々な苦悶が入り混じっていることを兄弟はよく理解していた。
暫しの沈黙のあと、
「まあ、この辺にしておこう。武芸で決着をつけるなら俺に分があると思うが、弁舌では到底兄上に敵わない」
シグルズが苦笑すると、エイステインも口許を緩めた。
「そうだな。我らはそれぞれ異なるものに秀でているのだから、足りないところを補い合えばよいのだ」
王たちの言い合いは余興とは言い難いものになったが、周囲に居た人々は兄弟の論争が激化して喧嘩に至らずに済んだことに安堵したのだった。
このように、二人の王は自己主張が強く、時には張り合ったりもしたが、それでも生涯仲がよかった。
エイステイン王とシグルズ王の共同統治は、一一二三年八月二九日にエイステイン王が病で亡くなるまで続いた。その後はシグルズ王が一一三〇年三月二六日に身罷るまで単身でノルウェーを統治した。
ノルウェー十字軍について
1107年から1110年にかけてのシグルズ王の遠征は、聖地イェルサレムでイスラム勢力と戦うキリスト教徒の救援としてイェルサレム王バルドヴィン(ボードゥアン1世)の依頼に応え、またシリアの要塞都市シドン攻略にも加わったことから「ノルウェー十字軍」と呼ばれます。
そのせいもあってか、シグルズ王の綽名は〈十字軍王〉(英語 Sigurd the Crusader)ですが、古ノルド語は Sigurðr jórsalafari 現代ノルウェー語(ブークモール)ではSigurd Jorsalfar で、本来は〈イェルサレム行きのシグルズ王〉の意味です。個人的に十字軍に参加した最初のヨーロッパの王として知られていることから、十字軍王の名が定着したと思われます。
しかし、13世紀にスノッリ・ストゥルルソンが著した『ヘイムスクリングラ』所収「マグヌースソンのサガ」には、十字軍の名称は出てきません。シグルズ王が率いた六十隻のノルウェー艦隊は途中幾つもの国や地域を訪れ、海賊や異教徒との戦いを繰り広げたことを述べながらも、ミクラガルズ(コンスタンティノープル)への大遠征として描かれています。13世紀当時は「ノルウェー十字軍」として認識されていなかったか、スノッリがそのように書かなかっただけなのかは不明です。
シグルズ王は1123年にはスウェーデンのスモーランドへ行き、古の信仰に戻っていた住民たちを(幾らか手荒な方法も用いて)キリスト教に改宗させました。これをスウェーデン十字軍と呼ぶことがあります。
エドヴァルド・グリーグの劇音楽『シグルド・ヨルサルファー』
ノルウェーの国民的作家ビョルンスティヤーネ・ビョルンソンの戯曲のためにエドヴァルド・グリーグが作曲した劇音楽「シグルド・ヨルサルファー Sigurd Jorsalfar」は、1872年4月10日にクリスチャニアで初演されました。三十分弱の作品ながら、大遠征に相応しい勇壮なマーチや王の歌、ヒロインのボルグヒルドの夢を題材にした穏やかなメロディーなどで構成されています。
補足
エイステイン王とシグルズ王は異母兄弟ですが、ハラルド苛烈王の直系(曽孫)です。
エイステイン王は地方領主の娘インギビョルグと結婚、娘のマリーアがいました。
シグルズ王はキエフ大公ムスティスラフ一世の娘でスウェーデン王インゲ一世の孫娘マルムフリーズと結婚。クリスティンという娘をもうけました。また、愛妾ボルグヒルドとの間に息子マグヌースがおり、彼がシグルズ王の跡を継ぎ、マグヌース4世となります。ただし血縁関係が不明な叔父ハラルド・ギリとの共同統治で、その後ノルウェーは百年に及ぶ過酷な内戦時代に入るのです。
内戦を経て、次にノルウェーが中世盛期の黄金時代を迎えるのは、ホーコン4世(ホーコン・ホーコンソン、1217 - 1263)の治世となります。
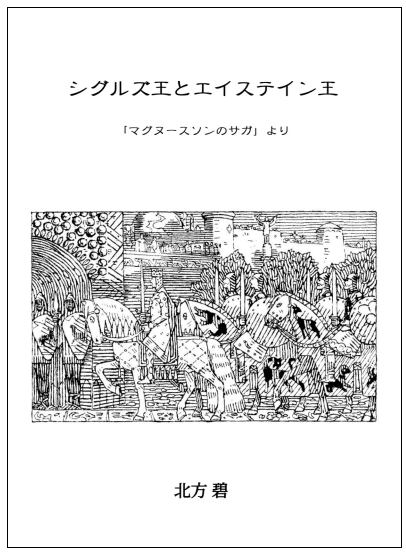
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
