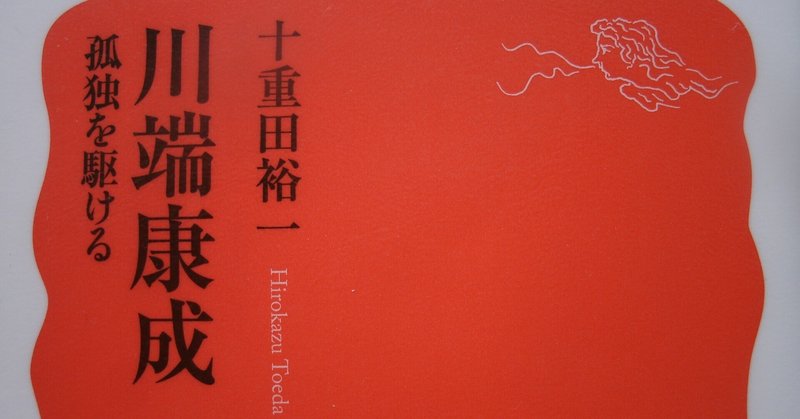
ノーベル文学賞の最初の日本人受賞者を巡って
十重田裕一の『川端康成 孤独を駆ける』(岩波新書 2023.3.17)は川端の作品と映画やテレビの新興メディアの興隆のリンクの指摘がとても興味深かったのであるが、それよりも気になった点がノーベル文学賞を巡る日本人作家の「攻防」である。最初に公開された日本人のノーベル文学賞の選考記録を引用してみる。
1958年 谷崎潤一郎・西脇順三郎
1959年 候補者なし
1960年 谷崎潤一郎(最終候補)・西脇順三郎
1961年 谷崎潤一郎・西脇順三郎・川端康成
1962年 谷崎潤一郎・西脇順三郎・川端康成・三島由紀夫(最終候補)
1963年 谷崎潤一郎(最終候補)・西脇順三郎・川端康成・三島由紀夫
1964年 谷崎潤一郎・西脇順三郎・川端康成・三島由紀夫
1965年 西脇順三郎・川端康成(最終候補)
1966年 川端康成(最終候補)・三島由紀夫(最終候補)
1967年 川端康成受賞
今となっては何故西脇順三郎がノーベル文学賞の候補に挙がっているのか日本人自身がピンとこないと思うが、西脇は英語で書いた詩がT・S・エリオット(1948年ノーベル文学賞受賞者のイギリスの詩人)やエズラ・パウンド(アメリカの詩人)に認められており、翻訳を経る必要がないために早くから認知されていたのであろう。
谷崎潤一郎も受賞に値するほどの実力は備わっていたものの、谷崎は1965年7月30日に79歳で亡くなってしまったために、選外になってしまうのだが、例え生きていたとしても谷崎が受賞していたかどうかは微妙だと思う理由は、谷崎は社会運動などと縁がなくいわゆる「政治性」が感じられないからであり、それは西脇順三郎にも当てはまるような気がする。
その点、川端は日本文学の普及に尽力し日本ペンクラブの会長まで上り詰め、ベトナム戦争や中国文化大革命などに意見し、新興メディアとの親和性も相まって目立つ存在であった。川端のノーベル文学賞受賞理由は「日本人の心の精髄を、すぐれた感受性をもって表現、世界の人々に深い感銘を与えたため:"for his narrative mastery, which with great sensibility expresses the essence of the Japanese mind."」とされているが、これは高度経済成長で失われつつある「日本人の心の精髄」を守るという意味合いもあったように思う。
後に1994年に大江健三郎が「詩趣に富む表現力を持ち、現実と虚構が一体となった世界を創作して、読者の心に揺さぶりをかけるように現代人の苦境を浮き彫りにしている : "an imagined world, where life and myth condense to form a disconcerting picture of the human predicament today."」としう理由で二人目の日本人ノーベル文学賞受賞者になり、川端康成が受けとった文化勲章は拒否した言わずと知れたゴリゴリの活動家でもあるが、川端が「内向き」の作風だとするならば、大江は海外の作品も積極的に作品に取り入れた「外向きの」の小説家で、想像を絶するテクニックで日本と西洋の文化の橋渡しを試みていたように思うし、そのように解釈するならばノーベル文学賞の受賞記念講演において川端が自身を「美しい日本」と形容し、大江が「あいまいな日本」と形容した理由も納得できるのではないだろうか。
ノーベル財団に影響力があったドナルド・キーンは「谷崎や川端が、もし三島に先を越されたら、日本の一般市民は奇妙に感じるだろう」として三島は受賞を逃したのだが、今から思えば三島の作家としての主な業績は『豊饒の海』を残して既に終わっている。三島の言動が「政治性」を帯び始めたのは1966年頃だろうが、三島が1970年11月25日に陸上自衛隊市ヶ谷駐屯地で自死した要因は、ノーベル文学賞を獲るために慌てて活動家として行動しようとしたものの、主義主張の辻褄を合わせようとして追い詰められた結果だったようにも見える(そんなおっちょこちょいではないか)。
