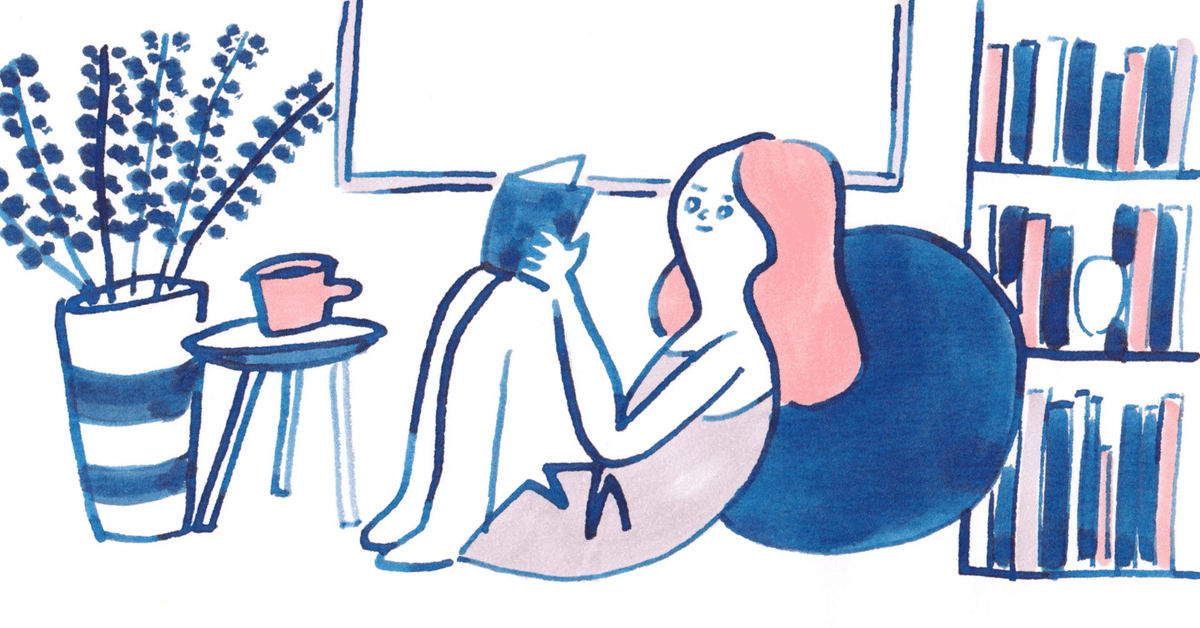
グローバル社会を再検討するための「遅さ」
前回の記事では、教育現場における「遅さ」の重要性について論じてきた。
良質な議論を形成するためには、最短ルートで「正解」を求めるような議論ではなく、ゆっくりとした時間の中で、自己や他者が変容していく姿を受け入れながら、議論する前には誰しもが立っていなかった場所にたどり着くような議論を展開すべきだ。
議論だけではなく「遅さ」は様々な場所に適応できる。
なぜ「グローバル」という言葉が噴出しているのか
近年の学校教育、特に私学では「グローバル人材」という言葉が飛び交っている。日本でいう「グローバル教育」というのは多くの場合は「英語教育」と言い換えることができてしまう。もちろん、グローバルという言葉が含んでいる世界は英語圏だけではない。ネイティブスピーカーの数でいえば世界一は断トツで中国語話者であり、英語話者はヒンディー語話者やスペイン語話者の数とさほど変わりはない。英語も、ある側面をみれば、世界の中のマイナー言語のひとつにすぎない。
そもそも「グローバル」という現象は大航海時代を端に発して始まった世界システム(ウォーラ―ステイン)を指すものであり、最近になって発生したような現象のようにもてはやされているけど、もう500年以上も続いている。近年になってなぜ「グローバル」という言葉が噴出したようにメディアに踊るかと言えば、近代的グローバルシステムの限界点が噴出しているからに他ならない。
資源・食料・労働力の供給の限界がここにきて明るみになり、コロナ禍やウクライナにおける戦争によってその傾向が加速度を増している。食料や資源はさらに供給を受けづらくなり、物価は高騰していく。国同士の紛争の危険度が高まってるとして各国は軍備を増強していく。そんな中で「グローバル社会でどう生きていけばいいか」という問いが生まれる。
「グローバル」を歪曲する学校現場
しかし、学校現場で「グローバル」という言葉が使われるのは「英語教育」に結びつけて宣伝文句として使われるのがほとんどだ。
その行く末は大学入試改革における英語外部利用の制度であり(直前に頓挫。これがなくなった本当にすごい。民主主義)、東京都で行われたESAT-J(英語スピーキングテスト)であった。実用的な英語の読み書きができるようになることが「グローバル」を生きていくということになる。
そこでは、グローバル社会の中で「民主主義」の御旗の下、帝国主義的に勢力を拡大しようとしているアメリカを追従することになり、その追従の結果、アメリカの功罪を検討しないまま同じく帝国主義な手法で領土を侵犯しようとする中国・ロシアに対する敵意を増幅させるだけである。この混沌としたグローバル社会を今後どのように構築していくべきか、という議論はないがしろにされ、敵意と戦略による国家経営がさらに広がっていく。
それは個人から個人への差別意識にもつながり、その差別の言葉はSNSによって拡散され、集団から個人への差別に繋がっていく。
今起きている現象を再検討しないで英語教育を増長させることになんの意味があるのだろうか。学校現場は「グローバル」という言葉とどう向き合っていくべきなのか。
学校は「グローバル」を再検討する場
本来、学校現場で行われるべきは「グローバル」という言葉の批判であり、再検討であるはずだ。日本が単独で資源・食料・労働力を国民に対して供給していくことは絶対に不可能だ。その方法はこれから技術革新を続けても実現することは無理だ。そうなれば、やはりこれからも世界システムの中で生きていくしかない。しかし、その中で生きていくということは飲み込まれていくということとは違う。
物価が高騰するとなれば、賃金を上げなければならない。しかし生産力が世界の中で相対的に低下している日本では思うような賃金の上昇は見込まれない。では、賃金を上げるためにはどうすればいいか、もしくは上げられないのであればどんな社会政策が必要なのか。
各国が軍備を増強させていく中、防衛費を拡大させることが安全保障上の最善策なのか。防衛費を拡大させるということは国民に増税を強いることであり、生活水準を下げてまで行うことなのか。中江兆民『三酔人経綸問答』において中庸である南海先生がプロイセンとフランスの軍備の拡大に対して「大いに兵を張るが故に、破裂すること有ること無し。」と述べているが、この小説風政治書が発行された明治20年から30年足らずで第一次大戦が勃発する。現代でも「抑止力としての軍備拡大であって、戦争のためのものではない」という説は多く聞かれるが、本当に軍備拡大は抑止力として機能し続けるのかはわからない。
ただ、グローバルを再検討するということは、イコール、ナショナリズムに身体をあわせることではない。グローバルとナショナリズムは共犯関係であり(小熊英二など)、「世界の中で一番である日本」という自己愛を増幅させることはグローバル社会をさらに妄信することになるという罠がある。
グローバル社会を検討しなければならない、でも自己を賛美してはいけない。というジレンマを抱える必要がある。ジレンマを抱えるために必要なのは「遅さ」だ。
「遅さ」を保つ=ジレンマを捨てない
こうした社会システムを検討するにあたって大切なことは「自分もそのシステムを利用しなければ生きていくことができない。けど、批判しなければならない」というジレンマを持つことである。
軍備の拡大を批判する。でも、軍備を完全に排除する(カントの言うように)社会では果たして安全保障を確保することができるのか。
低い賃金で働かなければならない、または低い賃金で海外からの労働者を働かさなければならない、ということは批判しなければならない。しかし、安い労働力によって今の私たちの生活が保たれているのだとしたら、どう変えていくべきなのか。でもやっぱり労働環境は改善しなければならない。
議論が固定化されないためには、こうしたジレンマを持つことが大切である。そして、ジレンマを持ちながら再検討・または議論を展開するにはやはり「遅い」議論が必要だ。いち早く結論を出そうとする議論では、ジレンマを抱いている時間的な余裕はない。カール・シュミットが言うようにわかりやすい「敵」と「友」にわかれて論戦を交わさざるを得なくなる。
対話に必要なのは、議論の中でどの参加者たちにもなかった境地にたどり着くことであり、そうした境地にたどり着くためには、ジレンマを抱えながらそのジレンマを丁寧に言葉として表現していき、意見を形成していく必要がある。ジレンマを抱きながら議論を展開するためにも、学校現場では「遅い議論」が求められる。いや、学校だけではなく社会のいたるところで求められることであろう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
