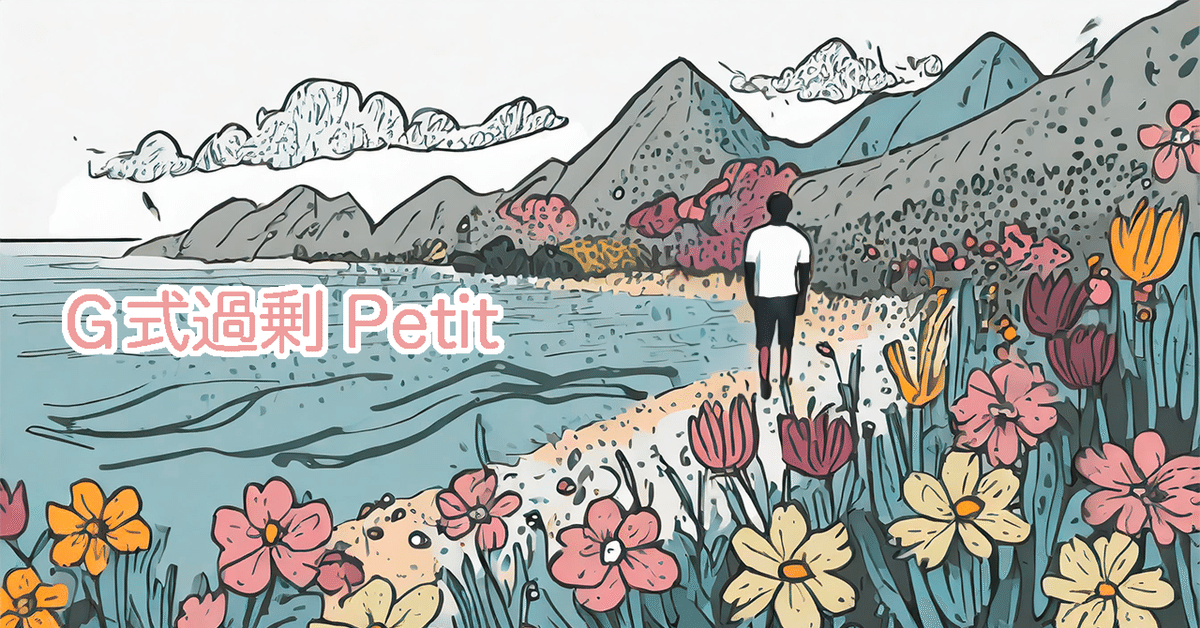
【研究と実践】OUR Projectに関するシンポジウムに参加した
シンポジウム「OUR Project(生活・文化拠点再整備事業)における市民参画プラットフォームをつくり、育てるために」
OUR Projectとは藤沢市の生活文化拠点施設再整備構想で、シンポジウムはこの構想に関するものでした。
冒頭の説明での施設整備というハードな計画と市民参画の事例との関連性が結び付かず、正直、頭の中に?マーク。そして、市民参画といいつつ”何を”、”どのように”というような具体的なプラン提示もないままに説明が進み、さらに混乱。
ですが。
パネリストのプレゼンを聴いているうちに「ああ、これは市民参画の拠点としての施設を模索していて、そのために市民参画にはどういう仕組みや意識が必要かという、市民参画そのもののデザインを考えてみようという会なのだな」と理解できました。
だったらはじめからそう言ってよ。
パネリストの2名の話は面白く興味深いものでした。
それぞれの活動がジャンルは違えど、人と人を繋げることで社会活動をインキュベートする。その場をどう構築運営していくのか。自分の目下の関心ごと(コミュニティとアート)が主題だったこともあり、すごく参考になりました。
パネルセッションも議論が噛み合ったよい展開でした。場内からの質問も当日の話題の文脈に沿って課題を深掘りできる良い内容だったのがよかったです。
自分、場内からの質疑応答は、的外れな内容になりがちであまり好きじゃないんですよね。質問応答をやる時はひと手間必要派です。実際に自分が主催の時はその場で手挙げ式の質疑応答はしなかったなあ。あ、これは脱線話か。
今回、得られた知見としては、
・コミュニティは弱いつながりの方が持続する。
・コミュニティは同質な集団だけではうまくいかない(30%理論みたいな話かな?)。
・人のつながりを生み活動を活性化するためには、場所(拠点)が必要。
・既存の言葉は良くも悪くもイメージがあり新しい行動に対する理解を歪める場合がある。新しい言葉使い続けることが重要。
自分が普段感じていたモヤモヤを言語化してもらえた感じもあり、すごく勉強になりました。
あと最後にひと言。司会進行役の人。無表情で仏頂面、ずっと会場を睨んでいるようで、なんかすごく怖かったなあ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
