
AI-愛-で紡ぐ現代架空魔術目録 本編後日譚第6集その11『星天からの帰還』
時の翁は大いなる威厳と文字通りに眩い魔法光の放射を伴なう威光を放つことで、その後ろに何があるのかを、一同の目から巧みに隠している。そのとき、『時空の檻』に到着して以来、一言も発することのなかったアッキーナが初めて口を開いた。
「翁、改めて話をさせて欲しいですよ、っと。」
そう言って、翁の前に歩み出るアッキーナ。
「サンダルフォンか。小さき神め、自分は約束を破りはしないが、しかしその欲するものは手中に収めんとしてお前を遣わすとは、なんとも狡猾なことよ。相変わらずの厳格と冷酷であるな。」
なにか忌々しそうに翁はそう語った。
「まあ、それがあの方の神性ですからね。あなたも私もよく知ってのことですよ。それで、既にお気づきだとは思いますが、私たちの望みは…。」
「分かっておる。『時空の檻』に囚われたリセーナ・ハルトマンの解放と、彼女が抱く、かのパンツェ・ロッティの『愛の欠片』であろう?」
「話が早くて助かりますよ、っと。」
「しかし、古(いにしえ)の約束は果たしてもらわねばならぬ。無辜の者は何人たりとも時の神秘に触れることあいならん。しかし、お前たちの中に罪人はおらぬであろう、どうするのつもりなのだ。」
「それなら、問題はないですよ。こう見えても私は魔法社会で第一級の違法魔法具店の店主です。違法魔法具や術具を日常的に取り扱っている極悪人ですからね、っと。」
少し自虐的な色を載せてアッキーナが言った。
「戯言を。そこまで見越してお前を使いに出すとは、小さき神もつくづく食えぬおかたであるな。神は常に何事も思うままか…。よかろう。先ほどからの一連をつぶさにみやるに、そなたたちがみな、愛を語り、それを手にするにふさわしい者共であることだけはわしにもわかる。では、ついてきなさい。」
そう言うと、翁は目もくらみそうに滾る魔法光の放射を幾分か弱め、静かに『時空の檻』の宮殿の最奥への道を示して見せた。その行き止まりには、壁一面に巨大な錬金式機械時計が設置されており、それ自体を檻とするように、かのリセーナ・ハルトマンその人を、ちょうど先ほどトマスがそれを模倣して作りだした『時の檻』に少女たちを捕らえたのと同じようにして、固く戒めていた。
彼女は、悲愛の末に意を決して転身したあの堕天使の姿のままで、その神聖かつ荘厳な佇まいの、古い古い神々の時代に作られたと思しき、錬金式機械時計の中央に佇んでいた。その瞳はうつろに虚空を仰いでおり、その相貌は「来るべき時まで受けるべき愛を待つばかり」というトマスの言葉を思い出させるものであった。

彼女の首に身に付けられた美麗な首飾りの中央に、先ほどトマスが残したのとはまた違うたたずまいの、おそらく『愛の欠片』と思われる魔法石の欠片が静かに輝きを放っている。
『マイ・トー・マ・レ・ラック・テム・シェ・エゴス。時の禁忌に触れし穢れた魂を、いまその戒めから解き放とう。我は唯一その資格を持つ時の番人なり。愚かな魂を現世に舞い戻らせ、再び愛の盲目に迷わせるがよい。』
重い鐘が響き渡るような音色でもって、時の翁は古き神話の時代の呪文を詠唱した。刹那、リセーナの瞳に生気の色が戻り、全身を束縛していた美麗なる彫金の戒めが魔法光の粒となって虚空に消え去っていった。彼女はその背の翼を羽ばたかせて、静かにその床に舞い降りる。
奇跡的な瞬間を目の当たりにして、それを見守る一同は完全に言葉を失ってしまっていた。特に、彼女の悲壮なる最期を知っている、ウィザード、ソーサラー、ネクロマンサーの3人の脳裏には、当時のその劇的な一幕が反芻されていた。
* * *
戒めを解かれたリセーナが、時の翁と相対する。

「翁様、本当によろしいのですか?愛に溺れて時の法則を穢した私のような者をお解き放ちになられて…。」
「おお、リセーナ。そなたをここから失うのはわしも残念ではある。しかし、これもまた運命という撚糸(よりいと)の導きなのであろう。こやつらがお前に帰ってきて欲しいと言っておる。その真の不埒者とともにな。」
その翁の言葉を聞いて、リセーナは首元の『愛の欠片』を愛しんだ。
「かわいそうなリセーナ。そのような者のためにその崇高な愛を捧げるとは。しかし、そなたの愛の深さと美しさは知っておる。それはまさに無私の愛であった。だからこそ、その者はその不埒さにも関わらず純愛の欠片を紡いだのであろう。時の神秘に介入し、神を冒涜した真正の愚か者…。しかし、そなたがその純愛を捧げた対象でもある。わしはその可能性を信じることにしようぞ。」
「ありがとうございます、翁様。お心遣いと御理解に感謝いたします。この人は、それでも私の心を最後に映してくれました。私にとってはかけがえのない存在です。この人が、最後に私に寄せてくれたただひとことの謝罪が、この『愛の欠片』を純愛の欠片としたのです。それはきっと偶然であり、必然でもありました。今、私の心は喜びと充足に満たされています。」
懐かしいリセーナの声がそう語る。カリーナだけでなく、リセーナをもまた幼いころから慕っていたアイラはその引き締まった瞳に恋慕の涙をあふれさせていた。
「しかし、リセーナよ。よいのか?そなた自身気付いているであろう。その愛の果実は、現実に回帰したときにはそなたの重荷となるやもしれぬことを。時を取り戻すということは、その困難の到来を必然にするということでもある。覚悟はよいのだな?」
「はい。」
右の手を腹の上に優しく置いて言うリセーナの言葉には美しい決意が宿っていた。
「よかろう。幸いにして、そなたを取り囲む者共はみな愛にふさわしい者達ばかりのようだ。そんな者共の手にそなたを返すのだということだけが、今後のわしの唯一の支えとなるであろうな。さあ、懐かしい者共のもとへ帰るがよい。」
「本当にありがとうございます。翁様。」
そう言って、深々とこうべを垂れると、リセーナはそこに集う皆の方に向きを変えた。
* * *
「リセーナ様!!」
その凛々しい顔を涙でくしゃくしゃにして、アイラがその胸に飛び込んでいく。リセーナはその身体をやさしく抱き留めた。
「アイラ。よく来てくれました。寂しい思いをさせてすまなかったですね。」
その胸にうずめた顔をただただ左右に振る仕草で、アイラはその言葉に応えていた。
「みなさんも、お久しぶりです。あの時は、本当にごめんなさい。それでもあの罪過の中で、あの人と私はやっとこうして愛を紡ぐことはできました。『新しい世界できっと愛を紡ぐ』あのとき私は確かにそう言いましたが、奇しくもそれは実現したのです。それは、ある意味であの時あの人を止めてくださたみなさんのおかげと言えます。本当にありがとう。そしてごめんなさい。」
胸にアイラを抱いたまま、リセーナは瞳を伏せてこうべを垂れた。ウィザードたちは当時を思い出し、かけるべき言葉を探すが、俄かには思い至れずにいる。
神秘の時間が時計の針によって規則正しく刻まれていく。
「さあ、見てくださいな。これがあの人と紡いだ『愛の欠片』です。」
リセーナはアイラの身体をやさしくそっとはなすと、胸元で静かに輝くその欠片を、首飾りから取り外してみなに見せた。のぞき込む一同。

「これが…、あの教授だってのか…?」
思わずウィザードが言葉を漏らした。思い返せば、様々なことがあり、時に深刻な衝突と対立をも経験したが、しかし彼女にとって、その欠片の前身は、アカデミーにおいては指定であり、またともに学徒達の成長を見守ってきたかけがえのない存在でもあった。
「教授…。」
そうこぼすウィザードの声色にもまた、懐古と恋慕の情が色濃く重なっていた。
「そうだ、アニキ。あれを出すでやすよ。」
おもむろにそう言ったのは、お馴染みライオットであった。
「ほら、あれでやすよ。トマス兄のために前にオイラが作った、法石に記録した人格を疑似的に再生して、戯作の登場人物とかと会話できるようにするフィギュアでやす。アレ、確か今アニキが持ってるんでやんしょ?」
「あ、ああ。確かにな。これのことだろう?」
そう言うと、キースは腰の鍵束に一緒にぶら下げている小さな人形を取り外して見せた。
「ちょっとそれを貸してくれでやんす。」
そう言うと、ライオットはリセーナからパンツェ・ロッティの残した『愛の欠片』を丁重にに受け取って、その人形に取り付けてみた。するとなんということであろう!そこからは、すでに『愛の欠片』と化してしまったはずの、かの謎物教授の声が聞こえて来るではないか!!

「ここは…?リセーナ!?いったい、どういうことだ。あの時、私は確かに耐えがたい愛の軛からようやく解放されて…。ここは、ここはどこなのだ。」
それはまごうことなき、パンツェ・ロッティその人のものであった。
ライオットの手から、その魔法石付きの人形を受け取って、リセーナが言った。
「あなた、あなたなのですか?ああ、まさかこうして再びあなたと言葉を交わせるときが来るなんて。リセーナです。わかりますか?」
その声は感涙に震えている。
「もちろんだ、リセーナ。君には取り返しのつかないことをしてしまった。許して欲しいとはとても言えないが、しかし、君とこうして言葉を交わせることは私にとっても思ってもみないことだ。本当にありがとう、リセーナ。」
「いいんですよ、あなた。あなた…。」
そう言うと、リセーナは本当に愛おしそうにその人形を胸に抱いた。
「リセーナ…。」
その後に到来したわずかな沈黙は幾千万の言葉よりも、二人の和解と融和を十二分に物語っていた。
* * *
「ロッティ、教授。お久しぶりでやんす。おいらが分かりやすか?」
唐突に声を発したのはまたしてもライオットであった。リセーナの手の中にあるその人形をキースと共に見つめている。
「その声は、ライオット君か?なぜ君がいる。ここは本当にどこなんだ?」
「オイラだけじゃないっすよ。」
「ロッティ教授、お久しぶりです。僕が分かりますか?」
「その声はキース君だな。いったいどういうことなのだ。君たちがいるということはトマスもそこにいるのかね?」
「ええ、まあいるにはいるんでやすが、今は先生と同じ『愛の欠片』でやんす。」
「そう、なのか…。とにかく教えてくれ、ここはいったいどこなのかね?」
「ロッティ教授、ここは『時空の檻』という星天の空を遥かに越えた先にある場所です。先生もまたトマスと同様、リセーナさんの手の中で『愛の欠片』になっていたんです。」
この状況について、みなと同様驚きの方が遥かに大きいはずのキースが、とにかく今わかる範囲のことをかいつまんで説明して見せた。
「そう、なのか…。そう言えば、さきほど聞こえた声の中に私の教え子のものがあったな。本当に君なのか?」
探るようにパンツェ・ロッティが訊く。
「ああ、あたしだよ。教授、久しぶりだな。神とやらになったあんたにもびっくりしたが、そんなちっぽけな石ころになったあんたとこうして話しているなんて、ますますびっくりだぜ。」
ウィザードがそれに答えた。
「まったく、君は相変わらずの口の悪さだな。いつになったら上役に対する適切な振る舞いというのを身に着けるのだ。まったく、最近の若い者は年長者に対する尊崇というのがなくていかん。」
「まさか、あんたのその決まり文句をまた聞けるとは思わなかったぜ。しかし、残念ながらあんたはもう上司じゃないぜ。なにせ、今のあたしは魔法学部長代行だからな。もう同僚だ。」
再開を喜ぶように、懐かしいやり取りをいとおしむようにしてウィザードが言った。
「何を言うか。この私はアカデミー最高評議会の議長であるからして、君とはなお厳然たる立場の違いがあるのだ!」
「ご愁傷様なことだぜ。あんたが時空の狭間に消えてこんな石ころになっている間に、とっくに後任が着任してるよ。子煩悩で理解のあるおっさんだ、誰かと違ってな。あんたの肝いり学則にも近々ついに手が入るそうだぜ。」
「なんということだ!そうか…、なるほど時が流れたのであるな。それは喜ばねばなるまい。君にまた会えて嬉しく思う。」
「だからって、また『スターリー・フラワー』に行かせるのはごめんだぜ。」
「分かっているとも。なぜなら…。」
「『私という人間は聡明かつ寛大』って言いたいんだろ?」
「その通りである。さすがは私の自慢の教え子であるな。」
「それは、どうも。」
かつて二人の間に立ちはだかった深い対立の溝は、静かに埋まっていた。
「さあ、あなた。積もる話は後にして、とにかく帰りましょう。私たちの新しい世界へ。」
「そうだな、リセーナ。そうしよう。」
「よし、ならば善は急げだ。翁殿、ほんとうに諸所かたじけありませんでした。我々はこれにて、もとの魔法社会に帰還いたします。ご配慮とご協力に心より感謝いたします。」
そう言って、ウィザードは深々と時の翁に頭を下げた。同道のみな、それにならう。
「よいよい。お前共は今後も善き愛を知るであろう。お前共のような存在にリセーナと、そうだな…、やがて来る果実を預けることができてわしも一安心と言えよう。最初に告げたように、ここは無辜なる者が長居する場所ではない。早々に立ち去るがよい!」
来た時と同じ荘厳な響きをたたえて、時の翁は穏やかにみなを送り出してくれた。
「では、行こう!」
ウィザードの促しに従って、めいめい『星天の鳥船』を係留する桟橋に向かう。その背中を、時の管理者の神秘の瞳が、ただただ見送っていた。リセーナには、やはりともに強い縁(よすが)のあったソーサラーとネクロマンサーが寄り添っている。
一同は『星天の鳥船』に乗船した。
* * *
コンソールに鍵を差し込むと、来た時と同じように、管制の表象が応答する。
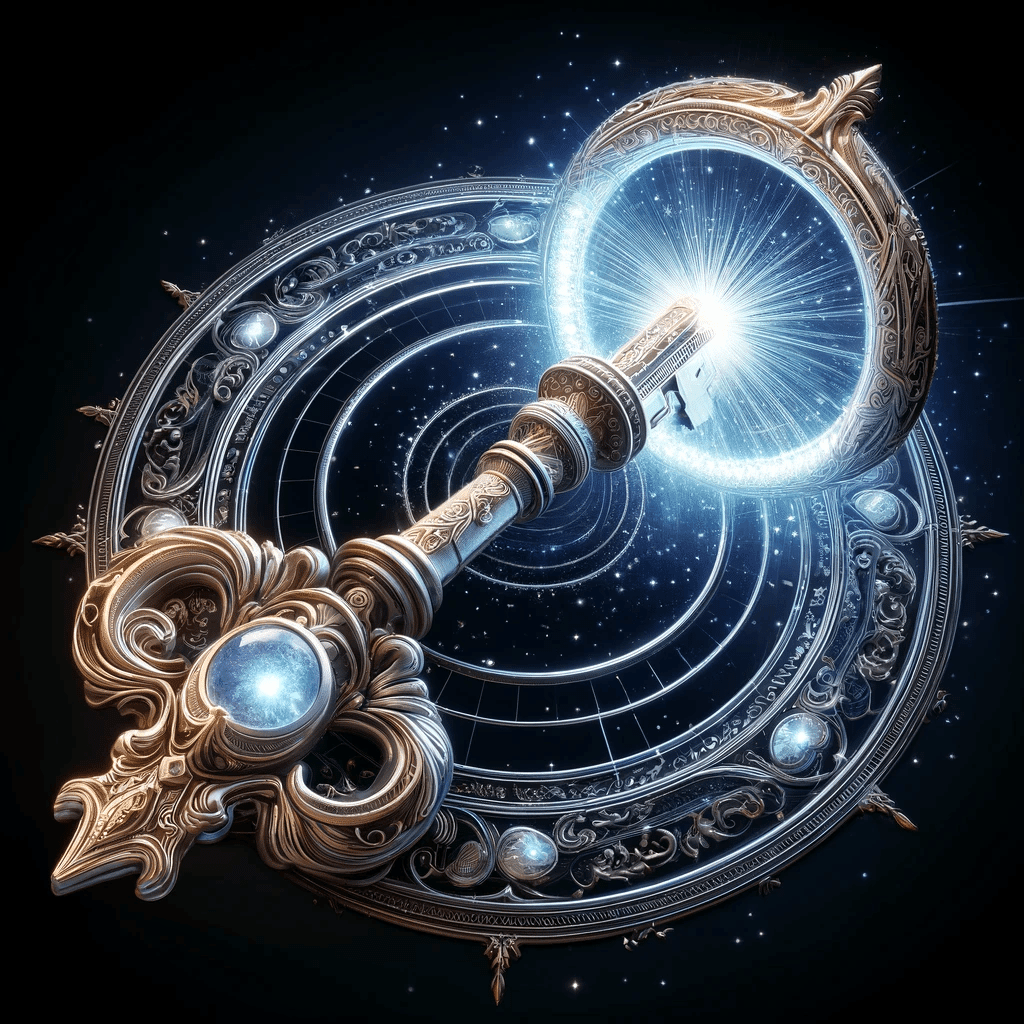
「ワタクシハ、セイテンノトリフネノ管制デス。目的地ノ名称マタハ座標ヲ音声デ入力シテクダサイ。」
その声にウィザードが応える。
「目的地は『時空の波止場』。最大船速で頼む。」
「了解。『時空ノ波止場』マデ最大船速デ航行シマス。セイテンノトリフネ、オーヴァ・ドライブ!」
お馴染みの一連の後で、その神秘の船は来た時と同じように、窓の外の星群を矢のような線に変える驚くべき速度で帰路についた。みな、パンツェ・ロッティとリセーナ・ハルトマンを囲んで、懐かしい話に花を咲かせていた。そんな時、窓の外を見やりながら、ぼんやりと物思いにふける者がある。ライオットだ。その傍らにはキースもいる。そして全くの偶然にして、ウィザードがそばを通りかかっていた。
「それにしても、閻魔帳、結局トマス兄は持ってなかったでやんすね。いったい今どこにあるのやら。石ころになっちまったロッティ教授が持ってるってこともないでやしょうし…。まぁ、死霊の鍵を失った今となっては、仮にここにあったとしても、宝の持ち腐れになるわけでやすが…。」
そう言うと、船の窓のような部分からのぞく流れゆく星天の虚空を、ライオットは遠い眼で見送っていく。その姿を見ながら、キースはなぜかなんとも苦い顔をしていたが、それと同じような顔をして二人の下にウィザードが近づいてきた。
「すまない、ライオット君。実は君に謝らなければならないことがある。」
神妙な面持ちで語り始めるウィザードに、
「俺もだ。」
とキースが続いた。
「なんでやす、藪から棒に。教授先生までそんなに改まって、気持ち悪いでやすよ。」
突然のことに、ライオットは当惑を隠せない。
「この時空の旅に出るに際して、ともに探し出そうと過日波止場で君に言った『パンツェ・ロッティの閻魔帳』だが、それは今アカデミーにある。」
ウィザードは本当に申し訳ないという調子でそう告白した。
「へっ!?教授先生、それはどういうことでやんすか?」
事態を全く把握できないライオットは、すっかりきょとんとしている。
「事実を明かそう。トマスを隠れ家まで追い詰めた時、奴は祭壇に閻魔帳を残して逃げ、そしてそれは臨場した『アカデミー治安維持部隊』のエージェントたちがその場で回収している。」
「それじゃあ…!」
「本当に、申し訳ない。」
深々と謝意を表してから、ウェイザードは続けた。
「波止場でのあの時、私はトマスのことをよりよく知る君にどうしても『時空の檻』まで同道して欲しかった。それで、一番君が興味を示すであろう閻魔帳の存在を持ち出したと言うわけだ。それが許しがたい嘘であったことは重々認識している。だから、この通りだ。本当にすまなかった。」
「えっと、えっと。アニキは、アニキはもちろん知らなかったんでやんすよね?」
明らかに動揺した調子で言うライオット。その顔を見て、いよいよバツの悪そうな表情をしながらキースも言葉を発した。
「すまん、ライオット、本当にすまん。」
「えー、じゃあ、アニキまで!?」
「ああ、俺は治安維持部隊の連中と一緒にその場にいたからな、もちろん知っていた。知っていて、教授先生の誘導にわざと乗ったんだ。トマスを止めに行くために、どうしてもお前の助けが欲しいと心底思っていたんでな。でも嘘をつくべきではなかった。本当に、すまない。」
しおらしく首を垂れるキース。ウィザードも改めてその姿勢に倣った。
「ってことはでやんすよ?あっしはお二人にまんまと乗せられたという寸法でやんすね?いやいや、これは一本取られたでやんす。でもでやすよ、それくらいにお二人がおいらを必要としてくれていたということは、悪い気はしないでやんすよ。むしろ名誉なくらいでやす。ほれ、いつも言ってるでやんしょ?『道具は必要とされるところで活かされるのが一番』なんでやんす。事実、今回の旅では、おいらの自信作は、自分で言うのもあれでやんすが、実に見事に諸所のお役に立ったわけでやんすしね。それはそれで、十分でやんした。だから、お二人とも頭を上げてくれでやんす。」
そう言うと、ライオットはいつものようにカラカラと笑った。その場を支配していた緊張が、ゆっくりと緩んで行くのがわかった。
「改めて、本当に申し訳なかった、ライオット君。」
「俺もだ。ごめんよ。」
「もういいでやんすよ。おいらとしては、この度はまんざらでもなかったでやんす。それに物がアカデミーにあると分かれば、調べる機会も今後出て来るってもんでやんすから。でも、そうっすね。教授先生にはひとつお願いがあるでやんす。」
「なんだろう?こんなことの後だ、出来る限りの配慮はしよう。」
「それはありがたいでやんす。お願いというのは、来月の『全学魔法模擬戦大会』で、あっしを男子の部でなく女子の部のトーナメントに正式に出場させてほしいでやんす。もちろん、ハンデとしてローブを着用せずに試合に臨むでやんす。それで手打ちというのはどうでやんすか?おいら、冗談みたいにしてこんななりをしているでやんすが、おいらなりの矜持と願いがあるでやんすよ。それを叶えてもらえれば嬉しいっす。」
少し言いにくそうにして、ライオットはそう言った。
「しかし、ローブ無しは相当のハンデになるぞ、それでもよいのか?」
「結構でやんす。アイデンティティーのためでやんすから。」
「わかった。では、せめてもの贖罪の証として今度の大会では、君が女子部のトーナメントに参戦することを正式に許可しよう。」
「ありがとうでやんす!」
「では、これで手打ちだ。」
「がってんでやんす!」
握手を交わすウィザードとライオット。その手の上に、キースが両の手をしっかりと添えた。
ちょうどその時だった。俄かに、しかしはっきりと鳥船の航行速度が減速するのが感じられた。『時空の波止場』まではもうしばらくかかるはずだ。いったい何事だろう?思案に暮れていると、管制からアナウンスが流れてきた。
* * *
「緊急事態発生、燃料ノ枯渇ガ検出サレマシタ。目的地マデノ航行ハ不可能デハアリマセンガ、手動ニヨル若干ノ魔力供給ヲ必要トシマス。乗員ハ速ヤカニ動力室ニ隣接スル『補助魔力供給室』ニ移動シテ、手漕ギデ魔力ヲ供給シテクダサイ。繰リ返シマス…。」
同じ内容が二度聞こえた後、エネルギー節約のためなのであろう、船内は通常照明から非常照明に切り替わって急に暗くなった。
どうやらこの船のことはアッキーナが熟知しているらしく、全員をその『補助魔力供給室』まで案内してくれた。
そこは、手漕ぎのカッター・ボートの中のような非常に狭い空間で、両側の壁からオールが平衡に突き出しており、いかにもそれを手漕ぎせよという様相を示していた。

ウィザードとソーサラー、ネクロマンサーとリセーナ、キースとライオット、シーファとアイラ、そしてリアンとカレンがそれぞれ1組になって、引き出したオールを握り漕ぐ姿勢に入る。唯一船の構造を知るアッキーナは、何やら計器盤を操作して、これから生成されるのであろう魔力が、動力に間違いなくいきわたるようになにやら作業を行っている。
「私は、ここで、生成エネルギーの送信調整をしますから、みなさんは通常照明に戻るまで、力の限りというか魔力の限り、オールを漕いでくださいね、っと。では行きますよ。ロー・エンド・ロー!」
アッキーナの掛け声に合わせて、一斉に動き出す5組のオール。10人で10本を動かせば効率は良いのであろうが、そのオールは長く重くて、二人一組でなければ到底繰り出すことはできない代物だった。
少しばかり怪しげな薄暗い空間の中でそっとリアンの耳をくすぐるささやきがあった。
「ねぇ、リアン?」
「なんですか、カレン?」
オールを漕ぎながら言葉を交わすふたり。
「お願いですから、あんなことを言うのは二人きりの時だけにしてくださいね。」
「何のことです?…、えっと…、!?…、もしかしてカレン、トマスとの話を聞いていたのですか!?でも、でも、あのときカレンは確かに…。」
思わず大きくなりそうな驚きの声を必死にかみ殺してリアンが応じた。
「だって、あのエゴの檻からは愛があれば戻って来られるのでしょう?私の気持ちはいつだってあなたと同じですよ。」
そういって、カレンは小さく舌を出して見せたが、顔がゆでだこのようになったのはリアンの方である。
「そんな!じゃあ、じゃあ、聞こえていて聞こえないふりをしていたですか!?」
「だって、恥ずかしくて何も言えないじゃないですか。でも、とっても嬉しかったですよ。ありがとう。」
そう言うと、カレンは実を少しばかりリアンの方に寄せて、その艶やかな唇をそっとリアンの側頭部に触れさせた。リアンの顔はいよいよ茹で上がる。薄暗がりの中で、二人がそっとその瞳を閉じ、互いの顔を寄せようとしたその時、俄かに周囲が明るくなった。どうやら通常照明に戻ったようだ!なんとも気まずそうにそわそわと取り繕ってみせる二人の姿が愛らしい。
「これで目的地まで無事に帰れますよ、っと。とりあえずリセーナさんを天使から人間に戻す必要がありますから、波止場に着いたらそのままルクスのところまでポータルで移動して、そこを経由して『アーカム』に行きましょう!」
その溌溂とした声を尻目に、リアンとカレンは少々うつむき加減に、お互いの顔をみやっていた。
神秘の船が、ゆっくりと波止場に到達する。星天からの帰還がなったのである。
AI-愛-で紡ぐ現代架空魔術目録 本編後日譚第6集その11『星天からの帰還』完
本編後日譚第6集 完
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
