
AI-愛-で紡ぐ現代架空魔術目録 本編後日譚最終集その6『信頼と絆、師弟の縁』
急激に魔力枯渇を起こし、深刻な意識障害を来した、ルシアン、アベル、ダミアンの3人に、その場に駆けつけた看護学部の医療班が応急処置を施していく。その様子を一段高いところから見守る人物の傍(そば)に近寄って来る人影が2つあった。
「マリクトーン教諭ですわね?」
審判席から今まさに立ち上がろうするマリクトーンの仕草を遮るようにして、聞き知った声がする。
「なんですか、あなたは!突然不躾に。高等部とは言えあなた方は学徒でしょう。分を弁えなさい。」
マリクトーンは明らかに不機嫌な様子でその声かけに反抗した。
「教諭の仰る通りだよ、セラ。我々は立場を弁(わきま)えなければいけない。いや、部下が大変な失礼をしたマリクテル先生。我々は『アカデミー治安維持部隊』のエージェントで、私はカステル・ウィンザルフ警部、こちらは部下のセラ・ワイズマン警部補です。」
「教師の名前を平然と間違えるあなたの無礼も相当なものだと思いますよ、カステル警部。それで、どのような御用かは知りませんが、私はあそこで意識を失っている教え子の下に駆けつけてやりたいので、今すぐそこをおどきなさい。」
そう言って、無理やりに競技フィールドに降りようとするマリクトーン。
「それはお急ぎの所、申し訳ありません、マリクテル先生。しかし、私たちの用も少々急を要しておりまして。セラ!」
カステルの言葉に合わせて、セラが一枚の書類を取り出し、それを開いてマリクトーンに見せた。俄かにその顔が青ざめるのが分かる。
「あなたに逮捕令状が出ています。発行は魔法学部長代行の具申によるものですが、既に最高評議会の追認は取り付けてありますのでご安心を。あなたには、アカデミー内で故意にいじめを黙殺・放置し、剰え、謀略によって被害少女たちに一層の不利益をなそうとした、著しい職務懈怠の容疑がかかっています。令状はその事実に基づくものです。早速我々に御同道いただきたい。」
カステルがマリクトーンに迫った。
「おまちなさい。いくら『アカデミー治安維持部隊』のエージェントとは言え、学徒が教師を逮捕するなど、越権にもほどがあるでしょう。せめて教職の上官を連れていらっしゃい。さあ、速やかに道を開けなければ、今度はあなたたちが綱紀委員会のもとで査問を受けることになりますよ。」
マリクトーンは何とかその場を逃れようと必死のようすだ。
「まあまあ、マリクテル先生。」
「マリクトーンです!」
「これは失礼しましたマリクテル先生。しかし、これが私たちの職務でして。この逮捕令状もまた、正規の手続きを経て魔法裁判所が発行し、最高評議会が追認したものですから、私共には先生に御同道いただく職務上の権限を持ち合わせているのですよ。失礼ながらお手を拝借。」
手錠をかけようとするカステルの手を必死に払いのけるマリクトーン。いつもの嫌味なほどに落ち着き払った余裕はすっかり鳴りを潜めている。
「まあ、教諭のお立場にしてはずいぶんとお見苦しいことですわね。」
「セラ、そんなことを言っていないで手伝ってくれると助かるのだが。」
「言われるまでもございませんわ、カステル。ちょっとそこをおどきになって。」
そういうと、セラは、カステルを若干退けてマリクトーンの前に出ると、携帯式魔術記録の映像をこっそりとマリクトーンに見せた。彼女の顔はみるみるうちに、色を失っていく。
「これをいったい…。」
「ご心配には及びませんわ、教諭。よく逮捕令状をごらんになってみることです。罪状はあくまでも『著しい職務懈怠』でして、こちらの件ではございませんの。ずいぶんと理解のある上司をお持ちのようでうらやましいことですわ。代わっていただきたいものですわね。」
「おやおや、私は君の、理解ある上司のつもりなのだが。まあ、精進するよ。聞いての通り、そう怯えられることはありません、マリクテル先生。たいそうご心配でしょう、こちらの件については、あなたのお優しい上司の方から我々に厳しい緘口令が敷かれていましてね。目下のところ外聞に触れることはないのですよ。さあ、お分かりになられたら、素直にご同道なさいませ。私としましても、敬愛すべき先生を公務執行妨害で現行犯逮捕するようなことは避けたいのです。」
そう言って、不敵な笑みを浮かべて見せるカステル。
「まあ、よくおっしゃいますこと。いずれにしましても先生、もう一度だけお聞きしますわ。令状はこの通りございます。私どもとご同道くださいますね?お答えによっては…。」
「これこれ、セラ。先生を脅すようなことを言うものではないよ。我々は常に尊崇の念を持っていなければ。ということで、ご同道いただいてよろしいですね?
どうやら、カステルの勝ちのようである。マリクテル、もといマリクトーンは肩を落としこうべを垂れて、観念の情を示した。
「おわかりいただき光栄です。セラ、ひとまずそれをしまって。」
「心得ておりますわ。」
「結構。そこの君たち。要逮捕者の身柄を確保した。手数をかけてすまないが、彼女をすぐに本部に護送してくれたまえ。」
カステルがそう声をかけたのは、傍に控える、おそらく中等部の高学年からなるのであろうエージェントの一団だった。
「セラ、念のため同道を頼む。」
「あなたはどうなさいますの?」
「私はちょっと別口でがあってね。とにかくここはまかせたよ。私とてそちらの方はあまり気乗りしないのだが、学徒想いのあの方に、これ以上ご負担をかけるのも酷な気がしてしまってね。」
「それはまあ、なんとも結構なことですわね。」
「そうだとよいが。とにかく、あとは任せたよ、セラ。」
そう言うと、カステルはマリクトーン移送の指揮をセラに、またその実務を中等部のエージェントたちに任せて、競技フィールドの方に降りて行った。
空の鉛色は一層濃くなり、今にも雨が降り出しそうだ。不快に湿気を帯びた冷たい風が開けた競技フィールドを吹き抜けていく。
* * *
審判席のところでこんなやり取りがされるほんの少し前、ちょうど、ルイーザが驚愕の術式を繰り出した時の、高等部1年の観覧席である。そこではキースとライオット、それからパンツェ・ロッティの人形が揃って試合を観戦していた。その彼らの目前で、かの異常事態は起きたのである。
「なんだあれは、見たこともない術式だぜ。」
「で、やんすね。相手が倒れてもなお手を緩めることがないなんて、実に恐ろしい限りでやんす。」
「まったくだ。やられた連中は魔力枯渇まで起こしていやがる。」
「あの子、術式を発動する前に『B.D.D.B.』と言ってたでやんすね?」
「ああ。いったいなんのこ…。」
キースがそこまで言いかけたところで、パンツェ・ロッティの人形の様子が変わった。
「『B.D.D.B.』だと!?キース君、君は今『B.D.D.B.』と言ったのかね?」
その声からは、いつもの鼻に着く余裕が消えていた。
「へい、ロッティ先生。その通りでやんす。なにかお心当たりがおありで?というか、ここでは様子が見えないでやすよね?」
そう言うと、ライオットはパンツェ・ロッティ人形に取り付けられた魔法石が、競技フィールドを確認できるように、置いてあったベンチから持ち上げてやった。
「これはいかん。実に不味いことになっているではないか。」
「どうしたでやんすか?すごい術式には間違いないでやんすが…。」
「ライオット君、これはそんなに生易しいことではない。とにかく、すぐに私を魔法学部長代行のところに連れて行きたまえ!」
「先生を、学部長先生のところへでやんすか?」
「そうだ、そう言っておる。とにかく急ぐのだ。事は寸暇を惜しむ。」
「わかったでやんす。しかし、このひとだかりでやんすからね。どこにいらっしゃるやら…。」
そう言って、教員用の観覧席をライオットが見渡していると、競技フィールドの内に『アカデミー治安維持部隊』のエージェントを引き連れて乗り込んでくるその姿を見つけたキースが声をかけた。
「ライオット、あそこだ。学部長先生は競技フィールドにおられる。とにかくお前は急いでロッティ先生をあそこまでお連れしろ。急げ。俺もすぐに行くから。」
「合点でやんす!ではお先に!」
そう言うと、ライオットは両手にパンツェ・ロッティの人形を抱いて観客席を抜け、競技フィールドへの入り口まで駆けて行った。
空模様はいよいよあやしくなり、その鉛色の空からは雨が今にも滲みだしてきそうだ。
キースは、ふとその視界に入った、審判席を取り囲むカステルとセラが気になるようで、何をしているのか様子が分からないものかと、しばらくのあいだ目と耳を凝らしていたが、距離があまりに遠すぎて何ともならなかった。
仕方なく諦めると、キースは踵を返してライオットたちの後を追う。
* * *
そして今、先を行くライオットの視界にウィザードの姿がとらえられてきた。彼はパンツェ・ロッティの人形を落とさないように慎重になりながらも、できるだけの速さで、競技フィールドへと向かって行く。少し遅れてその背をキースが追っていた。
そしてここは競技フィールド。
ネクロマンサー率いる看護学部医療班の懸命の応急処置によって、ルシアンたちはどうにか意識を取り戻していた。ネクロマンサーたち手練れの医療班の面々も、こんなに深刻な魔力枯渇は見たことがないという様子で、必死に処置にあたっていた。
意識を取り戻したルシアンは、魔法学部長代行であるウィザードを見ると、安堵したのか大声で泣き出した。
「先生、あいつ、ものすごく酷いんです。僕ら三人をまとめてこんなことにして。どうか先生のお力で、あいつをきっときつく罰してやってください。」
普段偉そうに振舞ってはいても、所詮は12歳のまだ年端も行かぬ少年である。目前で自分たちを容赦なく打ちのめしつくした『B.D.D.B.』がよほどに怖かったのであろう。涙をいっぱいに浮かべ、口を開いて大泣きしている。そこにいる誰もが、ウィザードは彼らを慰めるものとそう思っていた。
ところがである。彼女はあたたかい抱擁を与える代わりに、乾いた大きな音を競技フィールドに鳴り響かせた。ルビーの瞳に怒りの色が輝いている。ウィザードはルシアンの横っ面を思いっきり平手ではったのだ!
「馬鹿なことを言うな!罰せられるのはお前たちの方だ!こともあろうに衆人環視の競技中にあんな不届きなことをやらかすなど一体なにを考えている!!」
ルシアンは、思いがけない出来事に言葉を失ったまま、痛む頬を片手で抑えていた。
「でも先生、それをやったのはダミアンで…。」
「そそのかしたのはお前とマリクトーンだろうが!」
その言葉を聞いて、ルシアンの表情が一気に複雑なものに変わる。
「先生、何をおっしゃってるんですか?マリクトーン先生には全然かかわりのないことです。あれはダミアンの奴がかってにやっただけで。僕も、僕もそそのかしたりなんてしていません。」
そう言ってはみるが、ウィザードのルビーの瞳はもう全てを見通していた。
「ルシアン君、お前はあたしの目を節穴だと言いたいようだな。どうする、お父上に言いつけるか?しかし、あたしはそんなことでは動じないぞ!」
「それは、どういう意味ですか?」
「あたしは、お前とマリクトーンの秘密を知っているんだ。」
「!?」
その言葉を聞いて、ルシアンは覚悟を決めたようにこうべを垂れた。
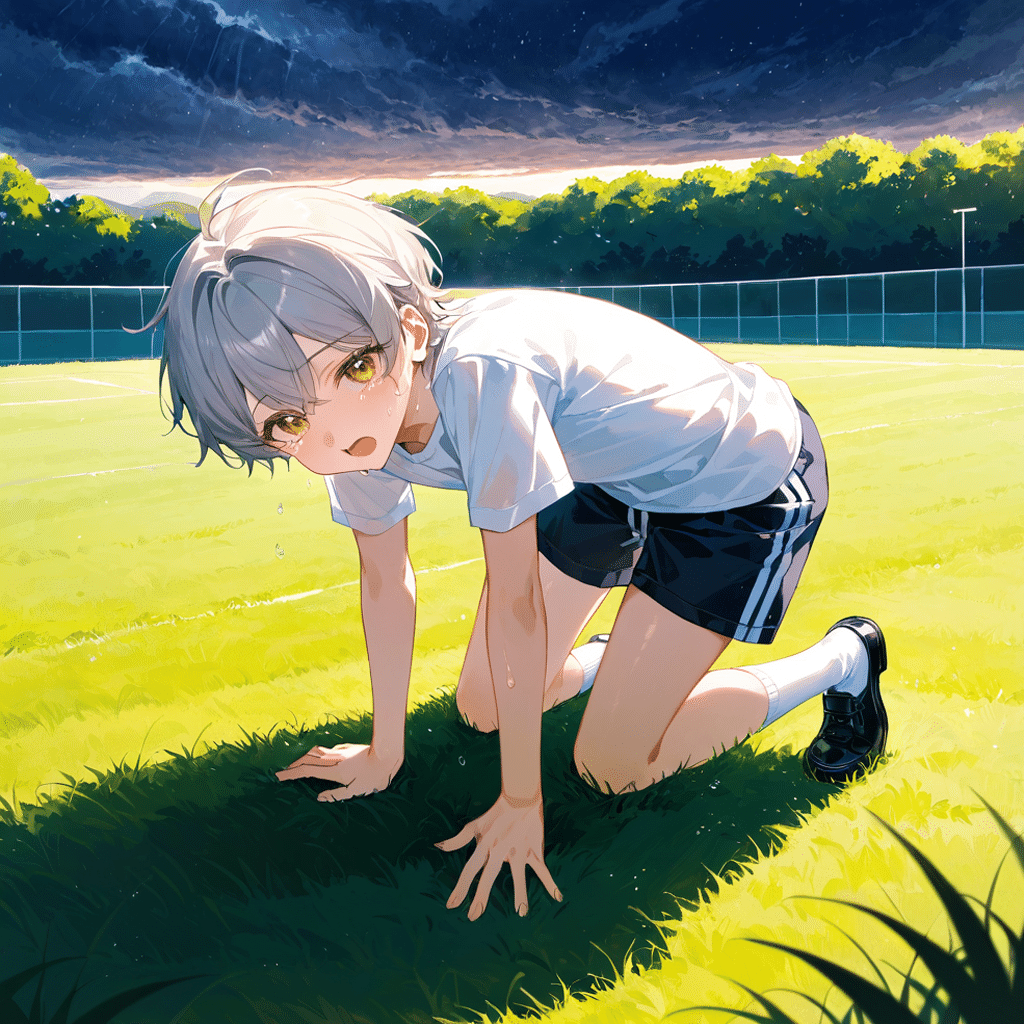
ウィザードが向きを変える。
「君は、ダミアン君だったな。」
「はい…。」
あの底意地悪くいつもへらへらしているその口の中で奥歯ががちがちと鳴っているのがわかった。
「お前は試合中に、自分が何をしたのかわかっているのか?」
「そんなにたいしたことは何もしていません。服の上からちょっ身体を触っただけで。」
「上からも下からもあるか!君は神聖な魔法模擬戦大会を下劣な下心で穢したのだ!言い訳をするよりも、そのことをよく胸に刻み反省するのが先ではないのかね!?」
ウィザードは一層口調を厳しくする。
「でも…。」
「でも、なにかね?」
「マリクトーン先生が…。」
「まて、ダリアン。よさないか。」
傍で泣きじゃくっていた、ルシアンが露骨に慌てた。
「でも、このままじゃ、俺が…。あ、あの、学部長先生。僕が、その、フィナにしたことは、マリクトーン先生が『勝ったらご褒美だ』ってそうおっしゃったから、だからやっただけなんです。」
「ダリアン!!」
ルシアンが声を荒げるが、ウィザードは黙ってそれを制止する。
「マリクトーンが、確かに君たちにそう言ったのだな?」
「はい、学部長先生、間違いありません。現に、ルシアンとアベルだって、あそこであんなことが起こらなければ、ルイーザに同じことをしてたんですから。」
「そうか、そうなのか。マリクトーンは君たちに実に興味深いご褒美を用意してくれていたと、そういう訳だ。」
ウィザードが完全にトサカに来ていることは、子どものころから付き合いのあるネクロマンサーには手に取るようにわかった。彼女をいったん冷静にさせるべきかとも思ったが、今自分の耳目に入ってきているおぞましい事実を諫めんとするウィザードの方に理があるように思い、その場では敢えてなにも言わないでいた。
「先生、誤解です。マリクトーン先生は僕らにそんなことをおっしゃってはいません。あれは、こいつが、ダミアンが勝手にやっただけなんです。こいつは、なんだかんだでフィナに熱を上げていたんです。そこにあんな絶好のチャンスが現れて、箍が外れただけなんですよ。悪いのはダミアンで、マリクトーン先生ではないんです…。」
そう言って、ルシアンは大粒の涙をこぼして泣き崩れた。
「そうか、そこまでマリクトーンをかばうか。ならば聞こう、アベル君!」
自分の名を呼ばれて戦慄するアベル。その顔もまた恐怖に引きつっている。
「ルシアンのいうこととダミアンの言うことのどちらが正しいか教えたまえ!」
「ルシアンか?」
アベルは一瞬躊躇い、泣きじゃくるルシアンを一瞥してから、首を横に振った。
「では、ダミアンの言うことの方が正しいのだな?」
おそるおそる頷くアベル。極度の緊張と戦慄で、彼はとても言葉を発することができずにいた。
「そうか、よくわかった。協力に感謝しよう、アベル君。」
皮肉を込めてそう言った後、ウィザードは厳然と言い放った。
「ダミアン、お前は『学内における不同意猥褻強要』の不良行為により補導する。それから、ルシアン、アベル、君たちはその幇助の不良行為のかどでルシアン同様に補導だ。あたしが直々に学徒指導室でその曲がった根性を叩き直してやるから、覚悟しておけ!」
そう声を荒げる、ウィザードのルビーの瞳は涙で潤んでいた。彼女は、自分の管理不行き届きの為に、学徒達を加害者と被害者に分かってしまったことを深く悔恨していたのだ。しかし、物事には許容できる限度というものがある。どこかでそれを学徒達に教えなければならない。それはウィザードにとって、実に胸の痛いことでもあった。
そこに姿を現したのは、先ほど別口があると言ってこちらに向かってきていたカステルである。カステルは、ウィザードの前で丁寧にお辞儀をしてから、言った。
「学部長先生。お疲れ様です。おっしゃっておられる、その彼らの補導と矯正指導につきましては私に御一任いただけないでしょうか?」
「カステル…。」
そう、彼女は、ウィザードの心中を酌み、汚れ役は自分が引き受けると申し出ているのだ。
「しかし…。」
「構いません、先生。それに、懲罰といえどもはやり一定の抑制が効かねばなりません。少々やりすぎがあったようなときには、それを止める立場というのが必要になりましょう。私の場合、レイ警視監然り、学部長先生然り、目を光らせる方が大勢いてくださるので心置きなくこの悪童どもを矯正させることができますが、先生の場合、先生をお諫めする者というのはほとんどございません。ということは常に先生はご自身の内なる葛藤にお苦しみになる、ということになってしましかねません。それならば、懲罰は私が引き受け、先生には私を監視していただく、というのが適当なように思えるのですが」、いかがでございましょうか?」
カステルはそう言った。
「そうか、カステル…。すまんな、助かるよ。そのようにしよう。では、簡易の口頭伝達にはなるが、カステル警部に辞令を伝える。君は『重要補導対象者』であるルシアン、アベル、ダミアンを学徒指導室に補導連行し、学徒指導の教官と共に、彼らの適切かつ必要な矯正のための指導に当たれ。監督はレイ警視監と私が行うこととする。正式の事例は追って発する。それまではこの伝達の趣旨に基づいて任務を全うせよ。よろしいか?」
「はい。カステル警部、謹んで辞令を拝命いたします。それでは、私目はこれにて。」
そう言うとカステルは、来た時と同じように丁寧にお辞儀をしてから、周囲で待機するエージェントに、
「連れていけ!」
と命じて、ルシアン、アベル、ダミアンの3人を補導した。

「いい部下をお持ちでうらやましいですね。」
ウィザードに声をかけたのは救護活動を終えたネクロマンサーだった。
「あんたにだってカレン達がいるじゃないか?最近はリアンも看護学部を手伝っているんだろう?」
「ええ。ですが彼女たちが一緒にいるのには別の理由があってのことですから。」
ネクロマンサーはそう言って微笑んで見せた。
「そうなのか?それはいったいどんな理由だ?」
「まあ、気づいていないのですか?それならば秘密です。と言ってもすぐにお気づきになりますよ。」
「なんだよ、それは。いずれにしても、これで悪童の処分はひとまず解決だ。と言っても、ルシアンの父、マクスウェル評議員が黙ってはいないだろうがな。」
「そうですね。」
「まあ、その面倒を引き受けるのも私の仕事ということだ。何でも、物わかりの言い部下に頼ってばかりというのでは示しがつかんからな。」
「あらあら、あの勇敢な乙女の仰ることとも思えませんね。」
そう言って、ネクロマンサーはくすくすと笑う。
「ったく、あんたらはいつまでそれを言うんだよ。もういい加減勘弁してくれ。中等部の頃の話じゃないか?だろう?」
* * *
「いや、まだ勘弁するわけにはいかんな。君にはもう少しやってもらわなければならない仕事ができた。」
そうウィザードに話しかけてきたのは、ライオットが連れてきたパンツェ・ロッティ人形だ。その意外な声に驚いたウィザードはそちらの方に振り向く。
「教授、藪から棒になんだよ。」
「教授か、君には、君達がまだ中等部の頃からずっとそう呼ばれてきた。君が教職を得て私のもとに配属となった後もな。まだそう呼んでくれるか、ありがたいことだ。」
パンツェ・ロッティの声は、どこか遠い感傷に浸っていた。
「いや、教授。そんなことは今はいいんだよ。それよりなんだよあたしの仕事ってのは?」
訊ねるウィザード。
「いいかね。先ほどあのルイーザという娘が繰り出した『B.D.D.B.』というのは神話時代の魔法で、魔王ルシファーのものである。」
「なんだって!!」
一同騒然となる。
「『B.D.D.B.』とは、『死血の剣舞:Bloody Dance of Deadly Blade』を現代魔術の書式で暗号化したものであろう。おそらく、彼女にそれを使うよう促したのは魔王の残滓(ざんし)に違いない。なぜ彼女が魔王の声を直接聞くことができたのかは分からないが、今日のことで、間違いなく彼女は彷徨う魔王の魂に魅入られたはずだ。」
「ちょっとまて、教授。あんたはいったいさっきから何を言っているんだ。もう少しわかるように説明してくれ。魔王なんて古代神話の登場人物で、『神』とやらと同じくらい眉唾な存在だ。そんなものが現代に蘇ろうとしていると、あんたはそう言っているのか?」
「その通りである。君は今、『神』は眉唾と言ったが、かつて神に直接会ったことがあるのではないのかね?」
パンツェ・ロッティのその言葉はウィザードにとっては重かった。
「会ったことがあるどころか、今もどういう因果か、こうしてその『神』とやらの欠片と話をしているぜ。」
「そうだろう。ということはだ。それと糊塗を同じくして魔王や『大魔王』もなお、この現代魔法社会のどこかで息をひそめているということは十二分にあり得ることになる。」
「まあ、確かに、あんたも一介の教授の皮をかぶって、神秘主義の『アカデミー最高評議会』の議長様としてひそんでやがったものな。そう考えればないはなしじゃあない。」
「その言い様はどうにも気に入らんが、その通りである。そして、かのマークス・バレンティウヌのように、その隠された古代神秘の力を引き出し得ようとする者が必ず存在する。魔法や大魔王についても然(しか)りと言わねばならんだろうな。」
「そうか…。しかし、あのルイーザが『魔王の残滓に囚われた』っていうのはいったいどういう意味なんだよ?」
「文字通りである。彼女は絶体絶命で、力を渇望すべき場面において、それが与えようという力を受け容れる選択をしてしまった。それは神化や魔王化に必要な儀式、魂の座への力の宿座以外のなにものでもない。」
「あんたがあの、時空の門の鍵を胸元に隠していたのと同じようにか?」
「よく覚えておるな。さすがは我が弟子である。」
「そんなことはどうでもいいんだ。つまりそう言うことなんだろう?」
「その通りである。」
目の前で繰り広げられる全く意味の分からない会話に、キースとライオットの二人はあっけにとられるばかりだった。しかし思い返せば親友のトマスもまた、太古の神秘を求めて『ダーク・サーヴァント』なるものに姿を変え、剰え、こともあろうに時空を旅して見せたのだから、あながちあり得ない話でもないと、そんな風に感じつつ、話に聞き入っていた。一部始終をウィザードとともに経験したことのあるネクロマンサーの精神は、遠い追憶の彼方を追っていた。
「でも、それは無茶苦茶じゃないか?あんたの場合は自分の愛だの野望だの為に、自らの意思で神の力を取り込んだわけだが、ルイーザの場合はある意味で無理やりだぜ。あんな場面で力をやると言われれば誰だって受け入れるるだろう?」
そのウィザードの指摘はもっともだった。あのおぞましい力を解放することをルイーザ自身が望んだわけではない。ただ、差し迫った必要に迫られたにすぎないのだ。
しかし、パンツェ・ロッティは言う。
「それが神と魔王の違いであると言うべきであろうな。神は契約に忠実であるが、魔王は目的の達成と実践を最優先にする。彼が堕落の王と言われる所以でもあるな。要するに、手段などについて、一顧だにしないのだよ。魔王とはそのような存在である。」
「それじゃあ…。」
「残念ながら、まもなく彼女は、内から湧き上がる力への渇望に自我を飲み込まれて、もう一つの魔王、『セト』の復活を目論むようになるであろう。そして自ら、力の極致である『大魔王』の座を得るために、それとの融合を図るはずだ。セトは、ルシファーが大魔王となるために必要なその半身なのだからな。
もし彼女を救おうと思うのであれば、これ以上力を覚醒させてはいけない。まず、絶対に『セト』に近づけないようにすることだ。今はまだ、彼女は彼女自身の名で自らを認識しているが、『セト』と接触して覚醒してしまえば、それはもはやルイーザという自身の名ではなく、『ルシファー』の名において自己の存在をとらえることになるだろう。そうなればもはや手遅れとである。何としても、彼女を『セト』から遠ざけ、これ以上力を渇望する必要を与えないことによって、内に宿る魔王の残滓が、自ら彼女を見捨てるように仕向けなければならない。それは随分と骨が折れることであるぞ。しかし、誰かがやらねばならん。」
「で、それがあたしの仕事という訳だな?」
「その通りである。」
「命を賭してでも、彼女の覚醒を防ぐのだ。」
「わかったよ。でも具体的にはどうしたらいいんだ。」
「まずできることは常時監視である。君は立場上彼女にずっとついているという訳にはいかんだろうが、ほれ、キューラリオンにかぶれたあの生意気で聡明なウォーロックがいただろう?彼女に任せてみるのはどうかね?」
「ユイアのことだな。」
「ユイア?そんな名ではなかったと記憶しているが…。」
「わけあって、あいつはその名前で一度アカデミーに戻ってきたんだよ。結局天使であることを隠しきれずに、今はこちらに戻れないでいるが。」
「それはむしろ好都合ではないか?この社会における公の立場がないのであれば、四六時中、あのルイーザという娘を見張ることもできない相談ではなくなる。」
「それはそうだが、しかし、あいつにもあいつの人生ってものがある。未来永劫という訳にもいかないぜ。」
「そんな悠長なことを言っている暇はないし、おそらく相手の方で、そんなに長い猶予はくれまいよ。だからすぐにでもつなぎをつけて、手配しなければならん。よいかね?」
「ああ、わかった。そうしよう。考えてみれば、ルイーザにあんたを持たせておくと言う方法もないではないけどな。」
「それもよい考えてであるは思うが、私はこの通り、話す以外にできることはもうない。であるからして、万一の時に対処が送れる可能性があっていかん。」
「それもそうだな。やはり、あんたの言う通り、ユイアに頼んでみることにするよ。また、『アーカム』に行かないとだな。」
「それはよい。すぐにでも行こうではないか!」
「なんだ、エバンデスさんに会いたいのか?帰って来て早々浮気とは隅に置けないぜ、教授。」
「そうではない。そうではないのだ。その…、あそこにはリセーナもいるであろうが。」
「ああ、そっちか。あんたもずいぶんと純真初心になったもんだな。」
そう言ってウィザードは笑った。
「まったく、君という者はいつまでたっても目上を敬うことを知らんで困る。」
「そうでもないぜ、あんたを尊敬はしてるさ。男としては到底無理だが、少なくとも教育者としては、大いにな。あんたから教わったことは実に多い。」
「世辞はよしたまえ。」
「はいよ。」
そう言って、二人は古くから続く師弟関係の縁(よすが)を再確認していた。
* * *
M.A.R.C.S.をみなでたどりながら、パンツェ・ロッティ人形とそれをもつライオットが言葉を交わしている。
「ロッティ先生は、『神』様だったんでやすか?もしそれを、欠片になる前に知ることができていたら、トマス兄はきっと喜んだやすよ。兄は、『神』様に憧れを抱いてやしたし、ロッティ教授のことも心底尊敬していたでやんす。ですから、同一人物だとわかったら小躍りしておかしくなるくらい喜んだでやすよきっと…。」
ライオットが、ふと声の調子を落とした。
「ふむ。トマスは私の理想をよく解する優れた弟子であった。どこぞのウィザードとは大違いである。」
「聞こえてるぜ。」
「トマスとも、同じ方法で話をすることができればよかったのだが…。」
「同感でやす。トマス兄の欠片も同じようにこの人形に繋いではみたでやすが、反応がなかったでやす。きっと、ロッティ先生が『神』様だったのが関係しているのかも知れませんでやすね。」
「うむ。それはあり得る。私は絶命するときには既に人を捨てていたからな。そのことが、こうして諸君たちと話ができることの鍵となっているというのは十分にあり得ることだ。しかし、全くの偶然であるにせよ、魔王の復活の企みが動き出した時に、こうして諸君らと時を共有できるのは幸いであった。諸君の身の回りで、魔王や『大魔王』について知るのは、キューラリオンと私しかいない。力の点ではあのウォーロックの娘も確かに『神』の領域にあるが、太古の神話の時代の知識という意味では、あの不勉強者はどうにも頼りにできんのだ。キューラリオンもまた、常にみなと一緒というわけにはいかない。こうして私が今ここにいるのには、なにか大きな運命の導きがあったのかもしれんな。」
「でやんすね。でもおいらはロッティ教授とまたこうしてお話しできて嬉しいでやすよ。」
「私とて同様である。弟子に恵まれて感謝であるな。」
二人がそんな話をしているうちに、ウィザード、パンツェ・ロッティ人形、そしてキースとライオットの4人は、霧の中に佇む『アーカム』の入り口前に到着した。ネクロマンサーは、その日起こったことをソーサラーに伝えるために、アカデミーに残ったようである。神秘の扉を押すと、それは静かに開いていった。
to be continued.
AI-愛-で紡ぐ現代架空魔術目録 本編後日譚最終集その6『信頼と絆、師弟の縁』完
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
