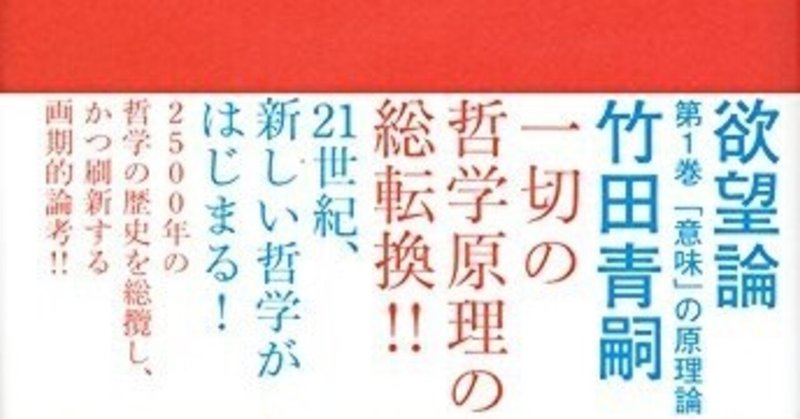
【解説】竹田青嗣『欲望論』(4)〜ニーチェ、フッサールによって、ついに問題の解明へ
1.ニーチェによる「本体論」の解体
こうして、ついにニーチェによる「本体論」の解体が哲学史に登場する。
竹田はまず次のように言う。
忘れるべきでないのは、あらゆる種類の本体論の背後にはつねに内的動機が潜んでいるということである。ある場合には敬虔な信仰、ある場合には美しき世界への憧憬、ある場合には世界の現状に対する倫理的抗議、またある場合には、単なるシニシズムあるいはデカダン。
ニーチェによる本体論の解体の遂行には、つねに本体論を支える動機についての鋭い本質的洞察第がともなっている。
ニーチェは、世界理説としての本体論がなぜ人間によって描き出されてしまうのか、その動機を描き出す。
それは、彼のルサンチマン分析に見事に結実している。
たとえば、『権力への意志』における次の有名な言葉。
形而上学の心理学によせて。――この世は仮象である。したがって或る真の世界がある、――この世は制約されている、したがって或る無制約的な世界がある、――この世は矛盾みちている、したがって或る矛盾のない世界がある、――この世は生成しつつある、したがって或る存在する世界がある、――これらの推論はまったくの偽りである〔中略〕。こうした推論をなすよう霊感をあたえるのは苦悩である。〔中略〕すなわち、現実的なものに対する形而上学者たちのルサンチマンがここでは創造的となっているのである。
「世界がかくかくでなければよかったのに」。このルサンチマンが、人びとをして「真の世界」という「本体論」にいたらしめる根本的なものなのだ。
ではニーチェは何を説いたのか?
「世界それ自体」といった「本体」などどこにも存在しない。それは徹頭徹尾「遠近法」的なものである。
これがニーチェの「遠近法主義」である。
ポストモダン思想家らによって、これは従来、相対主義の根拠として受け取られてきた。
しかし竹田は次のように言う。
ニーチェの「遠近法主義」は認識相対主義をまったく意味しない。〔中略〕ニーチェがおいた「原理」はむしろ、一切の認識は欲望相関的−目的相関的である、と総括されねばならない。認識が欲望相関的であること、このことは認識の相対性ということ以上に、認識の普遍性の可能性の条件を示すのである。
ここには完全に新しい一つの存在論が、全哲学史のうちではじめてその姿を見せている。すなわち「存在」とはわれわれの(生き物の)生それ自身が構成するものにほかならないという存在論、力の相関者としての「世界」こそが存在の第一審級である、という新しい存在論が現われている。
一切は「相対的」なのではなく「欲望相関的」なのだ!
ここにこそ、単なる相対主義から、普遍洞察性を問う哲学原理への転換の可能性がある。
「本体」などどこにもないし、普遍認識(人びとの間の普遍的な共通了解)のために必要でもない。
私たちは、世界が欲望相関的に現象すること、そしてその現象の仕方の普遍性を洞察することで、独断論にも相対主義にも陥ることのない道を切り開くことができるのだ。
それに対して、ニーチェから相対主義的観点のみを受け取った現代の相対主義は、未だに存在・認識・言語の不可能性ばかりを鬼の首を取ったかのように主張し続けている。
竹田は言う。
20世紀の初頭には、ヨーロッパの全体主義思想への対抗を一つの動機として、ムーア、シュリック、エイヤー 、カルナップ、ノイラートなどによる論理実証主義が登場して論理学的文脈における形而上学批判を開始する。さらにこの論理主義的合理主義を実在論的独断論であるとして、分析哲学およびポストモダン思想による相対主義的な形而上学批判が現われる。ウィトゲンシュタイン、クワイン、デイヴィッドソン、ストローソン、ダメット、パトナム、ローティ、サール、クリプキ、フーコー、デリダ等々。この20世紀における哲学、思想の変転は、じつのところすべて、昔ながらの普遍主義対懐疑主義の対立の現代的変奏にほかならないのである。
これら相対主義的哲学を、「欲望論」によって終焉させる必要がある。竹田はそう述べる。
2.ニーチェにおける「本体論」の残滓
さて、しかしじつはこのニーチェにも、残念ながら「本体論」の最後の残滓が見出せるのである。
「力への意志」仮説がそれである。竹田は言う。
あらゆる生き物の生成変化はその根本動因として「生への意志」あるいは「力への意志」を内存するという仮説は、妥当だろうか。
この仮説は、ニーチェ思想における〈何ものも、思考や感覚という出発点の背後にまわってみることはできない〉という根本ルールに背反しないだろうか。
ニーチェ自身が言ったように、また詳しくは後述するように、欲望=意識存在である私たちは、その欲望=意識を「可能にするもの」を同定することなどできない。
同定しようとした瞬間、それはさまざまな「本体論」の乱立となってしまうのだ。
われわれの欲望=意識を可能にしているのは、「神」である、「存在」(ハイデガー)である、「差異」(ドゥルーズ)である、「遺伝子」である……etc。
しかしどれひとつとして、その真を証明することなどできない。
竹田は言う。
現代科学では「遺伝子」が同種の根本原理、根本動因を意味するが、ニーチェの仮説は、力の拡大の原理が組み込まれた遺伝子という観念にほぼ等しい。
ニーチェの「力への意志」もまた、結局のところ確かめ不可能な仮説にすぎないのだ。
要するに、快−不快、情動、衝迫、すなわち生き物における「エロス的力動」の生成は、欲望−実存論的には本質的に一つの絶対的起点であって、これに何ものかを先構成させることはできない。
欲望(エロス的力動)こそが、これ以上遡ることのできない「確かめ可能」な底板である。それゆえ、一切の思考をこの底板から始発せよ。
これが竹田「欲望論」の最重要テーゼになるが、詳しくは後述することにしよう。
3.フッサール現象学
さて、ニーチェの本体論解体は、その後、フッサール現象学によって完遂されることになる。
ところが従来、現象学はおびただしい誤解にさらされてきた。しかも、互いに相反する主張と共に。
すなわち、一方においては、主観主義として。他方においては、厳密な客観主義として。
二つの異なった陣営からの二つの異なった現象学批判がある。一方は、ルーマンやハーバーマス、つまり実証主義的客観主義からの批判。ここで現象学は伝統的近代観念論、つまりドイツ観念論哲学の継承とみなされ、形而上学的観念論として批判される。他方は、デリダ、フーコー、ローティなど、相対主義=懐疑論からの批判。現象学を伝統的形而上学における認識論的基礎づけ主義の後継とみなして、その厳密認識主義、真理主義を批判する。この両極からの現象学批判という現象には理由がある。
現象学は本質的に二つの批判対象をもつ。第一に、伝統的な主観−客観構図の上に公然あるいは暗然に基礎をおく哲学的、論理的立場、形而上学的独断論と論理主義的、実在論的独断論。第二にその対抗者としての現代的相対主義=懐疑論。それゆえ、現代におけるこの両極の思考が現象学を敵視するのは必然的な帰結である。一方はそれを、世界の実在を認めない主観主義、意識主義、観念論として批判し、もう一方はまったく逆に、それを客観主義−真理主義を擁護する形而上学への復古として批判するのである。
つまり、客観主義の側からすれば現象学は単なる「主観主義」であり、相対主義の立場からすれば、現象学は「客観主義」と受け取られてきたのだ。
しかしこれらは、どちらも現象学の真のモチーフと意義がつかみ取られていないがゆえの誤解にすぎない。
現象学の核心を竹田は次のように述べる。
なにより重要なことは、フッサール現象学とその方法原理の中心動機を、ヨーロッパの認識問題の完全な解明として受けとること。そのためには現象学の根本方法を、「内在的意識」における「世界確信」の信憑構造の解明の方法として、すなわち存在対象の信憑形成の条件と構造の解明の方法として受けとること。「確信成立の条件」の解明の学として現象学を理解すること。
現象学は「確信成立の条件」の解明の学である。
現象学は、一切の「本体」を前提しない。
しかしなお、私たちがさまざまな「確信」を持っていることについては疑えないと現象学は言う。
たとえば私は、いま、目の前にリンゴが存在していることを「確信」している。
これは本当は、幻影なのかもしれない。夢なのかもしれない。
しかしそれでも、私はいま、このリンゴの存在を「確信」している(あるいは自分がそれを疑っていることを確信している)。
であるなら、その確信はいかに成立しているのか?
さらに言えば、この確信を、いかに他者と共有することができるのか?
この「確信成立の条件」解明の学としての現象学理解こそが、フッサール現象学の核心を最も的確に捉えた現象学理解なのだ。
次回は、この現象学的思考の要諦を紹介していくことにしたいと思う。
(続く)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
