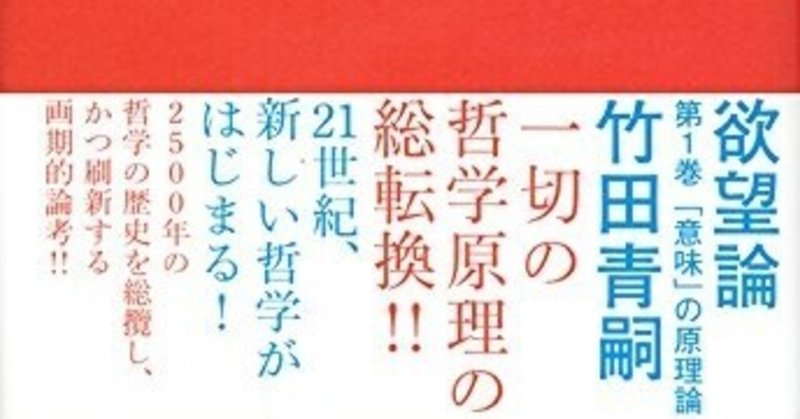
【解説】竹田青嗣『欲望論』(2)〜哲学2500年の根本問題「形而上学的独断論 VS 相対主義」〜
1.哲学と普遍戦争
それでは、本書の解説を進めていこう。
序文において、竹田は本書のモチーフをまずこう述べる。
哲学は世界から「暴力原理」を縮減するための戦いを闘ってきたし、その対抗原理を時間に耐えて徐々に創り出してきた。人間のこの歴史を理解するものは、現在、哲学が立っている重要な岐路を理解するであろう。その第一の意義は、形而上学的独断論と懐疑論=相対主義を終焉させ、そのことによって、人間の本質的自由の条件である理性の集合的探求としての「言語ゲーム」の本義を再生することにある。
前述したように、哲学の歴史は形而上学的独断論と相対主義の対立に満ちている。
前者は、「世界の真理はこうなっている」と主張し、後者は「それは決して分からない」と言う。
前者が行き着くところまで行けば、全体主義となる。
後者はそれを相対化するが、しかし「正しいものは何もない」と主張し続ける限り、自身の相対主義もまたその確かさの根拠を失うというパラドクスに陥ってしまう。
さらに悪いことには、相対主義は、行き着くところ、現実世界における「パワーゲーム」を招来することにもなりかねない。
「正しさ」の根拠がなくなってしまえば、世界は「普遍戦争」状態に陥るほかないのだ。
どういうことか?
「絶対に正しいものなどない」。相対主義はそう主張する。
もちろん、その通りだ。
しかしこのような態度は、行き着くところ、ナチズムにしてもスターリニズムにしても、そうしたものを批判する根拠さえ失うということなのだ。
逆に言えば、「みんな違ってみんないい」は、それ自体はとても寛容な言葉ではあるが、論理的には、ナチズムもスターリニズムに対しても、「みんな違ってみんないい」と言ってしまう思想なのである。
では、独断論にも相対主義にも陥らず、なお、普遍的で共通了解可能な哲学原理を提示することは可能か?
可能である。
竹田はそう断言する。
そのためには、まずは一切の「本体論」と、これと対をなす「相対主義」を終焉させねばならない。
2.ゴルギアス・テーゼ
まずは、相対主義から。
相対主義とは何か?
竹田はその方法を、ゴルギアス・テーゼと呼んで次のように総括する。古代ギリシアの相対主義者、ゴルギアスによって示された3つのテーゼだ。
(1)およそ何も存在しえない。あるいは存在は証明されない。
(2)万一存在があるとしても、決して認識されない。
(3)万一存在が認識されたとしても、決して言語化されえない。
竹田は言う。
ゴルギアス・テーゼこそは、ヨーロッパ哲学を通して存続するすべての懐疑論=相対主義の論理的原理を体現するものであり、その後現われた一切の懐疑主義、相対主義思想(ポストモダン思想・現代分析哲学を含む)の源泉である。
現代の相対主義哲学もまた、どれほど精緻化されているように見えようとも、結局のところこのゴルギアス・テーゼの枠内にある。
以下、竹田は2500年以上におよぶ哲学の歴史を総覧し、独断論と相対主義の対立を克服する原理を提示する。
3.世界理説の対立
続いて、形而上学的独断論について。
さまざまな形而上学的独断論どうしの対立は、哲学史において至るところで見られるが、その最も典型的にして最初の対立を、私たちはやはり古代ギリシアにおいて見ることができる。
パルメニデスの「存在」と、ヘラクレイトスの「生成」がそれである。
パルメニデスの思考の方向転換から取り出されたものは、第一に、世界の全体存在の「一」性。第二に、無から存在、存在から無への転移の不可能性、その帰結としての、世界の不変性と不滅性、そして生成、消滅の観念の仮象性である。パルメニデスのこの諸帰結が、後続するギリシャの哲学者たちの思索に決定的な方向づけを与えたことは、ただちに明らかになる。
この観念は、ギリシャ哲学における「存在」の概念の思考を一歩先の地平へと推し進める。すなわち、「存在」と「生成」という新しい対立の地平を創り出す。
一方に、「一」にして不変の「存在それ自体」という観念が登場する。
しかしそれには必ず、たえず変化し続ける「生成」としての世界というヘラクレイトス的観念が対立する。
エンペドクレス、レウキッポス、デモクリトスらは、この対立を克服すべく努めた。
一方に不変の「原子」があるが、この原子は「運動」する。彼らはそう考えたのだ。その推論は次のように要約できる。
(1)「原子」はそれ以上不可分な充実するもの(=ある)の最小単位である。
(2)諸事物の多様性と生成変化は、原子の形態、配列、位置関係の変化によって現われる。それを促すのはなんらかの「力」(動因)である。
(3)原子の生成変化が生じるには、充実体(ある)とともに空虚(ならぬ)が並存しているのでなければならない。
しかし言うまでもないが、これもまた1つの検証不可能な「世界理説」にすぎないのだ。
4.懐疑論=相対主義
「世界は本当はどうなっているのか」という問いは、以上見てきたようにさまざまな「世界理説」を生み出すことになる。
これら理説には、次の4つの主要な類型があると竹田は言う。
哲学的思考が生み出す四つの主要な理説上の対立。始元原理(要素)としての一元論と二元論(多元論)、存在原理としての「存在」と「生成」、認識原理としての実在論と観念論、感覚論と超感覚論、そして普遍主義と相対主義。なにより注意すべき点は、ギリシャ哲学において、これらの対立は純粋な論理的対立として追いつめられることで、明瞭に「認識の謎」へと、すなわち、認識の「正しさ」を何が保証しうるか、という問いへと、ゆきついたということである。
一元論と二元論。存在と生成。実在論と観念論。普遍主義と相対主義。
このように対立する世界理説が次々に現れると、ことの当然の成り行きとして、哲学者たちは「世界の真理など本当に分かるのか?」と問うようになる。
こうして、「真理など分かるはずがない」と主張する懐疑論=相対主義が登場する。
典型的なのは、「アキレスと亀」などのパラドクスで知られるゼノン。そして先に述べたゴルギアス。
ゴルギアスは、『自然について』(現存せず)において、先述したように次の3つを証明したと言われている。
第一に、なにものも「存在」しない。あるいは「ある」(存在する)という述語をつけることのできるものは何もない。
第二に、およそどんな認識も不可能である。たとえ存在があるとしてもわれわれはそれを正しく認識することはできない。
第三に、仮に何かが存在し、またその認識が可能だとしても、この認識を言葉によって表現することは不可能である。
これについて、竹田は次のように言う。
第一のテーゼは存在の謎を示し、第二のテーゼは認識の謎を、そして第三のテーゼは言語の謎を表示する。ギリシャ哲学における世界の存在についての理説はこうして哲学の本質的謎を生み出すところで第一の円環を閉じる。
相対主義は、その帰謬論的論証を駆使して、認識の不可能性をひたすらに主張するのだ。
5.ソクラテス、プラトン、アリストテレス
しかし私たちは、この世界の一切合財を相対化してしまうことなどできるのだろうか?
相対主義の論理は、「善−悪」や「美−醜」、「ほんとう−嘘」といった、人間的意味や価値を問うことを無効化してしまう。
しかし本当にそれでよいのだろうか。
この相対主義に抗して、人間的意味や価値の普遍性を問い直そうとしたのが、ソクラテスとプラトンだった。
彼らの哲学には、人間的意味や価値の本質を解明するための方法論の萌芽があった。
すなわち「対話」。
これは、のちのフッサールの「本質観取」に通ずる重要な方法だ。
このことについては後で詳論されるが、人間的意味や価値は、「本質観取」を通してのみ解明することができるのだ。
「本質観取」の方法の要諦は、内省によって経験からことがらの核心をなす本質を取り出し、それを間主観的に検証して共通了解へと持ち込むことである。
しかしソクラテスとプラトンのモチーフは、次のアリストテレスによって「自然主義」化されてしまい、哲学史において十分に展開されることがなかった。
アリストテレスのイデア批判の要諦は、「イデア」を天上に座するあらゆる存在の「本体」とみなす哲学的思考を、われわれの日常的、良識的な事物観へもういちど再転換しようとする視線にある。
自然主義的なものの見方は、現代人にはフィットするように思われる。
しかしそれは、行き着くところ「唯物論」と「観念論」の対立を再び生み出すことになる。
世界は、私たちの精神も含めて一切合切「物質」なのか? それとも私たちの「観念」こそが世界を生み出しているのか?
ここに、私たちは再び、確かめ不可能な「世界理説」の対立が再演されるのを見る。
さらに、自然−科学主義的世界観は、一切を物質原理に還元して考えることで、人間的「意味」や「価値」の探究を無効化してしまう。
後述する現代の物理学主義的哲学のように、それは人間的意味のすべてを脳信号などに帰するのが関の山なのだ。
しかし、人間的意味や価値の世界の一切が脳信号に還元されるなどと、いったい誰が「確かめる」ことができるのだろうか。
こうして問いは、次の近代哲学へと引き継がれていくことになる。
(続く)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
