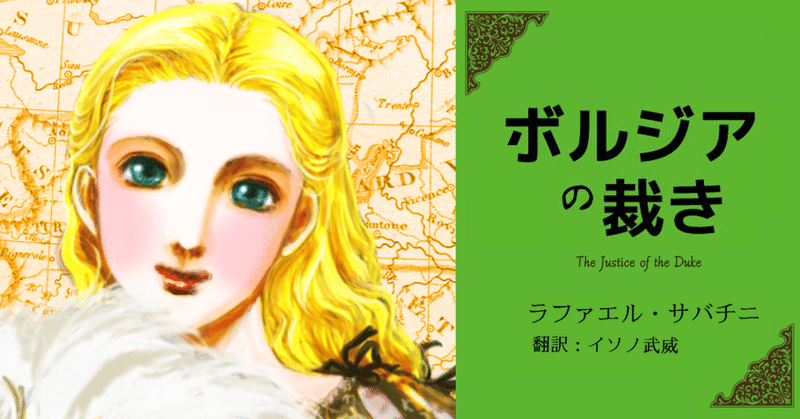
Ⅵ 覇者の愉悦
ⅰ
チェーザレ・ボルジアの権力と栄光は最盛期にあった。既に彼は裏切り者の傭兵隊長たちの始末を済ませていた。その者たちは反旗を翻し、一時は彼の動きを封じて覇道の歩みを遅らせたのみならず、その覇業を無に帰させしめる危険性すらあった。彼はシニガッリアに仕掛けた罠に鳥もちを塗り、そして――フィレンツェ共和国の書記局長マキャヴェッリの言葉を借りれば――楽しげな口笛を吹いて其処に彼らを誘い込んだのである。彼らが容易く誘い出されたのは、己の立場を誤解し、自分たちが猟師でありチェーザレが獲物であると考えた点にあった。彼はあっという間に、その思い込みを覆した。そして反逆者たちを捕らえると、雄鶏をひねるがごとくに、さしたる良心の呵責も覚えず彼らの首を絞めたのであった。反乱勢力はかなりの大軍であったが、彼はその一部を壊滅、離散に追い込み、残った兵をボルジアの大部隊に編入した上で南下し、ウンブリアを経由してローマへと帰還したのである。
ペルージャには、かつてボルジア軍の傭兵隊長を務めていたジャンパオロ・バリオーニという、辛くも彼の手から逃れおおせた比較的幸運な反逆者がおり、この男は戦支度を整えチェーザレ・ボルジアへの報復を壮語していた。しかし古代エトルリア時代に築かれた要塞の高みから、遥か遠くに一月の白光を受けた夥しい武具のきらめきを目にしたジャンパオロは、もはや一言も発しなかった。その代わりに荷物をまとめてこそこそと逃げ出し、ペトルッチの庇護を求めてシエーナを目指したのであった。
そして彼が門を出るや否や、ペルージャ――何世代にも渡って血塗られたバリオーニ一族に辟易させられてきた都市――はヴァレンティーノ公爵を歓迎するメッセージを託した大使を送り出したのである。
ジャンパオロはアッシジでこの報を聞いたが、彼の怒りはバリオーニ一族の基準においても類を見ぬ激しいものだった。彼は眉毛が濃く、胴長短足で猿のような体型をした男であり、蛮勇と部下を従わせる弁舌の才に恵まれた優秀な軍人として世に知られていた。ペルージャを去るに際しては一時的に分別を働かせたが、それはボルジアに対する憎悪に基づいた冷徹な打算と、ペトルッチと同盟して共にトスカーナを扇動すれば、再び公爵に抗する勢力を得られるかもしれぬという期待によるものであった。
しかし今、ジャンパオロは彼の都市であるペルージャが如何に不甲斐なく――というのが彼の見解である――征服者の頸木に首を差し出したか、それに終わらず我から跪いて敬意を表し、諸手を挙げて歓迎したことまでを知るに至った。彼は逃亡の決断を猛烈に悔い、激怒に我を忘れた。
彼は進軍してくる公爵に抵抗するようアッシジを扇動せんと試みるほど怒り狂っていた。しかし聖フランチェスコの都市は血気にはやるジャンパオロに対し、公爵が到着するより前に去るがよいと告げたのであった。何故ならば、既に公爵は間近に迫っており、貴殿は発見され次第、他の反逆者たちと同じ運命をたどるのが必定であろうからと。
ジャンパオロ・バリオーニは憤激を抱きつつ出立し、一路シエーナを目指した。だが、彼はアッシジの南三里ほどの地点で手綱を引くと、スパシアの丘に突き出た険しい岩山の上にそびえ立つ、荒涼たる灰色のソリニョーラ砦を見上げた。それは不屈の老狼グイド・デッリ・スペランゾーニ、その傲慢なること反逆天使にも劣らず、その猛々しき気性は――母方から血を受け継いだ――バリオーニ一族にも劣らず、教皇に対する不服従は異端者にも劣らぬ老伯爵の居城であった。
ジャンパオロは霧雨の中、しばし馬上で唇をすぼめながらソリニョーラを見つめていた。彼は思案した。今夜、チェーザレは淫売のようにいそいそと奴に身をまかせたアッシジで眠りにつくのだろう。明日、奴の公使はソリニョーラの領主の許に送られ、そしてかの老戦士がジャンパオロの理解している通りの男であるならば、グイド伯爵の返答は公爵に対する傲慢な拒絶に違いない。
彼は心を決めた。あの砦まで登り、スペランゾーニ伯を訪ねるのだ。伯爵が本当に抵抗するつもりならば、ジャンパオロは彼の背中を押してやるつもりだった。もしも伯爵の決意が、大抵の者たちのようにチェーザレ・ボルジアが間近に迫っただけで鈍るようなものでなければ、シニガッリアで無残に失敗したことを、この地で成し遂げられるかもしれない。それによって縊り殺された盟友たちの復讐は果たされ、イタリアはこの鞭打たれるがごとき責め苦から開放されるであろうと。公爵チェーザレ・ボルジアを刑鞭になぞらえている彼自身も、昨今は世を苦しめる鞭紐の一本を成しているのだが、しかしジャンパオロはそのようなことを気にかけるような繊細さとは無縁の男なのであった。
彼は武装した追従者たち――この全面的なる国外逃亡の際にも忠実に従ってきた数十名の兵士――を振り返り、ソリニョーラに登る意向を告げた。そして曲がりくねった山道を通り、先頭となって目的地へと進んでいったのである。
ウンブリアの広大な平原から峠道を登るにつれて、鉛色の冬空の下に木々もまばらな灰色の荒涼とした風景が広がり、丘陵の狭間からは幾つもの小さな町並みや村落が見えたが、それらの位置する丘の斜面や東の谷はソリニョーラの領域と領土を形成するものであった。このような集落はほとんど丸裸の状態であり、かの公爵を前にすれば格好の餌食とされるのは必定であった。だがバリオーニは、あの猛々しい老伯爵がそのようなことでボルジアに抵抗する決意を鈍らせるような男ではないと知っており、その決意に拍車をくれてやろうと考えていた。
ペルージャ人の小集団がソリニョーラの北門に着いたのは夕闇の迫る頃であり、聖堂の鐘がお告げの祈りを報せるために鳴っていた――純潔の聖母を称える夕べの祈祷は、あの不潔なるボルジアの教皇により、このイタリアに復活していたのである。バリオーニ一行は鎧を軋ませながら峡谷の間隙にかけられた橋の上を進んだ。眼下の深淵には、先日の雨で増水し、ウンブリアの土で茶色に染められた泡立つ谿流が怒涛のごとくテヴェレ川へと注ぎ込んでいた。
衛兵に素性を明かして都市に入り、更に険しく長い路を砦目指して進む一行は、彼らを北方から迫る侵略の前触れとみなした市民たちから畏怖の念をもって見送られた。
かようにして勇壮な要塞にたどり着き、降ろされた可動橋を渡って広い中庭に入った一行は、たちまち武装した兵士の一団に取り囲まれて、彼ら自身に関することだけでなく、チェーザレ・ボルジア軍の動向についても質問攻めにあった。ジャンパオロは手短に説明して彼らを満足させてから自分の名を告げ、直ちにグイド伯爵に会わせるよう要求した。
ソリニョーラの主人は天使の間――天国の門が開かれ雲間から天使たちが姿をのぞかせている、ルイーニ【註1】の筆によるフレスコ画の描かれた天井で知られる部屋――で行われている会議に参加していた。伯爵と同席していたのは、長老評議会議長デル・カンポ、職人組合の長ピノ・パヴィアーノ、谷からやって来た二人の紳士――アルディとバルベッロの領主、そしてアッシジの紳士ジャンルカ・デッラ・ピエーヴェ、最後に伯爵の主要な士官であるソリニョーラ城の家令と傭兵隊長サンタフィオーラの二名であった。
大きな傘付煙突の下で爆ぜる丸太の炎を除けば明かりのない薄暗がりの中、皆はオーク材の長机を囲んで座っていた。そして彼らと共に長机の終端、伯爵と相対する位置に座っているのが、この軍事的な会議には不似合いな参加者である紅一点――マドンナ・パンタシレア・デッリ・スペランゾーニ、グイド伯爵の令嬢であった。実年齢は小娘の域をわずかに出た程度だが、その肢体と容貌は輝くような女らしい成熟をとげ、その頭脳と人格は非常に男性的であった。彼女を表現するために、学者のチェルボーネは一年前に『ビラーゴ(男まさり)』【註2】という言葉を――しばしば誤用される方の意味ではなく、字義通り、その語源に忠実に「女の肉体に男の知性と精神を宿す者」という意味で用いていた。
グイド伯の一粒種にして相続人という立場に加え、そのような雄々しい資質の持ち主ゆえに、彼女は現在、この会議に加わりボルジアの侵攻に関する各々の主張について真剣に耳をかたむけているのであった。彼女は見事な長身であり、その物腰も美しい頭をかかげた姿勢も非常に堂々たるものであった。目は大きく、黒く、艶やかであり、髪は燃えるような銅色で、北方の娘たちに特有の優美な色合いをしていた。繊細な唇の豊かな色は身体の内に流れる温かな血を物語り、それによって形作られた口元が秘めた勇気と意志の強さを証明している。
出席者一同が待ちかねたかのように立ち上がって迎える中、ジャンパオロ・バリオーニが案内されてきた。拍車の音を響かせながら力強いがに股で入室してきた彼は、暗がりの中でちらつく火明りに照らされているせいか、全身の装甲と黒い顎鬚のある浅黒い顔とが朱を浴びたような不吉な姿に見えた。
進み出てきたグイド伯爵は彼を抱擁して暖かな言葉で歓迎したが、それは狡猾なジャンパオロ・バリオーニにしてみれば、一番知りたかったことを向こうから告げられたも同然であった。伯爵はジャンパオロを一同に紹介した上で、彼の到着はまことに時宜にかなったものであり、自分たちが深刻に欲していた助言をもたらし、それにより今後の行動方針を決定できるであろういう理由から会議への参加を求めた。
その名誉に感謝を表明し、彼は鎧を軋ませながら勧められた椅子に座った。グイド伯爵が明かりを所望し、求めに応じて蝋燭が運ばれてくると、その光はジャンパオロのやつれた風貌を浮かび上がらせた。彼の憔悴した雰囲気は汚れが付着した武具によって強調されていたが、それは彼が馬で乗り付けて、そのまま真っすぐ彼らの許にやって来たからであった。ジャンパオロはくすぶった目で会議の参加者をぐるりと見渡すと、アッシジの紳士、ジャンルカ・デッラ・ピエーヴェに気付いて陰鬱な笑みを浮かべた。
「馬を飛ばしてきたつもりだったが」と彼は言った。「私より先にアッシジの事件を報せた者がいるようだな」
デッラ・ピエーヴェはそれに答えて言った。「私は三時間前に到着し、アッシジが全面降伏して自ら門を開き、侵略者を迎え入れたとお伝えしました。コムナーレ宮は彼を歓迎する準備を整えており、ボルジア軍はあの都市にしばし留まって、抵抗勢力を相手に作戦を展開するための拠点とするつもりであろうと考えられます」
「そしてソリニョーラも、その抵抗勢力に数えられているのだろうか?」ジャンパオロはグイド伯爵に視線を定め、ずけずけと尋ねた。
ソリニョーラの主人である老伯爵は、穏やかに彼の視線を受け止めた。その精悍な顔は計り難い表情を浮かべ、薄い唇はきつく結ばれていた。それは端正で、力強く、狡猾な――決して易々と屈することのない人間の顔だった。
「それこそが」彼は悠然として答えた。「我々がここに集い、決断を下そうとしている議題だ。貴卿にはデッラ・ピエーヴェがもたらした情報に付け加えることが何かあるのだろうか?」
「ござらぬ。こちらの紳士は私が知ることを全て伝えてくれた」
「だとしても、貴卿が実に折りの良い時にやって来られたのに違いはない。我々の議論は膠着状態で、合意に達する見込みは高いとは思えぬ。差しつかえなければ、忌憚ない意見を聞かせてくれまいか」
「ご承知の通り、バリオーニ殿」バルベッロの主人――赤ら顔の陽気な中年紳士――が口をはさんだ。「我々の利害は異なっており、そして我々は当然ながら、己の利害を優先する」
「当然であろうな、貴殿の申される通りに」微量の皮肉と共にバリオーニが同意した。
「我ら、あの谷に住む者――ここに同席している我が友フランチェスコ・ダルディも当然含まれるが――我ら谷の住人は、攻撃に対しては隙だらけの無防備であり、城壁を備えた町も幾つかあるといえ、それとて砲撃に耐えるようなものではない。グイド伯爵とソリニョーラの人々が抵抗を主張するのは、まことに結構なことだ。ソリニョーラ砦は難攻不落と言ってもいい。この都市は糧食も豊富に蓄えられ、守備隊も整っている。もしもグイド伯爵がお望みならば、有利な条件で和平を結ぶまで長期間の抵抗を続けるのも不可能ではない。だが、その間、この砦の下方で生活する我々の運命はどうなる?チェーザレ・ボルジアは首都の頑固さに対して我々を報復の対象とするだろう。それゆえに我々は伯爵閣下にお願いしている――そして本件については職人組合の長も賛同している――アッシジやバリオーニ閣下のペルージャに倣い(ジャンパオロはここで表情をこわばらせた)、公爵の許に大使を送って降服を申し出るべきです、と」
ジャンパオロは頭を振った。「首都の抵抗に対して保護領に報復するのは、あの公爵の流儀ではない。彼はあまりにも奸智に長けている。己に下った者に対しては懐柔に務めるのが公爵のやり方だ。貴卿が谷の都市に及ぶことを懸念しているような炎も剣も使われないだろう。ソリニョーラの抵抗に対しては――もし抵抗するならばだが――ソリニョーラだけが攻撃を受けるはずだ。私があの公爵に仕えていた時に得た知識から、それについては断言できる。ファエンツァを思い出すがいい。ラモーネ平野の民は如何なる危害を被ったであろうか?何ひとつなかった。複数の砦が降伏の道を選んだが、暴力とは無縁だった。ファエンツァ自身が頑強に抵抗したにもかかわらずだ」
「あれは無益な抵抗でしたな」パヴィアーノ――組合の長――が、苦々しげに口をはさんだ。
「それは」とグイド伯爵が言った。「この議題の要点ではない。それにファエンツァはソリニョーラのように自然の要害に拠ってはいなかった」
「とはいえ最終的には」とバルベッロが抗弁した。「降伏は避けられませぬ。万の軍勢に対して永遠に抵抗を続けるのは不可能です」
「奴らとて永遠に我々を攻め続けることはできん」と傭兵隊長のサンタフィオーラが刈り込まれた頭を振り上げて言い放った。
バリオーニは椅子に深く腰掛け、眼前で繰り広げられる激論を傾聴していた。それはさながら、競技者たちの中央にボールを投げ入れて、それが試合中に幾度も飛び交う様を眺める者のようであった。
グイド伯爵も同じく論議にはほとんど加わらなかったが、無言で耳を傾けながら、その視線は発言者から発言者へと移動し、その顔は仮面のような無表情を保っていた。その真向かいの席に座る令嬢は、机に肘をついて掌に顎を乗せ、交わされる言葉を聞き漏らさぬように集中していた。抗戦の賛否が論じられるのに応じて、彼女の瞳は時に熱意で燃え上がり、あるいは蔑むように冷やかなものになった。だが一向に結論には至らず、議論が半時間に及んでも尚、ジャンパオロが到着した時点から一歩も前進してはいなかった。
この時、グイド伯爵は再びペルージャ人に目を向け、徹底抗戦を求めたサンタフィオーラの激烈な嘆願の後に訪れた一瞬の静寂を利用して発言をうながした。
「私の意見は諸君らの一助となるやもしれぬ」乞われたジャンパオロは、ゆっくりと話し始めた。「何故ならば、この提案はこれまで重ねてきた論議のどちらか片方を支持するものではないからだ。私が提案するのは中道策だ。無益な論争による時間の浪費を避けるにはそういった類のものが必要であろうし、諸君らも私の言葉を肯定的に受け止められるはずだ」
一同は期待をかき立てられ、熱心に耳を傾け沈黙を守った。パンタシレアの視線も他の者たちと同じく語り手の厳しい顔に定められ、彼がその趣旨を伝える間、一度も其処から離れなかった。
「諸君」彼は言った。「ここでは抗戦と降伏について議論されている。攻撃について、攻勢について考えるものはおらぬとみえる」
「考えてどうする?」サンタフィオーラは不機嫌な面持ちで問うた。「こちらが擁するのは、わずか五百の兵士だけだ」
だがバリオーニは横柄な仕草で手を振り傭兵隊長を黙らせた。「話は最後まで聞け、結論を先走るな。諸君も承知していよう――あるいは承知しておらぬかも知れんな、イタリアでは、あの一件について嘘ばかりが広まっておるゆえに――かの勇敢な紳士たち、我が友人たちはシニガッリアにおいて死をとげ――この私自身、辛うじて死をまぬがれることができたのは主の限りなき御慈悲によるものだった」そして彼は敬虔を装い十字を切った。「あれはな、諸君、かの公爵を罠にはめて全てを終わらせる計画だったのだ。奴が都市に乗り入れてきた時、石弓の射手たちが一斉に射掛ける手はずになっていた。だが、あれは悪魔――人の姿をした悪魔だった。奴は前もって警戒していた。プラエモニツ・エト・プラエムニツス(警戒は警備也)。奴は罠を逆転させ、自分を捕らえようと罠を仕掛けた者たちをその中に落とした。後は知っての通りだ」彼は身を乗り出すと、血走った目で出席者全員を見渡した。「諸君」しわがれ、熱のこもった声で彼はこう締めくくった。「シニガッリアでの失敗は、アッシジで成功するやもしれぬ」
どよめきが、彼の話を一心に聞き入っていた者たちの間に巻き起こった。彼は挑むような強い眼差しで一同を見た。「これ以上の言葉が必要であろうか?」彼は尋ねた。
「要りますとも」パヴィアーノは叫んだ。「如何にして、何時。方法と手段を」
「おお、無論だ。だが、まず最初に――」と、彼はグイド伯爵に向きなおった。「伯爵には、このような道を選択するご意志がありましょうか?イタリアからこの災厄を一掃し、飽くことを知らぬ欲望に憑りつかれた侵略者から、ご自身の、そして他の者たちの領地を救うために。チェーザレ・ボルジアを打ち砕くことは、即ち教皇軍の頭と脳を打ち砕くことです。さすればロマーニャへの侵略には終止符が打たれ、やがては中部イタリアにも安息が訪れるはずです。チェーザレ・ボルジアに命ある限り、トスカーナの王となるまで休むことはないでしょう。シニガッリアの一件以来、彼は非常に用心深くなっており、容易には近づけません。それでもアッシジに滞在している間ならば好機はあるはずです、貴方にそれを掴み取るお心さえあるならば」
グイド伯爵が眉を寄せて熟慮する間、何人かの出席者の顔には熱意が浮かび、激烈な賛意を表す者もいた。だが其処で、デル・カンポ翁から異議が唱えられた。
「貴方が提案しているのは殺人ですぞ」そのように告げた口調は、冷たく咎めるようなものであった。
「それが何だと?そのような埒もない言葉ひとつが、大の男たちを阻む障壁になるとでも?」バリオーニは猛々しく問い詰めた。
「少なくとも、ひとりの女を阻む障壁にはなりませんわ」マドンナ・パンタシレアの少年めいた明瞭な声が響いた。この評議会における初めての発言によって、彼女は場の注目を一身に引き付けた。彼女の黒い瞳には熱を帯びた輝きがあり、その白い頬には紅潮が高まっていた。一同の視線を受けて彼女は語り出した。「ジャンパオロ閣下のおっしゃったことは、まぎれもない真実です。チェーザレ・ボルジアに命ある限り、中部イタリアに平和はありません。一事によって、この一事によってのみ、ソリニョーラは救われるのです――チェーザレ・ボルジアの死によって」
彼女の朱唇から発せられた言葉――既にバリオーニによって語られた言葉――は喝采のどよめきによって報いられた。彼女の美しさと輝かしい女らしさ、それが彼らを動かした――道理や名誉、知識に抗しても、男として心を動かされずにはおられぬものだった。
だが老齢のデル・カンポは女性の名状し難い引力の影響を受けなかった。喝采が弱まると、彼は立ち上がった。老人は穏やかで冷淡な顔をグイド伯爵に向けた。
「我が君におかれても」と、彼は氷のように冷たい声で尋ねた。「ご賛同なされますのでしょうか?」
老伯爵の白い顔は硬く厳しいものだった。その硬さ厳しさは、しばらく思案した後で口を開いた時の声と同じであった。「デル・カンポよ、如何なる理由で反対するのか?そなたがそのように主張しておるのは明らかだ」
長老評議会議長は伯爵の厳しい視線を受け止めた。彼はいささか皮肉っぽく一礼した。「これをもって返答の代わりに」そう言って椅子を後ろに押すと老人は席を離れた。「我が君、そして皆様方、私が加担するつもりのない計画に関する議論がこれ以上進む前に、退出をお許し願います」
彼は再び一同に頭を下げると、毛皮で縁取られた長衣をまとい、静寂の中、ぞっとするような冷気を後に残して堂々と会議室から出ていった。
扉が閉まるや否や、動揺で顔面を蒼白にしたジャンパオロは立ち上がった。
「伯爵」ジャンパオロは叫んだ。「あの者をこの要塞から出してはなりません。我々の命がかかっているのです。これまで夥しい数の陰謀が、これよりも些細なことから失敗しているのです。チェーザレ・ボルジアの密偵は至る処におります。ボルジアの手の者たちはソリニョーラにも潜入しているでしょう。もしもデル・カンポがここで耳にした言葉を一言でも口にすれば、あの公爵は明日にでもそれを知る処となるやもしれません」
しばし沈黙が続いた。グイド伯爵の目はジャンパオロに問いかけているように思われた。
「全てが終わるまでデル・カンポ殿を閉じ込めておくには、この城の地下牢でも浅過ぎる」そう言ってから彼は小声で付け加えた。「まこと、どれほどの深さがあれば足りるであろうか」
伯爵はサンタフィオーラに顔を向けた。「疎漏無きように」彼が低い声でそう言うと、サンタフィオーラは立ち上がり、命じられたことを実行するために退出した。
マドンナ・パンタシレアは蒼白になり、両目を見開いた。彼女は長年の間、自分にとっても父にとっても誠実な友人であり続けたデル・カンポ翁に待ち受ける最悪の運命を案じた。だが、それでも彼女は、この処置の必要性を理解しており、女らしい情を押し殺して、彼を庇う言葉を口に出さなかった。
そして伯爵は厳粛な態度で一同に語りかけた。
「皆の者」彼は言った。「ジャンパオロ殿の提案は全会一致で賛同されたようだな」
「ちらと思い浮かんだのですが」とフランチェスコ・ダルディが口をはさみ、一同の注目は彼に集まった。彼は学者にして芸術の後援者であり、生来の抜け目なさに加えて世知にも長け、宮廷にも頻繁に出入りしており、ヴァチカンにおいてソリニョーラの雄弁家を務めていた時期もあった。「バリオーニ閣下のご提案そのままでは、いささかの懸念があるのでは」
これに対するバリオーニの返答は、険悪な目つきと苛立ちで鼻を鳴らす音、そして馬鹿にしたような短い笑いであった。しかしダルディはその反発を平然と受け止め、そうするうちにサンタフィオーラが再び会議室に入ってきた。
「待たれよ諸君」そう言ったフランチェスコ・ダルディは半ば微笑んでいた。「私はデル・カンポと仲良く牢獄暮らしを共にするつもりはない」
自分の席に戻った際、サンタフィオーラはぞっとするような微笑を浮かべていた。その笑みと沈黙が、一同が内心で傭兵隊長に問うたことに対する答えとなっていた。
「申してみよ」伯爵はアルディの主人にうながした。「貴卿の才覚は皆が承知しておるのだ、フランチェスコよ」
フランチェスコ・ダルディは頭を下げ、それから咳払いした。「ジャンパオロ殿は我々に、チェーザレ・ボルジアの死によって何が起こるかをご説明くだされた――最終的にもたらされる結果の重要性を考慮すれば、彼の殺害を正当化するには充分だ。だが我々、ここソリニョーラに住まう者は、その行為の結果として即時に何が発生するのかも考慮しなければならない。その直接的な結果は我々自身に影響するのですからな」
「国家の福利のために犠牲を払うのは、個人の義務だ」ジャンパオロは厳しく断言した。
「ジャンパオロ殿はシエーナでご自身の安全を図るおつもりなのだから、そのような美しい御題目も気安く口にできるのでしょうが」アルディの主人は辛辣に応じた。
数名の者が笑い、バリオーニは怒りで悪態をつき、グイド伯爵は間に入って彼をなだめた。
「私自身は」とフランチェスコ・ダルディは話を進めた。「個人の無駄な犠牲には反対であり、この件もそれにあたる。チェーザレ・ボルジアの側には、彼に心酔する傭兵隊長が何人もいるのは皆も承知のはずだ。コレッラ、シピオーネ、デッラ・ヴォルペ、他にもいるが、彼らは主君の死に対して必ずや報復を図るだろう。そして彼らが公爵の死に相応すると考える報復が手ぬるいもののはずがない。ソリニョーラは地上から消え去るだろう。一町、一村も残らず――女子供とて、彼らの激烈な怒りの前に容赦されるだろうか?おのおのがた、想像できますかな?」彼は問い、その問いに対する答は陰鬱な表情と沈黙だった。「だが私には代替案がある」彼は続けた。「これは、より効果的に我々の目的をかなえ、同じ成果へと導くはずだ、我々を――ソリニョーラを、アッシジを、ペルージャを。
「それはヴァレンティーノ公爵を生きたまま捕らえて人質とし、我々の包囲を続けるならば彼の首を吊ると脅すことだ。これで彼の傭兵部隊を抑止しておき、その間に教皇の許に公使を送る。我々は教皇聖下に対し、息子の生命と自由の引き換えとして我々自身の生命と自由を要求するのだ、教会による支配からの恒久的自由を約束した教皇勅書の発行を条件にして。そして聖下の筆を速めるために、所定の期限内に大勅書が我々の手に入らぬ場合は、公爵チェーザレ・ボルジアの首を吊るという脅しを加えるのだ」
「実に巧妙だ!」バリオーニは叫び、他の者たちも一斉に拍手喝采した。
「だが難点がある」フランチェスコは言った。「公爵の捕獲を如何にするかという問題だ」
「まったくだ、うむ」パヴィアーノが悲観的に同意した。
「だが策を用いれば」とグイド伯爵は強く主張した。「彼を誘い込むことは可能であろう。何らかの――何らかの罠に」
「それにはチェーザレ・ボルジアその人のような奸智が必要ですな」サンタフィオーラが発言した。
そしてしばらくの間、彼らは無駄な発言を続け、幾人かが思いつきを口にしたものの、これらは全て言うは易く行うは難しい類のものであった。半時間が経過しても一向に良策が思いつかず、いささか絶望の気配がただよい始めた頃、マドンナ・パンタシレアがゆっくりと立ち上がった。
彼女は机の端に立ち、天板に軽く手を置いていた。朽葉色の衣装に包まれたしなやかな長身はわずかに前のめりになり、その胸は上下し、顔は興奮で蒼白になり、潤んだ瞳は興奮に輝いていた。
「これ以上ふさわしい役目がありましょうか」ゆっくりとそう告げた彼女の声はゆるぎなく落ち着いたものだった。「ソリニョーラの未来の女主人が、今、この時代において、ソリニョーラの救済者となるのです。それにより私は、己が統治者として正統なる権利を有することを証明いたします。いずれ訪れる、その時のために――神もし許したまわば、それは遠い未来のことでありましょうが」
彼女の発言の後に続いた驚愕による沈黙は、彼女の父親によってようやく破られた。
「そなたがか、パンタシレア?一体、そなたに何ができると申すのだ?」
「皆様のような殿方にはできぬこと。これは女の武器が最も力を発揮する戦いです」
これに対して一同は口々に抗議した。ある者は恐れ、ある者は怒り、全員が興奮していたが、唯一の例外はバリオーニであり、彼は成すべきが成されるならば手段については頓着しなかった。
彼女は沈黙を求めて手を上げ、場は静まった。
「ボルジアと私の間には、ソリニョーラ救済という問題があります。これひとつだけでも私を駆り立てるには充分でした。けれど、それだけではないのです」彼女の顔は死人のように白さを増し、目を閉じてわずかにふらついた。それから自制を取り戻すと、彼女は再び説明を続けた。「ピエトロ・ヴァラーノと私は、この春に結婚するはずでした。そのピエトロ・ヴァラーノは、三ヶ月前にペーザロの市場で絞め殺されました――ボルジアの裁きによって。これもまた私とヴァレンティーノ公爵との間に存在する問題であり、この復讐の念は女の足だけが踏み入ることのできる道を通って近づかねばならぬ企みにおいて力となってくれるはずです」
「だが危険だ!」グイド伯爵が叫んだ。
「それは考える必要もないこと。私に何の危険がありましょう?私はアッシジでは知られておりません。あの町には、ほんの幼い頃に行ったきり。ソリニョーラですら私の顔を知る者は少ないのです。マントバから戻って以来、姿を見られる機会はほとんどありませんでしたので。アッシジでは細心の注意を払って行動するつもりです。皆様、この件で私を非難するのは間違いです。祖国の独立を護るため、何千という民の生命を救うため、私はこの計画に自ら乗り出します。ジャンパオロ閣下のおっしゃる通り、国家の福利のために犠牲となるのは個人の義務です。その上、ここで求められている義務は、ほんの些細なものに過ぎません」
男たちはざわめき、彼女の父親に視線を向けた。彼の発言を期待してのことであった。伯爵は両手で頭を抱え、じっと考え込んでいた。
「どのような――如何なる策をお考えなのです?」ジャンルカ・デッラ・ピエーヴェが、かすれ声で問うた。パンタシレアの即答は、彼女が如何にこの問題を十全に検討していたかを示していた。「私はサンタフィオーラ配下の傭兵部隊の兵士十数名を農夫と従僕に変装させて、共にアッシジに向かいます。そしてソリニョーラがチェーザレ・ボルジアに抗してアッシジに足止めをしている間に、私は彼を罠に誘い込み、拘束して、ジャンパオロ閣下が待つシエーナに連行する方法を考えます。この目的のためにはアッシジにあるそなたの館が必要です、デッラ・ピエーヴェ。私にあの館を提供なさい」
「あれを提供ですと?」恐怖しつつ彼は問い返した。「あれをネズミ捕りとして利用し、貴女を――貴女の比類なき麗しさを――チーズの代わりにすると?そう仰せなのですか?」
彼女は目を伏せ、深紅の血潮の色がその顔に広がった。
「ソリニョーラは」と彼女は答えた。「侵略の危機にさらされています。この谷の何千という女子供が住処を失い、死や、死よりも悲惨な末路をたどる危機にあるのです。そのような時に、ひとりの女が些細な……」――そして彼女は再び視線を上げて、一同に対し挑むようにその目を光らせ――「ひとりの女が些細な恥辱を受けるだけのことに、躊躇する必要がありましょうか?それを代償にして、その女は比べものにならぬほど多くのものを購うことができるというのに」と言った。
他の者たちが返す言葉も見つからぬままにいる処で口を開いたのは、彼女の父だった。あらわになった彼の顔は灰色にやつれていた。
「我が娘は正しい」彼はそう言って、更に――1500年代のイタリア人としては奇妙な論理ながら――「これは我が娘が生まれながらに支配するべく定められた民草に対する神聖な義務なのだ」と一同に宣言した。「男の力でヴァレンティーノ公爵に打ち勝つ方法が存在しない以上はな。デッラ・ピエーヴェ、そなたは館を提供せよ。サンタフィオーラ、そなたはパンタシレアが必要とする兵を」
訳註
【註1】: Bernardino Luini(1532年没)。ルネサンス・イタリアの画家。多数の教会フレスコ画を手がける。代表作はルガーノにあるサンタ・マリア・デッリ・アンジェリ教会の『Passione e Crocefissione キリストの苦難と磔刑』他多数。
【註2】: virago 現代英語では「じゃじゃ馬」「がみがみ女」の意味で使われるが、語源はラテン語であり「男の魂を持つ女」が本義。
ⅱ
無血開城したアッシジからは、チェーザレ・ボルジアのいつもの流儀により武力征服の痕跡が全て拭い去られ、公爵による占領はさしたる波乱もないままに平穏な日常の様相へと落ち着きつつあった。
君主が没し、玉座が崩れ去り、王朝が交代しようとも、民は食べ、生活し、日々の仕事に取り組まねばならない。かようにして、アッシジにはヴァレンティーノ公爵チェーザレ・ボルジアの姿を目にして眉を顰める者もいたが、大部分の市民は頭を下げ、ロマーニャの小規模な僭主制都市群を一つの強力な国家に再統合するという、人生をかけた大事業に取り組んでいる偉大なる名将に臣従の礼を執った。
チェーザレの軍勢は半数が周辺の土地で野営していた。残りの半数であるミケーレ・ダ・コレッラ指揮下の兵は、ソリニョーラに包囲攻撃を仕掛けるべく既に進軍を開始していた。降伏勧告のために送られたチェーザレの使者に対して、領主グイド伯爵は挑戦的な返答を寄越していたのである。
ソリニョーラは攻めるに難い地であり、チェーザレは性急な行動には高価な代償が伴うことを知る賢明な将だった。アッシジは快適な宿所を提供し、また、ここはフィレンツェやシエーナとの交渉のような仕事にはうってつけの中心地であった。よって彼は当地で忍耐強く腰を据え、コレッラに与えた作戦の結果報告を待っていた。
その作戦の要は、都市の南側にある城壁の下、丘にはさまれた場所に位置する城塞のほぼ真下に坑道を掘ることにあった。接近困難な地勢や守備隊の警戒と頻繁な襲撃によって、この調子ではコレッラが突破口を開くには一ヶ月はかかることが週の終わり頃には明白になった。チェーザレは砲撃について検討してみたが、すぐにその考えを退けた。あの岩だらけの斜面では、効果的な場所に砲台を設置するのは難しい。
この頑強かつ無益なソリニョーラの抵抗はヴァレンティーノ公爵にとって興味をそそる問題であり、この不可解な事象には、それを解き明かす真相が必ずや存在すると確信していた。シニガッリアの事件以来、更に疑り深く慎重になっていた彼は、あらゆる手を尽くしてその回答を求めた。
ある晴れた二月初めの朝、黄金色の日差しが迫りつつある春の訪れを告げる頃、市場から城下町へと急勾配の坂を馬で駆け下りていくチェーザレは、華やかな騎手たちに囲まれていた――鎧で身を固めた傭兵隊長たち、絹服をまとった廷臣たち、そして彼の真横を進む雪のように白い騾馬の背には、緋色をまとった教皇全権特使モリーノ枢機卿の端正な姿があった。
それは大部分が若き公爵自身と同世代の若者で構成された、まことに賑やかな騎馬行進であり、ソリニョーラのふもとに設営されたコレッラの陣を訪れるために進む間、この集団からは楽しげな会話と笑い声が漏れ聞こえていた。
サンタ・キアラ女子修道会前の空き地で、彼らの行進はしばし阻まれた。輿を置いた騾馬がサン・ルフィーノ大聖堂に通じる道路の一本に向かって進み、行く手を横切ったのである。その騾馬は二人の従僕に伴われており、輿の向こう側には大きな葦毛の馬にまたがった優雅な騎士がいた。
枢機卿はチェーザレに語りかけており、そしてチェーザレの方は話題に然程興味のない様子で視線をさまよわせていた。その視線はふと、件の輿を捕らえ、其処に見たものに引き付けられた。
帷は既に開けられており、チェーザレがそちらに視線を向けた瞬間、その騎士は前かがみになって、彼が輿の中に座す婦人に注目するように仕向けた――もしくは、彼にはそのように感じられた。その貴婦人のまばゆい美貌が彼の視線を奪い、そして同じ瞬間、彼女の目、子供のように大きく真剣な二つの目が彼に向けられた。
わずかな間隙を通して二人の視線は交差し、チェーザレは彼女の唇が驚いたかのように分かれ、その頬が血の気を失い象牙色になるのを見た。敬意を示すために――その女性に対してではなく、彼の一族が総じてそうであるように、彼もまた美をあらゆる徳の中で最も重視するがゆえに、彼女の持つ美しさに対して――征服者は帽子を脱ぎ、愛馬の背に向けて深く頭を垂れた。
議論の最中に水を差された枢機卿は、無関心の証であるその挙動に顔をしかめ、更に公爵の注意が完全に他に移っていることを明かされて渋面を深めた。チェーザレは彼にそっと尋ねたのである。「あの婦人が何者か、ご存知でしょうか?」
麗人に関する目ざとさについては定評のある高位聖職者は、即座にチェーザレが示す方を見た。しかしその刹那、帷は再び閉ざされ、彼の熱心な視線を当惑させるにまかせた。
チェーザレは唇に微笑を浮かべ、かすかに溜息を漏らし、それから深いもの思いに沈んだ。この出来事が提示した、極めてささやかな、しかし異常な要素に興味をそそられたのだ。彼は彼女に注目するように仕向けられ、そして彼の姿を見た彼女は蒼ざめた。その理由は何だろう?以前に彼女に会った記憶はない。会ったことがあるならば、あの顔をそう簡単に忘れるはずもない。ならば何故、彼の姿を目にしただけで、あそこまで奇妙な様子になったのだろうか?彼の前で蒼ざめる男はめずらしくない。それについては女も同じだ。しかし、それには必ず相応の理由があった。この場合、その理由とは何だ?
その輿と従者たちは路地に姿を消してしまっていた。だがチェーザレは尚も考え続けていた。彼は馬上で振り返ると、アッシジの紳士に話しかけた。
「あの輿に付き従っていた騎手をお目になされたか?」彼はそう問い、更に質問を加えた。「あれはアッシジの者だろうか?」
「おお、確かにそのようです、閣下」というのが答えだった。「あれはジャンルカ・デッラ・ピエーヴェでございます」
「デッラ・ピエーヴェ?」チェーザレは思案しつつ言った。「あれは参事会の一員でありながら、誓約が行われた際には欠席していた。なるほど!あの紳士と欠席の事情について知る必要があるな」馬を前に進ませてから鐙を踏んで立ち上がり、彼は旗手たちの頭上から呼びかけた。「シピオーネ!」
武装した傭兵隊長のひとりが直ちに彼の側まで進み出た。「あの輿と騎手を見たな」チェーザレは言った。「騎手の名はジャンルカ・デッラ・ピエーヴェだ。そなたは彼らの後を追い、あの婦人の住処を突き止めて報告せよ。それと共にデッラ・ピエーヴェをこちらに連れて参れ。彼にはコムナーレ宮で私の帰りを待たせておけ。必要とあらば拘束してもかまわぬ。必ずや彼を連れて来るのだ。下がってよい。行くぞ、皆の者」
バルダッサーレ・シピオーネは後ろに下がると、己の軍馬に拍車をかけて、密かに輿を追跡するべく駆け去った。
チェーザレは前進し、他の騎手たちは彼の周りに集まってきた。しかし彼は依然として、あの疑問について考え続けていた。「彼女は何故、蒼ざめたのだろうか?」
その理由を知れば、彼は自尊心をくすぐられたかもしれない。マドンナ・パンタシレアがアッシジにやって来たのは、ある人物を策略によって破滅させるのが目的であり、その人物については憎むべき怪物にして全イタリアの災厄として語られるのを耳にしたのみであった。自分が目にするはずと想定していたのは、病と天の報いによって年齢より老けて衰えた、醜悪で怖気をふるうような男の姿だった。その代わりに眼前に現れたのは若々しい騎手であり、きらびやかな衣装に包まれた身体は均整が取れて素晴らしく、その容貌も彼女がこれまで目にした全ての男性を凌駕する美しさだった。彼の瞳の輝きが自分の両目に注がれているのに気付いた時、彼女は己の魂を直に探られているように思えて、目が眩み、気が遠のきかけた。帷が再び下げられるまで、彼女は眩暈から回復することもできず、如何に気品ある雄々しい姿形をしていようとも、あの男は我が一族の敵であり、誓いを立てた通りに彼を破滅させることこそが己の崇高なる使命なのだと思い出すこともできなかった。
前へと進む輿の中で寝そべった彼女は、半ば目を閉じ、彼の視線が如何に熱心であったかを思い出して独り微笑を浮かべた。好都合だわ。
輿の帷が外側からわずかに持ち上げられた。「マドンナ、我々はつけられております」ジャンルカが小声で告げた。
パンタシレアの微笑はより大きく、より満足げになった。計画は追い風に乗って進んでいる。彼女はジャンルカにそのように告げた。
彼女の微笑とその言葉はジャンルカの怒りを燃え上がらせた――その怒りは、彼女がこの計画に身を投じた夜に火種が生まれ、それ以来ずっと燻り続けていたものであった。
「マドンナ」彼はかすれた声で叫んだ。「貴女がなさろうとしているのは、デリラのごとき妖婦の仕事ですぞ」
パンタシレアは彼を凝視し、そして己の任務の実態を容赦なく表した言葉を受け止めて、わずかに青ざめた。それから彼女は居丈高な態度により己を護った。
「僭越な」彼女はそう言い、その答えに打ち据えられたジャンルカは自制を失った。
「身の程知らずにも貴女をお慕いするほど僭越です、マドンナ」彼はほとんど怒ったように、それでも従者たちの耳に届かぬよう声をひそめながら言葉を返した。「それゆえにこそ、あまりにも不名誉な任務に没頭する貴女の御姿を見るのが耐えられぬのです。貴女の比類なき美しさを餌とした、卑しい――」
「おやめなさい!」そう命ずる口調は、彼が従わざるを得ぬほど厳しいものだった。
しばし沈黙し言葉を探すようにしていた彼女は、初めに高慢な一瞥をくれた後、二度と彼を見ようとしなかった。
「分際をわきまえなさい」そう言い放つ彼女の声は無慈悲なものであった。
「そなたの言葉は聞かなかったことにしましょう、ジャンルカ――全てを。私がアッシジに滞在する限りは、そなたの屋根の下に留まらねばなりません。この計画には必要なことですから。ですが、そなたは私との同席を避けなさい、そうすれば私はそなたの無礼を思い起こさずに済みますし、そなたも自分自身がそれほどまでに厳しく非難する者の姿を目に入れずに済みます」
「マドンナ」彼は叫んだ。「お許しを。そのような意味で申し上げたのではございません」
「デッラ・ピエーヴェ」軽蔑を含んだ、やや残酷な笑みと共に彼女は答えた。「はっきりと申しますが、そなたが何を意味したかなど、私にはどうでもよいのです。そなたが私の意志を尊重してくれさえすれば」
「お約束いたします、マドンナ」彼は苦々しげに答えた。「そして退出をお許しください」
ジャンルカは帷を下ろし、そうする間に輿は彼の家――サン・ルフィーノ大聖堂の側に建つ、アッシジで最も見事な邸宅のひとつ――の正門前に停止した。
蒼ざめ憮然とした面持ちで、彼はマドンナが従僕の腕を借りて輿を降りる様子を見守った。その従僕はいそいそと楽しい職務を遂行したが、それは常ならばジャンルカの役目のはずなのであった。それから彼は帽子を脱いでそっけない態度で一礼すると、自分の馬に拍車を入れて、のろのろとその場を離れた。この時、アッシジの若者が慰撫していたのは手酷い傷を負わされた自尊心であったが、彼はそれを傷つけられた愛と誤認した。それは愛と野望を混同したがゆえに、彼がソリニョーラの高貴なる未来の女伯爵に目を向けるようになったのと全く同じ錯覚であった。
そのような事情につき、突然、大型の軍馬にまたがった長身の武人に行く手を塞がれて呼び止められた時、この若い紳士は一触即発の状態にあった。ジャンルカはチェーザレの傭兵隊長を睨みつけた。
「貴様なぞ知らぬわ」彼は言った。
「残念ながら今までご縁がありませんでしたが、それを正すために参ったのですよ」シピオーネは穏やかに告げた。
「貴様の知己になど、なりたくもない」更に無礼な調子でジャンルカは応じた。
「そちらの気持ちはどうあれ、付き合ってもらわねばなりません。必要とあらば強要してもかまわぬという命令を受けているのでね」
これは叛逆罪に心当たりのある者にしてみれば忌まわしい言葉だった。ジャンルカの陰鬱な気分は恐怖によって払拭された。
「これは逮捕なのか?」彼は尋ねた。
シピオーネは笑った。「いやいや、違いますよ」彼は言った。「私は貴君を送り届けるために遣わされた、それだけです」
「だが、何処へだ?」
「質問攻めですね!コムナーレ宮へ、貴君の怠慢の埋め合わせをするため、我が君ヴァレンティーノ公爵に伺候するために」
ジャンルカは相手の無骨な顔を覗き込み、敵意がないのを見て取った。彼は気を取り直して、それ以上逆らうのは止めた。そして轡を並べて進む間、シピオーネから何らかの情報を引き出そうと努めたのだが、傭兵隊長は牡蠣そこのけに口が堅く、この黙秘によってジャンルカは再び不安を感じ始めていた。
コムナーレ宮に着いてからも事態は好転しなかった。控えの間で二時間以上もずっと、外出中の公爵を待ちあぐねることになったのである。退出を願っても、公爵は間もなくお戻りになられますと告げられるばかりであった。ひたすら忍耐を強いられた末に、彼は自分がある種の牢獄に入れられてしまったのを悟るに至った。公爵はあらゆる場所に間諜を放っているというバリオーニの言葉を思い出し、彼は最悪の事態を懸念するようになった。このような不安で一杯になった頭には、パンタシレアについて考える余地はなくなっていた――そのような些事は目前の大問題に取って代わられてしまったのである。
不安に苛まれる苦しみが極限まで達し、薄ら寒い待合室で震え始めた頃、案内係がやって来て、ジャンルカに公爵との会見準備が整ったと告げた。公爵が彼をこのような不安のうちに置いたのは、恐怖によって苛み、その精神を炉の中に置いた金属のように溶かす効果を狙ったものであったのか、それについては定かでない。とはいえ、この、長老評議会の同輩と共に忠誠宣誓を行わなかったアッシジの有力な紳士が自分に対して如何なる考えを持っているのかを誤りなく判断するために、狡猾なる公爵が意図的に仕組んだのだとしても不思議はない。確かなのは、ようやくチェーザレ・ボルジアの御前に出るのを許された時のジャンルカ・デッラ・ピエーヴェが、ひどく萎縮して、節義を守る意志の薄れた若者となっていたことである。
彼は宮殿の陰気な広間に案内された。其処は高い位置にある窓から光が射し込み、後脚で立つ獅子――アッシジの紋章――のフレスコ画が目に染みるような黄色地の上に赤色で幾つも描かれていた。巨大な暖炉で薪が燃やされているにもかかわらず、広間は冷えていた。ジャンルカが入室した時、其処ではチェーザレの傭兵隊長と侍従の一団が談笑していた。だが彼の到来によって、その場にいささか気障りな沈黙が生じ、紳士たちの一部からは気障りな注目を向けられ、あちらこちらに微笑む者、肩をすくめる者もおり、そのような全てが彼の不安をつのらせていた。
部屋の中央までたどり着いたものの、彼は其処でしばし所在なげにしていた。すると、紳士たちの一団を離れた公爵の長身が見えた。貴人は全身を黒衣で包んでいたが、上衣には金糸で唐草模様が刺繍されており、その見事さゆえに、遠目で見たジャンルカは公爵がダマスク象眼された鎧を身に着けているかと錯覚した。
進み出てきたチェーザレは、その若く白い顔に厳しく深刻な表情を浮かべており、その指は黄褐色の顎鬚をもて遊び、その眼差しは哀れむような、もの思わしげなものであった。
「そなたをもてなす機会を待って、一週間が過ぎてしまったな、デッラ・ピエーヴェ」彼は冷ややかにそう言った。「このままでは礼を失することになりかねぬゆえ、やむなく呼び立てることになった」彼は釈明を待つかのように、其処で言葉を切った。
だがデッラ・ピエーヴェは言葉を返すことができなかった。公爵の鋭い視線を浴び、この室内にいる全ての紳士から注視され、彼の心は麻痺したかのようであった。
チェーザレの目的は、デッラ・ピエーヴェの不服従が能動的な敵意によるものか、それとも受動的な敵意によるものなのかを見定めることにあった。それが受動的なものならば、捨て置いてもかまわない。だが、能動的なものならば、チェーザレとしては更に多くを知っておかねばならない。そしてこの間も、彼は情報を収集していたのである。
既に公爵は、彼の到着前夜にジャンルカ・デッラ・ピエーヴェがアッシジから抜け出し、その翌日に遠縁にあたるという美しい貴婦人を連れ帰った事実を確認していた。その婦人はジャンルカの館に滞在しており、従者たちから大層うやうやしく扱われているという。
チェーザレが入手した情報はこれが全てであり、これ自体は些細なものだった。宣誓にやって来なかったというだけならば、デッラ・ピエーヴェに疑念を抱かせるには些細に過ぎる事実だろう。だがデッラ・ピエーヴェの不服従と、あの輿に乗った美女が突然に顔面を蒼白にしたことを考え合わせ、公爵チェーザレは確認しておかねばならぬ問題があると判断した。そして今、眼前にいるデッラ・ピエーヴェの狼狽したやましげな挙動は、彼の判断の正しさを証明していた。
アッシジの青年が釈明の言葉を口にせぬために、チェーザレは詰問に入った。
「そなたはアッシジの一等市民のひとりであるにもかかわらず、先の日曜日に宣誓が行われた際、長老評議会の中に姿が見えなかった」と彼は言った。「欠席の理由を聞かせてほしいのだが」
「わ……私はその時、アッシジを離れていたのです、閣下」デッラ・ピエーヴェはそう答えた。
「なるほどな――だが、何処に出向いていたのかも話してくれような?」チェーザレは鋭く告げた――その口調は完全に、先刻承知の事実について問う者のそれであった。「そなたが答えをためらうのも無理はないが」彼はやや間を置いてから付け加えたが、その言葉によってジャンルカは自分の行動が既に知られているのだと確信した。
「閣下」彼は口ごもりつつ言った。「グイド伯爵は我が父の旧友でありました。当家は伯爵に多くの恩を負うているのです」
初耳の情報であったが、それを利用してチェーザレは更に言葉を紡いだ。
「そなたのソリニョーラへの訪問を咎めるつもりはない」彼はゆっくりと告げ、そして酷く動揺しているジャンルカは、その訪問について推察させるような情報を与えたのが自分自身であるとは思いもしなかった。「また、そなたのグイド伯爵への友情を責めるつもりもない。私が不快に感じているのは、そなたが彼を訪ねた理由の方だ」
チェーザレの放った思わせぶりな一言は、見事にジャンルカの急所に命中した。彼は蒼白になった。全ては露見しているのだ。
「我が君」彼は叫んだ。「天に誓って申します、私はソリニョーラで決定された方策に進んで関与している訳ではありません」
なるほど!その方策はソリニョーラで決定されたのか!チェーザレは脳内でそれについて検討し、デッラ・ピエーヴェが単独でその地に行き、ひとりの貴婦人――輿に乗った貴婦人、今日、彼を見て蒼ざめた貴婦人――を同伴して戻ったという事実を思い出した。彼女がソリニョーラからやって来たのは間違いない。あとは彼女の身元を確かめるだけだ。
「そなたの言を鵜呑みにせよと?」彼は尋ねた。
デッラ・ピエーヴェは拳を堅く握り締めた。「無論、私には己の言葉を証明する手立てはありませんが」彼は惨めな様子で認めた。
「いや、あるぞ。そなたが見落としている手立てがひとつある」チェーザレの声は極めて冷やかだった。「それは全てを包み隠さず打ち明けて、そなたの誠実を私に納得させることだ。にもかかわらず、そなたは未だ何も話そうとしない」彼は眼差しを険しくし、それから再び、全てを把握している者の口調で言った。「何ひとつ」そして更に「そなたが帰還する際にソリニョーラから伴ってきた、例の貴婦人についてさえ」と付け加えた。
アッシジの青年は打たれたかのように後ずさった。かの婦人がソリニョーラからやって来たという結論を導き出したチェーザレの思考の跡を追えぬ彼は、公爵がこの場で推論を重ねながら話しているとは夢にも思わず、既にパンタシレアの素性は百眼のアルゴスさながらに目ざといこの男に知られているに違いないと確信していた。
いよいよ追い詰められたデッラ・ピエーヴェは、偽りによって言い逃れようとして、グイド伯爵の砦を訪問した動機に言及した。「我が君」彼は前置きから始めた。「既にそれほど多くをご承知とあれば、後のことは申し上げるまでもないでしょう」
「私の差し当たっての目的は」とチェーザレは言った。「そなたの誠実を試すことだ」
ジャンルカは、チェーザレの掴んでいる情報が限定的なものであり、自分の言い分が通用する余地が残されていることを天に祈りつつ、熟慮の末に捏造した虚偽を思い切って披露した。
「一体、何の不思議がありましょう?抗戦を決意したグイド伯爵は、ご息女の安全を図り――愛娘を兵に包囲された砦の危険や不快とは無縁な場所に置くことを望まれました。かの婦人に我が家を避難所として提供したことは、閣下に対する私の誠実が疑われるような問題になるのでしょうか?我が父がグイド伯爵に大恩を受けていることは既に申し上げました。私の立場でこれ以上の不義理ができましょうか?」
チェーザレは計り知れぬ表情のまま、彼を見つめていた。なるほど!あの貴婦人はグイド伯爵の娘であったか。貴重な情報を得られたものだ。だがグイド伯爵の娘がアッシジに――チェーザレの駐留地の真っ只中に――やって来た理由が安全を求めての避難というのは、愚かで不器用な嘘だ。従って、彼女の存在には、ジャンルカがあくまで隠し通さねばならぬような他の理由があるはずだ。
公爵はかように推論した。そして筋道の通った結論を導き出すと、肩をすくめて軽蔑の笑みを浮かべた。
「これがそなたの誠実か?」と彼は尋ねた。「これでそなたは私の敵ではないと証明したつもりか?」
「これは真実です、我が君!」
「それは嘘だな」公爵は初めて声を荒げた。「容易く騙されるには、私はあまりにも多くを知り過ぎている」そして常の通りの落ち着いた調子に戻り、「我が忍耐を過信するな」と言った。「この地下に拷問台と吊るし責め装置があるのを忘れているようだな。必要とあらば、そなたに真実を述べるよう強いることもできるのだぞ」
ジャンルカの男気は恫喝に反発した。彼は意志の力を奮い起こして身を引き締めると、捨て鉢の勇気に鼓舞されて公爵を睨み返した。
「吊るし責め装置であろうと拷問台であろうと、私から言葉を引き出すことなどできません」彼は言った。「私にはこれ以上、話すことは何もないのですから」
チェーザレは無言のまま、彼について思案を続けた。公爵は不必要な、あるいは効果のない残虐行為に耽るような傾向はなかった。それに彼は、既にまんまと多くの情報を引き出しており、拷問台に頼らずとも残りを手に入れられるであろうと考えたのである。とはいえ差し当たり、デッラ・ピエーヴェがこれ以上は頑として何も言わぬであろうことは明白だった。彼はゆっくりと頷いた。
「これ以上、話すことは何もないと?曖昧な物言いだな。だが私はその本意を理解したつもりだ」
公爵は長身のシピオーネ隊長を含む炉辺の一団に目を向けた。彼は傭兵隊長を差し招いた。
「バルダッサーレ」彼は告げた。「デッラ・ピエーヴェ殿を連行し、追って指示あるまで拘束せよ。彼には見張りをつけ、誰とも面会させぬように」
パンタシレアに己の素性が割れているのを悟る機会を与えたくはなかった。その場合、チェーザレが手に入れた利は無駄になり、彼女がアッシジにやって来た真の目的は不明なままになってしまう。
この問題は少なからずチェーザレ・ボルジアの興味をそそった。彼はその夜、洞察力に優れた白面の秘書アガビト・ゲラルディに助言を求めた。しかし生来、穏やかで思いやりある人物であるはずのアガビトですら、デッラ・ピエーヴェから最後の一滴まで真実を絞り取るために、拷問という手段を使うよう勧めるのをためらわなかった。
「最終的にはそうするかもしれぬが」とチェーザレは言った。「だが、今はその時ではなかろう。今朝の彼奴は殉教者のような顔つきをしていた。これは良い傾向ではない。推論だが、彼はグイド伯爵の娘に懸想しており、それゆえに頑強になっているのではないだろうか。その全ての基礎をなす真相については、今の私には推測がつかぬ。この謎は、奸智に長けた――その点については悪魔に負けず劣らずの――フィレンツェのマキャヴェッリ書記局長をも困惑させるはずだ」
同じ頃、マドンナ・パンタシレア・デッリ・スペランゾーニは、ソリニョーラから同行してきた忠実な従者のひとりである、ジョバンニという名の青年と熱心に語らっていた。デッラ・ピエーヴェに当初の案を拒まれたために、この夜までの彼女は如何にして標的に接近するべきか思案に暮れていた。パンタシレアが望んだのは、彼が公爵への忠誠を装って、遠縁の娘エウフェーミア・ブラッチとして彼女を引き合わせることだった。しかしデッラ・ピエーヴェはこの計画自体に対する嫌悪からか、それを拒否して彼女の妨げとなっていた。
しかしパンタシレアはついにあの男とまみえ、彼の凛々しい外見のみならず、一目見ただけの彼女に丁重なお辞儀をするような、婦人に対する礼儀を貴ぶ騎士道精神もしっかりと見定めて、其処に活路を見いだしたのである。その上で彼女は、ジョバンニと共に明日の計画を検討していたのであった。
ⅲ
翌朝はすっきりとした快晴で、二月というより四月のような日和だった。柔らかな南風は温かく、ほのかに芳しく薫り、雲ひとつないコバルト色の空からは太陽がウンブリア平野を穏やかに照らし、テッシオ川の急流に銀色の火花を躍らせていた。
それはアッシジの城壁近くを流れる浅瀬でのことだった。早朝から六名ほどの紳士と共に出かけていたソリニョーラの野営地から戻ったチェーザレ・ボルジアは、思いがけなくも、マドンナ・パンタシレアに遭遇したのである。
彼女はうちしおれ、心細げな風情で地面に座っていたが、肩をもたせ掛けていた灰色の巨礫に視線を遮られ、公爵が真横に並ぶ位置に来るまでは、その姿は一部しか見ることができなかった。彼女はあの会議で身に着けていた朽葉色のドレスをまとっており、襟ぐりを広く開けた胴衣により喉元の完璧さと円柱のように見事な首筋を余すところなく見せつけていた。輝く髪は部分的にほどけ、その束は微風をとらえて、ほんのりと色付いた頬をくすぐるようにはためいている。ヴェールは既に滑り落ち、肩にかかっていた。
少しばかり離れた草地では、主人のいない騾馬が短い草を食んでいた。
彼女の姿を目にしたチェーザレは直ちに鞍から降りた。帽子を手にした彼が、陽光を受けた長いブロンズ色の髪を微かに光らせながらこちらに向かって歩いて来る間、パンタシレアは、その古代の闘士のように軽快な身ごなしと比類なき優雅さを感嘆しつつ眺める猶予を得た。
彼はひと目で彼女を識別し、ひと目で彼女の陥った苦境――本当であるか、装ったものであるかはさておき――を見て取った。そして真相はさておき、彼女の意図を探る好機に喜んで乗ることにしたのであった。
彼は深々と一礼し、そして気付けば彼女は、これまでの人生でついぞ見たことのないほど穏やかで美しい瞳と見つめあっていた。この完璧な男性的魅力、彼が体現する輝かしい若さと力強さは、パンタシレアの女性としての性質に対し、一瞬にして、そして抗い難く訴えかけた。己の任務を思うと彼女の心には痛みが走り、彼の眼差しを向けられた時には良心の咎めに襲われた。だがそれは、遭遇の衝撃に際して本能が示した瞬間的な抵抗に過ぎず、理性の冷たい手が即座に彼女の意志を制御し、支配した。
「お怪我をなさったようですね、マドンナ」彼はその卓越した魅力のひとつである、優しく、そして豊かで音楽的な声でささやいた。「不運に見舞われたのですね。我々に貴女をお助けする名誉をいただけますか?」
彼女はチェーザレに微笑みかけた。微笑みながらも、一瞬、唇を苦痛にゆがませたが、また笑顔に戻った。「足首を」そう訴えて、彼女は怪我した足に手を当てた。
「固定する必要があるようだ」そう言って彼は身に着けていたスカーフを素早く外した。
「いけません、いけませんわ!」彼女は叫んだ――彼の鋭い耳はそれを本物の恐慌による叫びと看破した。「家に帰れば侍女が手当てをいたします。家までは遠くありません」
「私に任せなさい」彼は強い調子で言った。「すぐに固定しなければ」
彼の視線を当てられて、彼女は紅潮した。顔を上げた彼女は哀れみを誘う風情で大層美しく、真っ赤に染まった頬が如何にも慎ましい乙女らしく見せていた。
「お願いいたします。どうかお構いなさらず」と彼女は固辞した。そして彼女が自分の役を演じたように彼も自分の役を演じ、目を伏せて従うと、分別を欠いた頑固さに遺憾を表して肩をすくめた。
次に彼女は、自分がどのようにして現在の苦境に陥ったのかを説明した。「私の騾馬は浅瀬を渡っておりました」と彼女は言った。「それが、こちらの川岸に上がろうとして石の上で足を滑らせ、膝をついて私を振り捨てたのです」
彼は真剣に案じているように見えた。「無礼な獣め、」そう言ってから「このような美しい荷を捨てるとは!」と続けた彼は、更に言葉を重ねた。「貴女のような方が、おひとりで遠出なさるのは慎むべきですよ、マドンナ」
「常のことではないのです。けれど、このような朝ですので、春の訪れに誘われて、つい自由に羽を伸ばしたくなって」
「危険な誘惑だ」彼は言った。「そのような誘いに乗った末に、多くの者が命を失ったのですよ。貴女はこの地方一帯にボルジア兵が屯していることを考えるべきでした」
「ボルジア兵の何を恐れなければならないのですか?」彼女は目を見開いて魅惑的な無邪気さで尋ねた。「貴方ご自身も、その一員でいらっしゃるのでしょう――違いまして?それなら私は、貴方のことも恐れなければなりませんの?」
「ああ、マドンナ」彼は叫んだ。「貴方のせいで、私は恐ろしくてたまらない」
「私が?」彼女は半ば微笑によって分かれた唇で問うた。
「貴女が貴重に感じ、私自身も劣らず貴重なものと考える自由が脅かされる恐れです。一度貴女と視線を交わした男が自由なままでいられようか?それより後に貴女の奴隷とならぬ男がいるのだろうか?」
その仰々しい科白を冗談ごとと片付けるように、彼女は快活に笑った。「まあ、こんな処で宮廷人からお世辞をいただけるなんて」彼女は言った。「てっきり貴方は軍人だとばかり」
「ここでの私は一介の廷臣です」と彼は深く頭を垂れて言った。「他の場所での私は公爵ですが」
彼は彼女の巧みに演じられた驚きと、突然の混乱を装った表情を観察した。「公爵――貴方が!」
「貴女の奴隷です」彼は言った。
「公爵様、私は盲目でございました――本当に、何も見えておりませんでした。どうせなら唖者であった方がまだよかったのに。私、公爵様から、どのような女と思われてしまったのかしら?」
彼女を見て、彼は溜息をついた。「人生はあまりに短い!それについて貴女にご説明するには、いくら時間があっても足りぬほどです」
彼の燃えるような眼差しに、彼女は再び頬を染めた。嫌疑や様々な思惑はあれども、尚も彼は――世の男ならば誰もがそうであろうが――彼女を目の保養と感じており、その賞賛は彼の瞳にはっきりと表れていた。
「私の情けない足のことを忘れておりましたわね」と彼女は話題を戻した。「すっかりお引き止めしてしまって。きっと随行されている紳士のどなたかが、お手を貸してくださるでしょう」
「否、この役目は他人任せにはできぬ。とはいえ、誰かに貴女の騾馬を連れてこさせよう」振り返った彼が鋭く命じると、部下たちは一斉に草地へと馬を急がせた。「杖があれば立ち上がることができますか?」彼は尋ねた。
「ええ、多分」
彼は身を屈めると、腕を曲げて差し出した。しかし彼女は後ずさった。「公爵様!」彼女は困惑したように小声で言った、「畏れ多うございます!お差支えなければ、あちらの紳士のどなたかのお力を」
「彼らのうち誰にも、貴女に手をお貸しするのは許さない」そう言って笑うと、彼は尚も再び彼女に自分の腕を差し出した。
「そんな風に厳しいご命令には――従うほかありませんわね」そう言って彼の腕を取ると、パンタシレアは無事な方の足で痛々しく立ち上がったものの、均衡を失って、小さな叫び声を上げながら彼にもたれかかった。
彼女を支えるために、彼の腕がすかさずその細腰に回された。彼女の髪が一瞬、彼の頬に触れ、甘い芳香が彼の脳を満たした。彼女は容赦を求めて哀れを誘うような詫び言をささやいた。彼は微笑し、無言で彼女を抱きしめたまま騾馬が連れてこられるのを待った。それから彼は余計なことは口にせず、彼女を幼子のように軽々と腕に抱き上げて鞍に座らせた。その力強さに彼女は驚いたが、それはこれまで多くの者たちが、より苛烈な意図で行使された際に驚愕した強さなのであった。
彼はちらりと、だが注意深く騾馬の膝を確認した。予期した通り、其処は艶やかな毛並みでわずかの傷も汚れも見つからなかった。彼女の足首も同様であろうと確信したチェーザレは、かすかな微笑を浮かべながら身を反すと、愛馬の鞍にひらりと飛び乗った。それから彼女の横に馬を進め、右手に騾馬の手綱を取ると、随行の紳士のひとりを呼び寄せて反対側で彼女を護るよう命じた。
「さあ、マドンナ、これで安心です」彼はうけあった。「では――出発だ!」
彼らは短い坂を下って水辺に向かい、飛沫を上げて浅瀬を渡るとアッシジに向けて馬を走らせた。その途上で公爵は気さくに話しかけ、パンタシレアはそれに当意即妙な答えを返しつつ、彼の魅力に対する感嘆の視線をちらちらと送り、そしてまた、単なる社交辞令だけではない賛辞に喜びを感じていた。街に入る際、公爵は何処まで送ればよいのか示すように彼女をうながした。
「サン・ルフィーノにある、遠縁のジャンルカ・デッラ・ピエーヴェの家までお願いいたします」
遠縁!またもやぺてんか、とチェーザレは考えた。彼女は自分の素性を何と説明するつもりだろうか。そう思った彼は、そっけなく質問した。
彼女の返答はよどみないものだった。「私の名はスポレートのエウフェーミア・ブラッチでございます、我が君」
彼はスポレートのエウフェーミア・ブラッチには何も言葉を返さなかった。その代わりに優しく微笑みかけ、その甘く邪気のない微笑みは、ジャンパオロ・バリオーニは彼の鋭さを過大評価していたのだと彼女に確信させた。
デッラ・ピエーヴェの館の入口で、彼は別れを告げた。その去り際、純粋なる悪意から、彼は自分の侍医であるトレッラを彼女の世話に差し向けると約束した。彼は自分が内心で面白がっていることも、彼女の瞳に一瞬浮かんだ不安に気付いたことも態度には出さなかった。彼女は過ぎた気遣いを懸命に固辞し、しばらく安静にすれば足は回復すると言った。その言葉を尊重し、彼がそれ以上の強弁をしなかったことで、彼女は明らかに安堵した様子になった。
彼はもの思いにふけりつつ馬を走らせてコムナーレ宮に戻り、アガビト・ゲラルディを呼んで一連の顛末を説明し、締めくくりに「そのような訳でな、アガビト」と言って次のような問いを投げた。「マドンナ・パンタシレア・デッリ・スペランゾーニはここアッシジに滞在し、スポレートのエウフェーミア・ブラッチと名乗り、デッラ・ピエーヴェの親族と称している。彼女は私の前に姿を現し、興味を誘い、魅惑しようと努めた。この謎が解けるか?」
アガビトの白い丸顔は、軽蔑にも値せぬとばかりに平静だった。「極めて単純です」彼は言った。「その女性は閣下のために仕掛けられた罠の餌です」
「アガビトよ、それでは答えにはならぬ。私が知りたいのは、その罠の性質だ。そなたには見当がつくか?」
「当て推測するには、この件はあまりにも深刻です」秘書は動ずることなく答えた。「しかしながら、あえてご忠告いたしますれば、お出かけの際は万全の警戒をもって武装を解かず、充分な護衛を伴わずにピエーヴェの舘にお入りになるような冒険はなさらぬことです」
チェーザレは黒い上衣を開いて、下に着込んでいる鎖帷子の鈍い輝きをアガビトに見せた。彼は「武装はしている」と言ったが、続けて「しかし、そなたの忠告の残りについては――」と肩をすくめた。「この種の罠には対処法があるのだ、仕掛けた者たちの頭上でバネ仕掛けが閉じるように仕向ける方法がな。シニガッリアでも似たような罠が用意されていた。然程前の話でもない、そなたも顛末は承知していよう」
「あの一件の場合、閣下は企みについて正確な情報を入手しておられました」
チェーザレは無情な微笑を浮かべて秘書を見た。「拷問によってレミーロ・デ・ロルカから絞り出した情報がな」と彼は言った。「今夜、地下の引き上げ装置を使えるように準備しておけ。刑吏と助手には私の指示があるまで待機させておくのだ」
アガビトが退出してしまうと、彼は他の問題に心を向けた。日没後、公爵は廷臣たちと晩餐を囲み、彼らを解散させてからはアガビトとその吏員たちと共に執務室にこもって、ローマやフィレンツェに送る文書の作成に夜遅くまで没頭した。
真夜中近くになって、彼はデッラ・ピエーヴェの尋問の準備が完了したかどうかをアガビトに問うた。秘書が答えを返そうとした、丁度その時、扉が開いて慌てた様子の従者が入室してきた。
「どうした?」眉をひそめてチェーザレが尋ねた。
「兵士たちがソリニョーラ砦下の陣営から戻りました。捕虜を一名、連行しております」
公爵は眉を上げて驚きを表した。「通せ」彼は命じた。すると、農民服に脚絆と十字の靴下留めという姿の若者が、両手を背中で括られ、二名の兵士にはさまれてやって来た。彼らと共に入室したコレッラ隊の若い士官に、チェーザレは直ちに問い質した。
「何があった?」
士官は敬礼した。「一時間近く前、ソリニョーラのふもとの丘でこの男を捕らえました。こやつは見張りの目を逃れて我が軍の野営地を突破しましたが、暗闇の中で岩を転げ落としたために我々の注意を引いたのであります。こやつは既にアッシジに入り、其処から帰還する処であると。暗号で書かれた手紙を隠し持っていたのを発見したのでドン・ミケロットが尋問しましたが、その手紙が誰から誰に宛てたものであるかは突き止められませんでした」
彼はチェーザレに、既に封蝋の破られた小さな紙を手渡した。それを受け取ると、公爵は不可解な暗号の配列に視線を走らせ、封蝋を調べ、最後にその紙を鼻先に運んで匂いを嗅いだ。そのかすかな芳香は、あの朽葉色の衣装をまとった女性を思い起こさせた。あの朝、ほんの短い時間、彼女がよろけたふりをして彼の胸にしなだれかかった時に、全く同じ香りを嗅いだのである。
彼は農民姿の密使に歩み寄り、冷厳な目で若者の凛々しくも落ち着いた表情を見つめた。
「何時、」と彼は静かに尋ねた。「マドンナ・パンタシレア・デッリ・スペランゾーニは、この手紙をそなたに託したのだ?」
若者の表情は一変した。その落ち着きは限りなく恐怖に近い驚愕によってぬぐい去られた。一歩後ずさると、彼は大きく目を見開いて、ひどく無感動に自分を見つめている公爵を凝視した。
「世間の連中が貴方について話していたことは本当だった!」興奮に我を忘れ、彼はついに叫んだ。
「噂が真実であることなど滅多にないぞ、我が友よ――信じるがよい、ほとんど無きに等しいのだ」そして公爵はもの思わしげに微笑んだ。「とはいえ、そなたは何と聞いた?」
「貴方は悪魔と契約していると」
チェーザレは頷いた。「それは私に関する大概の噂と同じ程度には真実だ。この者を連れて行け」彼は士官に命じた。「厳重に拘禁しておくのだ」それから若者に向かって「恐れることはない」と言い、「そなたには何ら身の危険はない。勾留期間は一週間もないだろう」とうけあった。
若者は涙で頬を濡らしながら外へと連れて行かれた――この恐ろしい公爵からは何も隠しおおせぬと確信し、己の仕える女主人のために流した涙であった。
チェーザレはアガビトに紙片を渡した。「写しを取っておけ」彼は簡潔に命じた。
「これは暗号です」アガビトは命令に当惑した。
「だが幸いにも鍵はわかっている。最後の言葉は十一字の数列で構成されており、更に二番目、六番目、十一番目の三つは同じ数字だ。この言葉を『Panthasilea』と想定してみよ。そなたの仕事は単純な作業になるはずだ」
アガビトはそれ以上何も言わずに羽ペンを手にして件の手紙に没頭し、その間、チェーザレ――その長身には毛皮で縁取られた足首まである緋色のローブをまとっていた――は思索にふけりながら部屋の中を行きつ戻りつしていた。
ほどなくして秘書は立ち上がり、チェーザレに写しを手渡した。
『今朝、ついに彼の注意を引くことに成功し、上々の出会いを演出できました。数日のうちに計画を実行する機会が到来すると思われます。こちらの準備は整っております。されど私は軽挙によって危険を冒さず、拙速は慎む所存です。
PANTHASILEA』
読み終えたチェーザレは、それを蝋燭の炎に差し入れて紙片を灰にした。「これには我々が既に知る以上の情報は記されていない。だが裏付けとしては充分だ。その手紙には元通りに封蝋を押してグイド伯爵に届けよう。こちらの兵士に使者の身代わりを務めさせ、本来の使者が傷を負ったために、グイド伯爵からの褒美を約束された無知な農民が代わりにソリニョーラへ手紙を運んだように装うのだ。
「そしてコレッラには、これからは使者を捕えずともよいと伝えておけ。さすれば坑道を掘り進むのも捗るであろう。ソリニョーラの者どもが、自らの命運がこのアッシジでの我が敗北にかかっているものと考え、しかも彼らの計画が順調に進んでいると信じ切っているならば、自らの努力だけを頼みにしている状態よりも警戒は緩むであろうからな。さて、次はデッラ・ピエーヴェの出番だ。彼を連行せよ」
ⅳ
アッシジの紳士が監禁されていたのは地下牢ではなかった。彼は宮殿の一室に何不自由ない状態で幽閉され、寝具も食事も身分にふさわしいものが提供され、看守からの扱いも丁重だった。よって彼がこの夜、この時刻に熟睡中であったのも不思議はないだろう。
その眠りから突然に起こされると、彼にあてがわれた部屋の中には四人の兵士がおり、そのひとりが掲げている煤けた松明の光が浮かび上がらせた彼らの姿は不気味で現実とも思えぬようなものだった。
「ご同行いただく」ジャンルカの肩にたくましい手を置いたまま、兵士のひとりが言った。
デッラ・ピエーヴェは不安を感じて起き上がった。目を瞬かせてはいるものの、すっかり覚醒しており、心臓は騒がしく鼓動していた。
「どういうことだ?」震える声で彼は尋ねた。「何処へ行けというのだ?」
「ご同行いただく」返答はこれだけ――この兵士は自分が受けた命令を厳守しているのであった。
哀れな紳士は恐る恐る兵士たちの髭面を見渡したが、それらは鋼の軍用兜の影で暗く怪しげに感じられた。それから抗っても無駄と観念し、彼は夜具をはねのけて寝台から降りた。
兵士のひとりが彼に外套を着せ掛けると、「参られよ」と告げた。「だが私の服は?服も着せてはもらえんのか?」
「必要ない。参られよ」
今や不安ですくみ上がり、己の最期の時がやって来たと確信したジャンルカは、言われるままに裸足で冷たい廊下を進むと、階段を下りて、つい昨日、公爵に謁見した広間に歩み入った。
彼が案内されてきたのは、チェーザレが彼の精神を拷問にかける目的――煎じ詰めれば慈悲深い目的と言えるだろう、この若者の肉体を損壊せずに済ませようという意向なのだから――で入念に準備を整えた舞台装置の中であった。
部屋の中ほどの壁際には、黒い布で覆われた机がひとつ置かれていた。其処に着席しているのは修道士のような頭巾付の黒い長衣に身を包んだ尋問者であった。その両脇には吏員が控えており、それぞれの前には紙とインク壷と羽ペンが用意されていた。机上には二つの枝燭台が置かれ、それぞれに六本の蝋燭が刺さっている。この広大な丸屋根の部屋には他の光源は一切なく、大部分が妖しい影に包まれたままであった。
奥にある炉床には鉄の三脚が据えられ、その上に置かれた火鉢の中では木炭が赤々と燃えていた。その炎の中に木製の柄が付いた道具が何本か突き立てられ、熱せられているのを、ジャンルカは戦慄を覚えつつ確認した。
部屋の反対側、尋問者の机に向かって巨大な蜘蛛の巣の細糸のように垂れている灰色の縄は、円天井の穹稜部の暗がりでほとんど見えない位置に据えられた滑車――拷問用の引き上げ装置のものだった。この縄の側には、革製の袖無し胴衣を身に着け、たくましく毛深い腕を肩までむき出しにした二人の男が立っている。同じ服装をした三人目の男は、彼らの前方に立ち鞭縄に結び目をこしらえていた。
部屋の中央に――忌まわしい無彩色の空間の中に存在する一点の色彩である――緋色の長衣をまとって立つチェーザレ・ボルジアは、絹の帯に両手の親指を掛け、頭には緋色の帽子をかぶっていた。どことなく哀愁を帯びた彼の眼差しは、今、ジャンルカに定められていた。
アッシジの若者はその場に立ち尽くし、恐怖に魅入られたように彼を見つめていた。ジャンルカは自分が如何なる目的により目覚めさせられ、寝台から引きずり出されたのかを理解した。自然に息をすることもできず、激しい鼓動のせいで息が詰まりそうだった。ふらついた彼は革の籠手を着けた兵士の腕に支えられた。
未だ一言も発されず、その静寂と冷たい呼気、暗闇、これ見よがしな下準備への恐怖とが交じり合って、ジャンルカにはこの光景が恐ろしい悪夢か何かのように見えていた。それからチェーザレの合図に従って、ほとんど足音も立てずに刑吏の助手が兵士たちから罪人を引き受けるために進み出た。彼を放した兵士たちは鎧を軋ませながら退出していった。
机の前まで導かれたジャンルカは、二人の恐ろしい護衛にはさまれて尋問者と向きあう位置に立たされた。
目深な頭巾の奥から聞こえる冷たい声は、ジャンルカには丸屋根の部屋全体に鳴り響くように思われた。
「ジャンルカ・デッラ・ピエーヴェ」その声は語った。「汝はソリニョーラ僭主グイド・デッリ・スペランゾーニ伯爵と語らってヴァレンティーノ及びロマーニャ公爵チェーザレ・ボルジアに対する謀議に加わり、ここアッシジにおいて偉大なる閣下を害する策略の手配を行った罪がある。その罪、死に値する。されど、閣下が神聖なるゴンファロニエーレ・デッラ・キエーザ(教会の旗手)であり、閣下の行なわれる戦いは即ち聖座の戦いであると見做されるが故に、汝の罪には死以上の罰が値する。即ち汝は公爵閣下に対してのみならず、神と神の地上における代理人たる教皇聖下に対しても罪を犯したのである。しかしながら聖書に曰く『ノロ・モルテム・ペッカトリス、セド・ウト・マギス・コンヴェルタチュレト・ヴィヴァト(主は悪人の死を望まれず、回心を望まれるものなり【註1】)』、閣下は聖なる父の御名において、汝が己の罪を正直に包み隠さず告白し悔悛するよう寛大な処置をお望みだ」
声の轟きは終わった。だがその残響はジャンルカの苛まれた脳に尚も鳴り続けていた。ふらつきつつ、この先に待ち受けるものを漠然と思い描きながら、彼はその場に立ち尽くしていた。彼はうなだれた。
「背後を見よ」その声が命じた。「汝自身の眼でしかと見るのだ、汝が頑なに抵抗を試みようとも、我々は汝の唇をこじ開ける手段には欠かぬのだということを」
だがジャンルカは見なかった。見る必要などなかった。彼は震えていたが、それでも尚、黙したままであった。尋問者が合図した。刑吏のひとりがジャンルカの肩から外套をはぎ取り、哀れな紳士をシャツ一枚の姿で立たせた。彼は自分が強い――無慈悲に強い――手に掴まれるのを感じた。彼らはジャンルカの向きを変えさせると、部屋の反対側にある引き上げ装置の方に引きずっていった。その中途で怖気づいた彼は、刑吏たちを止めようと全体重を乗せて彼らの腕に逆らった。
「やめろ、やめてくれ!」血の気が失せた灰色の唇でジャンルカは嘆願した。
突然、公爵が言葉を発した。「待て!」そう言うと、彼は一歩前に進み出て刑吏たちの行く手を遮った。彼の手振りで刑吏たちは後ろに下がり、部屋の中央にはジャンルカと公爵だけが残された。
「デッラ・ピエーヴェ」チェーザレは穏やかに声をかけるとアッシジの若者の肩に手を置いた。「己が何をすべきかを考えよ、己の前に何が待つのかを考えるのだ。それについて、尋問者は充分に明かしてはいなかったようだな。そなたも作動中の引き上げ装置を見たことがあるはずだ、この装置が人間の肩の関節をねじり上げる様子を」そして公爵はジャンルカの肩を掴んだ鋼鉄のような指にきつく力を込め、若者は己の腕に千本の火線が走り抜けるように感じた。彼が痛みで息を飲むと、公爵はすぐに力を緩めた。チェーザレは微笑んだ――穏やかで、慈悲のこもった微笑であった。
「そなたにとって、引き伸ばし責めが如何に耐え難いものかを考えよ。うけあおうぞ、そなたは遅かれ早かれ告白せずには済まぬ。そして、その先に待つのは何だ?解放か?否。一度引き上げ装置に掛けられた以上、そなたは公の法に委ねられた存在だ。そして法がそなたに口を開かせたならば、次には法がそなたの口を永遠に閉じさせるであろう。そのことを考えよ。損なわれた肉体の苦しみから、そなたを解放するのは処刑人の両手だ。考えるのだ、己の若さを――その人生を犠牲に求められているのだということを。その上、そなたの沈黙は何者の利益にもならず、そなたの告白は既に裏切られている者以外の何者をも裏切らぬのだ――頑強にふるまったとて、そなたの犠牲には何の意味もないのだ」
ジャンルカは青白い顔で哀れっぽく公爵を見た。
「そ……それを信じられたら!」彼はつぶやいた。
「そなたを得心させるのは容易いことだ。そして、そなたがそれを得心すれば、今、私がそなたを救おうとしているのは、私心を離れた公正に基づく行為であることも、おのずと得心がゆくであろう。
「教えておこう、マドンナ・パンタシレア・デッリ・スペランゾーニは、既に私に狙いを定めた網を広げている。今日、彼女は私の関心を引く目的で我が前に姿を現し、今夜、父親に宛てて、首尾よい作戦の開始と、一週間以内に彼女が反逆行為を完遂して私を罠に捕らえるであろうと報告した手紙を送った。
「既にこれほど多くを知りながら、私がみすみす彼らの企み通りになると思うか?そなたの知る情報がこれに加わったとて、如何ほどの違いがある?それを明かす前に拷問と死の苦しみを味わうだけの価値があると思うか?」
ジャンルカは震えた。「何を知ることをお望みなのです?」彼は尋ねた。「私にこれ以上、何をつけ加えることができると仰せなのです?閣下は既に、総てをご存知のように思われます――私が知る以上を。もしやそれは……」彼は突然、心に浮かんだ懸念を口にした。「かの婦人を捕らえる際の証拠として、私の証言をお求めなのですか?」
「必要な証拠は既にそろっている。彼女が父親に宛てた手紙があるのだ。それだけで彼女に審判を下すには充分だ。否、否。そなたに求めている情報は、彼女が準備した罠の正確な性質、それが全てだ。それを教えさえすれば、それ以上グイド伯爵や彼の娘を害することは求めぬ」
「そんな……それだけなんて――」
「それで全てだ」チェーザレは言った。「たったそれだけだ。そしてここには、もう一方の恐ろしい選択肢が控えている。これ以上の寛容が可能だろうか?話すのだ、さすればそなたは寝床に戻ることができる。用心のために、ソリニョーラが陥落するまでは抑留されるが、それ以降は完全に行動の自由が保証される。それについては宣誓を行おう。沈黙を守る場合は――」彼は引き上げ装置の灰色の拘束具に向けて手を振り、そして肩をすくめた。
それはジャンルカ・デッラ・ピエーヴェの沈黙の終わりであった。強情を張っても無意味だと、虚しい自己犠牲――彼の愛を僭越とみなし、あまりにも無慈悲に彼を利用した女性のための犠牲――に過ぎないのだと、はっきりと悟ったのである。そして彼は公爵が所望したささやかな情報をうちあけた――チェーザレの誘拐、それこそが陰謀の目的であり、マドンナ・パンタシレアがアッシジに滞在している目的であることを。
訳註
【註1】: エゼキエル書33章11節
ⅴ
翌日の正午に近い時刻、公爵家のお仕着せをまとった優美な小姓がデッラ・ピエーヴェの館に持参したのは、チェーザレ自身の筆による芳しい香りのつけられた手紙であり、数ならぬ身の求婚者のように謙虚な表現を用いて、公爵自ら訪問してマドンナ・エウフェーミア・ブラッチのご機嫌を伺う許可を求めたものであった。
パンタシレアは瞳を輝かせながらそれを読んだ。彼女の計画は驚くほど順調に進んでいた。フィーリウス・フォルトゥナエ(幸運の申し子)と仇名されるほど運のよさで知られるチェーザレ・ボルジアだったが、その彼にして、今回ばかりは幸運の女神も味方しなかったようだ。
貴人が求める許可を彼女はいそいそと与え、かのボルジアその人が、わずか数時間後に来訪することとなった。華麗な騎馬行列を小さな広場で待たせておき、客人は単身でパンタシレアの滞在する邸宅に足を踏み入れたのである。
彼は如何にも求愛者らしく豪華に着飾っていた。金布で仕立てられた上衣、片方は乳白色、もう片方は空色のタイツ、そしてベルトと剣帯には小国ひとつ買えるほどの高価な宝石が幾つも輝いていた。
彼女の姿があったのは、庭に幾つかあるテラスの最上段へと通じる窓付扉を備えた一室であり、其処は貴重な宝石を据えるにふさわしい台座であった。モザイクの床には東洋の絨毯が敷かれ、壁には高価なタペストリが幾つもかけられていた。書物とリュートが置かれた黒檀の机には象眼細工がほどこされていた。暖炉の側では二人の侍女が祭壇布に刺繍をしており、マドンナ自身は東洋の文様が織られた低い長椅子にもたれていた。室内にただようほのかな芳香――その甘酸っぱいライラック精油の香りは、昨夜、彼が手に入れた書状から嗅ぎ取ったかすかな痕跡と合致するものであった。
チェーザレの登場を受けて、彼女は立ち上がる素振りを見せたが、彼はそれを制した。優しい気遣いから負担のかかる行動を禁じ、必要とあらば力づくにでも彼女を座ったままにさせておくために、彼は素早く室内に歩み入った。其処までされて、彼女は微笑みながら長椅子に身を預けた。
彼女は白いドレスに身を包んでおり、髪をまとめた金色のネットにあしらわれた豆粒ほどのサファイアが眉間に垂れていた。
片方の侍女が、獅子の足を象った銀無垢の脚が付いた、古めかしい意匠の低い椅子を急いで整えた。彼はそれに座るとマドンナの足首の具合を真剣に尋ね、明日には立ち上がることができるでしょうという言質を得た。
二人の対面はごく短いものになったが、彼が彼女に抱く深い関心が匂わされており、宮廷式の典雅な言葉遊びに留まるものとはいえ、言葉の剣を交えるこのゲームにおいて、スポレートのマドンナ・エウフェーミア・ブラッチは初心者とは思えぬ技量を披露したのであった。
彼女は自分の任務にきつく拘束されてはいたが、それでも尚、彼の類稀なる優雅さと、きらびやかで堂々たる姿の美しさに目を奪われ、彼の印象的な瞳と穏やかで音楽的な美しい声が呼び起こす危険な悦びを拒むことはできなかった。
ようやく彼が辞した時、残された彼女は深いもの思いに沈んでいた。
その翌日、彼は再び訪れた。また更に翌日も。そして常に騎馬行列は下の広場で彼を待っていた。このゲームは彼の期待を大きく上回る興味深いものになりつつあった。獅子の口中に自分の頭を突っ込むような行為は、未だかつて経験したことのない感覚を与えてくれたのである。狩人を狩り、ペテン師をペテンにかけるというのは、彼にしてみれば目新しいことでもないが、しかしこのように愉快至極な状況下で取り組んだことはなかったのだ。
三度目の訪問では、侍女たちは彼の到着前に下げられており、彼女は独りきりでいた。このゲームにおける新たな一手が繰り出される前兆を感じつつ、その待遇が示唆する好意に感謝するために片膝をつくと、彼は女主人の芳しい手を取り熱烈に接吻した。しかし彼女の表情はひどく深刻であり、それが初めて彼を驚かせた。
「公爵様」彼女は言った。「誤解なさっておいでですわ。侍女たちを下がらせたのは、どうしてもお話ししなければならないことがあって、それは他の者の目のない処の方が御為であろうと考えたからです。公爵様、どうかもう、ここにはおいでにならないで」
これまでの人生でも経験のないほどの驚きであったために、彼はその感情が顔に表れるのを防げなかった。だが彼女は、その表情の急変を無念ゆえと取り違えた。
「もう貴女を訪ねてはならぬとは、マドンナ!」彼は叫び、その口調から、彼女は自分の受けた印象が正しいことを確認した。「私に貴女のお気持ちを損なうようなふるまいがありましたか?跪いて許しを乞います、このように貴女の足元に。どうか償いの機会を」
彼女は穏やかに頭を振ると、優しく悲しげに彼を見下ろした。「気持ちを損なうだなんて、そんなことが貴方におできになると思いまして?お願いです、どうかお立ちになって」
「できません。私の罪を知るまでは」彼の眼差しは、神殿で最も敬虔な信徒が見せるようなものであった。
「貴方には何の罪もありませんわ、公爵様。でも……」彼女は唇を噛んだ。うっすらと、彼女の頬が暖かな色に染まった。「でも、私は……私は自分の評判を考えなければいけないのです。ああ、どうかお怒りにならないで。連日のご訪問の間、随行の皆様が下で待ち受けているのを口さがない人々に見られたら、陰でどんな噂にされてしまうでしょう」
ようやく彼は、この愛らしい頭の中で働いている悪魔が如き奸智を理解した。「それが全てなのですか?」と彼は叫んだ。「他に理由はないのですか――何も?」
「それ以外に、どのような理由があるでしょう?」彼女は視線を逸らしてつぶやいた。
「おお、それならば改めるのは容易い。次からは私独りで参ります」
彼女はしばし思い巡らすと、穏やかに頭を振った。「それでは解決にはなりませんわ、それどころか、もっと悪いことになるでしょう。この家にお入りになるのを見られてしまったら。そうしたら――ああ、人は何と噂するかしら?」
彼は勢いよく立ち上がると、大胆にも彼女に片腕を回した。パンタシレアはそのふるまいを許したが、しかしチェーザレは彼女が身震いするのを感じ取った。「それが何だと――町の者たちの言葉に何ほどの意味があるとおっしゃるのです?」彼は問うた。
「意味は――貴方にとっては何の意味もないことでしょう。けれども私の――私のことをお考えください。そのような醜聞によって、操正しい娘としての評判はどうなってしまうでしょう?」
「あちらに――裏道がある――貴女の庭先に。あれならば誰にも姿を見られずに済む。私に鍵を渡しなさい、エウフェーミア」
瞼を伏せて薄目で彼女の顔を盗み見たチェーザレは、自分の予期した通りのものを確認して彼女を放した。彼は内心で笑っていた。彼はまさしく色恋にとち狂った間抜けな権力者、恋患いの道化者――自分を待ち受けている罠にいそいそと飛び込もうとしている、底抜けにお人よしな痴れ者であった。間違いなく彼女はそう考え、己の下劣な作戦の巧妙さに高揚を感じているはずだ。
彼女はチェーザレの前で震えていた。「公爵様、わ…わた……私には、そのような」
無駄に勿体をつけた駆け引きのせいで嫌気が差してきた。大胆も過ぎれば愚であり、それが彼をいささか軽蔑的な気分にさせていた。彼は一気に興が醒めた
「ならば仕方ない」と彼は言った。「二度とこちらを訪れまい」
チェーザレは今や彼女を恐怖に陥れていた。彼は彼女の黒い瞳に不安の色がひらめくのを見た。主導権を失った状況からの、彼女の速やかな立ち直りは天晴れなものであった。
「お怒りですのね」彼女はチェーザレの肩に顔を埋め、「鍵をお渡しいたしますわ」とささやいた。
彼はそれを手にして立ち去りながら、彼女がこれまで地上に生を受けた女の中で最も冷酷極まりない、情というものを知らぬ背信者であると確信していた。自分が去った後、彼女がその場に座り込んで、激しく泣きながら己を罵る様を目にしていたならば、彼の考えは異なるものであったかもしれない。それでも尚、この夜、彼女は父親に宛て手紙を書き、全てが素晴らしく順調に進んでおり、計画の完了は間近であると記したのであった。
ソリニョーラの方はといえば、このような報告の手紙と包囲攻撃の漫然とした進め方に惑わされて、おざなりな見張りを続けていた。時折、要塞の南壁下から鶴嘴を振るう音が聞こえ、コレッラの部下たちが其処で作業しているのは察知できた。しかし彼らは、もはや敵兵を追い散らすために打って出るようなまねはしなかった。別の、そして更に効果的に王手をかける手段を確保している以上、そんなことは命の浪費とみなしていたのである。
翌日の午後、かなり遅くなってから、チェーザレ・ボルジアはパンタシレアがこれまで彼の応接に用いていた部屋の窓付扉を軽くノックした。彼女はその部屋で独り待っていたのだが、忍ぶ仲の恋人のようにやって来た彼を迎える際の態度には、やや戸惑いが見られた。とはいえ、この日の彼は文字通り分別という言葉の化身であった。
二人は様々なことを語り合って午後を過ごした。やがて話題はアキラーノ【註1】の作詩法に、そして一軍人として現在チェーザレの旗に従っているスペルロー【註2】の作品に及び、公爵は追憶にふけった。彼は一度だけ、自分自身について、そしてイタリアにおける己の務めと、その崇高な目的について話した。彼が語るのを聞くにつれ、パンタシレアは彼の中に見いだしたものと、自分が見いだそうとしていたものとの相違に、またしても驚かされた。彼女が耳にしていた彼の人物像は、策謀と野心をこね合わせて作られたような人間であり、辛辣で良心に欠け、敵にも味方にも苛烈であり、人の心を持たず、それゆえに無慈悲な男というものであった。彼女が実際に見た彼は、極めて温和かつ優雅で喜びに溢れており、そして心配りも言葉遣いもめったに見られぬほど甘美なのであった。彼女は己に尋ねることを強いられた。彼の大いなる偉業は妬みを買わずに済むだろうか、彼の威勢こそが憎しみの源であり、それゆえに敵対する者たちから恨まれ続けているのではないかと。
その日の午後、卓上に置かれていた、甘いプッリャ産ワインが入った首の長いヴェネチアングラスの葡萄酒瓶は、侍女たちがあらかじめ用意しておいたものだった。説明し難い衝動に駆られた彼女は、夕暮れが迫りチェーザレが辞するために立ち上がった時、彼のためにそれを一杯注いだ。パンタシレアがゴブレットを満たす間、彼は卓の側に来て彼女の横に立ち、そして彼女が自分自身のためにもう一つの杯に注ごうとした時、彼は両手でその器を覆った。
それは、彼の熱烈な視線がしばしば垣間見せていた内なる情熱が、当人の意に反して表出したかのようであった。
「否、否」彼の美しい両目が彼女を見据え、その視線は彼女を包み込み、呪縛するかのように感じられた。「一つの杯を分かち合わせてください、マドンナ、私には過ぎた願いですが、それでも。どうか私のために乾杯し、この葡萄酒に貴女の唇の芳しい香りを残してください。そうしたら、次は私が貴女のために乾杯する番です。それで恍惚として神々しき酩酊に陥らぬならば、私は生命なき一握の土くれということになりましょう」
彼女はわずかに抵抗を示したが、しかし彼の意志は秋風が木の葉をもてあそぶように彼女の意志を翻弄した。彼は強烈な熱情に覆われたような両眼で彼女を凝視していた。何故なら彼は薬を盛られた葡萄酒にも、このような狡賢い術策にも精通しており、今、勝負しているゲームであえて不必要な危険を冒すつもりはなかったからである。
だが、この葡萄酒は無害だった。彼女はそれを飲み、杯を彼に手渡した。彼は片膝を曲げて酒杯を受け取ると、跪いて視線を彼女の顔に定めたまま、それを飲み干した。
それから彼はいとま乞いし、彼女は窓辺に立って、去り行く彼の姿を見送った。それは庭を進み、次第に濃さを増す暗がりの中に溶け込んでいった。彼女は身震いし、震える唇から嗚咽を漏らすと力なく椅子に沈み込み、昨日と同じく、流す理由などないはずの涙に暮れたのであった。
その夜、彼女は再び父である伯爵に宛てて手紙を書き送った。全ては期待以上の順調ぶりで進んでおり、三日以内には、ソリニョーラの解放を購うことを可能にするものを待ちかねている人々の手に渡せるであろうと。
訳註
【註1】: Serafino dell'Aquila(1466年 - 1500年)。アクィラ出身の詩人。ローマにてボルジア家の後援を受けていた。
【註2】: Francesco Sperulo(1463年 - 1531年)。1502年からチェーザレ指揮下の教皇軍で共に戦った軍人であり、詩人、高位聖職者でもある。叙事詩の形式でチェーザレの軍功を記録している。
ⅵ
その翌日、彼は再びやって来た。更に翌日も。今はグイド伯爵令嬢にとって、悲嘆による痛みを肌身で感じる季節であった。チェーザレが不在の時には彼の誘拐計画を練り、チェーザレを前にした時には全身がしびれたようになって魅惑され、自分の計画に対する恐怖と嫌悪で一杯になって、彼の意志に流されるままの存在と化していた。
そしていよいよ、ユダの罪業を行わねばならぬ運命の夜が到来した。パンタシレアが頼んだ通り――醜聞を避けるためという懇願を聞き入れて――黄昏時に訪れたチェーザレが目にしたのは、暗がりの中、炉床で炎を上げている丸太以外には明かりのない部屋で待つ彼女の姿だった。彼は令嬢の手を取って自分の唇に運んだ。それは氷のように冷たく、彼女の全身が激しく震えているのと同じく彼の手の中で震えていた。彼女の顔に視線を走らせたチェーザレは、赤々とした火明りによって青白さが誤魔化されてはいたものの、ひきつり、憔悴しているのに気付いた。彼女が自分と目を合わせようとしないのを見て、彼は――既に疑っていた通りに――罠が仕掛けられるのは今夜であろうと結論した。
「エウフェーミア!」彼は叫んだ。「私のエウフェーミア、すっかり冷え切っているではないか!」
その愛情が表れたふるまい、その優しく愛撫するような声、その情熱を訴えかける眼差しに、彼女は身を震わせた。「と……とても寒いからですわ」彼女は口ごもりながら言った。「北風が吹いているせいです」
彼はパンタシレアから離れて再び窓に向かい、彼女の視線はその背を追った。彼は分厚いカーテンを閉めて、未だ空に留まっている弱々しい日の光を完全に遮断した。
「さあ」と彼は言った。「これでもう少しくつろげるだろう」
彼は頭頂から爪先まで、秋の紅葉のような暖かみのある赤茶色で装っていた。暗いカーテンを背にして立つと、滑らかな天鵞絨の上衣ときらめく絹のタイツの上で丸太の赤い光が踊り、それが彼を炎の男に変え、腰に巻かれた金鱗の帯は流動する炎のように見えた。
長身で風格があり、見事にしなやかで優美な彼は、今や彼女にとって完璧なる男性美の具現化であった。火明りを借りて輝く華麗な炎の装いは、彼を人ならぬ幻想的な存在に見せていた。
彼が身動きすると、炎は輝き爆ぜ、小刻みに震え、金鱗の帯に沿って明滅した。彼は彼女の手を取り東洋の長椅子まで引き寄せて、自分の横に座らせた。火明りが直接当たらぬ範囲だが、それでも彼女の顔が照らされたままでいる位置だった。
意に反しながらも彼女は従った。彼女の直感は、かような炎に照らされた暗闇の中での危うい接近に警鐘を鳴らしていた。
「あ……明かりを用意させます」口ごもりつつそう言ったものの、彼女は立ち上がろうとせず、彼の手を外そうともしなかった。
「このままで」彼は穏やかに答えた。「明かりならば充分、それに私は長居できないのだから」
「え?」言葉にならぬ質問を発した彼女は、鼓動が早まるのを感じた。
「ほんの一時しかない、しかも更に悲しいことに、これが貴女と過ごす最後の宵なのですよ」
チェーザレは、彼女がぎくりとし、その顔に怯えによる痙攣が走り、問い返す声も半ば震えているのに気付いていた。「でも、何故ですの?」
「私は必要性という容赦なき主人に仕える奴隷なのです」と彼は説明した。
「成すべき仕事が私を待っている。明日の夜明けには、ソリニョーラ征圧のために突入する予定になっているのです」
これは重大な情報だった。彼女が作戦の実行を決断するには一刻の猶予もないように思われた。
「そ……それで本当に砦は陥落するのですか?」確信に満ちた口ぶりに興味をそそられて、更に多くを知らねばならぬと切望した彼女はそのように問うた。
彼は自信ありげに微笑んだ。「これをお聞きの上でご判断ください」と言って彼は続けた。「丘の下の南に面した城壁に弱点がある、これについては早い段階でコレッラが探り出していました。以来、我々はその場所をひたすら掘り進めていたのですが、ここ数日、奇妙なことにグイド伯爵方の警戒が著しく緩んでいるのです。ソリニョーラはさながら偽りの希望に惑わされた都のごとし。我々にしてみれば好都合です。我が方の準備は既に完了しています。この夜明けには、坑道を爆破して突破口からの侵入に成功しているでしょう」
「そうしたら、貴方とはもう、二度とお会いできないのですね」何かを言わなければと思い、彼女はそう口にした。次に、もっともらしく見せ掛けるためか、あるいは作為なき女心によるものかは定かでないが、更にこう続けた。「また次の征服地へと行かれてからも、思い起こしてくださる時があるのかしら、哀れなエウフェーミア・ブラッチと、彼女がスポレートで味わう孤独とを」
チェーザレは彼女の方に身を乗り出した。彼は首を前に突き出し、薄暗がりの中で燃えるように輝く両目はパンタシレアの瞳の奥深くを覗き込んでいた。それはあまりにも深く、自分の心中にある真実を見透かされずに済むまいと感じて彼女は恐ろしくなった。それから彼は立ち上がり、数歩先まで移動して全身に炎の輝きを浴びる位置に立つと、天鵞絨の靴に包まれた片足を薪載せ台に置いた。窓の外で砂利の踏みしだかれる音がする。誰かが其処で動いていた。彼女の部下たちだ、間違いない。
チェーザレはもの思いに沈む風情で立っていたが、それを見守る彼女の顔には、もしも彼が目にしていれば当惑するであろう表情が浮かんでいた。彼女の右手は喉と苦しげに波打つ胸との間を焦れたように往復し、その痛ましい運動によって、今、彼女を襲っている息が詰まるような感覚を露呈させていたのだ。
不意に彼はパンタシレアに向き直った。「貴女の許に戻ってこようか、私のエウフェーミア?」静かだが、しかし非常に情熱的な声で彼は尋ねた。「そうして欲しいのかい?」それから彼女に向けて両腕を広げた。
見上げたパンタシレアの視線が彼の視線と交差し、炎の網で相手を包み込んでしまうような熱情がみなぎる荘厳な瞳に見つめられて、彼女の感覚は揺さぶられた。突然、彼女は泣き出した。
「我が君、愛しい方!」彼女はすすり泣いた。
彼女はのろのろと立ち上がると、ふらつきながらその場に立ち尽くしていた。惨めに打ちひしがれた存在は、差し伸べられた腕の庇護を求める衝動に圧倒されながらも、得体の知れない恐怖と自分自身が企てた裏切りへの嫌悪で一杯になって、ひどく怯え切っていた。かつての自分は気高くも輝かしいことをしているように感じていた。それが突然、まさに計画が成就しようという今になって、自分の行為がこの世で最も恥ずべきものに見えてきたのである。
「エウフェーミア、さあ!」彼が呼んだ。
「ああ、駄目、駄目よ」彼女は叫び、震える手で焼けつくような顔を覆った。
彼は進み出ると、彼女に触れた。「エウフェーミア!」その声には抗うことを許さぬ魔力があった。
「私を……私を愛しているとおっしゃって」彼女は哀れにも訴えたが、それを要求するようにうながしたものは、最後に残された自尊心のひと欠片であった――何故ならば、これまでの親交の中で彼が口にした賛辞の中に、愛という言葉は一度も含まれていなかったのだ。
彼は穏やかに笑った。「その砲撃をもってすれば、一介の道化にすら要塞を落とせてしまう」そして言った。「自発的な降伏をお薦めします」
チェーザレは彼女の身体を両腕で包み、パンタシレアは彼の胸で本意と不本意、喜びと恐れの半ばする思いですすり泣き始めた。彼女は押しつぶされそうなほどきつく抱き寄せられ、彼の唇が彼女の唇を焦がした。彼女の嗚咽はふさがれた。ほんの少し前、彼女の目には彼が火によって作られた何かに見えていたが、今の彼女の五感には彼が生ける炎のように感じられた――それは彼女の血管と神経を駆けめぐって全身を焼き尽くし、その跡に恍惚の苦悶を置き残す火であった。
かようにして二人は抱き合い、踊る火明りが壁と天井に彼らを一つの巨大な影として描き出した。
それから彼は自分の首に巻きついて二人を結び合わせていた腕をそっと外し、彼女を自分からそっと遠ざけた。
「では、これでお別れです」と彼は言った。「我が魂は貴女の許に。我が肉体はいずこかの地に」
その言葉で庭に待機している同志たちを思い出し、彼女の心中に恐怖がどっと押し寄せた。パンタシレアは彼の胸にしがみついた。「駄目、駄目よ!」かすれた声で叫ぶ彼女の目は恐怖で見開かれていた。
「一体、どうしたのです?」微笑みながら問い返され、彼女は陶酔から醒めた。
「公爵様」息をあえがせつつも、彼女は可能な限り自制を保とうとした。「ああ、まだ駄目なのです!」
今や彼女は狂乱していた。支離滅裂であろうとかまわなかった。唯一の目的は、彼を引き留めること――ここに彼を引き留めることなのだ。彼を連れて行かせてはならない。同志たちを解散させなければ。彼に話さなければ。だが、何と言えばいいのか。それでも告白しなければならないのだ。彼に警告しなければ、そうすれば彼は自分の身を護れるかもしれない。千々に乱れた心で彼女は懸命に考えた。
「次には何時お会いできるかもわからないのよ。夜が明ければ貴方は旅立ってしまう。チェーザレ、どうかあと一時間……ほんの一時間、私のために」
毛皮のあしらわれた彼の上衣の縁をきつく握ったまま、彼女は椅子に身をゆだねた。「ここに、少しの間、私の横にお座りになっていてください。少し、お話を――貴方がお帰りになる前に、お話ししておかなければならないことがあるのです」
彼は抗うことなく彼女の隣に腰掛けた。その左腕はパンタシレアの身体に回され、再び彼女を引き寄せた。「さあ、話してごらん、可愛い人」彼はささやいた。「それとも、そうしたいなら黙っていてもいい。私がここにいるのが貴女の望みというならば、それだけで充分。ここに留まろう、ソリニョーラは明日も征服されぬままだ」
だが再び彼の抱擁に身をゆだねると、彼女の勇気はくじけてしまった。次第に力は薄れ、あれほど懸命に伝えようとしていたことを話すための言葉は失われた。彼の胸に身を預けたパンタシレアは、甘い気だるさに囚われていた。
時は飛ぶように過ぎた。丸太がシューシューと音を立て、火明りは次第に薄れていった。炎は小さく、消えかかり、堆積した白い灰の下で血のように赤い光に包まれた木材は限られた空間だけを照らし、恋人たちの周囲には黒い影が残された。
長い間を置いて後、溜息と共に若き公爵は静かに立ち上がると、乏しい光に照らされた場所に移動した。
「時の過ぎるのは早い――これ以上は」と彼は言った。
影の中から彼の溜息に応えるように溜息が漏れ、続いて素早く息を吸い込む音がした。「まだ置いていかないで」彼女は言った。「あと、ほんの少し……もう少しだけ、私と」
彼は身を屈めて火掻棒を取り上げ、燻る火をかき立てると、その中心に未だ燃え残っていた数本の丸太を押し込んだ。炎は再び燃え広がり、其処で縮こまっている彼女の姿を見分けられるようになった。掌に顎を乗せている彼女の顔は、闇の中で幽霊のように仄白く光っていた。
「私を愛しているの?」彼女は叫んだ。「愛しているとおっしゃって、チェーザレ。まだその言葉をお口になさっていないわ」
「まだ言葉などが必要なのですか?」彼はそう尋ね、その声音の心地よい響きが充分な答だと彼女は思った。
彼女は両手で顔を覆い泣き崩れた。「ああ、私は卑劣よ!卑劣なの!」
「何を言っているのです、可愛い人?」
「もう、お話ししなければ」彼女は懸命に自制しながら話し始めた。「もしもお耳を澄ませていれば、少し前に、このすぐ外で足音がするのにお気付きになっていたかもしれません。あの庭には貴方を狙う刺客がいるのです。私の企みでここに呼んだ者たちが」
彼は微動だにせず彼女を見下ろし続け、そしてパンタシレアは火明りの中で彼が微笑むのを見た。この時、彼女の頭に浮かんだ考えは、彼の信頼が大き過ぎるあまりに、今の発言を信じてもらえなかった――単なる冗談と受け取られてしまったのだろう、というものだった。
「本当なのです」そう叫ぶ彼女の両手は、わなわなと震えていた。「私は貴方を罠に誘い込む囮役として送り込まれたのです。貴方を人質にしてソリニョーラの安全を図るために」
彼はわずかに頭を振ったように見えたが、依然として微笑みを浮かべていた。
「ならば何故、それを私に話すのです?」
「何故?何故ですって?」蒼白な顔で、大きく目を見開きながら彼女は叫んだ。「おわかりになりませんの?貴方を愛しているからよ、チェーザレ、だから私には、もうこれ以上、自分の役目を果たすことができないのです」
彼の態度に変化はなく、ただ、その微笑がより甘く、より含みの多いものになっただけであった。嫌悪や怒り、あるいは憎しみを向けられることは覚悟していた。だが、この穏やかで甘い微笑みのように恐ろしいものは完全に想定外だった。その微笑みを見た彼女は幻妖な恐怖に駆られて後ずさった。たとえ彼が裏切りの報復として彼女を《あや》めるべく|懐剣を取り出すのを見たとしても、決して後ろに退くことはなかったであろうが。吐き気と眩暈で彼女は一言も発することなく、その場に横たわった。
すると依然として微笑んだまま、チェーザレは炉上の棚から細蝋燭を取り、それを炎の中に突き出した。
「火を灯さないで!」彼女は悲しげに訴えたが、彼がそれを意に介さぬのを見て緋色の顔を両手で覆った。
その細蝋燭の炎を用いて、彼は卓上に置かれた燭台の枝に挿さった全ての蝋燭に火をつけていった。豊かな光の中で、彼はしばし無言で彼女を探るように見つめた――依然として微笑みを浮かべながら。それから外套を取り上げて身にまとった。それ以上は一言も口にせず、彼は窓に向かって歩みだした。
彼が立ち去ろうとしているのは明白だった。叱責も非難もないまま去ろうとしているのだ。その侮蔑は彼女を無残なまでに打ち据えた。
「何もおっしゃることはないのですか?」彼女は嘆きの声を上げた。
「何も」彼は足を止めて答えたが、その片手は既にカーテンにかけていた。
痛みという拍車に駆り立てられ、彼の軽蔑という耐え難い鞭に打ち据えられ、突然、彼女の中に狂わんばかりの反発が引き起こされた。
「部下たちは、まだ其処にいるのよ」そう指摘した彼女の口調には荒々しい威嚇が含まれていた。
チェーザレの返答は彼女の理性を粉々に打ち砕くように感じられた。「そう、私の部下たちもね、パンタシレア・デッリ・スペランゾーニ」
うずくまりながら、パンタシレアは彼をじっと凝視した。つい先ほどまで羞恥と怒りで紅潮していた彼女の貌には、死人のような青白さがゆっくりと広がっていった。「知っていたの?」彼女はつぶやくように言った。
「初めて会った時から」彼は答えた。
「それなら……それならば……何故……?」震える声で途切れ途切れに投げられた言葉の最後は彼の洞察にゆだねられた。
ここに至って彼は声を高め、それは打ち鳴らされた青銅のように響いた。
「征服欲」凄まじい微笑を浮かべつつ彼は答えた。「既に十を超える国々を征服した私が、グイド伯の娘ごときを征服できぬとでも?この戦いにおいて、私はそなたと、そなたが用いる女の手管を打ち負かすことを目標に定めた。そして、そなたの告白、それがなされた時をもって、私が他の国々において征服者であるのと同様に、そなたの魂の征服者となったことを認めると定めていたのだ」
それから彼は常と変わらぬ落ち着いた口調に戻った。「それだけではない」と彼は続けた。「ソリニョーラの者たちは、そなたに厚い信頼を寄せるがゆえに警戒を緩めて我々が坑道を掘り進める猶予を与えることになった。この目的を果たすためにも、私には時間を稼ぐ必要があったのだ」
吊り金具のぶつかり合う音を響かせながら、彼はカーテンを引き開けた。
彼女は懸命に立ち上がろうとし、片手を額に、もう片方の手を心臓に押し当てた。
「そして私は?」彼女は押し殺した声で尋ねた。「私には、どのような末路が用意されているのです?」
彼は金色の光の中にいる彼女を見つめた。「マドンナ」彼は言った。「貴女には、このひと時の思い出を残そう」
彼は窓付扉の掛け金を外し、大きく開け放した。わずかの間、彼はその場で耳を澄ましていたが、銀の呼び子を取り出すと、それを鋭く吹き鳴らした。
たちまち庭園は騒然となり、待ち伏せていた男たちが機敏に動き出した。テラスの向こう側から、そのうちのひとりが彼に駆け寄ってきた。
「アメーデオ」公爵は告げた。「ここに潜んでいる賊どもを残らず捕縛せよ」
背後でうずくまっている白い人影に最後の一瞥をくれると、彼は闇の中に踏み出し、悠然とした足取りで去っていった。
その夜明け、坑道は爆破され、其処から急襲を受けたソリニョーラは陥落し、そして征服者チェーザレはスペランゾーニの城塞を我がものとしたのであった。
終
The Lust of Conquest "Lippincott’s" Oct, 1910. より
ここから先は
英国の作家ラファエル・サバチニによるチェーザレ・ボルジアを狂言回しにした短篇集"The Justice of the Duke"(1912…
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
