
【剣と拳】・前編
宵色の空の下、水晶の荒野にて。濁った空気を打ち払うように、二つの斥力が衝突していた。それらの力場の中心に、二人の男が立っている。一人は全身甲冑の騎士で、もう一人は屈強な大男だった。
「ニグレオスよ。我が全力、今こそぶつけよう」
大男が言った。全身には紅蓮の炎が巡り、双眸はそれよりなお燃え盛っていた。
ニグレオス……そう呼ばれた騎士が構えた。騎士の動きに同調するように、彼の背後の巨大な大剣が浮き上がる。一見すれば精巧なオブジェのようだが、僅か動くだけで空を裂くほどの切れ味を誇る。その大剣は、拳士の放つそれと同等の存在感を放っていた。
数秒の沈黙を経て、拳士が地を蹴った。大きく飛翔すると、空気を蹴ったかのように空中で急転換し、ニグレオス目掛けて急降下する。炎を纏いながら迫ってくるそれは、さながら迫りくる隕石のようである。
一方、ニグレオスの大剣が迎え撃つような体制で静止する。拳士の接近に対し、カウンターで切り捨てる構えである。時間が鈍化する。拳士の致命の拳がゆっくりと落ちてくる。喰らえば死。一方で、ニグレオスの大剣もまた致命の剣であった。
剣と拳。二つの必殺が衝突しようとしていた。決闘の極限状態の中、必死に拳士を迎え撃とうとするニグレオスの脳裏に、この決闘に至った経緯がリフレインした。
1
見渡す限りの光景が全て水晶で覆われた、特異な洞窟。歩く度に、地面や壁の結晶が、自分の姿を反射する。まるでナニカの井の中にいて、すべての行動が常に監視されているような、そんな錯覚さえ覚えさせるような不気味な場所を、騎士ニグレオスは一人歩いていた。
ニグレオス=グレイウォルムは、帝国メンセマトに仕える黒騎士である。黒騎士とはメンセマトにおける上級騎士の称号で、唯一他世界の情報を知り、魔札使いになることを認められた地位である。そんな彼が歩いているという事は、この水晶の魔窟もまた、メンセマトと異なる別世界の一つである。
世界のすべてが水晶で構成された世界。クォーツアイス。文明の痕跡さえ残らないこの地は、禁界域と呼ばれる危険な世界の一つであった。

ニグレオスの姿を映す結晶が、一瞬不気味に輝く。映るニグレオスの全身甲冑の姿が歪み、怪物のような見た目に変わっていく。これは比喩ではない。一瞬の後、水晶の中からまさにその怪物が姿を現したのだ!
「キシャァァァーッ!!」
ニグレオスは咄嗟に構え、魔札を唱える。怪物の凶暴な爪が迫っている。ニグレオスは咄嗟に怪物を蹴り、反動で数歩分飛びのいた。そして、二者の間に黒い影が揺らぎ、やがてそれが騎士の姿を象っていく。

「行け、我が騎士よ!」
ニグレオスの号令と共に、現れた騎士が怪物へと立ち向かう。怪物の爪と、騎士の剣が数度に渡り衝突する。やがて、騎士が爪の攻撃を潜り、その直剣で怪物の腹部を貫いた。

凄まじい絶叫と共に、怪物は息絶えた。消滅の間際、怪物の姿が凝縮され、1枚の魔札となった。そして間もなく、その魔札も消滅した。その様を見届けると、ニグレオスは召喚した騎士を自身の札に戻した。
このような襲撃は、クォークアイスに着いてから一度や二度ではない。突如として魔札生物が現れる。それが禁界域たるゆえんである。禁界域では、常に魔札使いは決闘状態を維持する事になる。魔札が尽きたとき、或いは自分を守る結界障壁が破られたとき、その魔札使いの命は終わることになるだろう。
ニグレオスは、クォーツアイスが禁界域と知った上で臨んでいた。この危険な水晶の世界は、以前からメンセマトで知られていた数少ない世界の一つだったのだ。危険性を知りつつ、慄く心を忠義で押しとどめ、ニグレオスは歩き続けた。
洞窟のカーブに差し掛かった時。ニグレオスは、結晶の壁にもたれる、人型を模したような結晶のオブジェを目撃した。ニグレオスは兜の中で目を細める。彼は知っているのだ。それが単なるオブジェではなく、元々人だったものが、この洞窟に取り込まれた成れの果てであることを。
五年前、それは何の前触れもなく発生した。メンセマトの帝都の広間に、突如クォークアイスに通じる泡が出現したのだ。泡の中から、まるで広間を浸食するように水晶が伸び、その中から邪悪な怪物の影が数体出現した。これらの怪物により、広間にいた都民、騎士、のべ50人が犠牲となり……すなわち、結晶化した。泡が閉じ、水晶が枯れるように崩れ塵になるまで、僅か数分の間の出来事であった。
当時、ニグレオスは黒騎士の階級ではなかった。他世界のことなど何も知らぬまま、当時事件のあった広間で、家族と……彼の妻と、子供たちと過ごしていた。そうして事件に巻き込まれ、生き残ったのはニグレオスだけだった。
彼は今でも、当時襲われた人々の姿を鮮明に覚えていた。水晶から現れた怪物は、凶悪な爪や牙を振るうまでもなく、ただ触れるだけで、その者を結晶に変えてしまった。すぐに駆け付けた騎士団の者たちも、怪物に応戦しようと剣を振るうも、その武器が怪物に触れたことで都民たちと同じ末路を遂げた。この結晶の怪物には、常人では触れることさえ敵わないのだ。
対して、ニグレオスはどうか。先ほど怪物を蹴った脚は、結晶化の気配は微塵もない。全身甲冑にはそうした防御の機能は存在しない。であれば、魔札使いとして決闘を重ねた彼の身体が、結晶化に対抗しているのだろうか? あの日、ただの騎士団副団長だった頃のニグレオス=グレイウォルムから、かけ離れた存在になってしまったのだろうか? 時折ニグレオスは自身の変化に戸惑いを覚えていたが、この世界に来てからは、特にそれを恐ろしく感じた。
家族を失ってから、黒騎士となってから、ニグレオスを待っていたのは別世界の恐怖であった。秩序だった世界も数多く存在するものの、すべてがメンセマトの常識の埒外で、今まで自分が立っていた場所が、極めて刹那的で危うい均衡によって辛うじて保たれていたことが、ニグレオスの心を苛んだ。そして、何よりいま、ニグレオスはその埒外の側に立っているのだ。
ニグレオスは眼前のオブジェをじっと見つめる。もしこれが自分の妻子で、なんらかの力で元に戻せたとする。そのとき自分は、かつてと同じように、大事な人たちと接することができるだろうか? 帝国への忠義が揺らいだことは微塵もない。帝国で共に過ごした同胞たちへの想いもまた変わることはない。それでも、今の自分は黒騎士で、魔札使いなのだ。答えのない問いがニグレオスの頭を巡り続けて、そして。
「「「キシャァーッ!!」」」
突如、後方から放たれた絶叫によってニグレオスは我に返った。振り向くと、そこには三体の怪物。不覚。既に怪物どもはニグレオスに迫ってきている。この距離では、魔札を唱えても即座に対応できない。また、背面は壁とオブジェ、先ほどのように距離を取ることも困難であった。
(不味い、どうする……!?)
咄嗟にニグレオスは防御姿勢を取る。結界障壁の消耗具合からして、1、2体の攻撃は耐えることができる。3体目はどうする? 詰み。最悪の想像が浮かぶ。そんな表情を兜越しに読み取ったのか、それとも野生故の邪悪な本能か、怪物が笑みを浮かべながら、大爪を振り下ろそうとし――
「ハァァ――ッ!」
怪物たちの更に背面から放たれた炎が、怪物たちをまとめて焼き払った。怪物たちは絶叫する間もなく、その場で崩れ落ち、消滅した。ニグレオスは思わず後ずさろうとし、右手が人型オブジェに触れる。コツ、コツ。水晶の中から歩いてくる大男の姿を、ニグレオスは知っていた。
「久しぶりだな、ニグレオス。ここで会えるとは思わなかった」
「ヴァン・リユウ……!」
ニグレオスが男の名を呼ぶ。リユウ。そう呼ばれた男がニヤリと笑った。

2
不気味な水晶の魔窟を、ニグレオスはリユウと並んで進んでいた。不思議なことに、リユウと会ってからというもの、魔物の奇襲はピタリと止んでいる。襲う相手の力量を測っているとすれば、なるほど利口な敵だ、とニグレオスは思った。何しろ、このヴァン・リユウという男は規格外の魔札使いなのだ。
リユウが一歩進む度、彼から放たれる存在の圧のようなものが、結晶を通して洞窟全体に伝播しているような感覚をニグレオスは感じていた。おそらく、錯覚ではないのだろう。時折、リユウの姿を映す結晶が、まるで重量過多の荷物を載せた木箱が耐えきれずぺしゃんと壊れるように、破裂する姿を見た。そして恐らく、リユウはそれを意図して行っていないとニグレオスは推測していた。
「……今回は、戦いを挑んでは来ないのだな」
耐えきれず、ニグレオスが口火を切った。このまま無言で歩いていたら、結晶のように自分も破裂してしまうと感じていたのだ。すると、リユウはばれたかとばかりに頭を掻き、言った。
「再戦を挑みたいのは事実だ。だが、今日のおれの目的はおまえではない。もしおまえから挑まれれば喜んで受けて立つ腹積もりだったが……分かりやすすぎたか?」
なるほど、やはり規格外の男だ。ニグレオスは思った。リユウが今発している闘気は、ニグレオスへの敵愾心を抑えている結果なのだ。その結果生じる現象の規模が大きすぎて、それが自分に向けられた意思だったなどとは、ニグレオスは微塵も思わなかった。
禁界域では、魔札使いは常に決闘が行われている状態となる。この時、他の魔札使いがいれば、決闘の同意なく、いつでもその場で戦いを行うことができるのだ。更に、その気になれば、自分に有利な状況を敷いてから奇襲を仕掛けることも可能となる。
ニグレオスは、リユウが奇襲を行うような魔札使いだとは考えなかった。が、逆にニグレオス側が仕掛けてくるのではという期待を持たせては、任務に支障が出るのでは、とも考えた。少なくとも、この闘気を抑えてもらわねば、気が気でなかった。
「我も貴様に構っている暇はない。聖杯探索、それが我がここに来た目的だ」
ニグレオスは目的を打ち明けた。リユウは再戦の意思がないことを聞きがっかりした様子だったが、すぐに言葉を返した。
「聖杯とはなんだ?」
「メンセマトに古くから伝わる伝承だ。人々を惑わす結晶の魔窟、その最奥に聖なるアーティファクトがあるという。実際は強力な魔札か、その湧きスポットだと考えているが……その事実を確かめ、可能であれば回収するのが我の任務だ」
湧きスポットとは、魔札が出土する場所を指す俗的な通称だ。魔札とは、なにも新聞紙や書物などのように、誰かが記したり刷ったりしてできるものではない。むしろ鉱石の類に近いだろう。太古の神々や英雄の時代の残滓、当時の歴史を色濃く残す遺跡や遺物の中から、不定期に出現するのだ。世界によってこの現象の解釈や名称は異なるが、多くの渡りの魔札使いの間ではこの湧きスポットの俗称が広く浸透していた。
「おれがそれを聞いて、魔札を欲しがるとは思わなかったのか?」
ニグレオスの話を聞き、リユウが苦笑した。
「貴様はむしろ、強力な魔札を使う者と対峙する方が好みだと思うが」
「なるほど。確かにその通りだ」
またもリユウが笑った。素直な男だ。ニグレオスはそう思った。
「ならば、次はおれの目的を話そう」
今度はリユウが話し始めた。
「クォークアイスには、数百年を生きる魔物の女王が潜んでいると聞いた。やつが従える結晶の魔物には一切の攻撃が通じない……らしい。もし噂が本当であれば、魔物とは魔札によってつくられた生物で、その主人である女王は魔札使いだ。おれは戦いたいと考え、来た。」
「どこで聞いたのだ? そのような話」
「ガッデンヒルという世界の酒場だ。行ったことはないか?」
その名にニグレオスは聞き覚えがあった。地獄のような炎熱の世界で、鬼や溶岩族といった熱に強い種族の文明都市が存在するらしい。治安は悪いが、逆に互いの素性を気にされないので、アウトローの魔札使いがよく出入りしているとも。同僚の黒騎士の一人が、多くの他の世界と共に、ガッデンヒルの説明をしてくれたのを覚えていた。
「結晶の魔物が魔札生物なのは事実だ。奴らが通常の武器を無効化する様を実際に見た事がある」
ニグレオスの脳裏に、5年前の苦い記憶が蘇る。魔物の討伐に大砲まで持ち出されたが、砲撃を受けても魔物たちの結晶の身体は一片たりとも傷つきはしなかったのだ。
「それを聞いて安心した。ここに来るまでかなり大変だったのだ」
リユウが高揚に満ちた表情を見せる。いつの間にか、先ほどまで発していた闘気がなりを潜めていることに、ニグレオスは気づいた。女王とやらに矛先が向いたのだろうか。
「……おまえの話を合わせると」
唐突にリユウが切り出した。
「この洞窟には数百年生きる女王がいる。そして、そいつが聖杯とやらを守っている……かもしれん。なるほど、これは倒しがいがありそうだな」
「…………」
ニグレオスは応えなかった。魔物の女王の存在に、脅威を感じたからだ。ニグレオスは忠義の騎士である。有言実行を体現し、数々の異世界任務に赴いてきた。だが、彼は口にこそ出さないが、常に他世界の危機に怯えていた。逃げ出したくなる自分を堪え、立ち向かっていった。しかし、何度挑もうと、恐怖が薄れることはなかったのだ。
この先に、あるいは5年前の惨劇を引き起こした元凶がいる。かつての自分なら、自暴自棄になって果敢に挑んだかもしれない。だが、多くの他世界を知り、様々な恐怖を知った今、果たして己は今回も戦えるだろうか。竦む脚に活を入れ、リユウに合わせて歩く。
唐突に、リユウが足を止めた。ニグレオスもまた同様にした。その理由は明白だった。彼らの眼前、洞窟を進んだ先の広間に、赤く輝く大水晶が現れたのだ。その水晶の中には、まるで伝承に聞く人魚のように、ゆらゆらと影が泳いでいた。そして、赤い結晶の先、広間を抜けた先に細い穴があり、その中からは超自然の光が漏れ続けていた……湧きスポットである。
「おれの言った通りだったか」
リユウが笑った。ニグレオスは無言で身構えた。やがて、赤い大水晶の影が縦に大きく伸びると、それは躍り出るように水晶から出現した。

3
眼前の影は、やがて人型の女性体を象り始めた。その姿は歪つで、常に揺らぎ、変化し続けている。あくまでシルエットを模倣しているだけなのだろう。その証拠に、顔に当たる部分には耳と鼻と口がなく、かろうじて目に当たる部分が妖しく輝いていた。
「なるほど。さしずめ影の女王と言ったところか」
リユウが前に進み出た。
「おれはおまえと戦いに来た。この決闘受けて貰うぞ」
「―――」
影の女王、そう呼ばれた存在が音を発した。明らかに、口以外の器官から放たれたその音は、辛うじて聞き取れるくらいの高音で、言語体系の埒外だった。ただの音の羅列である。そのため、リユウも、ニグレオスも、女王が発する音の意味は分からなかった。だが、すぐに女王が魔札を展開すると、戦いの意思があることは両者ともすぐに理解した。
ガゴンッ! その時、ニグレオス達の背後にあった道が壁に閉ざされた。突如水晶が発生し、道を塞いだのだ。振り返ると、影の女王はゆったりとした動作で手を動かし、二人の魔札使いに手招きした。
「やる気は十分のようだな」
リユウは笑みを浮かべた。
「ニグレオス。どうやら奴は、個別に相手をするような気はないらしい。どうする?」
「決まっている」
ニグレオスもまた、剣を構え、魔札を展開した。
「クォーツアイスに挑んだ黒騎士は過去にもいた。そしてほとんどが死んだ。奴がその元凶なのだとしたら、我は弔いのため戦わねばならない」
「では共闘といこうか」
リユウは頷き、魔札を展開した。ニグレオスは少し意外に思った。この男は一対一の試合形式に拘るかと思っていたのだ。しかし、この男が仲間であるならば心強い。ニグレオスは内心、この状況に感謝していた。
影の女王対、騎士・拳士の即席タッグ。影の女王は言葉のない音を放つ。それに合わせ、二人の魔札使いは声を合わせ、開戦の宣言をした。
「「衝突!」」
合図と同時にそれは起こった。女王とリユウ達の間の地面が突如隆起し始めたのだ。割れ目から九つの結晶が湧き出ると、それらは何らかの魔力によってゆらりと浮かび上がり、静止した。
「これは……!」
「禁界域ならでは、か。影の女王は、この決闘の前から複数の魔札を使用していたのだ。見ろ」
リユウは女王の手札を指さした。魔札の決闘では、決闘開始時に引く枚数は5枚と決まっている。ところが、女王の手札は2枚だけであった。事前準備をしていたにしても、明らかに減り過ぎている。ニグレオスはそう考えた。
ニグレオスはこの時、道中で襲ってきた魔物たちの様子を思い返していた。魔物どもは、邪悪な水晶の中から現出していた。それらの水晶と、眼前に浮かぶ結晶がもし同一のものであるとしたら。もしそれらの魔物が、あの魔女の手札から召喚されていたとしたら――
「洞窟の道中に襲ってきた魔物は魔女の仕業だった、ということか」
ニグレオスが言い当てた。はじめから、己と奴は決闘していたも同然なのだ。
「この決闘、先に行かせてもらうぞ。リユウ」
「うむ。任せた」
黒騎士が一歩前に出て、魔札を1枚引く。そして1枚の魔札を使用した。結晶の地面に十字の斬り痕が刻まれ、中から一体の黒騎士が現れた。自身の甲冑の色と真逆の色、白く仄かに輝く剣を携えた剣士であった。

「行け、対魔の黒騎士よ! 魔物を撃破せよ!」
ニグレオスの号令と共に、騎士が水晶目掛けて斬りかかる。対象の水晶は、他の八つのそれと異なり、結晶中に淀んだ黒の光が明滅していたのだ。ニグレオスはこれを、魔物が潜む証だと読み取ったのだ。召喚された黒騎士の退魔の剣、その切っ先が水晶に届く。
「獲った!」

SLAAAASH! 輝剣は見事に結晶を切断。中にいた魔物……邪晶獣はうめき声をあげる間もなく絶命した。浮遊結晶群を挟んだ先、邪晶獣の使役者であった影の女王の姿が、まるで一瞬苛立ったかのように大きく揺らいだ。
「まだだ。これからだぞ、魔物よ」
ニグレオスが更なる魔札を使用した。黒騎士の掲げる剣が輝きを増すと、その後方に延びた影の中から、新たな黒騎士が出現した。騎乗した黒騎士だ! NEEEEEEEEEEEEIGH!

「貴様を守れる生物はいなくなった!」
騎馬が跳躍し、浮遊水晶群を飛び越えようとする。騎乗兵が長剣を構え、女王本体に狙いを定める。洞窟内とはいえ魔札生物の動きは正確だ。天井すれすれまでに高度を留め、落下と同時に剣撃を喰らわせられる、その筈であった。
だが、剣は女王に届かなかった。水晶群が自律的に魔女の手前まで後退し、黒騎士の一撃を受け止めたのだ。
「ぬぅ……!あの水晶をすべて壊さぬ限り、女王には傷ひとつ与えられないか」
ニグレオスは状況を理解し、黒騎士を退かせた。
「最初の魔物への一撃で一つ、今の一撃で二つ。残る七つの水晶が未だ女王の身を守る、か」
リユウは腕組みの姿勢で分析していた。
「1枚の魔札がこうも決闘の仕組みを変えられるものか? あまりに固すぎる」
「我も同じことを考えていた」
ニグレオスが同調した。
「これほどの能力、アヴァター以外に考えられん。あの女王、決闘開始時点で、もしくはこの洞窟自体に常にアヴァターを呼び続けているのやもしれぬ」
アヴァターの魔札。それは魔札使いにとっての切り札である。手札にはなく、条件さえ整えばいつでも召喚できる魔札。いずれも使用者の性質を反映した強力な力を持つ代わり、破壊されれば即敗北が決定するリスクも抱えている。
(洞窟を進む中で感じていた我を凝視するような邪悪な気配……その根源があの魔物の化身だったのやもしれぬ。さながら、魔窟は影の女王めの腹の中だったという事か)
ニグレオスの戦慄をよそに、影の女王は自身の手番を推し進めた。人ならざる音域の音を発し、魔札を1枚引く。滑らかで、しかしあまりに機械的にすぎる不気味な動作である。彼女が1枚の魔札を地面に放つと、それは妖しげな輝きを放ち、効力を発揮しはじめた……!
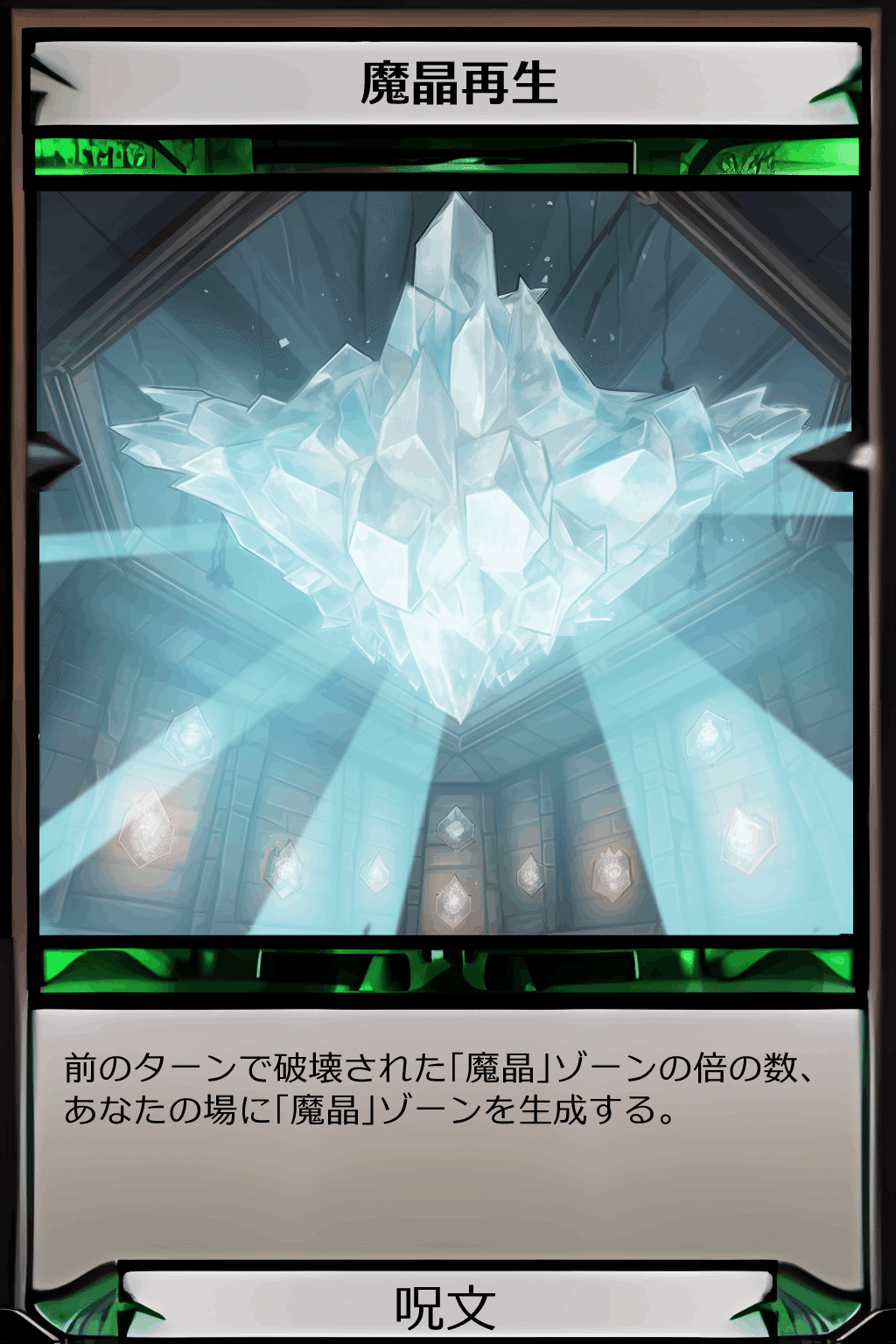
天井の水晶から眩い光線が地面に放たれる。それはリユウ達を狙ったものではなく、浮遊水晶群の付近へと命中した。最初に生じたときと同様に四つの水晶が浮き出て、浮遊群へと加わった。
更に、女王がもう1枚の魔札を唱えた。優雅な所作であった。紫色の水晶が一瞬誕生したかと思うと、すぐに付近の水晶群の色と同一になり、浮遊群へと加わった。これで計11個の水晶……!
「これではキリがないな……!」
ニグレオスが吐き捨てるように言った。
「……くるぞ」
リユウが言ったと同時、影の女王のシルエットは三つに分割され、水晶群の中へと飛び込んでいった。シュン、シュン。小さく分かれた影は浮遊する水晶の中を高速で飛び交う。非常に俊敏で、影らが潜む水晶を把握した瞬間には、既に次の水晶へと移っている。捉えるのは困難であった。何巡目かの移動の後……影はいきなり飛び掛かってきた! 対象はリユウだ!
リユウは攻撃方向に対し、迎え撃つ形で拳を構えていた。ニグレオスは、かろうじてその姿を横から目撃していた。常人には捉えきれない影の魔物の移動を、まるではなから把握していたかのような動きだ。そして、リユウが構えていたのは当然ただの拳ではない。その拳には、既に魔札の輝きが宿っていた……!

「ハッ!」
拳の反撃! 魔物は強烈なダメージにより破裂し、水晶ごと砕け散る……その筈だった。だが、その場で拳を受けたのは、攻撃してきた魔物とは別の魔札生物であった。

「ニィィィ……イイ…………」
水晶そのものに擬態していた魔物は、おぞましいほどに濁った断末魔をあげて砕け散った。一方、拳を躱した魔物はすぐさま浮遊水晶群の結晶内に飛び込み、やがて浮遊水晶群を挟んでリユウ達の反対側に飛び出、再び影の女王の姿を象った。
「あの擬人状態は、魔物どもで構成された仮初の身体だったというのか」
ニグレオスは一連の攻防に驚愕した。仮にリユウが今の攻撃で傷を負っていれば、より混乱していただろう。だが、隣の大男は未だ健在で、その眼差しは戦況を見極める軍師のように険しかった。その様が、ニグレオスをすぐに冷静にさせた。
「今の攻撃で、女王は最後の手札を使い切ったな」
ニグレオスは女王の手に握られている魔札が存在しない事に気づいていた。これまでの水晶群を作るのに2枚、そして先ほどの攻撃で1枚消費。計3枚の手札を使い切り、この手番中女王にできることはない。
「おれの反撃に対し囮を使って攻撃者の正体を隠し通した。最後に使った1枚、よほど重要な魔札と見た」
「どうにか見破る手段はないか? 倒せれば越したことはないが」
「やってみよう」
リユウが言った。彼が魔札を引くと、一陣の風が起こり、浮遊水晶群が恐れ震えるように揺れた。
「あれらの水晶すべて……壊してみようか!」
リユウは魔札を唱えると同時、渾身の一撃で大地を砕いた! CLAAAAAAAAASH!! 洞窟の地面が抜け、そこには二層目の地面が待っていた。ニグレオスとリユウはさっと着地したが、浮遊水晶群はまるで支柱を失ったかのように急速落下し、そのすべてが砕け散った。最後に、影の女王が不安定な身体を揺らがせながら、ゆっくりと第二の地面に降下した。

「10個あった水晶群がすべて破壊された……!」
ニグレオスは感嘆の声と共にリユウを見た。
「さすがに強力な魔札でな。おれの手番になるまで使うことができなかった」
「十分だ。今の一撃で奴の策略は一気に潰えたのだからな」
「それは……違うようだぞ」
拳士は険しい表情で言った。彼の双眸の見据える先、影の女王の足元に、まるで新芽が生えるように、結晶の蔓が伸びはじめたのだ。
「どういうことだ? 奴の手札は0枚のはず」
「どうやら、今の一撃はまずかったらしい。倒してはいけない魔物を倒したようだ」

それは重力拳で破壊された魔物から生み出された芽であった。生成された水晶蔓は、自分が鉱物であることを忘れたかのように膨張し、弾けた。そして中から生み出された水晶が、新たな浮遊水晶群となって影の女王の前に展開されたのだ。その数……20!
「流石に重力拳をもう一度撃つ手段は……ない。手番終了だ」
リユウが悔しげに宣言した。ニグレオスは驚愕した。影の女王の、反撃を想定した一手に恐怖を抱いたのだ。今までニグレオスは、あの水晶は単に魔物を潜ませ、盾にするためのものだと考えていた。だが、たった今の攻防で、魔物は水晶に罠を潜ませ、リユウの強力な攻撃を防いだのだ。なんという邪智。
一対二の決闘の場合、一人側のプレイヤーが再び手番を得る。よって、次は影の女王の手番である。影の魔物は、すべてが掌の上で踊っていたかのように、愉快げに身体を揺らしながら新たな魔札を引いた。
女王の手が輝く。手札1枚の魔札、その強大な力に20の浮遊水晶群が呼応する。水晶の中に陰りが生まれ、魔札の力を浴びるごとに成長し、新たな魔物が生まれた……すべての水晶から! 計20体の魔物の攻撃を浴びれば、いかなる魔札使いであろうとたちまちに結界障壁は砕け、敗北してしまうだろう。

水晶群の中の魔物からの視線を、ニグレオスは感じた。その邪視は、己とリユウと、どちらを喰らおうかと迷っているようであった。さながら、馳走を前に何から手を付けようかと迷う稚児のようである。当然、選ばれた者の運命は、死……ニグレオスは自身の手札を見る。今の手札に、攻撃を耐えられる手段はない……! そして、その様を見て好機と見たのか、魔物たちは己に向かって、まさに今、飛び出さんとしていた!
(…………っ!)
ニグレオスの視界が、突然5年前の記憶と重なった。あの日、眼前に迫る魔物たちを前に、騎士は凍り付いたように何もできなかった。力を得たと思っていた今もそうなのか。あの日は奇跡的に免れた危機が、過去が、死神となって、5年越しに命を刈り取りにきたようであった。……せめて、決闘の中で散れるのが幸いか。人であるうちに、誇りある中で散れるのならば。ニグレオスが、甲冑の中の目を閉じようとした、まさにその時。
「この瞬間、おれは魔札を唱える」
横から力強い声がした。ニグレオスは急に現実に引き戻された気がした。見やると、そこには未だに勝負を諦めていない、燃える男の双眸があった。このヴァン・リユウという男は、たとえ攻撃対象が自身であっても、必ずこうしただろう。そう思わせる力強さに、ニグレオスは先の己の腑抜けぶりを恥じた。そして魔札の発動を待つと、思いがけず、迸る力はニグレオスへと流れ込んだ。

「引け! ニグレオスよ。おまえならばこの局面、どう乗り越える!」
その声には全幅の信頼と、力強さがあった。ニグレオスは、己でも驚くほどの声量の、鬨の声で応えた。そして、まるで伝承にある魔剣に相対した勇士のように、己の山札から、一枚の魔札を引き抜いた。一陣の風がニグレオスから放たれ、襲い来る魔物たちは、その勢いを削がれ後退する。
「ゆくぞ、リユウ」
「うむ、征こう」
ニグレオスが、今まさに引き当てた魔札を放つ。札から迸った強大な輝きが、彼の場にいる黒騎士の剣に重なる。対魔の剣が青白く輝き、やがてその剣の何倍もの大きさの焔となると、騎士は炎纏う大剣を振り抜いた。一薙ぎから放たれた炎が、すべての魔物を……捉えた!

更に、リユウもまたその場で拳を放った。先ほど唱えた呪文の効果で、攻撃を行えるのだ。空を切った筈の拳だが、凄まじい拳圧そのものが凶器となり、またニグレオスの呪文と重なり合った。風と炎とが合わさった一撃は全魔物を殲滅せしめ、更には浮遊水晶群をも呑み込み、焼き滅ぼした。攻撃の余波が旋回するように魔窟中に広がり、無数の水晶群を砕き続ける。
強大な一撃を受け、よろめく影の女王が立ち上がった。彼女もまた、先の一撃によって膨大なダメージを受けていた。更に、必殺のつもりで放った手勢は全滅している。彼女の不安定な肉体が、まるで怒りに震えるかのように大きくぶれていく。
「貴様の戦術も遂に粉々に砕け散った。次の我が手番で、貴様自身の首も……」
挑発するように、ニグレオスが言いかけたが、その言葉をリユウが遮った。
「この手番中におまえは終わる」
そう言ってリユウは、1枚の魔札を唱えた。対象の魔札生物を滅ぼす必殺の魔札であった。

「馬鹿な!? たった今、奴の魔物はすべて撃破して――」
そこまで言いかけて、ニグレオスにもその答えが分かった。決闘が始まった直後、リユウと交わした会話が脳裏によぎったのだ。
(((これほどの能力、アヴァター以外に考えられん。あの女王、決闘開始時点で、もしくはこの洞窟自体に常にアヴァターを呼び続けているのやもしれぬ……)))
「先ほどの攻撃は、すべての敵を狙ったものだった」
リユウが言った。
「ならば、奴の化身にも攻撃は与えられた筈だ。だが、決闘がこうして続いている以上、アヴァターの破壊には至らなかった。そういうことになる」
リユウが淡々と推理を話し続ける様に、ニグレオスは改めて畏怖を覚えた。めぐるめく戦況の中、この男は常にアヴァターの存在……つまり、自分の勝利に繋がる方法を考え続けていたのだ。生死のかかる決闘の中で、どこまでの勝利への飢えがあれば、そのような思考ができようか。
「はじめは小さな違和感だった。この洞窟の大地を殴った時、僅かな手ごたえを感じたのだ。そして、先ほどの攻撃が洞窟中に響いた様から、一つの答えに辿り着いた」
「なんだと……!? では、奴のアヴァターとは、すなわち……」
「そうだ。この水晶の洞窟が、奴のアヴァターだ」

この会話を、果たして理解したのか。影の女王の姿が怯えるように揺らめく様をみて、ニグレオスも確信した。文字通り、この洞窟は奴の腹の中だったのだ。
「よって、おれは今から、この洞窟を破壊する」
ニグレオスの手が真紅に染まる。血よりも鮮やかな致命の赤。一瞬の貯めとともに、一撃が……放たれた! SMAAAAAAAAAAAAASH!! 水風船に穴を開けたように、今の一撃で穿孔された洞窟が、破裂するように自壊しはじめた。実際には、あまりにも攻撃が強大すぎて、洞窟たるアヴァター全体にまでダメージが行き届いたのだろうか。
水晶片が雪のように舞い、炸裂音と共に洞窟が崩れていく中、ニグレオスは改めて、リユウという魔札使いを認識した。常に勝利のために闘う、恐れを知らぬ強大な拳士。一瞬の静寂。そして、洞窟が完全に……破裂した。
水晶の洞窟だと思われていた世界、クォークアイスは、実際のところは水晶の生える荒野が無辺際に広がる世界だった。今は、砕けた長大な洞窟の名残が、無数の水晶塵となって鈍い輝きを大地に晒している。
影の女王の姿は、跡形もなくなくなっていた。彼女が入っていた赤い水晶もまたなくなっていた。今、荒れ地に立っているのはリユウと、ニグレオスの二人だけだった。そして彼らの眼前に、虹の光彩を放つ超自然の鉱石……すなわち、湧きスポットがあった。
「あれを回収すれば、我の任務は終わる」
ニグレオスが言った。だが、その前を遮る者がいた。ヴァン・リユウであった。
「もしも」
リユウが言った。
「おれもあれがほしいと言えば、おまえは戦ってくれるか?」
一瞬、それまで魔物に、影の女王に向けられていた敵意を、ニグレオスは感じた。共に戦っていたことでしばし忘れることができたが、この男が放つ敵愾心は、尋常の圧力ではなかったのだ。
ニグレオスは無言で構える。リユウは、フッと笑いを浮かべ、そして……寝息を立てて倒れた。圧力から不意に開放され、ニグレオスも尻餅をついた。
スキル:浪費癖搭載につき、万年金欠です。 サポートいただいたお金は主に最低限度のタノシイ生活のために使います。
