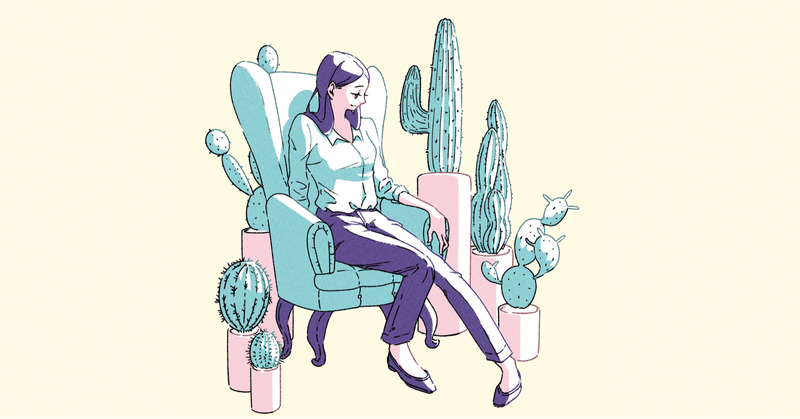
雑文(79)「チ〇〇のチーズ揚げ」
ある部族の村を訪れたある夏の日でした。
私たち取材班はテレビ局の意向で、というか特番撮影のために必要な機材を担いでメキシコに来たわけですが、事前に契約していた現地コーディネーターが約束の時間を過ぎても待ち合わせの空港に現れず、滞在時間が限られていたのでプロデューサーの判断で私たちは空港の冷房の効いたロビーから炎天下の外に出て、私を合わせて総勢五名のクルーたちは自力でタクシーを拾って、取材予定の部族の村に向かうことになりました。
車内でプロデューサーは終始不機嫌で、年上のディレクターに愚痴って、ときおり「おまえのせいだ」と怒鳴って、最年少のアシスタントディレクターが「まあまあ」とあいだに入ってプロデューサーを宥め、私は、愛想笑いを浮かべるしかない最悪の雰囲気でした。
二時間ほどでしょうか。
車が停まると目的の村に到着しました。
最年長のカメラマンが重たい機材をトランクから降ろし、私は身軽でしたからカメラマンさんの機材降ろし手伝いに協力しましたが、無愛想な運転手をはじめ、険悪な三人は私たちに目もやらず相変わらずの不機嫌のまま、タクシーから降りても言い合いを延長しておりました。
「悪いね。君の仕事じゃないのに、助かるよ」汗だくのカメラマンの阿部さんが私に笑いかけます。
「いえいえ。関係ないです、みんなでやらないと」私は阿部さんに微笑み返すと、プロデューサーたちをちらっと見ます。
「悪い人たちじゃないんだ。ただ、予定どおり行かなくて焦っているだけだ。ほんとうならこんな海外ロケじゃなくて、首相襲撃の事件を取材したかったが、会社の意向でこっちに回された。不本意なんだろうね」そう言って、阿部さんは哀れむようにプロデューサーたちを眺める。
「わかっています。私たちの仕事をしましょう」
「すまないね」
阿部さんがまたそう謝って、私たちは降ろした撮影機材を日陰に避難させる。
プロデューサーたちが部族の村長らしき男と話している。
打ち合わせだろう。
どういう流れで撮影するのか、片言の英語と簡単なジェスチャー、アシスタントディレクターはフリップ絵を駆使して、村長の男に説明している。
私は遠くからその様子を窺う。
タレントさんの出番はまだだと言わんばかりに、それは事務所との契約で決まっているように、私を故意にその打ち合わせに参加させない。これは自分たちの仕事だと主張するように、その輪に私を参加させない。
撮影前の打ち合わせが終わり、私は、阿部さんが回すカメラに向かって、「ここが秘境にある、〇〇部族が住む集落です」と神妙な表情と神妙な語り口でなにも知らない視聴者に騙る。むろん部族は近代化しており、謝礼を払って本来祭りの時にしか着ない民族衣装を着てもらい、私たちを出迎えてもらう。スマホやパソコンなんかの近代的な機器は隠してもらい、焚き火や吹き矢など自給自足の非近代的な暮らし向きを演じてもらう。
台本どおりだった。
演出と言ってよいのか。
演者としてエンタメ番組をこしらえる。これは嘘や捏造ではない、あくまでバラエティ番組、まじめな報道番組ではないのだ。
部族衣装に着替えた私は、焚き火を囲む若い男たちの集まりに招かれた。露出度の高い衣装だが、放送時はモザイク処理するからとディレクターが苦笑いするが、私に映る彼らにはモザイクが入っていないので困る。セクハラではないか。むろんは私はシャツやズボンの上に民族衣装を着ているから放送局のコンプライアンスには引っかからないんだろうけど、きっとこれは風習というか、男社会の弊害だろう。
笑みを崩さず、感動の別れを演出する若いある青年と台本どおり会話を交わす。村長の息子だ。告白されるので私は断る。だが、彼はあきらめない。そんな国境を越えた愛の物語。むろん、高い地位にいる村長の息子であるから彼はすでに結婚しており、夫人は五人いる。夫人たちは家の使用人だと私に紹介された。台本どおりだ。台本どおり。
「美味しいですね」
焚き火越しに彼に笑う。
「なんですか、これ?」
彼は笑って言う。「君がここに来た時、そう、さっき触れ合っていた、あれ(チーボ)」と現地の言葉で答える。通訳がいないのでなんとかニュアンスでわかる。村で飼ってる鶏(チキン)だ。それに淡白な味わいは鶏肉そのものだ。
「美味しい美味しい」と言って彼に手渡そうとしたが、部族でもあまり食べないのか遠慮がちにたぶんこう言った。
「大切なお客さんが来た時に振る舞うんだ。だから遠慮せずに食べてください」と。
お腹が空いていたのもあったから私は出された鶏肉を遠慮せずに平らげた。「美味しい美味しい」と彼らに言いながら。
別れの日、彼と抱き合い、別れが惜しいと泣いた演技をカメラ越しに決め、村から去る時も何度も手を振る彼に振り返り、目薬を点して流した人工の涙をハンカチで拭いながら、点しすぎて真っ赤になった瞳でカメラからフレームアウトする。
車内でプロデューサーは上機嫌だった。
私の演技がよかったからではなく撮影から解放された安堵からだろう。むろんプロデューサーたちは近くのホテルに泊まっていたので野宿に近い夜は過ごしていない。私は阿部さんと村で一夜を過ごした。たんにディレクターがホテルの予約を忘れただけで、私たちはその選に漏れただけだ。タレントだから特別扱いしないぞとはプロデューサーの口癖だった。
飛行機に乗って日本に帰る。
海外ロケを終えた充足感から帰りは機内で熟睡できた。
後日談というか、カメラに映ってはいなかったので阿部さん以外は知らないが、焚き火を囲んで食べた鶏肉は鶏肉ではなかった。むろんそのシーンはカットになって、焚き火のシーンは私の「美味しい美味しい」と言うポジティブな台詞で終わる。その後、阿部さんから衝撃の事実を打ち明けられ、青ざめる私の映像は残っていない。あまりの衝撃で、というか翌日の撮影に備えてメンタルを戻さないとならない。けれど、たらふく食べたあの味が忘れられない。私は翌日も演技しながらずっと頭の片隅ではそのことばかり考えていた。あの人工の涙には多少のほんとうの涙も混じっていたことは私しか知らない。
自宅に着いた。
主人と息子が出迎えてくれた。
夕飯の支度は任せてと、疲れを気遣う彼らに言った。献立は決まっていた。あの味が忘れられない。どうしてももう一度食べたかった。
夕ご飯ができあがる頃、居間に主人と息子がやって来た。
「おお、美味そうだな」と主人が食卓に着き、息子も笑って席に着く。
「美味しいから」と私は流し台で手を洗い、彼らに合流する。
箸をつけて主人が言う。「美味しいな、これ。鶏肉? ぜんぜん脂っこくないから、いくらでもいけるよ」
「うん。美味しいね」と息子も笑うが、どこか不安げだ。
「そうでしょう。美味しくてね、いくらでも食べられるでしょ」私も箸をつけ、彼らに笑顔を振りまく。
「チーズとの相性が抜群だな、うんうん」と、主人は何度も頷く。息子の異変に気づき、主人が息子にたずねる。
「どうした、食わないのか? 食べないなら食っちゃうぞ」
「違うんだ、そうじゃない。美味しいから置いているの。母さん、チーちゃん見なかった? いつもなら匂いを嗅ぎつけ、すぐに来るんだけど」
「チーちゃん?」私は咀嚼しながら息子に笑う。
「母さん、このお肉ってなんなの? 鶏肉? にしたら少しさっぱりしてない?」
「美味しくない?」
「美味しいけど」
「おまえ、これって鶏肉だろ?」なにかを察してか主人もたずねる。
私は彼らを交互に見つめ、口を開いた。
驚嘆の表情を浮かべる彼らが定点の隠しカメラ画面に記録される。
むろんバラエティ番組のドッキリではない。仕掛け人や台本はない。番組セットで録画映像を観る司会者やタレントからのリアクションはない。
これはあくまでドキュメンタリーであって、ノンフィクションだった。
むろんノンフィクションを書いたフィクションであることは、作中の彼らは知らず、まさか第三者に公開されているとは演者である彼らの知るところでない。
念のために最後に断っておきますが。
後、本作の補足ですが彼らが食べたお肉はむろん愛玩動物ではありません。彼らが食べたお肉は、子ヤギ(チーボ)であって彼らは文化圏の違いからカルチャーショックに驚いたのです。子ヤギのチーズ揚げを食いっぱぐれたチワワのチーちゃんはお昼にチャオちゅ〜るを食べすぎて夢の中。きっと夢の中でチャオちゅ〜るのチーズ揚げを食べる夢を見ているんでしょうね。めでたし、めでたし。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
