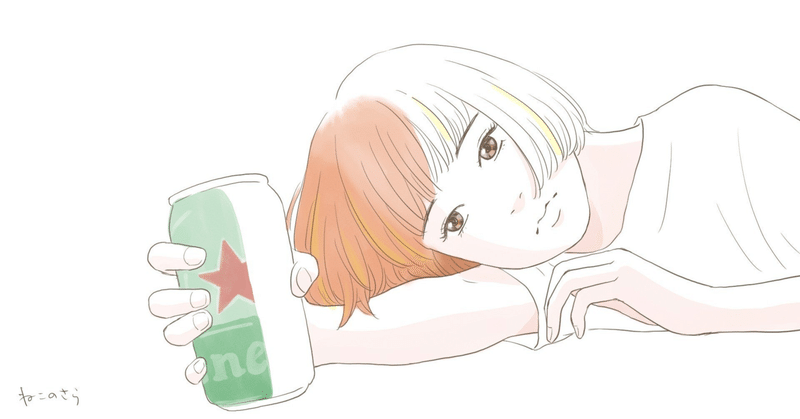
9年ごしの失恋が、私に残していったもの
学生だった頃。
「どんな人が好きか」という話になるたびに、私は「冷蔵庫みたいな人」だと答えていた。
背が高くて、どっしりと落ち着いていて、こちらが開けたい時に自由に扉を開けさせてくれる人。
その理想通りだったのかはさておき、ここではだから、その人のことを冷蔵庫と呼びたいと思う。
高校2年の秋、私は冷蔵庫のことを好きになった。
彼は高校のクラスメイトだった。
180センチを超える細身の長身。色白で、うっすらと栗色がかった猫っ毛と瞳孔。
恥ずかしながら、少女漫画に出てきそうな人だった。我ながらよくそんな人に惚れたと思う。
冷蔵庫は、東大を目指していた。
いつもテストの点で盛り上がるグループの中に彼はいて、もちろんだいたいは、彼のほうが上だった。
勝った時の、わざとニヤリとしてみせる感じ。負けた時の、すごいと純粋に褒めてくれる笑顔。
みんなが盛り上がっている時に、一歩引いて、だけど一緒に盛り上がる。そんなテンションにも共感した。
寒い日には、しっかりとコートを着て、手袋とマフラーをしてくるところも好きだった。
なにより冷蔵庫は、聞き上手だった。
その頃関係が最悪だった父に、ボロクソに怒鳴られた翌日も、
布団叩きで殴りかかってこられた翌日も、
目覚めた時には往復ビンタされていた翌日も、
冷蔵庫は、しずかにうなずいて聞いてくれた。
ひどいねーと言いながら、余計なことは言わなかった。もう聞きたくないというような素振りも、またその話かという顔もしなかった。冷蔵庫の扉を開け閉めするように、私は彼に、その頃のつらさを吸い取ってもらっていた。
そして私はいつの間にか、自分も東京に行きたいと思うようになっていた。
◇
進級して、受験生になっても、その関係性は変わらなかった。
テストの点を張り合い、いやなことがあれば聞いてもらい、たまにふざける。
放課後は同じ自習室を使っていて、私は冷蔵庫から少し離れた後ろの席を定位置にしていた。
皺のないピンとした白いシャツ。
それをなるべく見ないように、集中するのが自分のなかのルールだった。
冷蔵庫がそこにいると思うだけで、私はいつも緊張した。
話す時にはドキドキしたし、話したあとには舞いあがった。
暑くなり、寒くなり、1月の卒業式の1週間後、センター試験を皆で受けた。
国立大の個別試験があり、発表があり、冷蔵庫よりも一年早く、私は上京することが決まった。
「好きなんやけど」
3月に行われたクラス会の夜。
食べ放題の安い焼肉屋からの帰り道、私は冷蔵庫を呼び止めていった。
一瞬の間が空いて、いつものちょっとシニカルな口調で、彼は言った。
「きれいになって待ってなよ」
あのクールぶった冷蔵庫が、そんな歯の浮くようなセリフをどんな顔で言ったのか、私は全く思い出せない。
忘れてしまったのではなく、たぶん緊張で、顔なんて見ていられなかったのだと思う。
心臓がけたたましく鳴っていた。
張り裂けそうなくらいにドキドキしていた。
実った恋なんて初めてだった。
私はすっかりその気になってしまっていた。
◇
上京して一年目。
周囲では続々と初々しいカップルができていくのを傍目に、私はずっと冷蔵庫のことを待っていた。
ところが彼からの連絡は徐々に減り、一年が経つころ、ぱったりと途絶えてしまった。
友人伝に、どうやら二年目も東大に落ち、別の東京の大学に入ったらしいと聞いた。
その大学も、充分すぎる難関校だった。
だけどそういう問題じゃないんだろうなとか、
それ以前に私のことが嫌になったのかもしれないとか、
どうでもいいからもう一度会いたいとか、
いろんなことを考えて悶々とした。
連絡のないまま一年が経ち、二年が経った。
もうダメになっているのだとわかっていた。
他の恋をした方がいいのだと気づいていた。
実際、もし他にいい関係になる人がいたなら、きっと私はそこまで冷蔵庫に執念せずに済んだだろう。だけど、そうはならなかった。
当時の私には、人から好意を示されると、急に相手がくすんで見えるところがあった。「私を好きになるなんてつまらない人だ」と、どこかで軽蔑しさえした。
自分のことが、とにかく好きじゃなかった。
今思えば私はずっと、自分にばかりベクトルを向けていた。
冷蔵庫のことも、「冷蔵庫と一緒にいる自分が好き」な部分もあったと思う。
嫌い、きらい、と言いながら、嫌いな自分のことで120%になっていて、相手のことをきちんと見られていなかった。
結局、誰とも特別な関係には進めないまま、三年経っても、五年経っても、事あるごとに私はうじうじと冷蔵庫のことを思い出していた。
◇
きっかけはもう、忘れてしまった。
でもどうせ私からだったんだと思う。
あの高校の日から8年。かれこれ長すぎる片思い(のようなもの)が、10年目の大台に乗るかどうかという頃。冷蔵庫とふたたび連絡がつき、二人で会うようになっていた。
冷蔵庫が指定するのは、落ち着いていて料理の美味しい、いいお店ばかりだった。
彼は大学院を卒業し、ピカピカの一流企業に就職し、かつてやりたいと話していた、ど真ん中の仕事についていた。
その日は、ひどい雨だった。
降りたこともない駅の、駅から少し離れた四川料理の店で待ち合わせをした。
会うことが決まると、私はいつも、何日も前から緊張した。
そわそわしながら用意して、早すぎるのに家をでて、いつも何十分も早く待ち合わせ場所に着いてしまう。
その日もざぁざぁ降りの中、店を確かめるように一度歩き、駅まで戻り、時間ちょうどになる頃にもう一度歩いた。冷蔵庫は、少し遅れてやってきた。
せっかちな私は、そろそろ何か話があってほしいと思っていた。
でも、何かが起きる気配は全くなかった。
いつも通りにたわいもなく話し、店を出て、メトロの駅に降りる直前、
「好きなんだけど」
冷蔵庫の背中に向かって小さな声で、でも叫ぶように私は言った。
「えっ」
彼は、思ってもみなかったというような振りをして、だけど口許には、薄い笑みを浮かベた。
「…好きなんだけど」
その反応に困ってもう一度言うと、
「ちょっと、座って話をしよう」
と言われ、なぜか、すぐそばにあった喫茶店に入ることになった。
席について、注文をして、お店の照明に照らされながら、「で、どういうこと」と冷静にうながされて私は焦った。
どうもこうも、好きだと言ったのだから、付き合うとか付き合わないとか、そういう答えを返すものじゃないのかこの世では。
なぜかボールが私にあるので、仕方なくもう一度、「ずっと好きやった」といじけたような声で言った。冷蔵庫は「まじで」なんて言いながら、やっぱり謎の余裕をかましてくる。
「うーん」「うーーん・・・」
冷蔵庫がそう言って迷っている素振りなんかを見せるので、私はもうわけのわからない勢いのまま、
「好き」
「めっちゃ好き」
「ずっと好き」
「好き」
「すごいすき」
「すき」
・・
何年ぶんも、溜まりに溜まったすきを吐き出した。何度も何度も、壊れたようにすきだと言った。心の中は、もっと嵐のようにモヤモヤしていた。だけど、好き以外の言葉が出てこなかった。
飽きるほどにすきだと言って、もうどうすればいいんだという段になって、冷蔵庫が思い切ったように言った。
「やっぱり、ダメだ」
ハッキリとした口調でそう言われたので、私はもう、何も聞けなくなってしまった。
一体、何に迷っていたのか、何を考えていたのか、何がダメだったのか。
思えば聞きたいことは山ほどあったけれど、
「ダメだ」
それがもうこの場の答えなら、それ以上聞きたいことは何もないようにも思えた。
「そっか」
私は一気に冷静になった。
冷蔵庫はその後も、何か平然と雑談をしようとしたけれど、私のほうがなんだかあまり盛り上がらずに、すぐにお会計をして店をでた。
目の前にあったメトロの駅に二人連れ立って降り、改札でわかれることになったとき、
「またね」
冷蔵庫はそう言った。
「うん、またね」
私もつい、反射的にそう返してしまって、改札の中に歩いて行った。
◇
呆然としながら電車をのりついで最寄り駅に降り、やまない雨の中をびしょびしょになって、ワンルームに帰りついた。
狭い部屋で、ベッドの足元にぺたんと座り、ぼーっとした。
ついに、おわった。
ぽっかりと空っぽになった心の中に湧いてきたのは、それまでとは違った感情だった。
ま た ね ?
もう、彼の「またね」に期待することなんて、なんっにもなかった。
いや、正直4%くらいは、「え、またねがあるってこと…?」と思ってしまう未練がなかったわけではないけれど、それを押し潰してあまりあるほどの、もう十分、もうお腹いっぱい、もうやめてくれ、やっと終わった、という、もはや逆ギレに近いようなふつふつとした気持ち。
思えば、ずっとこんな調子だった。
気まぐれに返ってくるメールの返事。会えば優しい。でもそれだけだ。
実際に彼からしてもらったことなんて、高校生の頃に話を聞いてもらったくらい。
それには多大に感謝しているけれど、それ以外には、ほとんど思い出せるものはなかった。
気まぐれにもらった一言にしがみつき、なんて事のない優しさを、飴でもなめるようにくりかえし味わい、自分に暗示を掛けていた。
最後の喫茶店で「好き」と口では連呼しながらも、心の中には、
「ほんとうに?」
「そんなに?」
「この数年間を何も知らないのに?」
「私が好きなのは、私が、自分の中に作り上げた彼じゃないの?本当にきちんと彼を好きなの?」
といった様々な、不安にも、後ろめたさにも似た気持ちが起きていた。
そんな各種の事実に、私はとうとう向き合わざるをえなくなっていた。
そういうダメすぎるいろいろが見破られていたのか、それとも全然別な理由だったのかはわからない。
だけど、「ああ、そりゃぁダメだよなあ」と、自分自身でもしみじみと思った。
今日、「ダメだ」と言ってもらえてよかった。
そう頭では理解しながら、まだ興奮のさなかの落ち着かない気持ちで、何度も何度も溜め息をついた。
かなりの時間ぼんやりとしてから、私はそばにあった携帯を取った。
何度も何度も、鳴らしたいのを我慢した電話番号も、
すぐに返すのは良くないかなと、送れないまま見ていたメールアドレスも、
何回かだけ往復したLINEも、
ひとつずつ、きれいさっぱり消してしまった。
それから昨日と同じようにシャワーを浴びて、朝と同じシーツにくるまり、いつもと同じように、一人で休んだ。
◇
その翌週末の、土曜日の朝。
何かの本で見たマッシュルーム・ガーリックトーストなるものと、もらい物の国産紅茶を淹れて、朝ごはんを食べていたとき。
私は唐突に、「ああ、自分は、冷蔵庫よりも素敵ないい人と出会えるに違いない」という気持ちになった。
それは予感というよりも確信だった。
出会ってやる、という気概や決意でもあった。
わりに美味しかったそのトーストを齧りながら、どんな人がいいのかを考えた。
次に好きになるなら、自分からいっぱい連絡をくれる人がいい。
返信に時間を空けたほうがいいかとか、くだらないことでグズグズ悩まなくてもいいような関係を築ける人がいい。
もしプライドが傷つくようなことがあっても、それも共有してくれる人がいい。
いっぱい喋ってくれる人がいい。
ハグが好きな人がいい。
ムダ毛一本、剃り逃さないようにしなきゃと思わせるような人よりも、人間だから生えてるさと言ってくれるくらいの人がいい。
ドキドキしたり緊張したり背伸びしないといけない人よりも、安心してありのままで、笑い転げられる人がいい。
私のことを大好きになって、たくさん好きだと言ってくれる人がいい。
ふたを開ければ、どんどん、どんどん、いろんな希望が思い浮かんだ。
はじめて冷蔵庫を好きになった頃から、もう9年も経っていた。
一人暮らしをして、仕事もして、貯金も料理もして、奨学金も返しながら、自分の生活をもう何年も営んでいた。
頑張りすぎてメンタルをやられるような経験も何度もしていた。
高校生の頃に抱いていたような、「ありのままの自分じゃダメだ」、「頑張っていない自分はダメだ」、そういう潔癖さもだいぶ薄らいでいた。
そりゃあ、「好きなタイプ」もすっかり変わっているわけだ。
それは楽しい朝食だった。
清々しくて、前向きで、身軽な自分。
だけどそうやって考えながら、山ほど泣いた。なんに泣いているのか、自分でももうわからなかった。
そのまま私は、出会い系アプリに登録した。
登録したのは初めてではなかったけれど、それまでとは比べ物にならないくらい、本気だった。
そしてやがて、夫に出会った。
◇
アプリを始めて夫と出会うまでも、そうそう簡単だったわけじゃない。
出会ってからも山ほど喧嘩をしたし、この人で良かったのかなと思ったことがないわけでもない。
だけどそれもひっくるめても。
あの朝、ひとり、手の込んだトーストをパクつきながら、「理想高すぎだよな」「でも理想はタダだしな」なんて強がっていた自分に、
「一生ひとりでご飯食べてたらどうしよう」なんて、そんなことに、足元が抜けるくらい怯えていた自分に、
できるならこっそり耳うちしてあげたい。
あなたはこれから、その理想を超えて余りあるくらいの、最高の夫に出会うことになるよ。
ちょっと褒めすぎ? いや、たぶん大丈夫。
私の、長文になりがちな記事を最後まで読んでいただき、本当にありがとうございます。よければ、またお待ちしています。
