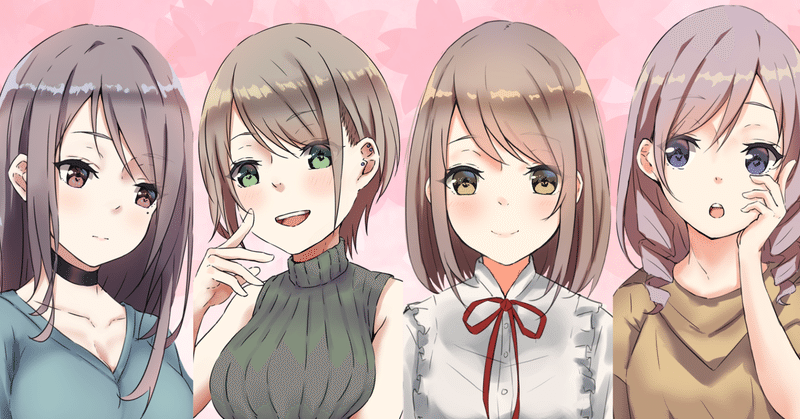
小説:色街乙女™オーディション当日
1 白河梨々香
色街の東側にある川の河川敷で、梨々香は芝生に寝転がって、ときおり芝を掃くあたたかい風に身を任せていた。川の流れはおだやかで、川の水にすすがれた澄んだ空気が、梨々香の胸を上下に揺らしていた。彼女は静かに目を閉じていて、なにも考えてはいなかった。心地のよい虚無感が彼女の中心にあるなにかを包んでいた。
そのとき、どこからか芝生を踏みしめるような音が聞こえてきた。それはだんだんと近づいてきた。それでも彼女は目を開けなかった。近づいてくるものが、梨々香にとってなんの危害も加えることのない、なによりも安全な存在だと確信していたからであった。
「梨々香。時間に間に合うのか?」と発せられた、絶対に忘れることのない声は、大好きな父のものであった。
「おとうさん。呼びに来てくれたの?」
梨々香は目を開けて、立っている父を見上げるようにした。父の背には、青い空と真っ白い雲が控えていた。
「それもあるが、部屋から梨々香の姿が見えてな。あまりにも気持ちよさそうだったから、来てみたくなった」と丸みのある声でいって、父はやさしく笑った。梨々香の家は、川沿いのマンションの3階であった。
「そっか。じゃあ、そろそろ準備しよっかな」
梨々香は両手をうしろについてゆっくりと立ち上がり、白いワンピースについた芝生をパタパタとはたいた。栗色の髪が揺れて、形のよい白い耳が髪の間から覗いた。対岸には釣り人がいて、太陽の光にキラキラと光る糸をたらしていた。父と梨々香は自宅のほうに向き直って、大小の影を作りながら歩き出した。その姿は胸をえぐるほどにうつくしく、まるではじめから決められていた景色のように、釣り人の目には映っていた。
2 月崎梓
色街のメインゲート前にある駅には、10人ほどしか乗車待ちの客がいなかった。月曜の昼時の駅は、色街にくる客は少なく、通勤通学の人もすくなく、いつもそんな様子であった。梓は島式ホームへとエスカレーターを駆け上がり、すべり込んできた車両にギリギリのところで飛び乗った。扉のゴムが梓の肩に軽く触れ、瞬間的に彼女は「わっ」と声を上げた。車両にいた数人の視線が彼女に集まったが、すぐに何もなかったように車内は平常を取り戻した。梓は色街を出て、自分の職場であるデパート1階の化粧品売り場に口紅を買いに行くところであった。風俗嬢を母に持つ梓が、色街外のデパートで働けているのは、父が優秀な医師として内外から認められているからであった。今日はアイドルグループのオーディションがあり、そのための化粧をしていたのだが、口紅の色が合わず、どうにも納得がいかず、家を飛び出してきたのだった。たびたび時計で時刻を確認しながら走って化粧品売り場に着くと、肩で息をしているけわしい表情の梓に後輩の店員がすぐに気づいた。
「どうしたんですか」後輩は真顔で無感情にいった。
「口紅を買いにきた」梓は大きく息をした。
「カタキを討つような顔で」といいながら、後輩は梓に通路を譲った。自分の立っている通路の先に口紅コーナーがあったからだった。梓は素早くコーナーの前に立ち、あれこれと色を試し、納得のいくものを見つけ出した。
「これ、シールでいい」梓は後輩の手元に突き出すように口紅を差し出した。
「はい。あれ? 今日オーディションですよね?」後輩はやっと感情を表に出した。
「間に合えば」といって、梓はデパートのシールがぐるりと貼られた口紅を持って、来た道を戻った。
3 雫石カロナ
「朝からオムライス? またお昼に食べるの?」カロナの母が、キッチンでオムライスを作っているカロナに話しかけた。母は出かける用事でもあるのか、髪をカーラーで巻いていた。
「今日はバイトは休みなの」カロナはぎこちない手つきでチキンライスを包み始めた。オムライスは大好きだったが、自分で作るのは苦手だった。
「そうなのね。最近ずっと忙しかったでしょう。ゆっくりするといいわ」母が艶のある明るい声でいった。母は陽気さをそのまま声帯につめ込んだような声をしていた。
「それが、そうもしていられないのよ。前に話してたオーディション。今日なの」カロナは完成したオムライスを皿に移し、テーブルまで運んだ。
「今日なの!? うまいことやってきなさいよ。あがり症なんで心配だわ」
カロナは、できる限り考えないようにしていたのに、と思った。自分があがり症だという事実を改めて意識させられ、急に息苦しさに襲われた。冷蔵庫を開け、ケチャップを取り出した頃には動悸がしはじめていた。
テーブルについて適当にケチャップをかけ、カロナはまかないのオムライスを食べるときと同じようなすばやさで平らげた。ゆっくりしていたら、食欲が減退して食べ切れなかったに違いなかった。
「あとはお母さんが片付けるから、そのままでいいわよ」母は身振り手振りを加えて、ちゃきちゃきとした早口でいった。
「ありがとう、お母さん」といって、席を立ち、自室に戻ろうとカロナが振り返ったとき、うしろからなにかが割れる音がした。カロナがふたたび振り返ってみると、床には見事に割れた皿が転がっていた。
「お母さんが皿を割るなんて」
「不吉だわ」
4 糸貫ゆい
ゆいは昼間から長風呂を楽しんでいた。心身の調子をととのえ、このあとの予定にそなえる意味もあった。ゆいが湯船から出たところで、呼び鈴が鳴った。風呂場の壁に埋め込まれたモニターに、来客者の顔が映った。
「ねーちゃん、鍵忘れた。開けてくれ」といったのは、高校生の弟だった。背中にはギターを背負っていた。
「えぇ? いまお風呂なのよ。てかさあ、あんたもチップ埋め込んできたんでしょ? 手をかざせば開くはずよ」つい最近、チップを体内に埋め込むことが義務化されたのだった。
「それで開かないから困ってんだよ」
「もうっ。からだ拭いて出るからちょっと待ってて」せっかくゆっくりいい気持ちでいたのに、と彼女は心のなかでつぶやいて、すこしだけ眉根をよせた。
彼女はからだを拭きおさめ、バスタオルを巻き、リビングにある玄関ロック解除のボタンを押した。ビープ音のあとにガチャリ、という音がして、弟が扉を開けて入ってきた。「サンキュー」といって、弟はそのまま自室に入っていった。と思っていたら、部屋から顔だけを出して、ゆいに「どうせまた迷うんだから早めに出たほうがいいぜ」といった。弟は今日がオーディションの日だと覚えていたのであった。弟は高校でバンドを組んでいるので、今回の企画についてなにかと気になるようであった。
ゆいは方向音痴で、よく道に迷うのだった。ゆいの自宅は階上38番ゲートのすぐそばなのだが、ほぼ反対側の地上2番ゲートまで行かなければならない。原付バイクで行くので距離的には問題ないのだが、色街の入り組んだところを通らなければならなかった。果たして、ゆいはオーディション会場である2番ゲートそばの公民館にたどり着けるのだろうか?
5 白河梨々香
オーディション会場の公民館に着くと、すでに数人の女性の姿があった。ただ、梨々香が思っていたよりは少なかった。受かる確率は高い。そう彼女は率直に思った。と同時に、ひといきに緊張感が高まった。心のどこかで、どうせダメだろうという諦めを装った逃げ道を用意していたからだった。正面からぶつかっていくのは怖い。おじけづくという言葉が、そのときの梨々香にはぴったりだった。
受付を済ませると、首にかけるタイプの番号札をもらった。首にかけるということは、ダンスの審査はないだろうと思った。歌唱審査だけなら自信はあった。腹筋とピッチ感覚は、吹奏楽部で鍛えてきたからだった。
まだ開始時刻まで時間があったので、ロビーの椅子に腰掛けて本を読むことにした。本は有川浩の図書館革命だった。もう何度も読んでいる本だった。何度も読んでいる本だから、気持ちを落ち着けるのには最適だった。
周囲のことが気にならないほど読書に集中していたとき、突然エンジンがうなる音とガシャンという音が聞こえてきた。音の方向を見ると、駐輪場の自転車が何台か倒れ、そこにバイクが突っ込んでいた。勢いはそうでもなかったようで、運転している女性はバイクにまたがりながら申し訳なさそうにしていた。それでも心配だったので、梨々香は外に出て駆け寄った。
「大丈夫ですか?」
「へへへ、間違って1速入れちゃって――お騒がせしました」女性はひきつった笑顔でいった。どこか自分の世界を生きているような雰囲気の女性だった。梨々香はその女性と行動を共にした。彼女もオーディションを受けに来ていたのだった。
梨々香の歌はまずまずだった。受け答えも及第点。あとは一週間後の選考結果を待つばかりであった。
6 月崎梓
オーディションには無事に間に合った。梓が受付の最後であった。無論、梓の化粧は完璧であった。首から番号札をさげて、最後尾に並んだ。もう2人進めば、パイプ椅子に着席するところであった。
オーディションが行われている会議室に入ると、センターに置かれた椅子に座らされた。月並みな自己紹介と質問のやり取りのあと、歌唱審査が行われた。歌ったのは、昭和歌謡の「氷雨」だった。昭和歌謡をテーマにしたグループだと聞いていたので、当時の歌を何曲か聞いて、そのなかから選んだのであった。あたしが酔ったら歌になるようなきれいなもんじゃない。ダル絡みするがね、と自嘲気味に頭のなかでつっ込んだ。
きれいめのジャケットを着て、ハットをかぶってメガネをかけているのがプロデューサーだった。きわめてあやしい雰囲気だったが、悪い人には見えなかった。受かったらとりあえず一回飲みにいってみないとな、と考えた。
オーディションが終わると、18時過ぎくらいになっていた。そのとき梓の頭に浮かんだのは、酒を飲むことだった。色街に酒を提供する店はない。公民館を出て2番ゲートを出れば外の街である。梓は迷わず外の街に繰り出した。
古ぼけた朱色のちょうちんに誘われ、居酒屋に吸い込まれた。梓は煮込みとホッピーセットを頼んだ。 カウンターのいちばん端で、高い位置に置かれたテレビを見ながら、おしぼりで手を拭いていると、ガラリと引き戸を開けて客が入ってきた。それは間違いなく先ほどのプロデューサーだった。
「あれ、きみ――月崎さんだっけ?」
「そうです! よく覚えてましたね!」
「まあ、最後だったから」
「あっ、なんか期待しちゃいました」
7 雫石カロナ
意外とあっけなく終わってしまったな、とカロナは思った。オーディションの帰り道、スーパーに寄って帰るところであった。これでなにかが変わるのだろうか。ふとそう思った。はっきりとした目的があるわけではないが、オーディションに受かれば、なにかが大きく変わるような気がしていた。受からなくても、すこしは変わるような気がしていた。バイトをいつまで続けるの? 恋人は? 結婚は? いや、まだ自分は若い。まだ大丈夫。そういう思いがいつもカロナの心にあった。陽気な妹に対して、なぜあたしはこんなにも陰気なんだろう――
カロナはいったん家に帰って買ったものを置き、カメラを持って出かけた。色街の夜景を撮ろうと考えたのであった。当初、色街は計画されて作られたので、区画整理されて整然としていたが、ここ20年のあいだに区画の分割、増築や改築が繰り返され、だんだんと複雑化していったのだった。道は枝分かれし、横丁が増えていった。そんないまの色街を高いところから眺めると、全体がほの赤く、まるで人間の欲が生き物に姿を変えたような、働く人々の悲しみの叫びが今にも聞こえてきそうな、ただ死を待つだけの肉体がそこにあるような、そんな風に見えるのだった。
23番ゲートのそばにあるビルの屋上に出て、カロナは一度空を見上げてから、色街の写真を撮りはじめた。でもすぐに中断した。ファインダーが涙でにじんできたからだった。そのとき、ドアが開く音がして、自分を呼ぶ声がした。
「カロナ。またここにいるの」呼んだのは姉だった。そこは姉が働く風俗店が入っているビルだった。
「お姉ちゃん――」カロナは声を詰まらせた。
「泣いてるの?」姉が心配そうに声を落としていった。
「お姉ちゃんはいま、しあわせなの?」
8 糸貫ゆい
ゆいはオーディションを終え、バイクで帰宅した。会場の駐輪場にバイクで突っ込むというエラーをやらかしたが、オーディション自体は無事に終わったといってよかった。家に帰ると弟も母もいなかった。おそらく弟が自分の夕食のついでに取ったのであろう、テーブルの上には出前の炒飯が置いてあった。ゆいはなんとなくテレビをつけて、炒飯を食べ始めた。大学の課題が残っていることを思い出して、急に憂鬱な気分にとらえられた。その憂鬱な気分に引きずられて、高校の頃の忘れもしない記憶に入り込んでいった。
色街の西のはずれには、紅葉のきれいなスポットがあった。あの日、待ち合わせていた友達は風俗嬢になった。自分もそうなればすこしは救われるのだろうか。友達は「割り切る」という言葉をよく使う。それはどのようなことなのだろう? あの日のことを思い出すと、感覚まで戻ってくる。いくらほかの人たちと身体を重ねても、あの日の感覚は忘れない。それでも自分は新しい感覚に心をうばわれる瞬間はある。友達は仕事で新しい感覚をおぼえたとき、いったいなにを思うのだろうか。感情のない人間にでもならない限り、本当の意味で行為を客観視すること――割り切る? ――は不可能なように思える。そんなことを考えても、結局、体感をしていない自分には答えの出しようがない。いつもそう結論づけて、思考することを放棄するのであった。
すっかりさめてしまった残りの炒飯を別の皿に移し、ラップをかけた。寝る前にもう一度、風呂に入ろうと思った。そのとき、玄関の扉が開いた。母が帰ってきたのであった。
「オーディション、どうだった?」おかえりと声をかける前に母がいった。
「道には迷わなかったよ」といった。わたしは迷ってるけど、と心のなかでつけ加えた。
9 白河梨々香
「いまどき郵送なのか」父が紅茶を飲みながらいった。
「そう。そろそろ着く頃だとは思うんだけどなあ」梨々香はカタカタとPCで文字を打ちながらいった。ある作品の二次小説を書いているのであった。
「タバコを吸うと捗るか」父がつぶやくようにいった。
「えっ」梨々香は絶句した。気づかれていないと思っていたからだった。自室の窓を開けて、からだを外に半分出すような体勢で吸っていたから、部屋にも自分にもニオイはついていないと思っていた。その時代、喫煙者のイメージは非常に悪かった。なにより、父は嫌煙家だった。
「いや、かまわないんだ。悪いことではない。ただ、気づいてるのに黙ってるのも変だと思ってな。俺は異常に鼻がいいんだ」紅茶をソーサーに戻す音が、妙に空間に響いた。
「吸ってるよ。いま書いてるアニメのキャラが吸ってて、それにあこがれて」平静をよそおっていったつもりだったが、不自然な口調だったな、と彼女は思った。そのとき、外でバイクの音がした。郵便を乗せて走るバイクの独特な音だった。
「見てくる!」梨々香は勢いよく立ち上がって、玄関を出て行った。
しばらくすると、オレンジ色の封筒を手に持って、息を切らして戻ってきた。エレベーターを待てず、階段を使ったからであった。父と一緒に確認したくて、その場で封を切らずに帰ってきたのだった。
「開けるよ――」梨々香が封を切って、なかから3つ折りにされたA4サイズの紙を取り出した。開くと、そこには合格の文字があった。
「やったー!」彼女は父に抱きついた。そのとき揺れた髪から漂ってきたタバコの香りを、父はなぜかとてもいとおしく思った。
10 月崎梓
「ぎゃー! 受かった!」梓は郵便受けの前で叫んだ。通行人が変な顔をして通りすぎて行った。
梓はなにかしたかったが、そのなにかがわからなかった。わかったときには、すでに足がその方向を向いていた。激辛カレーを食べに行ったのであった。
カレーを食べたあと、家に帰って焼酎をロックで飲んだ。シメと酒が逆転したので調子が狂うかと思いきや、最高の気分だった。誰かにいまの喜びを伝えたいと考えたが、家には誰もいなかったし、直接連絡したい人もいなかった。彼女はSNSを開いて、合格した喜びを書き込んだ。普段おとなしい通知が、その日だけは騒がしくなった。
翌日、その喜びを抱えたまま、梓はバイトに行った。ずっと顔がほころんだままだった。はじめて客に「笑顔が素敵ですね」といわれてまた喜んだ。
その日の夜、病院勤務から帰ってきた医師をつとめる父と、看護師の母に合格を報告した。ふたりとも心から喜んでくれて、急遽ありあわせの材料で鍋を作り、ささやかなお祝いをした。
「歌うことが、もっとも自分を表現できる手段。その思いのスタート地点に立ったな」といって父は日本酒で満たした升に口をつけた。
「これで飲みかたが綺麗になるといいわね」母がおどけた調子でいった。梓の深酒とダル絡みぐせを暗に指摘したのであった。
「今日は無理」梓は深酒するつもりでいた。さいわい明日のバイトは休みであった。
酒盛りは終わり、梓はふらふらと自室にもどった。なんとなくベースを持って、思いつくままにさまざまなフレーズを弾いた。そのときふと、グループとしてこれから歌うことになる楽曲を想像してみた。それは救いようのない歌だった。
11 雫石カロナ
カロナはオーディションに合格した。母も姉も心から祝福してくれた。不吉な予感は的中しなかった。 姉は屋上であった出来事のあと、なにも変わらずに過ごしていた。カロナの「しあわせなの?」という問いには答えていなかった。それは否定ではなく、しあわせの意味をまだ見出していないのだと、カロナは希望的にとらえていた。
夜、喫茶店のバイトが終わったあと、そのまま店で食事をとった。朝にオムライスを食べてしまったので、サラダサンドにした。カモミールティーとあわせると、とてもリラックスした気持ちになれた。
「父親のことは、やっぱり気になるかい。いや、愚問だね」マスターがグラスを拭きながら、カロナにいった。普段その話題には触れないので、カロナは不思議に思った。
父は行方知れずで、自分の出生には秘密がある。それは子供の頃に直感したことで、いまは確信に変わっていた。
「気になりますが、気にしても仕方ないんですよね。たいていそういうことは、知らないほうがいいことが多いんです。だからきっと、わたしの場合もそう」伏し目がちに、さめた声でいった。
「今日みたいなおめでたい日にする話じゃなかったな。なんか妙に気になってな」マスターの言葉は、いい訳じみてはいなかった。続けてマスターはいった。
「話した勢いでというんじゃないが、俺の考えだが、もしかして、有名になって、父親になにか思いを伝えたいと思っているんじゃないのかな」
「――どうでしょう」感情を包み込むような口調だった。心のなかは、感情で満たされているのかもしれなかった。
「結局、チキンライスが重要なんだよ」
12 糸貫ゆい
ゆいはラブホテルでその知らせを聞いた。通知が届いたら、すぐに連絡をくれと母と弟に伝えていたからであった。連絡をくれたのは母だった。母は喜びのあまり取り乱していたので、ゆいはしばらく電話を切ることができなかった。連れのためには、早く電話を切らなければならなかった。電話を切るとすぐ「もうだめだ」といって、その日の相手は、ゆいを引き寄せた。
ゆいは新交通システムに乗って、色街のメインゲート最寄りの駅にたどりついた。まだ下腹部には痺れるような感覚が残っていた。やはりこれを客観視できるとは到底思えなかった。全身の倦怠感に包まれていたゆいは、駅から自宅までタクシーで帰ることにした。色街のタクシーは外の街より格段に安く移動できるのだった。
タクシーで色街を走ると、青年から老年まで、さまざまな年代の人たちが歩いているのが見えた。この幅広い年代の人たちを受け入れる風俗嬢という職業が、もっとも人のためになっているのではないかと思えてきた。自分の「今ここ」という貴重な時間と空間を、わけ隔てなく、もっとも純粋な欲望のために、差し出して対価を得ているのである。
家の前で停車したタクシーは去っていった。赤いテールランプが、風俗店の赤い看板の先へ消えていった。赤い看板の奥に入れば、まったく別の世界が広がっているのだ。時計を見ると、21時だった。ちょうど女の子が部屋に入ったころだろう。客はリピーターかもしれないし、はじめて会う人なのかもしれない。わたしはいちいち真剣に考えすぎなのだろうか? そんなこと、ずっと呼吸のように繰り返されてきたことなのに。
13 終章
合格したメンバー4人、初顔合わせの日だった。都内のとあるスタジオで、プロデューサーは4人を待っていた。女性スタッフがひとり、スタジオのエントランスに控えていた。
「おはようございます!」はじめにあらわれたのは、白河梨々香だった。さっとお辞儀をして、顔を上げて髪を耳にかけた。女性スタッフに名前を告げると、奥のスタジオへと案内された。
スタジオに入ると、プロデューサーはお茶を飲んでいた。梨々香があいさつをする前に彼は気づいて「どもども。そこのソファーに座ってて」といった。「えっ、あ、どうも」といって、彼女は腰掛けた。
つぎにスタジオに入ってきたのは、糸貫ゆいだった。ゆいもソファーに座るようにうながされ、腰掛けようとした。そのとき、梨々香と目が合って声を上げた。「あ! あのときの!」「バイクでつっ込んだ人!」梨々香は目をまん丸くさせた。
「なんだ? 知り合いなのか?」プロデューサーが不思議な顔をして問いかけた。
続いてふたりの女が入ってきた。雫石カロナと、月崎梓だった。彼女たちが着席するのを待ってから、プロデューサーはひとくちお茶を飲んで、声を張って話しはじめた。
「今日は集まってくれてありがとう。私はプロデューサーの浜林だ。よろしく」といって軽く頭をさげた。メンバーも挨拶を返した。そのときの声はそろっていて、浜林の期待感は高まった。
「まず、グループ名を発表しよう。僕が3つほど候補を出して、友人知人に投票してもらって決めた名前だ」浜林はポケットから紙を取り出して、メンバーの前で広げた。そこには「色街乙女」と大きく書かれていた。
「いろまちおとめと読む。色街と乙女という相反することばを組み合わせた」浜林はメンバーの様子をうかがった。しかし無反応であった。
「なんだ? だめか?」
「いや、ダメではないんですけど、パッとしないというか、刺さってこないというか」と月崎がいった。
「乙女じゃないし――」ゆいが小声でいった。
「ま、まあ、そういう意味でいう乙女というのは設定だから、かならずしも本人がそうである必要はない」浜林があわてて言葉をおぎなった。
「あたしは乙女です」梨々香が断言した。
「定義としてはわたしも」カロナが目をそらしていった。
「えっ、えええっ! そうなの? ほんと? カロナさんのその色気はなんなの」梓が大げさに反応した。
「気にするな。設定なんだから」浜林は無理に作ったような笑顔でいった。
「いや違うんですよ。あたしも同じ。経験ないから」カラカラとした声で梓がいった。
「そうなのか? なんか、ちょっと意外だな。外の街の女性のほうが早いんじゃないか」といった直後、これはまずいことをいったか、と浜林は冷や汗をかいた。4人の表情を気まずそうにうかがったとき、梨々香がすごい顔をして自分をにらんでいることに気づいた。
「色街で生まれた女だからって、しょせん貞操観念が低くて、若い頃から誰にでもからだを許してるんじゃないかって思ってません? すぐに流されて、それくらいたいしたことじゃないって、男が喜ぶならそれでいいやって思って、そうやってたくさんの男とかかわってきたんじゃないかって、そう思ってません?」
「いや、そこまでは思っていないが――」浜林は完全にうろたえていた。
「こんな街に生まれたから、あたしはかえって慎重なんです。そう思われるのが嫌だし、そうやって蔑まれるのも許せない。本当に乙女みたいなこといいますけど、はじめては本当に好きな人がいいんです。その気持ち、わかりますか?」高音だが軽くない、芯のある声で梨々香がいった。
「悪い。悪かった。あやまるよ。申し訳ない。僕にはわからない。わかるわけがないんだ。僕は外の街で生まれ育った。しかも男だ。わかるわけがない」浜林は素直に頭をさげた。
「よかったです。気持ちがわかるっていったら殴るところでした」梨々香の言葉には、おどしではない断定的な響きがあった。
「さて、つぎの話に移ろう!」浜林は雰囲気を変えるために、声の調子をがらりと変えていった。
「まず、曲を聴いてくれ」浜林はレコーダーの再生ボタンを押した。流れ始めたのはデビュー曲の綴じ紐であった。このときはまだ歌詞ができていなかったので、仮歌のかわりにガイドメロディが鳴っていた。
「まあ、こんな感じだ」もう反応は期待していなかった。
「歌詞はどうするんですか?」梓が聞いた。
「小倉欽一郎さんに書いてもらう」
「誰ですか? そのかたは」首をかしげて梓がいった。まったく見当がつかない、という顔をした。
「焼きそば屋だ。木更津焼きそば」
「焼きそば? なんだがちょっと話が見えませんね」梨々香が淡々といった。
「そのうち話すよ。私は適任だと思っている」と浜林はいって、みんなに言葉が行きわたるのを待った。
「さーて、今日はこれで終わりにしよう! みんなでメシといきたいところだけど、それはデビュー曲が完成したあとにしよう。ひとり酒好きがいるから、いい店を紹介してもらってな」といって、浜林は梓の顔をちらりと見た。
「えへへへ」梓はニヤニヤしながら頭をかいた。
「よし、帰ろう! お疲れさま!」と浜林が号令をかけて、全員、スタジオの前で別れた。
梨々香はツナマヨおにぎりを買って、家に帰って食べた。ゆいは馴染みの店で馬刺しを買って、家で家族と食べた。カロナは家に帰って、チキンライスのレシピを見直そうと思った。あたりめを買って、梓は家で一杯やった。
彼女たちには、まだはっきりとした目標はなかった。浜林から伝えられてもいなかった。そもそも浜林自身にも、まだはっきりとした目標は見えていなかった。すべてが手探りだった。
色街のなかでは自由に過ごせている彼女たちも、一歩街を出れば、烙印を背負って自由を失った悲しい女たちなのである。色街に押し込まれた、欲をメシの種にする卑しい女の仲間なのである。彼女たちが自分自身を悲しい人間だと思わずとも、外の者たちは、風に吹かれて俗に堕ちた悲しい人間だと考えようとするのである。彼女たちが「わたしは、しあわせだ」といっても、外の者は「おまえは、しあわせじゃない」というのである。彼女たちが、まるでしあわせになっては困るかのようにいうのである。彼女たちがいなければ、自分の価値を見出せないかのようにいうのである。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
