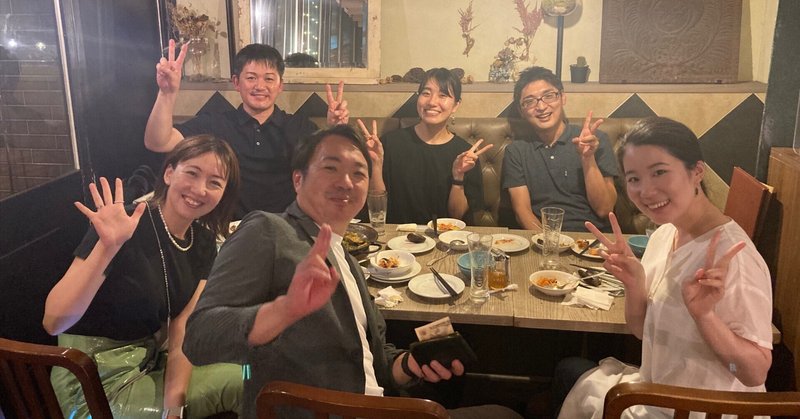
今こそ、注目すべき東京へのワーケーション
東京へのワーケーション。それは地方創生だけの頭でいると違和感が満載かもしれない。しかし「場所を変えて豊かに暮らし働く手段」として、ライフスタイル・働き方の一環として考えていくのであれば、寧ろ東京へのワーケーションはもっと注目されるべきである。
今回は、関西地方在住者の私自身の目線から、東京へのワーケーションの魅力などを存分に語っていきたいと思う。
そもそも、東京は日本の人気観光地の1つである

まずこのフレーズ自体、聞き慣れないかもしれないが、東京は江戸時代からは政治の中心として栄えてきており、そもそも歴史・文化のある街だ。京都や大阪と異なり、武士の時代の安定期に中心だったこともあり、その文化は関西地方と異なるものを持っている。
「都道府県魅力度ランキング」で知られている「地域ブランド調査2022」の調査結果によると、「観光に行きたい都道府県ランキング」第4位は東京都だ。上位3道府県は北海道、京都府、沖縄県であるから、実は東京都がいかに根強い人気のある観光地であるかが分かる。
東京都内へ毎日通勤で仕事をしている方からすると、必ずしもそうでないかもしれないが、地域外からすると東京は「遊びに行く場所」でもあるのだ。また同じ関東地方内でも、週末に東京都内へ観光に行く方もいるだろう。
東京都観光客数等実態調査の出典によると、最も訪れたいと思われているエリアは新宿・大久保で以降、銀座、浅草、渋谷、秋葉原、上野と続いている。
東京は今も昔も、観光面でも人気の地域の1つなのである。つまり、多くの人にとって、東京はビジネスだけじゃない目的地に十分現時点でなっているのである。
今こそ、地方都市から東京へワーケーションに行くべき理由

ワーケーションでよく行政や地域のプレーヤーからも出るのが「地方創生」や「東京一極集中からの脱却」だ。特に私自身も東京一極集中は日本にとって良くないと考えている。また、東京が絶対的であるという考え方も好きではない。
そんな私でさえも、東京へのワーケーションはお勧めをする。主に以下の理由だ。
① 「人に会うワーケーション」を行いやすい
東京都内は、紛れもなく日本で一番多くの人が集まっている。そのため、東京都内に友人や知人がいないという人の方が珍しいだろう。そのため、誰かに会うことはできる可能性は高いし、紹介も受けやすいメリットがある。
② 何度行っても街の選択肢が豊富
私自身、東京はいくつかの同規模な街の集合体と考えており、その点が大阪や名古屋、福岡などの大都市と異なる部分だ。歴史的にもたまたま離れていたところが都市化によって都心と一体になった歴史を歩んできたエリアが多い(特に新宿、渋谷、池袋、品川など)。そのため、地域によってカラーが異なるため、自分に見合った街を探すことが可能だ。
③ 出張の延長から試すことができる
東京への出張の機会は、他の地域へ行くよりも多くの方にあると思う。そうなると、例えば後泊に1泊してみたりなど工夫がしやすく、出張ついでに自分自身がお試し的にワーケーションをすることができる。いわゆるブレジャーと呼ばれるスタイルとなるが、重く考えずにトライアルできるのである。

④ 宿泊により朝一という人混みと無縁の観光を楽しむこともできる
これは出張にも同じことが言えるかもしれないが、たとえば浅草などでは、人混みの時間帯を訪れるのか、朝イチの誰もいない時間帯を訪れるのかでは、ゆっくりさは大きく異なる。宿泊地次第であるが、朝イチの浅草観光で人の少ない時間帯で街歩きすることも可能。
⑤ 何よりも、一緒にやる仲間を見つけやすい
もちろん、滞在中1人でいても良いが、知人や仲間と一緒にやるのも楽しいのがワーケーション。東京都内で行うことで、知り合いを呼びやすいというメリットもある。
東京という街の性質上、人によっては、定期的に刺激を受けることができるという声もある。いつもの暮らしと違うポイントで刺激を受けられるのは良いメリットだろう。
何よりも自分自身がこの5つの利点を感じながら体験することができたのは非常に大きいし、全てでなくても、1つでも2つでもできることがあるならば、試しに行いやすいのも東京でのワーケーションの利点となる。これは紛れもなく、東京という世界最大規模の都市圏だからできることでもある。
私自身も、好きなワーケーション先の1つである東京

私自身は、東京も良いワーケーション先だと感じていて、仕事と共に地域での日常に触れることが多い。過去に体験した地域では、日本橋、赤坂見附、渋谷、新宿の4カ所だ。
たとえば、日本橋では、滞在箇所を日本橋の地で130年の歴史を誇る「ホテルかずさや」にステイ。東京のホテルは大手資本や外資などが増えてきている中で、江戸時代からの伝統を引き継ぎ、関東大震災なども経験した宿泊事業者だ。
2020年(コロナ禍の影響で2021年に延期した)東京オリンピックを見据えて、一度取り壊して新しく建て替えてリニューアル。東京のど真ん中でもこのように歴史を大切にする宿泊施設はたくさん存在している。

そうすると、隙間時間での街歩きも楽しくなるものである。近くには歴史ある日本橋の他、周囲がどれだけ高層ビルが増えていようが、その存在だけは残り続ける福徳神社など、あるけど細かいところに目がいくものである。
ちなみに、日本橋という地は非常に地域アイデンティティーが強い。それは地名にも残っていて、1947年に当時の京橋区と日本橋区が合併して現在の中央区になる際に、日本橋区が消滅するのに惜しむ声が多くあり、元々日本橋区だったエリアの地名に「日本橋〇〇町」とつくようになった。
東京都内であっても、ワーケーションを楽しむ基本の1つである「時間の余白」を持つことで、様々な発見や新しいアイディアが生まれてくるものである。

赤坂見附では、星野リゾートOMO3東京赤坂を拠点に滞在し、早朝の早起きは三文の徳ツアーに参加して、赤坂や溜池山王、永田町などを街歩きしてそれぞれの歴史的な物語を聞きながら、時代の変化を楽しみながら学んだりした。赤坂は元々武家地だった。
そして、永田町の地名が、このあたり一帯は武家地で、永田姓の旗本(はたもと)屋敷が並んでいた、つまり永田さんの屋敷が多かったことから、この町名が付いたという歴史も非常に興味深かった。当時の永田さんも数百年後には、まさか自分たちの地域が日本の政治を動かす中心地になるとは思ってもいなかっただろう。

新宿では、仕事終わりに東京の方々と一緒にゴールデン街のお店を貸し切って一緒に飲みに行ったこともあった。これはまさに、ワーケーションで行った地域の方とご飯を食べたり、交流するのと同じような感覚だ。東京へのワーケーションでも十分に実現できるのである。
東京周辺在住者が東京都内へ、マイクロワーケーションができる

東京周辺在住者が、東京都内へワーケーションに行くメリットは、直接的なワーケーションというよりも「マイクロワーケーション(MICRO WORKATION)」という考え方から語ることができる。「マイクロワーケーション」は株式会社パナソニックが提唱している考え方だ。
長時間かけて移動してリゾート地や観光地で働く「ワーケーション」とは異なり、近所の河原や公園など自分にとって「身近」で「心地の良い」場所で、気分を切り替えて仕事をし住む街の魅力を再発見する、新しい「はたらいきかた」の提案です。
私自身も、関西地方に在住だが、普段と異なる場所へ気分を変えて仕事をする機会が増え、街の魅力を再発見することができた。例えば、大阪梅田と京都四条河原町は普段よく行くエリアだが、間の高槻や千里中央、尼崎・西宮・神戸三宮、大阪難波など、少し異なる場所に足を踏み入れるということで、気分を変えながら仕事ができる。
いきなり遠方に行くのが難しくても、近距離で、日帰りで、場所を変えて仕事や暮らしをすることは十分に可能だ。コスト的にも安く、何度も変えていくことができる。それが「マイクロワーケーション」の1つの取り組みやすさである。

東京は、街が大きいため、ラインナップが非常に豊富だ。先ほど挙げた地域外の方が行ってみたいエリアである、新宿・大久保、銀座、浅草、渋谷、秋葉原、上野だけでも名前を挙げるだけ複数ある。その他の小さなエリアも含めて、全てを訪れた東京周辺在住の方はかなり少ないと思われる。
パナソニックのデザインチーム「FUTURE LIFE FACTORY」で、「マイクロワーケーション」は提唱された。当時チームに所属していた、発案者の大嶋佑典さんはこう語る。
長期間リゾート地や観光地に赴く従来のワーケーションとは異なり、近所の河川敷や公園など、住まいから1時間以内で行ける距離で、心地良いと感じる場所で仕事をするのがマイクロワーケーションです。より気軽にリフレッシュできますし、自分が住む土地の魅力を再発見する機会にもなります。
つまり、東京周辺在住の方は、東京都内でマイクロワーケーションをたくさんトライして、その後のワーケーションデビューに備えても良い、何度でも失敗できる練習もできるということでもある。
友人を集めて、コワーキングでもくもく仕事会をやってみても良いだろう。日常的に場所を変えていくことも東京だとラインナップが非常に豊富である。
東京へ行くワーケーションはもう「逆ワーケーション」じゃない

以前までは東京へ行くワーケーションのことを「逆ワーケーション」と揶揄しているケースが散見されていた。私自身は非常に違和感があったし、これはまさしくワーケーションをただの東京→地方での移動軸でしか考えていない、視野の狭い議論の中にあったのだろう。
しかし、今では日本国内においてもそういう風潮は減ってきており、東京以外の在住者のワーケーションの選択肢の1つに東京は既になっているということだ。地方都市在住のアドレスホッパーから見ると、東京はハブの地域で、一度立ち寄って次の目的地に飛ぶことも可能。
東京がワーケーション先であるという観点は、東京以外の地域のワーケーション実践者にとって非常に重要だ。海外から来る際は必ずその国の首都を調べるし、我々が海外に行くときは、その国の首都または最大都市は高い確率で調べるだろう。ましてや東京は都市圏人口が世界一でもあり、世界的知名度も抜群だ。
この観点は1つ重要なポイントがあり、よく自社のワーケーション向けサービスが関東地方在住者以外に利用されずに広がらないという声を聞く。答えは明白で、そのサービスに東京で使える拠点が限りなく少なく、東京以外の人が使いづらいサービスになっている点である。
これは今後海外の利用者にも同じことが言えてくるだろう。だからこそ、事業者にこそ、東京都内でのワーケーションをしてみて欲しいものである。

日本ワーケーション協会では、早い段階からこの観点には目をつけており、地域の公認ワーケーションコンシェルジュは東京都内として、渋谷からも誕生している。その小池ひろよさんは、東京でのワーケーションの思いを以下のように語ってくれた。
「日本の東京、東京の渋谷」。こんなにも多様性ある人やカルチャーと混じり合う地域は日本のどこをみてもないのではないかと思います。日本全国・世界から人が集まる渋谷。国際文化都市渋谷。日本の関係人口創出のみならず、世界との接点、Hubとなる機能をもつメディア的役割を担う渋谷。一方で、ローカルが活きている街だともいえます。
ワーケーションと聞くとなんとなく都心から地方へ動くイメージがありますが、地方から都心へワーケーションする方もいらっしゃいますよね!まだ知らない、知られていない渋谷の魅力をぜひお届けしていきたいです。

これからワーケーションはライフスタイル・働き方の一環として、コロナ禍以降も実践したいという方は増えてくるだろう。その中で「東京はワーケーション先じゃない」という認識を撤廃し、是非「東京も1つの素敵なワーケーション先である」という考え方が増えてくることを願っているし、それがさらにワーケーションの選択肢を広げることになるだろうと思う。
(参考)斉藤晴久さんの株式会社AnyWhereで展開する東京都エリアパス。東京都内のコワーキングを巡るのに使いやすいサービスの1つ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
