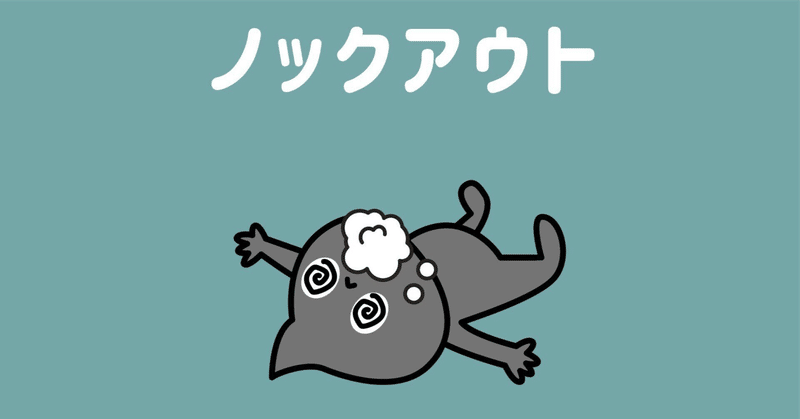
#556 メンバー固定化から考える教育の機会均等
私は中学生の頃に野球部に所属していました。公式戦は基本的に全てトーナメント方式で行われるため、どうしても試合に出るメンバーは固定化されてしまいます。
部活を選ぶ際に友人がテニス部を選んだ理由に、絶対に試合に出場できるからというものがありましたが、なるほどなと思っていました。
当たり前の話ですが、公式戦に出てプレーをしなければ本当の意味で技術の上達はありません。高校野球に限らず、トーナメント方式で行われるシステムは、ある一部の生徒のみにその機会が与えられ、結果技術の差がどんどん開いてしまうという現実があるでしょう。
そんな固定化に待ったをかけた出来事がありました。それは高校野球のピッチャーです。以前は一人のスーパーエースが全ての試合を投げ、二番手投手はほぼほぼ登板する機会はありませんでした。しかしながら、熱中症は身体の故障などを考慮して、今では球数制限もあり、多くの学校では多くのピッチャーを登板させるようになっています。
またプロ野球でも、キャッチャーはピッチャーとの相性に合わせて試合に出場するようになり、今までよりも多くの選手が試合に出場するようになっています。
『 矢野燿大氏 阪神が長年抱える「正捕手が固定できない」問題をド正論でバッサリ!』の記事の中では、阪神タイガース元監督の矢野燿大氏がキャッチャーの併用について持論を述べています。
「結果的に打順も出場メンバーも固定になるだけで始めから固定することがいいとは思わない」
ここで私がテーマとしたいのは、「教育の機会均等」という観点です。プロ野球ならいざ知らず、中学・高校の中で行われる活動は全て教育活動の一環です。何かを固定化することで、自らの成長の機会が失われてしまうならば、それは教育的な視点が欠如していると言わざるを得ません。
当たり前の話ですが、人は試合に出て活躍することでそのスポーツを面白いと感じることができます。技術が劣っているからといって試合に出れないというのは、何か違和感を個人的に感じる。
そんなことを考えならが、今日もビールを飲みながら野球をみる私。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
