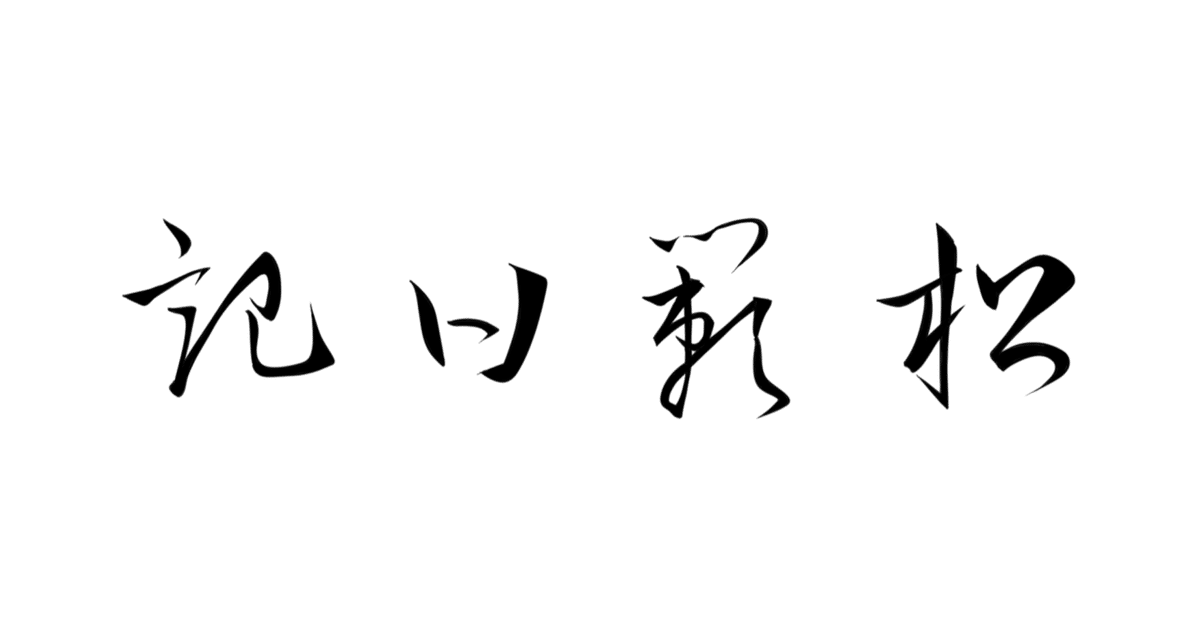
松籟日記 喫茶店と、『ノマドランド』を観た話
ノマド、という言葉が好きじゃない。
Nomad (英)やnomade (仏)とは、一説にはギリシャ語のnomadosを語源とする単語らしく、この単語の意味は『牧草地』である。転じてノマドは『遊牧民』を意味する単語として使われていた、最近までは。
近年、意義が変わってきた。高性能なラップトップやタブレットPCというのを駆使し、小洒落たスーツを着た人々がスターバックスやらタリーズやら、ヴェローチェやら、といった喫茶店のような公共スペースで仕事をしているのを見かけることがある。オフィスではなくそういうところで仕事をする彼らのことを正式には『ノマドワーカー』というらしいのだが、これが一人歩きして「ノマド」「ノマド」と馬鹿の一つ覚えのように流行った時期がある。
公共スペースで仕事をすること自体は別にいいと思うのだ。私も文筆の仕事をこなすときにたまにやる。ただ、オフィスがあるのに、そしてオフィスで仕事をした方が設備や環境の面では絶対に効率的なのに、敢えて披瀝するようにスタバでMacBookを広げるのは性癖の一種なのだろう。まず店に入ったら新作を一つだけ頼み、それを写真にとってインスタグラムにあげ、その一杯きりで粘りながら窓際で資本主義の権化のような高性能機器を見せびらかすのが『ノマド』とはちゃんちゃらおかしな話だ、と私はここ10年くらいずっと思ってきた。横並びで同じように私とラップトップを叩いていたとしても、珈琲をじゃぶじゃぶ飲んで頭を掻きむしり、血走った目で1ページを、1行を捻り出そうとする私とは優雅さが違う。それこそ、私が諦めて煙草を蒸しに席を外したら、あんなに仕事が捗っていた素振りだったのに忽然といなくなっていたりもする。全くもって不思議な生き物だと思う。
私は俗に『学生さんの街』と呼ばれる場所に起居していたし、或いは今もそうかもしれない。レストラン、ではなく定食屋があって、そこは揚げ物と量が多く、声の大きな女将がいる、そんな街だ。バーではなく居酒屋や焼肉屋が犇く一角だ。そしてこの街に忘れてはいけないファシリティが二つあって、雀荘と、喫茶店なのだ。
学生の場所は、社会の中で実は結構限られている。これは面白いことで、学生というのは無限にも等しい未分化な将来性と、何らの押し付けられたステイタスに束縛されない自由性を兼備したおよそ理想の生き物であるように思えて、キャンパスを出てみると居場所がないのだ。だから、古い大学のある街だったりすると、五月蝿いし不潔だし臭いし、その癖にシャイで学友以外とは目も合わせなかったりするし、金も持っていないからコーヒー1杯で本当に1日粘るような、そんな非生産的極まりない生き物である学生たちに優しい空気が流れている。その一つが先述のような、揚げ物を言わずとも大盛りにしてくれる気前のいい定食屋であり、口数の少ないリタイアしたマスターがゆっくりコーヒーを落としてくれて顔と名前を覚えてくれる喫茶店なのだと思う。それに甘えて学友たちと喧々囂々、恋に部活に学問に、と花を咲かせたり、或いは気に入りの本を一冊持って静かに読もうと思ったら隣にそんなグループがいたりして喧嘩になったりして……そういった取り戻せない時間を持つ者たちが、やがて大人になり、今度は違う形で、その時の学生たちと関わってきた、そういう一種の社会保障が『学生さんの街』であり、根幹に喫茶店、があった。
喫茶店が好きだ。神田神保町や本郷、三条、四条、追分、もはやそういったところでしか見られない、示相化石のような、古き良き喫茶店が好きだ。褐色の時間がとろとろと流れているような、あの場所じゃなきゃいけないのだ。そこでコーヒーを飲み、煙草を吹かしながら好きな本を読んだり、締め切りに追われたり、たまに悪友とチェスボードを囲んだりする、あの時間。煙草は吸えない店も増えてきたし、最近ではCOVID-19のゆえに飲食が軒並み何がしかの打撃を受けてはいるけれど、お洒落なーーといっても、メインの客層が友達づれのインスタグラマーよりは、何をしているのかわからない爺さんだったり、妙齢のやたら綺麗な女人だったり、或いは大人びたセーラー服の少女だったりが、1人で長居できるようなーー喫茶店で、ケーキとコーヒーを楽しむのも、これまた悪くないものだ。
懐かしい風景がある。誰かの記憶だが、大学の北門を出たところにある、パンの美味しい喫茶店だ。そこに、近所の神社の境内で毎夏行われる、『納涼古本まつり』と銘打った古本市で蒐集してきた蒐集してきた国枝史郎の『蔦葛木曽桟』と『神州纐纈城』を持って、額に玉の汗を浮かべ、しかし目当ての古本を掘り出してきた達成感と、これから誘われる文学の世界への期待にフラットな胸を膨らませて走り込んでくる、姫カットの学生がいる。そんな、夏の風景だ。
私にカフェやコーヒーショップではなく、『喫茶店』というものに並々ならない感傷があるのは、あそこが渾沌から具象を掴み取る、そういうクリエイティブな営みと極めて親和性がよいからなのかもしれない。本質はそこで、だから学生たちは別にコーヒーが美味いかどうかは関係なく、チェーン店よりもちょっと高めの一杯であっても喫茶店へと足を運ぶのかもしれない。尤もあやつらはその一杯しか頼まなかったりするのだが。
安定は桎梏であり、自由は欠落なのだ、と思うのだ。得てして束縛は欠落ではなく、欠落は束縛ではない。
縛められない、背負うものがない、ということはぐらぐらとしていて、身軽でどこにでも飛んで行けるようで、群れをなさなければたとえ死んだとしてその鳥の亡骸は誰にも気付かれず、悼まれることもなく、土くれに帰るだけだ。
ゆえに私は簡潔に言って、自由の真似事が嫌いなのだ。
特に、安定した土俵から自由の真似事をする者が好きじゃない。憧憬を語るのは万人の権利であり構わないのだが、贋作に金を払うのは趣味が悪いし学がないではないか。ゆえに『ノマド』改め『ノマドワーカー』はネガティブに観てしまうし、何よりその言葉の響きが好ましくない、と思っていた。
この敵愾心にも似た埋み火は、個人的な事情によるものも大いにあるとは思う。むかし、数学を教える塾を作ろう、という話をして計画を煮詰めていたときに、『ノマド』を新しい働き方だ、と吹聴し、喫茶店で仕事をするのが格好いい、と思っている性癖の輩に、肝煎りのそのプランニングを蹂躙され、横領され、果てにその話がなくなる、という頓挫を経験したことがあって、袈裟まで憎い、というだけの可能性はある。
そんなわけで、『ノマドランド』という映画、これが金獅子賞を取って巷間の話題に上る前から認知はしていたが、観ようとも正直思わなかった。友人に誘われなければ、きっと観なかったのではないか、とも思う。まず、どこかの誰かが書いた煽りが酷いじゃないか。『これは現代のノマドである』、だって。「現代のノマド」なんて言われたら、うっ、フラッシュバックが。
観た後では、誘ってくれた友人に感謝している。私は狐の怪異だが、彼女は齧歯類の怪異のようなもので、知る人には飛ぶ座布団の名を冠して「鼯」と呼ばれている。この悪友・鼯が「『ノマドランド』観にいこう」「今日いこう」「今から行こう」と言い出さねば、きっと私はこの作品を観ることがなかった。
ノマド、とあるが、別にスタバの阿呆たちをフォーカスしたものではなかった。むしろ、「現代のノマド」とは、元の語義の『遊牧民』に近いものとして使われている。
2008年、アメリカの大手証券会社が破綻したあおりが世界を襲った。ネバダ州の工場城下町エンパイアで働いていたファーンも、その恐慌に翻弄された一人であった。エンパイアの街が封鎖され、職を失い、夫との思い出の家も追い出された彼女は、わずかばかりの家財道具をバンに積み込んで、糊口を凌ぐべく、日雇いの仕事を探し広いアメリカを流浪する生活を始めることになった。高くない給料、選べない仕事、高齢者と呼ばれる年齢には堪える肉体労働の疲弊、病や怪我と隣り合わせの日々。その中にあっても、彼女たち「現代のノマド」は人間の尊厳を失わず、似た身空の互いを手を取り合って扶助し、友情を育み、生きていく、そうした知られざる実情を淡々と描出していく映画、それが『ノマドランド』だ。
『あの頃ペニー・レインと』や『スリー・ビルボード』で高い評価を受けているフランシス・マクドーマンドが主人公ファーンを演じている。また彼女は原作となった書籍を映画化する際の指揮取りも自分でしており、これによりマクドーマンドは製作者と主演の両方でアカデミー賞を受賞した初めての俳優という栄誉を手にすることとなった。
助演には『グッドナイト&グッドラック』などを代表作とするデヴィッド・ストラザーンが起用されている。私は自閉症を扱った『テンプル・グランディン』での彼の演技が好きだった。彼が演じた「デヴィッド」もまた、ファーンと同じような境遇を背景に、バンで生活し日雇いに従事する老人である。
そして、この2人を除き、ファーンが関わっていく高齢労働者たちは、実際に車上生活を送っている人々である、というところが、この作品に凄絶なリアリズムを賦与している由縁だ。演技を体験したことのない人間、というのは数えるほどしかいないだろうが、演劇を体験したことのある人間、というのはそう多くない。ゆえに、この演劇未体験の人間を役者として起用することは、味を変えるという点で刺激的なスパイスになり得るが、それが料理本来の味を損なうことも多々ある、諸刃の剣である。斬新さだけに飛びついて素人を起用し、監督の手腕が問われるという意味での問題作になったようなものは邦画では枚挙に遑がないが、そういう意味でも『ノマドランド』は非常にエキセントリックで影響的だ。本作がスパイスによって味が損なわれることがなかったか、それはぜひスクリーンで確かめて欲しいところだが、少なくとも私から言えることは、この素材無くしてこの味にはならなかった、ということである。
ヴェニス、トロントと連覇してアカデミー賞に乗り込んだ『ノマドランド』は、まるで良血の競走馬のようだが、理想の血統を掛け合わせることで洗練による表現型の収束を継代的に企図してきたブラッドスポーツの代表格である競馬と、最近のハリウッドを始めとする映画業界のトレンドは真っ向から相反する、といっても良いだろう。『多様性』という言葉が取り沙汰されるようになったのは、その議論の渦中に身をおかなくとも知っているはずだ。ディズニー作品ですらその類にもれないが、これはかなりトラップを含んだ論調である。つまり、あらゆる作品が多様性を標榜しようとする、これは前提として尊重されるべきことではあるのだが、そのやり方が問題だ。アメリカのような多人種国家のヒューマンドラマを描くなら、コーカソイドから有色人種まで幅広くアクターをキャスティングすることも理に叶っている。しかしながらこれが島嶼国家の鎖国下のドラマを描こうとしたならばどうだろう。なんとかしてインド人を起用しよう、とシナリオや世界観、果てには歴史認識まで歪めてしまうのは、本末転倒だ。
これは極端な例ではあるのだが、そもそも理想の多様性とは『多様な群がある』状態であるはずで、人工的に作り出したわざとらしい今般の多様性は、『多様な要素を持つ、似たような群がたくさんある』という状態に陥っている。例えるなら展示に失敗した水族館だ。身近な沼や川の魚、湖の魚、湾の魚、浅い海の魚、深い海の魚、温暖な海の魚、寒冷な海の魚……そうした生態ごとに調えられたたくさんの水槽を並べ、そこでそれぞれの差異や、似たところを議論し、それがどのようなバックグランドに起因するものか、どのような環境に適応するためにそのような形や生活となったのか、つまりは自然発生したルールがどのように生物の種のあり方や、他の種との関わり方を育んできたのか、そういったところに目を向けるべきが多様性的な考えである。それに対し、『わざとらしい多様性』とは、「どの水槽にもいろんな環境で生きる魚を入れておかないといけない」という勘違いに基づいて、全ての水槽に深海魚からサワガニまでを十把一絡げにぶちこんだ状態だ。しかも、同じフロアのありとあらゆる水槽が、そういった混沌の状態あるのだ。それがどのようなトラジェディを惹起するかは明白で、寒冷な水槽で温暖な汽水を好む魚は生き辛く、深海の圧では表在する扁平な小魚たちは生きられまい。それが、今の『多様性標榜症候群』に陥った社会のひとつの風刺だ。
間違った認識による似非多様性に毒され始めた今日の映画業界に一石を投じる作品としても、私は『ノマドランド』を好意的に観た。その理由の一つは間違いなく監督の腕によるものであり、紐解けばそれは監督の半生によるものなのだと私は考える。今回、原作に惚れ込んだマクドーマンドが監督に起用したクロエ・ジャオは、北京に生まれ、カウンターカルチャーとしての欧米大衆文化に憧憬を抱き、ロンドンの寄宿学校で学び、ロサンゼルスの高校を出、アメリカのサウスハドリーにある大学で政治を学んだ後、ニューヨーク大学で映画を専攻した、というキャリアを持っている。ダイバーシティに対して経験の量と質が違う彼女の視点は鳥瞰的であり、その人間観察は的を射ていて天才的ですらある。多様性とは多くの人種を一つの画面に収めることでは決してないし、生物学的な女性と男性を半々にすればいいわけでもないし、登場人物に必ずセクシャル・マイノリティとして設定したキャラクターがいれば『多様性』が守られるわけではない。そんな当たり前のことを忘れつつある国際社会に対してジャオの作品はシニカルだ。人間がいて、生活を営む。そのスタイルには長年の習慣があり、そういう行動を取るに至った経緯がある。人に歴史あり、とはいうが、趣味や嗜好、使用言語やものの考え方、金銭に対するスタンス、他者との関わり方……そういったあらゆる要素がその人を作り、その人の経験してきた過去の日々とその人の今日とは不可分である。だから、その人を尊重しようとすることが、その人のこれまで一切の体験を尊重することになる。尊重とは思考を停止して彼や彼女と付き合うことを意味するのではなく、善も悪もある要素のひとつひとつに理由があり、その選択の行き着く先が眼前の、自分とは異なる人間を形作っているのだ、と理解することである。
ゆえに穿った見方をすれば、日頃の行いの所為でこの作品を絶賛しなくてはならない層、というのも映画業界にはいる、ということである。彼らは何かを理解する必要はなく、『ノマドランド』を称賛しなくてはいけない。だってあれだけ観たかったはずの多様性がここにはあるからね。
それはさておいて、自由と多様、この普遍的で、それゆえにクリエイターが取り上げたがるが迂闊に手を出すと大火傷を負うテーマに対する非常に深い洞察が、少なくとも根幹のところで3人6つの目の視点から伺える。それは主演・製作指揮のマクドーマンドによるものであり、監督のクロエ・ジャオによるものであり、そして原作者のジェシカ・ブルーダーによるものだ。その全てを盛り込んで食傷モノにしてしまうこともできたはずだが、それをしないのが監督のセンスというものだろう。教条的で自己陶酔の激しい作品としてではなく、コアのところにシリアスな認識があっても、それを上手く『映画』という、あくまでエンターテイメントのひとつに落とし込む手法がずば抜けて上手い、という、それだけでもこれを観る価値がある。平たく言えば、『細かいことはわからなかったけど、すごくいい映画だった気がする』、これを思わせる手管、ということだが、そういう意味では近年のものだとマイケル・グレイシーの『グレイテスト・ショーマン』に近しい。シリアスな題材を『正しく』扱いながら、映画としての興行と両立させるのは至難の業で、製作陣の手腕が露骨に問われるところだ。
緩衝に大きな役目を果たしているのは、アメリカの雄大な自然だ。そしてそれを、本筋を使って上手いこと引き立てている。具体的に言えば、現代資本主義の象徴たるアマゾンの大工場で超大規模の流作業に従事するシーンがあるからこそ、ファーンが後半で仕事をする自然公園の雄大さが映えるのだ。機能性の優れた大型キャンピング・トレーラーを弄って楽しむファーンやリンダをフォーカスするからこそ、荒地や砂漠、といった人知を超えた広大な風景を行く矮小な存在が網膜に沁みるのだ。私が特に驚いたのは、本当にラスト近くの数シーンなのだが、遺棄されたエンパイアの街に戻って、荒廃した元の家を訪ね、家の裏庭から砂漠が見える景色をファーンが見に来るところだ。死期を悟った友人が、残る僅かな気力と体力を振り絞るように、もう一度見たいと言っていた大自然を見に行ったことに触発されるように、ファーンは封鎖されたエンパイアを訪れるのだが、そのシーンの最後は、固定されたカメラが砂漠や連なる山の峰の遠景を映し、そこを左に向かってファーンの後ろ姿が遠ざかっていく、というものだ。主人公をカメラで追ってしまわないのがいいし、人間を画角の中央に収めないのが抜群にエモーショナルだ。そうして気づかせるのだ、ファーンを始めとする、リタイア層をも巻き込んだ金融恐慌、そういった社会的災害すらも人事を超えたところにあるという点でまた『自然』であるのだと。
万物は流転する。人間は単為生殖もできないし、もはや狩猟採集経済には戻れない。人とは関わっていかなくてはいけないのだが、その関わり方すら、文明や経済によって変遷してきたし、今も重大な過渡期にある。自然とは『人の手が触れていないもの』ではなく、『人が生活に合うように手を入れる余地のあるもの』のことであり、その定義に即せば山や海や砂漠だけを自然だと思い込むことは極めて不自然だ。先行きの見えない未曾有の公衆衛生上の一大事にあり、動員数を大きく減らした映画祭だったが、不動の評価を得た作品がこれである、ということは、人間同士の関係性、ひいては人間と自然の関係性に対して、苛酷な希望を我々に示してくれるものなのではないか、とすら思う。
悪友が観賞後に言った。
「人の心だけが動いていくようだった」。
それを聞いた私は、心の運搬に馬ではなくキャンピングカーを用いるようになるなんて、西部劇も変わったものだな、と思ったのだった。
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
