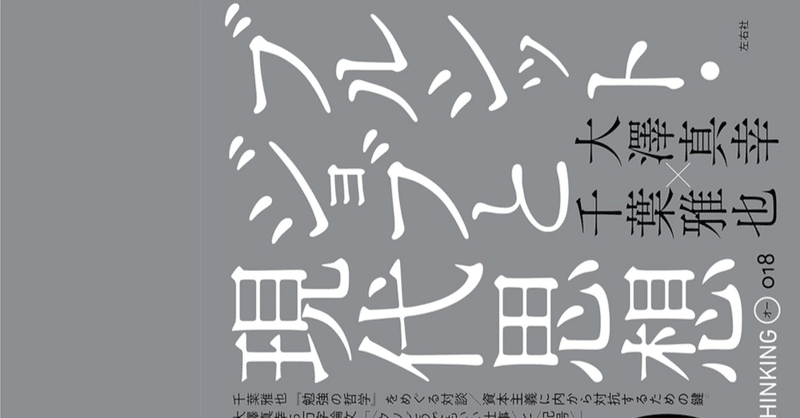
ブルシット・ジョブと現代思想
概要
近年、「ブルシットジョブ(訳 : クソどうでもいい仕事)」というワードが知られるようになってきた。
ブルシットジョブは、「働いている本人はその仕事に意味が無いと思っているが、体外的には素晴らしい仕事であるかのように振る舞わなければならない仕事」と定義される。
ある調査によると、被雇用者の3分の1は自らの仕事がブルシットジョブ(BSJ)だと考えている。というデータが得られたらしい。
BSJはその定義から仕事の性質によってではなく、働いている本人の認知によって現れるものであり、
重労働・低賃金のようなシットジョブ(SJ)とは異なる。
むしろ、世間的には、どちらかというと羨ましがられるような、華やかで高賃金な仕事にBSJは多いとされている。
もし、被雇用者の3分の1という多数の人々が、自分の仕事をBSJとして考えているのであれば、それはパーソナリティ等の問題ではなく、社会システム上の問題であると推察される。
BSJはなぜ生じるのか、BSJはどのように乗り越えることが出来るか。
これを考える本。
BSJの例
BSJとしてよく挙げられる仕事には以下のようなものがある。
(働いている本人から、私の仕事はBSJだ。と報告されたものをタイプ別に分類したもの)
尻ぬぐい
誰かの失敗のリカバリーをメインに担当する仕事書類穴埋め人
名前の通り。形式的作業を淡々と処理する仕事タスクマスター
勤務時間いっぱいまで働いてもらうために、次々とタスクをひねり出す仕事...etc
一般的には、高い地位・高い給料を備えた、世間的には羨ましがられるような役職にこれらの仕事は多いとされる。
金銭的価値とBSJ
高い給料を貰えるにも関わらず仕事に対してモチベーションが上がらないBSJと関連する、以下のような実験がある。
障害児援助のために募金活動を行うとして、高校生を集め3グループに分ける。
グループ1 : 募金活動の意義についてのスピーチを聞いた後、募金活動を実施する
グループ2 : 募金活動の意義についてのスピーチを聞き、寄付額の1%がバイト代としてもらえると知らされた後、募金活動を実施する
グループ3 : 募金活動の意義についてのスピーチを聞き、寄付額の10%がバイト代としてもらえると知らされた後、募金活動を実施する
また、各グループは、他のグループの存在を知らない。
通常、この様な設定の時、貰える金銭的報酬の大きさが、そのままモチベーションにつながると考えられる
そこから、募金活動に関する熱心度は
グループ3 > グループ2 > グループ1
であると推察される。
しかし、実際の結果は、
グループ1 > グループ3 > グループ2
という順で熱心度(寄付金の総額)は多かった
グループ3 > グループ2
の関係は、金銭的報酬の大小で説明がつきそうだが、
グループ1 > グループ3
の関係が一体なぜ生じるのか。
これが、この実験が示唆するものだった。
資本主義社会がBSJの元凶
募金活動に関する実験から、BSJについて考察を深められるポイントが2つある
1つ目は、なぜ金銭的報酬の無いグループ1が最も熱心に活動を行っていたか
BSJが示すように、金銭的報酬とモチベーション必ずしも正比例しない。
であれば、BSJには何が足りないのか。その仕事に対するモチベーションは何で上げることが出来るのか。
これを考察する材料となる。
2つ目は、もし、あらかじめ3グループの情報が開示されていて、好きなところに入れると言われたらどれを選ぶか。
恐らく、最も金銭的報酬の高いグループ3に入ることを希望する人が多いはず。
しかし、その希望に反して募金活動に対する熱心度は、純粋に募金活動のみを目的に行う人々の方が高い。
BSJが年々増加傾向にあることと、人が選びたがる仕事の特徴との関係が、この実験には反映されているかもしれない。
最終的に本書では、
「資本主義というシステムによって生じる、目的と手段の倒錯がBSJの元凶」
と結論付けている
まず前提として、人間は自己成長や他者との関りに関して高いモチベーションを持っていると考える。(高次の欲求)
また、自ら積極的にそのような活動に打ち込んでいる時、人は幸福感や満足感を感じる。
例えば、趣味に没頭する時、友達と食事をする時などが挙げられる。
しかし、自己成長や他者との関りのような「高次の欲求に紐づく本来的な価値」が、資本主義社会というシステムの中では、「生存という低次の欲求に紐づく金銭的価値」となって覆い隠されてしまうことがある。
つまり、自らを充足させるために積極的に行う「意欲的活動」が、資本主義社会で生きる(即ちお金をある程度得る)ためにやむを得ず行う「労働」に成り下がってしまう。
まとめ
"お金を稼ぐこと"それ自体は、本来的には手段なので、目的としては色褪せている。(お金を稼いだ後に何かがあるはず)
しかし、資本主義社会においては、"お金を稼ぐこと"が目的であるかのように表象する。
すると、自己成長や他者との関り等の仕事に備わる本来的な目的が、"お金を稼ぐこと"という色褪せた目的で覆われてしまう。
こうなることで、その仕事の本来的な価値を見失い、BSJと認知される。
と、この本では主張する。
では、BSJを乗り越えるにはどうすればよいか。
究極的には、資本主義社会からの脱却ということになるが、それは到底無理。
となると、個人の認知を変えるしかない。
今携わっている仕事の"本来的な価値"に気づこう。そのために勉強をしよう。
と締めくくる。
感想
所々良いと思うポイントはあったけど、全体通しては微妙な印象。
この本は大きく2部に分かれていて、1部が対談、2部が論文という構成。
1部は、BSJを乗り越える手段としての"勉強"というテーマで対談がされているのだけれど、
正直、要らないのではと思った。
2人の人間が、お互いに、哲学やってます感の応酬を繰り広げているだけで、イマイチピンと来なかった。
一見さんお断りみたいな、置き去り感あった。
2部は、中盤良かったけど、終盤微妙だった。
中盤の、金銭的報酬とモチベーションに関する実験を引いてきて、BSJと関連を見出したこと。
人生の目的足り得る本来的な価値が、単に生きる手段としての金銭的価値に覆われてしまうことで、モチベーションが下がるのではないかという考察。
この2つは興味深かった。
ただ、終盤の結論に至る材料が少なくて、イマイチ納得感が薄い。
非資本主義社会にBSJ的なものがあるのかとか、昔はBSJだと思っていたけど今はいい仕事だと思っている。みたいな人は何が理由でそのような変化が生じたのかとか、そういった情報もあればよかったかもしれない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
