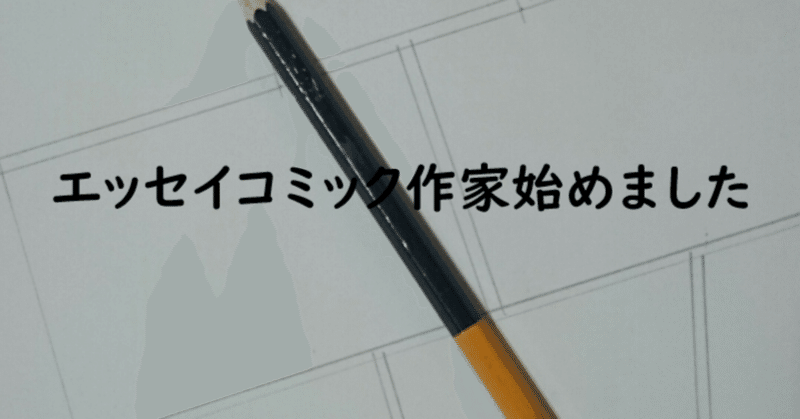
エッセイコミック作家始めました 第一話
あらすじ
プロの漫画家を目指し漫画家アシスタントのバイトをする灰谷由には一馬という一人息子がいる。一馬は理由があり実家の祖母が育てていた。
ある夜、灰谷はもう一つのバイト先で強盗事件に遭遇し、目の前で大切な友人を亡くしてしまう。逃げた犯人には自宅で待ち伏せされ格闘し、犯人逮捕に貢献した。
その話を漫画にした事をきっかけに、念願の漫画家デビューを果たす。
彼女が連載する雑誌や新聞の発行数は伸び、メディアへの露出も増えていく。大好きなアーティストとの対談も果たした。
しかし売れる毎に彼女の才能を疑う噂が拡がる。
息子を自分のもとに戻した灰谷はネットに広がる誹謗中傷に耐えながら自分のやるべき事を見つけていく。
日曜日、いや既に日付が変わっているから月曜日の午前一時前。そろそろ最後のウエーブがやってくる時間帯だ。ウエーブとは言葉の通りで波の事。つまり店に客が沢山やってくる時間の事だ。
コンビニには何度か集中的に集客がある繁忙時間がある。例えば会社員が弁当を買いに来る昼の休憩時間や、帰宅ラッシュ時などがそうだ。ここは学生街でもあるから、通学時はかなり混むらしい。そんな繁忙が予想される時間はシフトを厚くして来店に備えている。その最後の時間がこの時間なのだ。それがウエーブ。他の時間帯の人達の事は分からないが、それを私等深夜帯メンバーがウエーブと呼んでいる。
今現在、店内に客はいない。五分程、ウエーブを待っている状態が続いている。
おでんは全商品二割引、菓子パンのシールを集めてプレゼントが貰えるサービスの案内アナウンスが、静かな店内に響いている。
東京メトロ東西線早稲田駅の出入り口が、自動ドアの向こうに見える。何番出口だったかは忘れた。滅多に地下鉄を使わないから、そういう事を機にしていない。終電から降りた乗客達がそこからぞろぞろと出てくる。とはいえ。休日の終電の乗客は少なく、ウエーブは漣ほどだろう。市場も休んでいるので納品も少ない。私一人でもこなせなくもないが、防犯上の理由もあって二人態勢にしている。
東京は物騒な事件が増えている。闇バイトとかいうやつらしく、それに登録してしまった若者は、会った事の無い指示役の指示に従い強盗事件を起こす。奴らが狙うのはお金のある高齢者宅か高級貴金属店なのだが、何があるか分からないから念の為に防犯体制を強化しなさいと本部から通達が来たらしい。
今日の相方は杉山昇。身長180を越える大柄な男。齢四十の売れない劇団員だ。超一流大学を卒業し、一流企業に入社したものの、役者への夢が捨てきれず会社を辞めて役者業に専念している男。でもなかなか役者では食べてはいけず、こうやって深夜のコンビニでバイトをしている。まぁ、私が言えた事でなないが、実に勿体無い生き方をしていると思う。
終電が遅れているのだろうか。なかなかウエーブが訪れない。変な格好をした男が一人、車道を背にガードレールに座っているのが見える。きっと恋人か誰かが帰ってくるのを待っているのだろう。
杉山はレジの前で煙草の棚にもたれながら、何かをしている。私は月曜発売の雑誌を並べ終え、他の商品の陳列を整理しながら、横目で奴の行動を追っている。私は奴が何をしているかを知っている。奴は客が置いていったレシートを真四角に切り、太い指を起用に使いながら折鶴を折っているのだ。それを小箱に集めて喜んでいる。ちゃんと処理をしてくれたらいいのだが、処理を忘れる事が多く、早朝のメンバー達に「深夜は暇でいいですね」なんて嫌味を言われてしまう。
杉山と私の付き合いは長い。実はこのバイトを紹介してくれたのも奴なのだ。十年程前になるだろうか、奴の所属する劇団の公演ポスターのデザインを私がしたのだ。それから奴の劇団との付き合いが始まり、杉山と親しくなった。
私は奴の秘密を二つ知っている。正式に言えば奴の周囲の連中は皆知っているのだが、皆がそれを知っている事を奴は知らない。
まず一つ目は圧倒的に演技力がない事。
これは役者にとって致命的な事だ。奴は恐ろしいほど芝居が下手なのだ。私は何度か奴の所属する劇団の公演を観に行った事があるが、彼の芝居の下手さは観ているこっちが赤面してしまう程だ。皆はそれを知っている。それでも演出家が使い続けているのには何か別な理由があるのだろう。まぁ、確かにあの大きな体は舞台映えする。妙に彫りの深い顔は、昭和の時代劇俳優のようで特徴はある。やけに明るく能天気な性格は、人望にも繋がっている。劇の内容に直接影響しない変なキャラによく使われる。
奴のもう一つの秘密は、ゲイである事。まぁ、これは単なる推測にしか過ぎない。推測といってもかなり信憑性の強い推測である。奴はいい歳をして未だ独身、浮いた噂もない。奴の口から女性の理想や好みなどの発言を聞いた事はない。口調や仕草がオカマっぽい。男性と寄り添いながら歩いている、という目撃情報も多数ある。そしてこんなに近くにいる私を口説いてこないが何よりの証拠だ。
因みに私も奴に一つだけ秘密を握られている。何の拍子だったか忘れてしまったが、私は奴に、母親と確執がある事も、その母親が訳あって私の子供達を預かっている事も言ってしまった。ただ、何故そうなったのかは訊いてこない。興味が無いのか、それとも奴なりに気を使っているのか、そもそも忘れてしまったのか定かではない。
奴は外の様子に気も留めず、ただひたすら折鶴に集中している。と、いう私も書籍コーナーの一冊が気になって、業務への集中が散漫している。
『週刊少年スカイ』が黄金の光を放ち、私の購入を待っている。
『週刊少年スカイ』は私が小学五年の頃から、二十五年間欠かさず読んでいる。ご存知少年漫画誌の金字塔である。ここから沢山のヒーローたちが誕生し世界中へ旅発っていった。そして私が漫画家を志したきっかけを作ってくれたのも『週刊少年スカイ』なのだ。
身勝手なあの女の下で生活しながら、現実から逃避できたのも『週刊少年スカイ』のおかげだ。
私は女子なので当然、少女向けの漫画雑誌も読んでいるが『週刊少年スカイ』には何か特別な魅力を感じているのだ。
「ねえ、ちびちゃん」
ヒーローとは程遠い大柄馬鹿野郎が突然声をかけてくる。私は聞こえないふりをした。
「ねえ、ちびちゃん」
奴は更に大きな声で呼んでくる。さすがに無視を続ける訳には行かない。
「だから、そのちびちゃん、って言い方止めてくれない」
奴は色々な言い方で私を呼んでいる。苗字の灰谷から『はいちゃん』と呼んできていた時期も、名前の由から『ゆうぽん』と呼んできた時期もあった。漫画家である事から『まんちゃん』とベタでくだらない呼び方をしていた事もある。そしてここ数年は新しい呼び方をしない。どうやら『ちびちゃん』という呼び方に落ち着いたようだ。
「だってあんた、ちびなんだもの」
確かに私は背が低い。そして童顔でもある、化粧気もなく三十を過ぎた今でも未成年と間違えられる事がある。背が低い理由は遺伝もあるだろうが、私が運動を避けて生きてきたという事も要因の一つだろう。
「それに声がでかい。お客さんがいたらどうするのよ」
「だってお客さん居ないじゃん」
ああ言えば、こう言う。こちらがどれだけ正しい事を言っても、理屈を重ねて論破してくる。私は奴のそんなところが嫌いだ。
「それで、いったい何?」
「なんか暇ねぇ」
「きっと終電が遅れているんだよ。それに日曜だから」
「もう月曜だけどね」
杉山はまるで悪戯小僧のような顔で言い返してくる。
失敗した。またやってしまった。私は自分の発言を後悔した。
奴は根っからの国語オタクだった。勿論文芸も好きだが、言葉自体に深い興味を持っている。子供の頃は国語辞典を愛読していたらしい。大学では文学部で日本文学や哲学を学んでいた。演劇サークルに加入したのも、そもそもは言葉の可能性を極めたくなったかららしい。
細かい言葉の違いを指摘してくる。そんな時の奴の言い方や態度が憎たらしくて苛々する。私はその無意味な苛立ちを避けるために、細心の注意を払っていたつもりだった。
因みに私はこれを『スーパーボールの原則』と呼んでいる。壁に真っ直ぐにぶつけたスーパーボールは、跳ね返って自分に当たる。
「早く読みたいんでしょ?」
古いミステリードラマの探偵のように私の心を読んで、嬉しそうにしている。右手を半分だけ閉じて、顎の前で揺らしている。恐らくパイプでも咥えているつもりなのだろうが、私には餌のバナナを食べるゴリラにしか見えない。
「えっ、なんの事」
私はあえてとぼけてみせた。正直、奴と話す事が面倒になっていた。
「今のお嬢さんは、漫画が読みたいはずです」
奴は芝居を続けている。また、やってしまった。自分の意思に反し、奴の遊びに乗ってしまった。短時間の間に『スーパーボールの原則』が二度も証明されてしまった。
しかし天は私に味方した。待ちに待ったウエーブがやってきたのだ。
駅の出口から乗客が出て来た。自動ドアが開き、先頭の男が入ってくる。
「いらっしゃいませ、サンライズマートへ、ようこそ」
私と杉山が合わせてそう発して、探偵ごっこは終了した。
弁当、惣菜コーナーに向う者、ドリンクコーナーで缶酎ハイや発泡酒を買い物カゴに入れる者、明日の朝食として消費期限を気にしながら菓子パンやサラダを買う者など客層は様々。水商売風の女性はATMで売り上げを入金している。一直線に書籍コーナーに向かい『週刊少年スカイ』など月曜発売の雑誌を立ち読みする者もいる。彼は『週刊少年スカイ』を買うのだろうか、立ち読みで終わらせてしまうのか私は心の中で賭けてみる。不謹慎かもしれないがこれくらいの楽しみを許して欲しい。
ふと思い出した。
ガードレールの男は何をしているのだろう。
私は書籍コーナーを気にしつつ外を見た。ガードレールの男はまだ同じ場所に居る。待っていた人は来なかったようだ。もう終電は出ている。間もなく出入り口のシャッターが下りるはず。そんな心配をする間もなくレジに客が並び始めた。
「いらっしゃいませ、お預かりします。ポイントカードのご利用はございませんか?」
買い物カゴの中の商品を取り出しバーコードをスキャンする。
「お惣菜は温めますか」
漫画を描く事意外に何のとり得もない私だが、流石に五年以上も勤めていると手際が良くなっている。
「お会計、千二百六円頂だいいたします。お支払いは現金で宜しいですか。二千円お預かりいたします。七百九十四円のお返しとレシートでございます」
最近では新人の教育を任される立場になって、そのお陰で時給が五十円上がった。本人には絶対言えないが隣にいる無能な先輩より時給が高いのだ。
「有難う御座います。またお越し下さいませ」
三十分ほどのウエーブが終わると、私はレジを出て商品の補充を始めた。補充といってもそれ程商品は減っていないので、陳列の整理に重きを置いた。
杉山はまた折鶴を始めようとした。まだ店内には二名の客が居るのに、いったい奴は何を考えているのだろう。人間性を疑いたくなる、いや、もう既に何度も疑っている。疑いまくっている。奴のいい加減な性格、仕事に対する態度、写楽の浮世絵のような顔、才能のない事に気付いていない事、全てが嫌いだ。自分が駄目人間なくせに、ひとのミスを執拗に責めてくるところなんて秀逸に嫌いだ。そんな杉山でも漫画の凄さを認めている事だけは、意見が一致する。
―そう、漫画は数多ある表現媒体の中で最強なのである―
だってそうでしょ。小説は文字でしか表現できないよね。主人公がどんな顔をして、どんな服を着ているかなんて正確には表現できない。それらは読者の感性にお任せしないといけない。
杉山達がやっている舞台だってそう。舞台という限られた空間での表現には限界がある。場面転換や役者の数などに制限がある。
映画やテレビドラマだってそう。どんなに素晴らしい脚本があっても、下手な芝居をされては中身が半減する。中途半端なアクションやCG映像はかえって観る人が冷めてしまう事がある。
しかし漫画はその限界を簡単に超えてしまうのだ。そう、宇宙空間で壮大なバトルを繰り広げる事も、十メートルを超える巨人を従えて冒険に出る事も、二百キロの剛速球を投げる事も簡単に出来てしまう。主人公の顔も、着ている服も読者任せでなく細かく伝える事ができてしまう。それが漫画なのだ。杉山はそれを理解してくれる数少ない友人の一人だ。国語オタクの読書好きで、役者馬鹿でありながら、漫画最強説を唱える可愛い奴なのだ。
「もう時間だから1レジを持って行くね」
「そうね。よろしく」
私は入り口に近いレジ、通称1レジのドロアを引き出した。そのレジの横に『隣のレジをご利用下さい』と書かれたパネルを置いた。その時突然、ドロアに杉山が『週刊少年スカイ』を乗せてきた。
「何これ、どうしたの?」
「ちびちゃん、今週誕生日でしょ。ちょっと早いけど誕生日プレゼント。ちびちゃん、たんおめ」
そう言いながら更に折鶴を乗せてきた。私はそれを息で吹き落とし、足で蹴る。
「これが誕生日プレゼントなの!誕生日プレゼントならもっと高い物を買ってよ」
私はあからさまに首を捻った。
「高い物って。ちびちゃんなんか興味あったっけ?」
私は考えた。ただ黙って終わりにしたくない。
「USAGIちゃんのチケットとか」
良かった。杉山に言い返す言葉があった。USAGIちゃんとはUSAGI CITYを略した言い方で、USAGI CITYとは私が大好きな男女四人組バンドの事だ。付き合いで他のバンドを見に行った時に、たまたま見つけてはまってしまった。確か、この時も隣には杉山が居たような記憶がある。うん、間違いない。杉山の知り合いのバンドを見に行った時だった。次ステージに上がったUSAGI CITYと衝撃的な出会いをした。
アニメソングのように軽快で元気丸出しの熱いメロディに、カエデの歌唱力が私の心を掴んだ。後でカエデが声優の勉強をしていた事を知って納得した。杉山の知り合いのバンドの事は1ミリも覚えてないけど、USAGI CITYの演奏はしっかりと心に残っていた。
「えっ、高価なの?」
「うん、今度のワンマンは6000円」
今思えば、才能を信じながら誰からも評価されず燻っていた自分と重ねていたのかもしれない。USAGI CITYはつい最近まで小さなライブハウスで演奏していた。複数のバンドが入れ替わりで出演する、いわゆる対バンというのに出演していた。毎回4~5組のバンドが出るのに100席を埋めるのもやっとだった。あんな素晴らしいバンドが、小さなライブハウスさえ満席に出来ない事が不思議でたまらなかった。自分の見る目が無いのかと悩んだ事もあった。それが今は一組で5000席を一瞬で埋めてしまう。たった一曲のたった1フレーズが、SNSで話題になり、メジャーデビューを掴み、他の曲も評価された。CMやテレビドラマのタイアップも決まり、日本中に彼らの名が知れ渡った。チケットが取れないという情報が拡散され、更に彼等の価値を高めた。世の中は何が起こるか分からない。
もし自分の作品がアニメ化されたら、主題歌としてUSAGI CITYの曲を指名しようというモチベーションで戦ってきたが、その夢は砕け散った。彼等は日に日に遠い存在になっていく。私が見た事の無い景色を見ている。
「それって高価なの?」
「今の私にはね」
「買ってあげようか」
「買えないよ」
「馬鹿にしてるの。6000円位出せるわよ」
私はため息交じりに「抽選なんだよ。超人気者なんだよ」と言った。
杉山は「へぇ~」と感心する素振りをしながら『週刊少年スカイ』に手を伸ばした。
「嬉しくないんでしょ?」
杉山は悪戯小僧のような顔で『週刊少年スカイ』を奪い返す素振りをみせた。勿論私はそれをボクサーにようにかわした。
「いや、嬉しいよ。嬉しいに決まってるじゃん」
「じゃあ、いいじゃない」
私は、聞こえるか聞こえないかぎりぎりの細い声で奴に礼を言った。奴は得意げに笑っていた。確かに今、一番欲しいのはこれだ。誰よりも早く『週刊少年スカイ』を読んでヒーロー達の活躍を感じたい。滑稽なキャラクター達に笑わして貰いたい。誰よりも先に『週刊少年スカイ』を手に取りたくて日曜深夜のコンビニでバイトをしているといっても過言ではない。
「欲しい人がいて、あげたい人がいる……でしょ?」
「ありがとう」
私は駅弁売りのように1レジのドロアを両手に持ち、バックヤード兼、更衣室兼、商品庫兼、休憩所兼、事務所に進んだ。ドロアの上には愛しの『週刊少年スカイ』が行儀良く座っている。
今すぐ読みたい。だけど仕事中は読まない……時々、立ち読み程度はするが、真剣に読む事はない。楽しみは後に残しておくタイプなのだ。ショートケーキの苺は最後に食べるタイプなのだ。まぁ、私にはショートケーキを買ってくれる優しい母も、苺を取り合いする兄弟や友達もいなかったけど。
事務所に入ると、一旦ドロアを事務机の上に置き、ドリンクを補充した。滑り進む缶コーヒーの向こうに、折鶴に夢中になる杉山が見えた。どうせ暇潰しをするなら台詞の一つでも覚えればいいのに。そんな事をいつも考えているが、奴には言えなかった。どうせ自分勝手な理屈をぶつけてくるに違いない。
私は椅子に座り、レジ金を数え始めた。レジと繋がっているタブレットを開き、数えた売上金を打ち込む。レジ上の売り上げと、実際にドロアにある金銭が合っているかを確認する。そして釣銭を残し専用の袋にその金銭と集計レシートを入れ金庫にしまう。それがこの時間の仕事の一つだ。一般のショップや飲食店なら、閉店後にまとめてこの作業を行うのだが、コンビニのように二十四時間営業の業態は閉店がないので、営業中に定期的に行う。
既にカード支払いの金額やクーポンの割引額が打ち込まれている。釣銭の金額も設定されている。どこから数えてもいいのだが、私は一万円札から順番に数えて打ち込む。札は暇な時間に予め十枚ずつ纏めているが、一応この時に数え直す事になっている。五千円、千円と打ち込んだ時、客の入店を知らせるチャイム音が流れる。薄暗い事務所の中でそれを表すランプが光る。
客は一人、細身の男だ。防犯カメラの映像でそれが確認できる。杉山は背筋を伸ばし、接客の姿勢をとった。
客の男は入店すると、そのままレジに向かった。恐らく何かの支払いか、タバコを買いにきたのだろう。特別不思議な光景ではない。
私は紙幣を一旦袋に入れ硬貨を数え始めた。
―あれっ、あの男、何処かで見た覚えがあるぞ―
妙な胸騒ぎが、私の記憶の先っぽを掠めた。
―あっ、さっきまでガードレールに座っていた男だ―
何の確証もない。顔をはっきり見た訳でも、服装を覚えている訳でもない。ただ何となくだが、そんな気がする。だからどうだって言うのだ。仮に私の推測が当たっていたとしても特別な事ではない。待っていた人が現れず、地下鉄の出入り口のシャッターが閉まったのを目にして、諦めて一緒に入るはずだったこの店に一人で入ってきたのだろう。ただそれだけだ。ただそれだけなのに、胸騒ぎが治まらない。
気が付けば私は、防犯カメラの映像に夢中になっていた。先日導入したばかりの最新式の防犯カメラからの映像は、とても鮮明だった。戸惑う表情の杉山を確りと捉えている。サングラスを掛けた顎の尖った男が、何かを言っている。ただ、その音声は拾えていない。聞こえるのは、店内から微かに届く、カネヲダセ、という声だけ。
カネヲダセ……?
かねをだせ……
金を出せ……
嘘でしょ?あいつは「金を出せ」と言ったのか?勘違いだよね。勘違いに違いない。ヒーローを求める私の脳が、悪役の言葉を欲しがっているようだ。早くレジ締めを終わらせ、家に帰って『週刊少年スカイ』を読んで欲求を満たさなければ、心がエンストしてしまう。幻聴がそれを教えてくれたのだろう。
私は改めて現金を数え始めた。時々防犯カメラの映像を気にしながら。
くすんだグリーンのコートと赤いネクタイ。何処かで見た記憶のある服装。いや、衣装。あっ、そうだ、あの刑事ドラマの主人公だ。二十年以上も前のドラマの主人公の格好に違和感を覚えて、私はずっと店の外にいる彼を気にしていたのだ。それが分かった瞬間、胸の痞えが消えた。
「いいから、早く金をだせ」
束の間の安堵を襲ったのは、店内から届いた肉声だった。幻聴なんかじゃない。はっきりとした生の声だった。私は思わず口を強く押さえ息を飲み込んだ。それと同時に心臓が暴れ出した。
私は恐る恐る事務所のドアの開き、その隙間から店内を覗いた。
男の体が僅かに震えている。緊張で震えているというより、苛立ちを隠せないという様子だ。いや、その両方かもしれない。それに反して杉山は落ち着いているように見える。それどころか笑っているようにさえ見える。何故だ、何故だ。私の頭は混乱を極めた。
杉山の馬鹿さはよく知っている。しかし流石に強盗を目の前にして落ち着けるような程の馬鹿だとは思っていない。
混乱する頭は一つの推測を導いた。その瞬間、緊張の糸が切れた。
「ああ、良かった」
私は思わず言葉を漏らした。間違いない、あの男は、何処かの劇団員なのだ。仲間が遠くでカメラを構えてこの様子を撮っているのだ。本人も胸ポケット辺りにスマホを忍ばせ、杉山の間抜け顔を狙っている。そのどっきり映像を舞台の転換時やオープニングで流すのだろう。
こんな事は以前にもあった。その時のターゲットも杉山だった。杉山が道を歩いているところを、迷彩服を着た劇団員が襲ってくる。騒ぐ杉山の様子を撮った映像を劇場で投影する。実に単純な映像だったが、劇場内は笑いに包まれた。
それの第二弾の撮影が今夜だったのだろう。店内の客が居なくなり、杉山一人になった瞬間を狙って決行したのだろう。うける事だけを考えている奴らの頭の中には、店の奥にもう一人の従業員がいる事など想定されていない。
私は再び安堵した。何か、この緊張と緩和が心地良い。面白い漫画を読んでいる時と同じ感覚だ。
最近よく耳にする『迷惑系○○』とか『暴露系○○』とか『○○テロ』と同じ類のやつで、世間からの批判される事を覚悟でやっているんだ。バズるためなら何でもやるのが、奴らの手口。漫画家と同じで役者になりたい奴など数多いる。そこから抜きに出るには相当なリスクを覚悟しないといけないのだろう。
相当なリスク……いやいや、リスクは大き過ぎる。この動画が世間に出たら、奴らは御用になる可能性だってある。店内は外から丸見えなので通行人に通報される可能性も大きい。杉山はその責任をとって辞めないといけない。知っていて止めなった私にも責任が及ぶかも知れない。かと言ってこの後の展開が楽しみでしょうがない。知らなったフリをするのが得策だ。私は椅子を少しずらした。スマホから微量の音楽を流した。曲は何でも良かったのだがUSAGI CITYが世に頭角を現した『微熱』にした。っていうかそもそも他の曲は入っていないのだけど。とにかく店内と物理的な距離をとってアリバイを固めていく事にした。
犯人役の顎の尖った男は、右手をコートのポケットに入れ、それを突き出している。恐らく拳銃のつもりなのだろう。男は執拗に「金を出せ」と繰り返す。被害者役の馬鹿野郎はまたタバコの棚に寄りかかり不敵な笑顔を見せている。
私は奴等の間違いに気が付いた。まず、犯人役の顎の尖った男の衣装は刑事を想像させる事。そして杉山が落ち着き過ぎている事。
衣装は間違っているとはいえ、犯人役は迫真の演技を見せている。まあまあ実力のある役者なのかも知れない。ここまで緊張感が伝わってくる。この映像制作に役者として相当な覚悟で望んでいる事がわかる。この場合杉山は演技に乗ってあげないといけない。彼らが望んでいるのは、杉山が強盗を目の前にして慌てふためく様子だ。仮にドッキリに気が付いていても、それをやってのけるのが役者だ。まぁ、そんなリアルな演技を奴ができるはずもないが。
まぁ、両者共馬鹿だという事だ。恐らくこの映像はボツになるだろう。撮影した後でとんでもない事をした事に気が付き披露される事はないような気がする。
やっぱり奴らは危なっかしい事をしている。とりあえず、今何もなく終わったとしても、もし店のオーナーが防犯カメラに残った映像を見てしまったとしたら。もしこの映像がどこかに漏れてネットでアップされたとしたら、と考えたら冷や汗が止まらない。これは大、大、大問題だ。
今はSNS等で情報が拡散される時代。この映像が一瞬で拡散され店の評判も、劇団や杉山の評判は落ちてしまう。近くで傍観していただけの私にさえ影響が及びかねない。こんな幼稚なアリバイ工作じゃバレバレだ。
ヤバい、ヤバい、アリバイを増やさないといけない。いや、早くこの茶番を止めないといけない。今、それができるのは私ただ一人。私がヒロインになって愚かな奴らを救ってやらないといけない。妙な正義感が私の小さな身体を動かした。USAGI CITYの『微熱』が大サビを迎えて、ヒロイン登場のお膳立てが整った。
私は店舗のルールを破り、売上金を事務所の机に置きっぱなしにして、意気揚々と事務所のドアを蹴り開けようとした。
その瞬間、耳の奥に激しい痛みを覚えた。鼓膜の前で何かが破裂したような衝撃だった。
事務所のドアが微かに揺れたように感じたのは気のせいだろうか。
私は身を屈め、事務所の奥に進み、恐る恐る体を起こした。そして防犯カメラの映像モニターを覗いた。
レジの中に店のユニホームを着た大きな男が転がっている。その横で店とは関係ない男がレジを漁っている。
意味が理解できない。私は今、何を見て、何を感じているのか、全く分からない。知らない映画の一部が間違って映し出されているのか、それとも少年漫画への憧れが強過ぎて幻覚でもみているのか、分からない。何故だろう、何故なんだろう。息が詰まり声が出ない。耳鳴りが邪魔して何も聞こえない。映画か幻覚か分からない映像だけが私の目から離れない。
悪寒が襲ってきた。手足が震え始めた。全ての臓器が喉下に込み上げてきた。脳より先に体が現実を把握し始めたようだ。
『どうしよう』この言葉が大量に分裂して頭を占領する。犯人役、いや犯人は一レジにドロアが無い事に慌てているようだ。二レジ、三レジに移ったところで解除する術は知らないと思う。だとすると次に狙うのは、この事務所だ。私はこの建物から逃げる事を考えた。しかしそれが更なる混乱を生んだ。この店、唯一の出入り口は犯人の居るレジの横の自動ドアだけだ。あの自動ドアを突破出来る可能性は皆無だ。この小さな体を最小限に縮めても、犯人の視覚から逃れる事はできない。もし仮に自動ドアの前まで辿りつたとしても、自動ドアが開く音で気付かれ弾丸が飛んでくる。そう、現実は漫画のように上手くはいかないのだ。『どうしよう』の細胞分裂が巨大なモンスターと化して私の背中にへばり付いた。
隠れられる場所がないか、事務所を見渡したが、それらしい場所は見つからない。小さな事務机と、従業員用のロッカー、商品の入ったダンボールが壁際に詰まれているだけだ。天井下の小窓から外灯の光が差し込んでいる。
天井下の小窓……そうだ、あの窓からなら脱出できるかもしれない。子供が一人やっと通れる位の小さな窓だが、私ならいけるかもしれない。差し込む外灯は希望の光だったのだ。
私は事務所に置かれた冷凍ストッカーに、缶ドリンクのダンボールを重ねそれに登った。小窓の鍵を開き、頭と右肩を押し込んだ。何故か左脇にレジのドロアと『週刊少年スカイ』をしっかりと抱えていた。体が収まれば何も問題は無い。後は音をたてぬよう全身を出して、飛び降りないといけない。
左脇に抱えたドロアと『週刊少年スカイ』を両手に持ち替え、水泳の飛び込みのような格好でするりと小窓を抜けると、ビルの非常階段に転がり落ちた。
子供の頃の私は運動神経が悪く、その劣等感に母親の異常性が加わり同級生達と関わる事を避けてきた。そんな私が幾つもの障害をクリアし、悪から逃げ切ったのだ。これまで私を幾度と無く救ってきてくれた漫画の中のヒーロー達が、私に憑依し再び救ってくれたのだ。そんな事を思い浮かべ胸を撫で下ろした瞬間、二回目の銃声が響いた。
「はっ」
再び息が詰まった。そして直ぐに一人の顔が浮かんだ。
「陳君」
私はその名前を思わず発した。ちょうどこの時間は私と交代する留学生の陳君が出勤してくる時間だ。お客様の可能性もあるが、タイミング的には陳君だと考える事が妥当だ。出勤していつものと状況が違う事を感じて、犯人に対して何らかの対応をしたのだろう。そして……そして、犠牲になったのだろう。
確かに動揺はあるが、正義感は既に捨てていた。杉山や陳君、そしてこれから色々ありうる犠牲には悪いが、まずは自分の身を守る事を優先しよう。
私はヒーローでもヒロインでもない。物語の主人公は私の頭の中で生まれ、漫画にする事で初めて動き出す。現実の世界にはいないのだ。
非常階段の踊り場で新たな選択肢が生じた。下に降りて警察に走るべきか、屋上に上がってスマホから110番しようか。何故だろう、何故だか分からないが私は迷わずに後者を選んだ。
私は忍び足で屋上へ足を進めた。建物は四階建ての古い雑居ビル。地下が居酒屋で一階が私達の働くサンライズマート。二階から四階まではそれぞれ違う会社のオフィスが入っているが、この時間には人が居る気配すらない。地下の居酒屋も定休日で誰も出勤していない。そう、このビルには私と殺人犯しかいないのだ。リスクを残してまでビルを離れる事が出来なかったのは、まだ心の何処かでヒーローの存在を信じていたのかもしれない。
五年もこのビルに通っていたが、屋上は勿論、非常階段を上がるのも始めてだ。存在は知っていたし、他の階の人達が使う姿も見た事はある。
セキュリティが甘く、屋上に上がるのは容易だった。給水タンクと小さなプレハブの倉庫。吸殻入れ代わりの空き缶は濁った雨水で満たされていた。その周りを錆びたパイプ椅子が囲っている。
私は迷わず倉庫のドアに手を伸ばす。有難い事に鍵は掛かっていなく、ドアは簡単に開く。中は倉庫というよりゴミ溜めと言った方が正確なのかも知れない。埃だらけのダンボールと壊れた電化製品が重なっている。もう何年も使っていないような掃除道具は異臭を放っていた。私はその隙間に身を埋め静かに震えていた。
あれからどれ位の時間が過ぎたのだろう。僅か数分から数十分といったところだろうが、私には相当な時間が経ったように思えた。パトカーのサイレン音が近づいてくる。何台も続いてパトカーが来ているようだ。もう直ぐ私はこの環境から開放される。後は犯人がここに逃げて来ない祈るのみだ。
全てのサイレン音が止まった。警察がこのビルの周辺を囲っている事が想像できる。希望が少しずつ確信へと変わっていく。私はここから飛び出したい気持ちを抑え、助けが来る事を待つ事にした。体育座りで震える膝を抱え、祈り続けた。
祈りが通じたのか、誰かが非常階段を登って来る音が聞こえた。足音は複数。警察に間違いはない。
足音が近づいてくる。男たちの会話が微かに耳に届く。無線機で通信している事も何となく分かる。屋上の小さな倉庫内に篭りながら人の気配が迫っている事を感じた。何か外が慌しくなり始める。ドン、という音が響く。誰かが倉庫のドアを鈍器のような物で叩いた。
「誰かいるのか?」
強い口調だった。私はその声に戸惑いながら問いに返した。
「います」
「一人か?」
「はっ、はい一人です」
「誰だ?」
「灰谷由です。下の店の従業員です」
「ハイタニだな?」
強い口調と私の戸惑いは続いていた。声の主は別な相手に話し始める。
「屋上の小屋でハイタニユウを発見。確保します」
無線での報告だろうか。私の戸惑いの山は最高峰に達していた。
「ハイタニ、よく聞け。私は新宿署の山城だ。こちらは完全に包囲している。何の抵抗もするな」
「はい、勿論です」
「よし。このドアを少しだけ開けて確認する。全ての持ち物を床に置いて両手を頭の上に乗せなさい」
「はい、乗せました」
朝の日差しの眩しさに、目を細めた。ドアが完全に開くと再び闇が襲った。視線を塞いだのは盾のような物だった。
「よし、そのままゆっくり立ち上がりなさい」
私は言われるままに、立ち上がると、盾の間から屈強な男が二人現れ体あたりしてくる。一人が肩を掴み、一人が腰を押さえてくる。激痛を忘れる位、困惑が勝っていた。現状に理解が全く出来ない。そんな時、妙な臭いが漂ってきた。それは花火で遊んだ後のような臭いだった。困惑は更に増す。
「ありました」
また違う男が、私のコートのポケットから何かを取り出した。
コート……。私は何でコートなんて着ているんだろう?コンビニのユニホームを着ているはずの私が、何故かくすんだグリーンのコートを羽織っている。白いワイシャツに赤いネクタイを結んでいる。どこかで見た事のある格好だが、それが何なのかは検討もつかない。息が詰まり瞼の自由が奪われる。血の気が引き、体の震えが止まらない。
「これはお前のだな?」
私は恐る恐る男の手元を確かめた。黒いぼやけた物体が、少しずつ鮮明に浮かんでくる。目に映ったのは小型の拳銃だった。全身の力が抜けその場に崩れ落ちた。
「やっていません。私は何もやっていません」
男達の力が更に強くなっていく。私はそれでも必死に訴え続けた。
「本当です。私は何もやっていません。私は何もやっていません」
最悪の目覚めだった。私とした事が、まるで三流漫画のような夢を見てしまった。いや、私自身の発想力が三流だから夢も三流なのかも知れない。それにしても酷い夢だった。たっぷり眠ったはずなのに、何故か疲労感が拭えない。
私は始めて高梨一樹に会った日の言葉を思い出した。高梨一樹とは私を担当する漫画編集者だ。まぁ、担当といっても連載をしている訳でも、読みきりを書いた訳でも無いから、実際には何の契約も交わしていないのだが、切るに切れない事情があって担当者代わりになってくれている。
あの女と離れる為北海道の家を飛び出し、上京してきて直ぐにトンボ出版のコミック部に電話をした。その電話に出たのが高梨一樹だった。東京の『と』の字も知らない私は彼の指示通り、神保町の喫茶店に入って、彼と会い、書き溜めてあった数作の漫画を見せた。その時彼はこう言い放った。
「こんな漫画を書く奴なら五万といるよ」
彼が言うには、私の画力はオリジナル性に欠けるものの特別な問題は無いらしい。しかしストーリーがありきたりでつまらない。私が想像する物語には、読者を引きつける魅力が全く無いのだ。「これじゃ、売り物にはならない」、彼ははっきりと言った。私の目の前は一瞬にして真っ暗になり、肩を落とし、その場を離れる為立ち上がろうとした時に、彼は私の手を掴んだ。少女漫画のシーンのような状況にハッとしたのを覚えている。
「確かに才能は無いけど、まだ終わった訳ではない。画力はあるから他の方法を一緒に探そう」
彼は真っ直ぐな目でそう言ってくれたのだ。
それから、それまで以上に漫画を研究し、新しい作品を書いた。その度に彼に見せるが、首を縦に振ることはなかった。
今でこそ杉山のような友達は何人かいるけど、当時は東京で唯一の知り合いが高梨だったから、彼を頼るしかなかった。彼は私が母を憎んでいる事を知る数少ない人物の一人だ。漫画はいつになっても認めてくれない。しかし心と体は簡単に奪っていった。打ち合わせという体で私の家に来ては、私を抱いた。童顔で漫画オタクで、ファッションにも興味が無く化粧すらしない私だったが、彼といる時は女であると確認できた。
そして妊娠した。
妻子のいる男の子供を宿し、産み、結果として一番頼りたくない母を頼らなきゃいけない状況を彼は作った。そう、私には幼い子供が居て、それを北海道の憎き母が育てている。
それの罪滅ぼしだろうか、彼は私に仕事を紹介するようになってきた。
仕事と言ってもアシスタントだ。連載を抱えている漫画さんの手伝いをするのだ。まだまだ出始めで高給のアシスタントを雇う事のできない漫画さんのアシスタントを破格で請け負い、その連載が終われば次の漫画家さんのアシスタントを紹介される、というシステムがいつの間にか構築された。仲介料を取られない派遣スタッフみたいなものだ。自分自身もネットなどでイラストを売り込み、ポスターとかショッピングカードなどのデザインをして小遣いを稼いでいる。ここ数年は漫画家さんのアシスタントと、イラスト、深夜のコンビニのバイトで食い繋いでいる。
夢と分かっていながらも、何故か心のモヤモヤが払拭されず、念の為に杉山にメッセージを送った。たった一言〈生きている?〉返事は直ぐに返って来た。〈ちびちゃん、どうしたの?〉と。私は胸を撫で下ろす。良かった、奴は生きている。私と違い、今頃は涎を垂らしながら良い夢でも見ていたのだろう。私は〈ごめんなさい、なんでも無いよ。寝ているところごめんね〉と返信した。吹き出しに『OK!』と書かれたスタンプが返って来て、二人のやりとりは終了した。
安心するとまた疲れが襲ってきた。もう一眠りしたいところだが、そうは言っていられない。今日の午後は、麻島先生のアシスタントの仕事が入っている。
麻島まりか先生は三年前にトンボ出版新人賞を獲って、デビューを果たした。十年に一人の逸材と呼ばれ、トンボ出版の期待を背負っている。麻島先生の才能を少しでも自分の物にして、一刻も早く私もデビューしないといけない、という理由で高梨はいつものようにこの仕事を紹介してきた。まぁ、確かにそうなんだ。早く私の名前が売れないと、子供を手放してまで東京に残った意味がないのだ。あの女に借りを作ったままではいられない。
麻島先生も、少年漫画が好きだったのだろう。主人公の線の描き方や、動きの付け方から、それが分かる。特に目は分かりやすい。少女漫画のキラキラでと、少年漫画のキラキラは違う。私も、麻島先生も後者だ。これらから麻島先生は、少年漫画好きだと分かる。かなり自信はあるが、でも憶測に過ぎない。今日は麻島先生に、そこ等辺を聞いてみようと思う。
私はさっと顔を洗い、短単に歯磨きを済ませ、化粧も寝癖も直さず(まぁいつもの事だけど)、脱ぎ捨てあった服を着て部屋を出た。
アパートの自転車置き場で、自分の自転車を出して、跨ると颯爽と風に飛び込んだ。心は躍っている。早く麻島先生に会って、少年漫画について語りたい。年齢も近いから、話は盛り上がるに違いない。
高田馬場にある、麻島先生の自宅件仕事場、通称『アトリエMARIKA』に着く頃には、頭の重さも眠たさも忘れていた。今夜はコンビニのバイトは無い。麻島先生の仕事が終われば完全なオフだ。昨夜、読めなかった『週刊少年スカイ』の続きを読んでゆっくり眠ろう。そう考えると、更に心が激しく踊りだす。
ここは自宅からも、バイト先のコンビニからも近く、通うのに便利だ。しかも麻島先生は優しいし、わがままも言わない。もう一年以上、麻島先生のアシスタントをしているが、できれば長く付き合いたいと願いっている。今やっている『週刊リバー』の連載が続いて欲しいと祈るばかりだ。
マンション前のガードレールに自転車のチェーンを結び、入り口に進む。オートロックの部屋番号を押すと、聞き覚えのある男の声が返ってくる。
「灰谷です」
「あっ、おはよう。今開けるね」
声が暗い。あまり良い状況ではないようだ。
「はい、お願いします」
マンションのドアのロックが解除される。私はドアを開け中に進む。エレベータで五階に上がると『アトリエMARIKA』の表札が貼られたドアを開ける。
「おはようございます」
淀んだ返事が返ってくる。
苦しい顔をした麻島先生の横で、更に苦しい顔をした高梨がいる。そして、この光景に慣れてしまった自分がいる。今週もまだネームが完成していないようだ。
麻島先生の作品が連載されている『週刊リバー』は漫画雑誌ではない。一般の週刊誌で、グラビアに始まり、事件事故、政治経済から芸能ネタまで広範囲の情報を提供している。大物作家による連載小説やコラム、エッセイ、漫画も多く扱われている。成人男性をターゲットにした雑誌ではあるが、漫画やコラム等の人気が手伝って、男女問わず広い年齢層に支持されているそうだ。
理想のサイクルは、麻島先生が土日に下書きと構成にあたるネームを完成させて、月曜日の朝からケント紙への下書きが始まり、ペン入れをする。そこに私が背景を書き、ベタやスクリーントーンを貼っては削っていく。その作業を繰り返し締め切りである木曜日の午後には完成する。最近はデジタルで描く人もいるが、まだまだアナログが主流だ。麻島先生も私もアナログの線の良さを知っていてデジタルに移行するつもりはない。
作業の第一段階であるはずのネームがまだ終わっていない。ネームが終わっていないという事は、下書きにも入っていないという事だから、ペン入れもベタもトーンも入れられない。つまり、私はする事がないのだ。だからといって出勤しない訳にはいかない。間違いなく訪れる締切日の為にいつでも始められるよう、控えていないといけないのだ。
私は彼の紹介でこれまで七名の漫画家先生のアシスタントをしてきたが、今までこんな事は無かった。全く無かったとは言わないが、ここまで酷いのは始めてだ。麻島先生は極端に仕事が遅い人なのだ。それだけに担当する彼が仕事場に足を運ぶ事も多くなる。私個人としては嬉しい事かもしれないが、総合的な事を考えると心境は複雑だ。
私は黙って自分の机の椅子に座り、机上を整理するフリをして指示を待った。とはいっても指示などはない。今日はかなり遅くなりそうだ。そう思うと、急に眠気が襲ってくる。
私は睡魔と闘うべく、視線をテレビに移した。理由は分からないがこの現場では、ずっとテレビが点いている。音楽やFMラジオを聴きながら作業をする漫画家は多いが、テレビをつけっ放しにしている人は始めてだ。何故か画面に背を向けているし、音声は消してある。麻島先生自身が見るためでも、情報を得るためでも無さそうだが、この環境がやり易いのか、終日テレビの映像が光っている。
テレビでは、昼の情報番組が放送されている。何処かで恐ろしい事件でも起きたようで、規制線が張られた建物の周囲を警察が行き交っている。その前でリポーターが神妙な面持ちで何かを伝えている。
「あっ」
私は思わず大きな声を発していた。麻島先生と彼が驚愕している。
「どうしたの、急に?」
目を見開いた麻島先生が私に問いかけた。私は小刻みに震える指でテレビ画面を指した。
「これ、なんですか?」
「あっ、これね。朝からずっとこのニュースばかりやってるよ。東京、そうそう、この近くのコンビニで強盗殺人事件があって、犯人がまだ捕まってないらしいの。警察が沢山いたでしょ?」
街が騒がしい事はいつもと変わらない。でも、確かにいつもより警察官は多かったような気がする。パトカーも数台見かけた。しかし遅刻を避ける事に必死になっていたので、気に留める事はなかった。
「これ、私がバイトしている店です」
「えっ、そうなの」
そう言うと、麻島先生は言葉を詰まらせた。高梨一樹はただ唖然とした表情でテレビ画面と、私の顔を交互に見ている。
「でっ、でも、良かったね。やっ、休みの日で」
言葉を選ぶように麻島先生がそう言う。言葉は発したが目は合わせてこない。
「いや、休みじゃありません。出勤していました」
そう言い放つと私は部屋を飛び出していた。気が逸りエレベータを待つ事もせず、階段を駆け下りた。自転車を停めてあったチェーンを外し、走り出す。真冬の風を浴びているはずだが、体は火照っていた。
何故だろう。涙が溢れてくる。流れる汗と、零れる涙が頬で混ざり、それを冷たい風が奪っていった。私は脇目も振らずペダルを漕ぎ続ける。何かに牽きつかれるかのように、見慣れた道を進んでいった。
慣れた道のりだが、いつもと何かが違う。時間が違うから多少は街の色合いも違うだろうが、それだけではないようだ。空気も道路も、交通標識も錆びた色に変わっている。
そして、止まっている。
目的地には人だかりが出来ていた。血の臭いを嗅ぎ付けた獣が群れで、草むらの中の小鹿を狙っているように感じた。道路脇は警察車両が占領し、規制線の周りは報道陣と野次馬が囲んでいた。空を見上げると、無数のヘリコプターが旋回している。
「どけてくださ~い」
私は生まれて初めて自分の意思で叫んだ。
「どけろ~」
まるで何かの映画のように、人ごみが二つに別れ私はその間を進む。急ブレーキの音が響くと、二台のテレビカメラの隙間に自転車が収まった。私は何の迷いもなく規制線を潜ろうとしたが、制服を来た警官が静止してきた。
「私です。私です。私です」
どうしたんだろう。自分の名前が思い浮かばない。
「いったいどなたですか?」
「だから私です」
他の警官が慌てて集まる。幾つかのカメラがこの様子を捕らえようと構えている。パシャパシャ、とシャッターが切られる音が耳を襲う。
「だから、私なんです。現場で犯人を目撃した灰谷由です」
やっと自分の名前が出てきた。次の瞬間には報道陣が一斉に集まってきた。店内の警察達も動きを止め、私達の様子に注目している。自動ドアが開き、男が飛び出して来た。白髪に、痩せ型、がに股が特徴的。そう、私はこの人に会いに来たんだ。
「灰谷く~ん」
サンライズマート早稲田店、オーナー兼店長の岡田悟さん。岡田さんは手を大きく振りながら、老体の限界を振り絞り走って来る。奥さんの恵子さんもゆっくりと歩み寄ってきた。
「店長」
「灰谷君」
岡田さんの瞳は潤んでいた。一度私の目を見つめ、抱きしめてきた。顔面蒼白というのはこういう事なのだろう。顔色は明らかに悪く、目の下の隈が浮き出ている。止めたはずのタバコの臭いが私の鼻を刺してきた。私は糸が切れた操り人形のように体の力を緩めた。
「灰谷君、ごめんね。辛い想いをさせたね。相当怖かっただろう」
岡田さんも、私の顔を見て少し安心したようだ。抱きしめる体の力が抜けていくのが分かった。互いが互いを支え合って、やっとこの体勢を維持している。
「いえ、私は。それより」
「ごめんなさい。ごめんなさい」
岡田さんは体制を崩し、私の膝まで崩れ落ちてきた。私は腰を下ろし、俯く岡田さんの肩を抱きしめ直した。恵子さんは私と旦那さんの肩に手を添え、静かに俯いている。いつも凛とし背筋を伸ばし、綺麗な化粧でレジに立つ恵子さんの面影はそこに無かった。
「岡田さん、奥さん、大丈夫ですか?岡田さん」
「本当にごめんなさい。杉山君と陳君には本当に申し訳ないと思っている。ごめんなさい。本当にごめんなさい」
岡田さんは、顔をくしゃくしゃにしながら泣きじゃくった。恵子さんも嗚咽混じりに亡き崩れた。カメラのフラッシュが眩しく、私は目を細めていた。
#創作大賞2023 #お仕事小説部門
こんな僕ですがサポートをして頂けると嬉しいです。想像を形にするために、より多くの方に僕の名前・創作力・作品を知って欲しいです。 宜しくお願いいたします。
