【ゲームと私】第1回『サンサーラナーガ』
※note公式お題「#自己紹介をゲームで語る」の本編記事になります(前回6/21に準備稿を掲載)。小学低学年で初めてゲーム(ファミコン)に触れた自分が、自分でゲームを作るようになるまで――を、結局、数回に渡って連載形式で語ろうと思います。語りたいゲームは厳選しても数あることになるし簡単には語り尽くせないと思うので......。
ファミコンが流行っていた当時(80年代後半)、世間でも、友達の間でも話題になっていた「ドラゴンクエスト(I~IV)」「ファイナルファンタジー(I~III)」については、後にゲーム制作をすることになる自身にとっても、RPG体験の最初に触れることになったゲームであり、ゲーム制作をするための土壌を作ったゲームだったことは間違いない。
ドラクエとFFのヒットの後、それに続く多くのRPGが現れたわけだが……ドラクエ・FFによってRPGの魅力の虜になった私(当時、小学校低学年)は、それら多くのRPGに触れていくことになる。(遡ってRPGの始祖であると言える「ウルティマ」「ウィザードリィ」にも触れている。)
そんな中で自身が嵌ったのは、各々若干知名度の差はあるだろうが、ドラクエ・FFに次いで当時比較的有名だったと思う「桃太郎伝説」「MOTHER」といったところからそれより少しマイナーかと思うが「貝獣物語」「サンサーラナーガ」といった作品だ。
(この知名度の差については、その後更に売上の増えるSFCに移行した後に続編がどのくらいヒットしたか、あるいは更にその後、ファンやフォロワーとなるクリエイター等によってどのように語られたり広められたりしたか、等にもよるかもしれない。今では「MOTHER」は国民的認知度・人気のRPGと言ってもいいと思うけど、それはSFCの「MOTHER2」によるところが大きい気がするし、おそらくファミコン当時は「桃太郎伝説」の方が有名で売上も大きかったのではないかと思われる。個人としては嵌っていたのだけど、友人の間でそれほど話題に上ったような記憶はないようにも思う。「桃太郎伝説」は調べると100万本以上の売上、とある。「MOTHER」は30万本程か。)
ドラクエ・FFが自身のゲーム制作の最も基礎の地盤になったRPGとして、世界観や物語の構築の仕方に最も影響を落としたのは「MOTHER」と「サンサーラナーガ」だと思っている。
いずれのゲームも個別に記事を書いて語りたいところだけど、今回は「サンサーラナーガ」の方に焦点を当てて記事を書きたいと思う。
●「サンサーラナーガ」
その頃の王道のRPGがいわゆる中世ヨーロッパ的世界観が主体であったのに対し、「MOTHER」は現代、「桃太郎伝説」は昔の日本……というふうに独自性を打ち出していたが、「サンサーラナーガ」は古代インド……という設定だったのだが、実際のところはグラフィックや雰囲気からそこまでインドを強く感じたわけではなかった。モンスター名なんかにはインドっぽさが現れているが小学生的にはそもそもあまりわからないところだったし、とにかく、インドっぽさというのはそこはかとなく、くらいのものであった。
が、それがよかった。と思う。インドっぽさというのを雰囲気の味付け程度にして、その上で後は作り手独自の世界観、という世界を構築していたといったところと思う。このよくわからない混沌とした世界が、当時のやはり中世ヨーロッパ的世界観が主流のRPGを体験してきた自分には新鮮だったし、魅かれるものがあった。その世界の住人達のあくも強かった。優等生的なRPG・それに追従する普通のRPGといった感じではなく、と言って不良でもなく、どこかひねくれ者のRPGといった感じだったろうか。それまでに既に幾つかのRPGをプレイしてきておおよそ一般的なRPGの在り方というものに慣れてきていたところだったので余計にそこが新鮮で惹かれたと思う。(ドラクエの旅の扉(水たまりのような形状)等RPGには各々の作品に特徴的なワープ装置が存在するが、トイレ(便器)をワープ装置にするRPGが他にあっただろうか……。)
(と言って、グラフィック自体はそんなに色んなオブジェクトがマップチップで丁寧に書き込まれているわけでもなく、ファミコンの荒い記号的なドット絵なのだけど、それがまたこの世界の混沌さにマッチして、また、不思議と町なんかのマップの造形・配置に風情を感じ、建物等の陰影の入れ方はこの作品独特の深みや闇の部分を表していたように思う。)
このRPGが、押井守の作(監督・シナリオ)によるものだったことを知るのはもっと後に自分が大人になってからのことだけど。(と言って、そもそも押井守作品の中で自身が最も好きなのはやはり「サンサーラナーガ(1・2)」なのだが……「天使のたまご」も好きだけど。)

「サンサーラナーガ」の目玉はこのRPGのテーマである"竜を育てる"というところだけど今回は、そこに主眼を置かず自身がこのゲームを面白いと感じたところに焦点を当てて語りたいと思う。
●自由度
「サンサーラナーガ」はとても自由度の高いRPGだった。(後にSFCで出る「サンサーラナーガ2」の方が勿論グラフィックにしてもサウンドにしても進化しているけど一作目の「サンサーラナーガ」の方が自由度は高く、破天荒だった。)
マップの造りが、歩いていこうと思えばほぼ世界のどこへでも行けてしまう……という。その点「FF2」なんかと近いマップの在り方。厳密には最序盤ではレベルや装備の問題でどこへでも、というわけにもいかないけど、ある程度進んだ段階、まあ序盤が終わってちょうどゲームに慣れてきた頃あたりには、本来その段階で行くべきではない場所にでも行ってみることができる。イベントは発生しないけど、ちゃんとその町にあるお店で武器やアイテムを買うことができるし、強力な敵と戦うことも(勿論上手く戦えば勝つことも)できる。
これが、楽しかった。
自由に自分の足で世界を歩いて、色んな場所を見て回ることができる。寄り道の感覚。本当はまだ行ってはいけないところに行ってしまっているということ。小学生の時のリアルの方での、禁止されている校区外に内緒で遊びにいく感覚。とかだろうか。
今だと、オープンワールドということになるか。しかし当時はオープンワールドという言葉があったわけではなく、「FF2」や「サンサーラナーガ」においてそのことが想定されていたのかどうかもわからない。あらかじめオープンワールドとして設計されているわけではなく、実際には本当は行ってはいけない想定なんだけど、レベルを上げあたりテクニック次第で行けてしまう、というのが面白いのだ、という気もする。
物語とは全く別で世界観だけで楽しんでしまうこともできるというところ。
「サンサーラナーガ」は世界観が作り込まれているので(物語の方も面白いのだけど)、世界観の方だけを楽しむこのマップの造りはとても合っていたように思う。
(ちなみにここは少し余談だが、私はゲームの在り方としてはオープンワールドが好きでも、現代のオープンワールドのゲームをほとんどやったことがない。というのも現代でオープンワールドというと、どうも、3Dで360度全方位に動けるゲームというものだという認識があるから……幾つかはプレイしてみたが、私は3D・360度全方位のゲームはいわゆる酔ってしまうというのかプレイ感・操作感に納得できたことがなくて基本的にプレイしない(「ゼルダの伝説 ブレスオブワイルド」は世界観が好きだったのでプレイしてみている。オープンワールドのRPGで体感したいのはああいう感覚という点はまさに、だったけど、でもやっぱり私には3D・360度全方位移動がプレイ感・操作感の妨げになってしまう。別に3Dで世界を見たくないわけではなくあの見え方自体は好きなんだけど、プレイ感・操作感に馴染めないのが残念。この感覚は聞く感じだと同じファミコン・SFCメイン世代の人は割とそういう人もいる?)。2Dで、オープンワールドというのかどうかはわからないけどオープンワールド的というのか、ある程度、どこへでも自由に……というのを近年で体感できたのはロマサガの系譜と言えよう「オクトパストラベラー」だろうか(この作品はこの作品で近年のRPGの中で「undertail」と並んで最も語りたい作品の一つなのだけどまた別途……)。
とにかく、2Dゲームで、オープンワールド的な、ある程度、自由に世界各地に移動できるという感覚を求めたくて、自身でそういうゲームを作ってしまう、というところは、ある(ここにシナリオを絡めていくと、レベルデザインやフラグ管理がぜーったいに難しくなってきてしまうんですけどね……)。(もう少し具体的に言うと、ロマサガに近いデザインでこの自由度を求めて作ったのが「12亜神伝」で、本稿上述で触れているFF2やサンサーラナーガ的な理不尽・破天荒な自由度を求めて作ったのが「ユトレピアの伝説」のそれぞれのマップのデザインになる。))
「サンサーラナーガ」の自由度に関しては、このどこへでも自由に……という以外にも、村人や犬にいたるまでのゲーム中のNPCと自由に戦う(「はなす」「どうぐ」等の一般的なRPGのコマンド以外に「たたかう」があるのだ)ことができるという破天荒なシステムも魅力だった。戦う際に一人一人ちゃんと台詞を喋ってくれるし(ただ当時善良な(?)小学生にとっては心が痛むのであまり使わなかったのだけど)。NPCの牛を戦って倒して、その肝を密売みたいなことして大金を手に入れることもできた(これも良心が咎めて結局やらなかったけど……)。借金して金を借りることができた(ちなみにこれも良心が...)のも当時相当に破天荒なシステムだったのではないか(借金取りまで来て、それもまた戦って倒すこともできた。けどこいつは大変強かったと思う)。モンスターとの戦いで勝利すると、竜に食べさせたり(回復するしこれによって竜が成長する)、えものにして売ったり武器を作ったりもできた(さすがにNPC倒して食わせることまではできなかったと思うが)。
ともあれ、この自由度は「サンサーラナーガ」の魅力の一つではあったと思う。
(「サンサーラナーガ」自体がそこまで語られることがないかもしれないけど、「サンサーラナーガ」の自由度(特にオープンワールド的な自由度の部分)については更にあまり語られることがないかもしれない。しかしここは確実に「サンサーラナーガ」の魅力であるので、語っておきたいところでした。)
そして何よりの魅力は、世界観と物語というところになると思う。
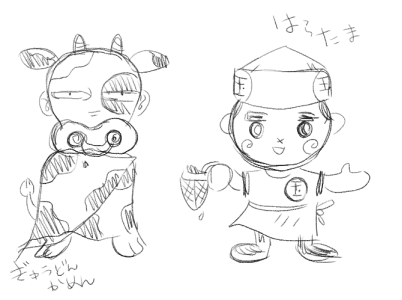
●世界観・物語
ゲームにおいて世界観を語る際、実際には何を語ることになるか。それは人それぞれになるだろうけど、自身の場合は、世界観の設定だけではなく、実際にゲーム中に出てくるアイテム名・モンスター名・NPCの台詞等のテキスト、実際にその世界を表現するグラフィック(マップチップ・モンスター・NPC等のキャラチップ)等をトータルに含めたものと考えている。(ただ、ゲームを幾つかの要素に分けて評価・評点を付けるような場合は、グラフィックに関しては独立した評価項目になることが多いので、難しい所なのですが……その場合のグラフィックはあくまで、グラフィックそのものの質という面での評価であって、世界観の方に含めるグラフィックの評価というのはあくまでその世界観・世界の雰囲気をどれだけ上手く表しているか……というものになりましょうか。音楽についてもそう言えるのじゃない、とも思うけど、音楽は音楽でまた別途語りたいくらいなのですが今回は、省きます。)
物語というのは基本的にはシナリオと言い換えてもいいと思う。ゲーム特にRPGの場合は、シナリオが一本の一続きのシナリオというわけではなく、本編に影響のないサブシナリオや、ほんのちょっとしたイベント等もあるが、それもまた物語の部分に入るだろう。(世界観の方で挙げた「NPCの台詞」というのが物語に含めるか世界観の方に含めるか若干迷うところ。)
さて「サンサーラナーガ」のシナリオだけど、竜のたまごだと思ったらダチョウのたまごだったというオープニングから、竜を育てるというゲームのテーマに沿ったメインシナリオ・数々の珍事件(いわゆるお使いイベントが多いのは多いのだけど)、一度竜がいなくなって(そこでダチョウと旅したり)竜との再会にはちょっと感動するところもあり、何より、小学生には「?」という感じだったけど印象的だった最後の戦い、エンディングも切なくて……とシナリオそのものも面白かったけど、随所でRPGの王道的展開を裏切っている奇抜なところが多いシナリオだったかと思う。
しかし基本的には、「サンサーラナーガ」を思い出して思うのは、どういう話の筋だったかというよりは、あちこち世界を巡ってその土地その土地の変わった人達や親切な人達だったりがいて、行く先々で色んな珍妙な事件に巻き込まれ、という、めくるめく夢のような感覚だ。
後から振り返った時に、なんだかはっきり覚えていないけど、印象的な夢だった。何か大事にしたいような夢だった。という、いつまでも覚えている、時々思い出す夢というような印象。そんな印象を残す物語・世界観が「サンサーラナーガ」の最も大きな魅力であるように思う。
(これは押井守の創作法でもあるのかもしれないけど(私は割と初期のマイナー作品しか見ていなかったりしますが)、この手法は、私が後に宮崎駿監督の「千と千尋の神隠し」やシュルレアリスムの方法等から学び自身の創作法を確立していく段階で一度過去の作品を振り返った時に、「サンサーラナーガ1・2」を鑑みて(この時に、幼い頃に印象を残した「サンサーラナーガ」も「ビューティフル・ドリーマー」も同じ押井守監督による作品だったと知ったのではなかったかと思いますが)、自身がこういう作風や手法を好む一番原点になった作品かもしれない、と改めて思った次第です。)
世界観については、アイテム名・モンスター名・NPCの台詞、どれを取っても今まであまり聴いたことのないような珍妙だったりシュールだったり哲学的だったりするテキストが、世界各地にちりばめられている。コレクション要素のようなものはなかったけど、それをただ見聞きしていくこと、この世界を全て見たいと思うことはつまり、コレクションして回っているのと同じようなことでもあると思う。
この点については、糸井重里が同じようにそういった優れたテキストを作った「MOTHER」と双璧を成す程のセンスだったと、私は思う。(「サンサーラナーガ」では押井守とコンビの伊藤和典がその部分の仕事を成していることになる。)
どうして、「MOTHER」のようには知名度が上がらず、むしろ今でも、マイナー、という感じに留まったのか(「サンサーラナーガ」もSFCで2が出ており、「MOTHER」同様に一作目を凌駕する出来になっていると思う。勿論ゲームである以上システム面やゲームバランスやテンポ等のプレイ感も物語・世界観同等に重要なものとなるので、その面で「サンサーラナーガ2」は若干難しい面があったのは否めないとは思う。例えば敵、けっこう固かったですよねとか、武器も壊れるし……テンポ・バランス・ユーザビリティといった面で)。純粋に、「サンサーラナーガ」は「MOTHER」と同等位にもっと広まり、評価されてもいいのでは……と思うところで、しかし、確かに、「サンサーラナーガ」の魅力というのは、不思議と心に残る、印象的で大事にしたい夢のように、誰かにこっそり話し聞かせたくはなるけど、基本的には自分の中に大切にとっておきたい密やかな夢の記憶のようなものであるようにも思う。
(とは言え、「MOTHER」程売れていないとしても当時だと20万~少なくても10万本くらいは売れているんじゃない? と思うと、そこそこの人が「サンサーラナーガ」をプレイはしているんじゃないか。その皆が多かれ少なかれ、今回私が書いたような思いを、共有しているのならいいな……と思ったり。自分の中にこっそり秘めておきたい、秘密めいた夢の中の出来事のようなお話、として。......)

*
最後に、宣伝かというと無料ゲームなので宣伝ということもないでしょうか(そもそもこの記事のテーマが「#自己紹介をゲームで語る」なので自己紹介にもあたる部分ですか)、私がフリゲ時代に作った(k.imayui名義で公開した)RPG「ユトレピアの伝説」と「12亜神伝」のリンクを置いておきます。
自由度の話のところで挙げていますが、自身のゲーム制作の土壌の根幹となったドラクエ・FFの上に、本記事で書いた「サンサーラナーガ」の影響を多分に反映しているRPGになっていると思います。特に「ユトレピアの伝説」に関しては、それだけでなく自身が当時受けたファミコン諸作品の感動やトラウマの数々をどう自身の中で消化し作品として昇華させるかというのが自身のゲーム制作において超えるべき一つの壁というかテーマとしてあり、それだけが創作の動機ではないですが、それは一つの大きな創作上のテーマではあったと思います。(ちなみに本記事で少しだけ触れているサンサーラナーガのシステム面での特徴だったえものシステムについても「ユトレピアの伝説」に取り入れていますね。えものを直で素材として武器に換えたり以外にえものを素材に替えた上で素材から武器作ったりとか多少違う面もありますが。)
「12亜神伝」の方は、より、自由度の余談で述べている、自身にとって、こういうRPGを作りたい、というRPGの在り方自体を追及しているRPGになるでしょうね。(ただこっちはこっちで自己表現の欲求というのか自我が抑えられなかったのか(もう七年前の作です)、自身の生の精神のようなものが露呈してしまって物語を崩してしまっているかもしれないような面はあるんですよね、終盤で、終盤ではそういうことが起こりやすいのか……ゲーム制作は難しい、いや、フリゲなので、そこはそういうもので・そういうものでこそよかったのかもしれませんが。評価は賛否両論になってしまいますものね......それはわかっていても、止められなかった、ということでしょうか。ゲーム制作は難しい...)
自由度、物語・世界観といったところが、最も自身がRPGにおいて重視するテーマであり、それとゲームシステムをどう絡めるか、という部分もまた世界観の表現と大きく関係する部分であり、(そしてこれも上で述べていますが、残るゲームとなるためにはユーザビリティ面等も重要なわけですが、)そのトータルとしてのゲームデザインを追求していければと思っています。
※尚、本記事「ゲームクリエイターになるまで~ゲームと私~」は結局、一回では語りきれないものとなっており、今後も今回語れていないゲームやそれ以降のSFC~フリーゲームまでを、可能な限り・可能なペース(たぶんゆっくり……)で、自身なりの視点で語っていければとも思っています。
これも重ねてになりますが、元々私自身は、エッセイの類は書きたくない...作品だけを作ってそこに伝えたいとこは全部詰め込みたい...とずっとこれまで思ってきた人間なのですが、長くやってきて、それだけじゃだめということもあるのかも(作品を見てもらえない)と、また仕事の合間休日にnoteを始め(始めた後またすぐ忙しくなってしまったのでしたが)、自身の創作についてまとめる機会かも、外部に出すことで見えてくるものもあるかも、という思いもあり、苦手なエッセイ風なものを書いている次第でもあります。
よければ気軽にフォロー・コメント等頂ければと思います。
※本記事を書くにあたって、ゲームの内容について厳密な検証まではしておらず、当時の記憶頼りのままの部分も多いので、売上やゲーム内のシステム等について誤り等もあるかもしれませんが、その点は、ご了承ください。その上でご指摘等も頂いてもかまいません・ありがたく思います。勿論ちょっとした感想・雑感・思い出等何でも感じた所あれば気軽にコメント等頂ければと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
