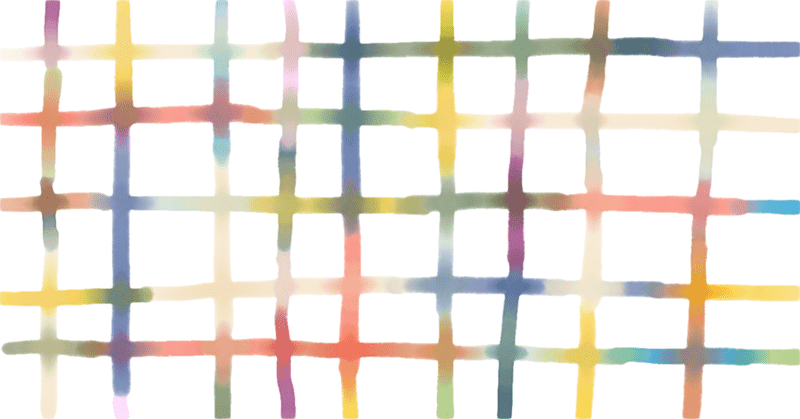
広辞苑を読む。29
起きたら土砂降りだったので、二度寝してしまった。お昼頃ようやく布団から抜け出して、ブランチを食べ、机上に広辞苑を開く。今日はP139から読んでいこう。
【息が長い】一つ仕事を倦むことなく長期にわたって続けているさまをいう。「息の長い刊行物」
めちゃくちゃ息が短いです。せめて広辞苑ぐらいは……。
【息を張る】深く呼吸して息を腹にこめる。
最近ずっと猫背で息も浅くなって大変よろしくないので、なんとかしたい。
【粋】(「意気」から転じた語)①気持ちや身なりのさっぱりとあかぬけしていて、しかも色気をもっていること。②人情の表裏に通じ、特に遊里・遊興に関して精通していること。
現代でいう「粋」とは何だろうか?
【意義】②物事が他との連関において持つ価値・重要さ。
「他との連関」というのが気になる。まあそもそも価値って他と比較しないことには判定しにくいか。
【行き憂し】行きづらい。行くのがいやである。
めっちゃわかる。
【生き甲斐】生きるはりあい。生きていてよかったと思えるようなこと。「—を感ずる」
最近、生きがい感じてますか? 英語で「IKIGAI」とも言われるけれど、あれはちょっとビジネスライクすぎる感じもする。
【生き方】①生きる方法。生活の方法。②(正しくは「行き方」か)人生に処する態度・方法。
この区別がよくわからない。「あの人の生き方は」っていうとき、①の意味にも②の意味にもとれるし。信念に伴った行動選択みたいなやつが「行き方」なのだろうか。
【経緯】こみいった関係。事件の経過。
漢字で書いてあったら間違いなくケイイって読む。
【息急き切る】息をきらして急ぐ。ひどく急ぐさまにいう。
文学的表現。
【閾値】①ある系に注目する反応をおこさせるとき必要な作用の大きさ・強度の最小値。②生体では感覚受容器の興奮をおこさせるのに必要な最小の刺激量。しきいち。限界値。
これが低すぎると感覚過敏ということか。
【生きている化石】(living fossil)地質時代に反映した祖先型に形態的によく似た現生の生物。シーラカンス・カブトガニ・イチョウなど。また、祖先型の化石が知られていなくても、明らかに原始的な型を保っているナメクジウオなど。生きた化石。
「生きた化石」っていう方がよく聞くけど、確かに今生きてるんだから、生きている化石だよな。
【いきなり団子】さつまいもを生のまま小麦粉の皮で包み、ゆでたり蒸したりする菓子。汁に入れる場合や、粒あん入りもある。熊本県・福岡県で作る。いきなりだんご。
某ステーキチェーンの親戚店ではない。ぱっと見プリンみたいでかわいい。
【生き抜く】苦しみや困難を乗り越えて、どこまでも生き続ける。生き通す。
この説明は今までの中で一番かっこいい。
【「いき」の構造】九鬼周造の主著。一九三〇年(昭和五)刊。「いき」の美意識が、媚態・意気地・諦めの三つの契機から成り立つとし、日本人の美意識や価値観を解明する。
読んでみたいけれどなかなか手が伸びない……。
【生きはだかる】望みもないのに、この世にいたずらに生き残る。
なんかもっと力強いイメージだったけれど、そういう意味だったのか。
【医業類似行為】医師でないものが行う医療行為。資格制度のある按摩・マッサージ・指圧・鍼灸・柔道整復業や、資格制度の無いカイロプラクティック・整体・リフレクソロジー・アロマ-セラピーなど。
アロマとかまで入るのか。
【イギリス連邦】(The Commonwealth of Nations)イギリス連合王国(英本国)を構成するイングランド・スコットランド・ウェールズ・北アイルランドおよび近隣諸島と、多くはかつて英帝国に属しその後独立した諸国の連合体。
広辞苑では51になっているが、再加入などがあり現在は56国になっている模様。かつての英国の強大さが窺い知れる。
今日はここまで。ほぼ「生き〇〇」と「行き〇〇」だったが、「行き」の項目は全て「→ゆき」に飛ばされたので、ヤ行が大変。
次回はP143【熱り立つ】から。
昔々、あるところに読書ばかりしている若者がおりました。彼は自分の居場所の無さを嘆き、毎日のように家を出ては図書館に向かいます。そうして1日1日をやり過ごしているのです。 ある日、彼が座って読書している向かいに、一人の老人がやってきました。老人は彼の手にした本をチラッと見て、そのま
