
三重県明和町: 学生と企業が連携し地域課題解決に挑む勉強会(全4回のシリーズ1回目)
三重県明和町において、産官学の連携のもと、地域の課題解決を目指す特別な起業勉強会が開催。イマクリエは、令和5年度に明和町から産学官連携による三重明和インキュベーションセンター利用促進業務を受託し、本勉強会の企画、運営を担当しました。
どの様な経緯で明和町とイマクリエは「地域課題解決」に向けて県内外の企業経営者と皇學館大学の学生が協力したのか。
その過程と実際の勉強会の様子、そしてその先に見据える未来について全4回に分けて詳しくご紹介します。
第1回目では、勉強会開催に向けての紆余曲折やそれぞれの想いなどをお届けしたいと思います。
企業誘致に向けて県内外企業との面談の次に「勉強会」を企画
多くの地方自治体が直面している課題の一つに「人口流出」があります。特に「若者の流出」は大きな問題です。
地方で生まれ育った若者が、就職先として大企業が集中し経済の中心となる東京などの都市へと流出しています。そのため、地方の企業は人手不足に悩まされ、発展が停滞していくことも。
地方の自治体などはこの若者の流出に対して、それぞれの対策を行っています。多くの自治体は、首都圏などからの移住や企業誘致に力を入れており、人口増加を行うように。
三重県明和町でも同様の課題に直面しており、企業誘致などに力を入れてきました。
2022年12月に新たなサテライトオフィスである「三重明和インキュベーションセンター」を開設。この施設は、明和町の中心地で大型複合施設に隣接している好立地にあり、企業誘致を行う上で重要な存在です。
イマクリエと明和町の関係性は、この企業誘致事業を共に行ったことがきっかけ。
明和町は、豊かな自然と歴史を有する三重県の魅力的なベッドタウン。
近年では、産業用大麻の生産をはじめとする革新的な産業で注目を集めており、地域経済の活性化に向けた新たな動きが見られます。
大麻産業に興味のある企業やIT関連企業など、多くの県外企業と対話を行い、関係性を構築。

そして県外の企業との関係性が出来た明和町は翌2023年度事業として、インキュベーションセンターのさらなる活用促進を目的に、何かイベントを行いたいと考えていました。
そこで、イマクリエから最初に提案したのが「企業間勉強会」。
県外企業と明和町企業が「地域課題」に対して意見交換していくというもので、主目的は県外企業が明和町の地域課題解決ビジネスに参入するきっかけを作っていくことです。
この提案に対して明和町の方々は「悪くはない」といった反応。
正確には「悪くはないが、足りない」という感じでした。
企業+学生の勉強会
話し合いの中で議論に上がったのが、勉強会を開催しても「参考になった。また何かありましたらよろしく。」程度で終わってしまう可能性が大きいのではないのかという点。
「勉強会」に対して企業が本気になるカンフル剤の様なものが必要なのではないかと考えを巡らせている中で「学生を交えてできませんか?」という提案が明和町の方から出ました。
学生が参加することによって企業同士で考えつかないような新鮮なアイデアが生まれて「勉強会」に活気をもたらすということ。
この提案を直観的に「素晴らしい」と感じました。
私も自身が在住する町の活性化協議会に参加していて街づくりの会議にも出席しています。その会議には高校生も参加しているのですが、彼ら・彼女らの発言は会議を大いに活性化させています。
大人同士だとどうしても空気を読んだ発言が多くなり、会議が停滞することもあります。そんな時に高校生の意見は突拍子もないものもありますが確信をついたものもあり、気付かされることも多かったのが事実。
明和町でも県外企業と明和町企業の「勉強会」に学生を交える案で考えようということになりました。その上で「学生にもメリットを」ということで県外企業を含めた就職説明会もインキュベーションセンターで開催するという案も出ました。
学生をどの様に集めようかという点に関しては、明和町とすでに関係性があった伊勢市にある皇學館大学に打診することになりました。
皇學館大学と明和町の繋がりは、平成30年に産学官連携日本酒プロジェクトを明和町と行ったことがきっかけ。その後も、皇學館大学の新田均教授が理事長を務めるHIDO(一般社団法人麻産業創造開発機構)がインキュベーションセンターに入るなど関係性は継続していました。
そこで、下記2案を皇學館大学の新田教授に提案することに。
県外企業と明和町企業の「勉強会」に皇學館大学学生が参加
県外企業を含む就職説明会に皇學館大学学生が参加
その提案に対して新田教授からの回答は意外なものとなりました。
皇學館大学学生が参加する「起業」勉強会の開催へ!
「就職説明会をインキュベーションセンターで開催するよりも大学に来てもらった方がいいので、あまり魅力的ではないですね。それよりもうちの学生と企業の方による起業勉強会はどうでしょうか?」
皇學館大学の新田教授から、まさかの逆提案を頂いたのです。
新田教授に真意を聞いたところ、興味深い回答が。
「皇學館大学では、現代日本学部の経営革新コースがあり、その中の2年生の何人かが起業したいという考えを持っているのですが、大学では学生に生の経営学に触れさせることはできない。そこで企業の経営者の方との勉強会を通じて起業とは何かを学生に学んで欲しいのです。」

大学生の中には、早いうちから起業を志望する学生もいますが、実際の会社設立には資金調達、ビジネスプランの作成、法的手続きなど、多くのハードルが存在します。そこで勉強会を通じて学生は起業を体験してみるという試み。
「本当に起業するためには何が必要かを実際に起業した経営者の方などと接することで学生に学んで欲しい」というのが新田教授の考えでした。
その後、新田教授や明和町の方と協議を行い、企業同士の勉強会に大学生が参加というスタイルから「大学生が主導の勉強会」に変更。
起業を考える大学生が自身のビジネスプランを企業の方にアドバイスをしてもらいながらブラッシュアップしていくという内容で行うこととしました。
勉強会は複数回で開催する方向へ。
最初に大学生が自分で考えたビジネスプランを企業の方に見てもらい修正点などアドバイスをもらい、より精度の高いビジネスプランにしていき、最終的には参加者の前でプレゼンを行うというものです。
大学生向けのビジネスコンテストとは違って、プランを出して終わりではなく、実際に起業した方などからフィードバックをもらえるのがこの勉強会のポイントです。さらにビジネスプラン案は「地域課題解決ビジネス」を主として考えたプランとすることと設定しました。
そしてもう1つ、大きな特徴を設けることに。
それは学生にとっても、我々にとっても大きな刺激となりました。
学生が「自分たちでつくる」起業勉強会に!
起業勉強会を開催するにあたって、新田教授から「運営に学生も参加させてほしい」との提案がありました。
というのも、今回参加する学生は自分で起業を考える学生。
自分のやりたいことを自分で考えて実行し、環境も自分で整えるという経験をさせたいということでした。
大学の講義とは違い、この起業勉強会では学生が主体的に動くことが出来る。企業との勉強会でビジネスプランが出来上がるだけではなく、運営を通じてマネージメントも学べるということです。
新田教授は「この勉強会は起業を考える学生にとって、メリットが多い。しかし企業の方にとってはどうなのか?」と心配されていました。
確かに企業の方が、学生のビジネスプランを見てアドバイスを送り、時に相談に乗るという勉強会では時間も労力もかかるが目に見えるリターンは無い状況。
ただ、運営をする我々には不安もありましたが、こうも思っていました。
「きっと企業の方でもこの勉強会を面白いと考えてくれる人がいるはず。」
そうした漠然とした自信は自分自身の心の変化を感じたからです。
大学生の参加で自治体や企業も本気になるはず!
ここまで明和町の方や皇學館大学の新田教授らと話をする中で、私の中でも変化が見て取れる様に。
変化に気付いたのは新田教授の「学生も運営に参加させてほしい」という提案があった時です。
運営は明和町とイマクリエで行うが、そこに学生も一緒に参加していく。
その事を想像したときに、胸が熱くなりました。
長く社会人をしていると、良くも悪くも仕事がパターン化してしまう事も。
そんな中で社会に出ていない学生と一緒に仕事をすることで「何か新しいことが出来るかも」という期待感が生まれたのです。
学生だからいだくことが出来る期待感を、企業の方もいだけるのではないかと思う様に。
学生との交流で、普段の仕事では気付かない発見や教えることで改めて分かることなど、多くの刺激をもらえるという事がメリットになるはずです。
そして学生の強みである「将来性」。
そこにも企業としてのメリットがあると考えたのです。
学生との勉強会を通じてダイヤの原石を探す!
企業と学生がお互いに勉強会を通じてビジネスに対する考えや姿勢を知る事は、それ自体が「就職活動」になるのではないかと考えました。
現在の就職活動は学生がエントリーシートを記入して、面接や試験といったステージを複数回繰り返すというもの。
企業の仕事を直接体験するためにはインターンを行うといった方法が一般的です。その過程は長期に渡り、断続的に行われるといった形。
一方で今回の様な勉強会を就職活動として考えれば、短期集中で企業の方と関われます。
長期にわたる就職活動では、複数社にエントリーして同時進行で行うのが一般的。短期集中の就職活動であれば、1社ずつしっかり考えられるという想像をしました。
また企業にとっても、勉強会を通じてエントリーシートや面接では見えない学生の特徴を知ることも可能となるので、それこそ「ダイヤの原石」を見つけることも可能なのでは?
勉強会を始める前の段階では、あくまで想像の範囲を出ませんでしたが、そんな思いを馳せていました。
そして2023年12月に第1回勉強会が開催。
第1回目にして、想像していた以上の出来事が起こりましたが、その様子は次回のnoteで紹介させていただきます。
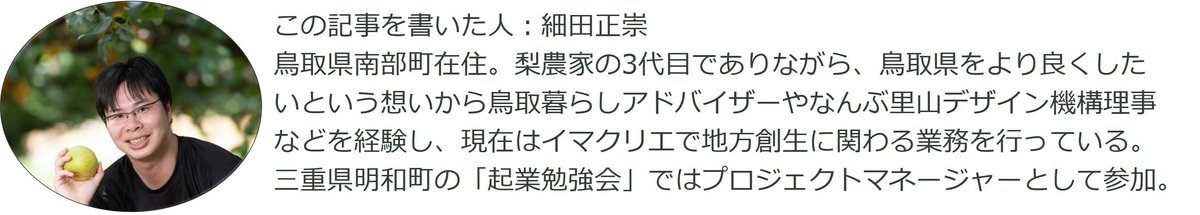
自治体担当者様からのお問い合わせはこちらから
