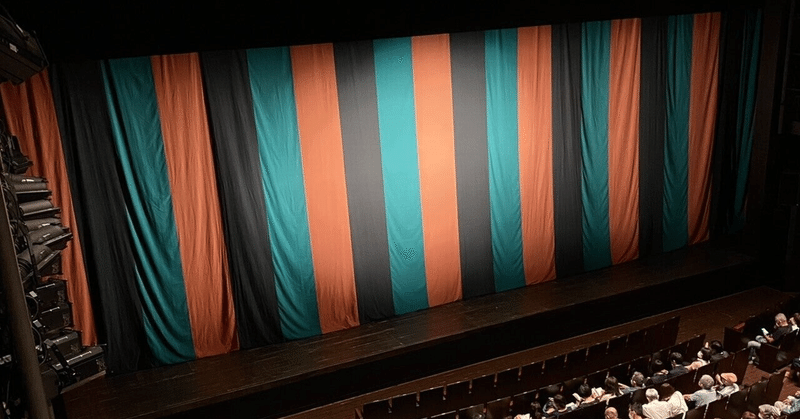
芸術は古びない
くどいですが、
「芸術性」と「娯楽性」について
書いていきます。
私なりの解釈ですが、
「芸術性」の高さに
指標のようなものを作るとしたら、
以下のような観点が
あると思います。
芸術性の三要素
・普遍性がある
・言葉で表現できないもの
・哲学的な題材
誤解のないように、
もう一度言っておきますが、
「私なり」の解釈です。
私も長いこと、
映画、音楽、文学、マンガ、
ゲームなど、
多くの作品に触れてきました。
そんな中で、
「芸術性が高い」
と思う作品は、
この三つのいずれか、
あるいは三つのうち二つか、
すべてを満たしていました。
三要素について、
一つひとつ見ていきましょう。
普遍性がある
私は昔、お笑い芸人を
目指していたことがあって、
ざっくりわけると、
お笑いには二つのパターンがある
と思っていました。
それが普遍性の有無です。
普遍性というのは、
すべてのものに通じる性質。
また、広くすべての場合に
あてはめることのできる性質。
だそうです。
この言い方は、
ちょっと難しいですね。
要するに、誰にでも
当てはまるような性質を
「普遍性」というんですね。
「お笑い」って、
「普遍性」とは
相いれない部分があるんですよね。
別に、お笑い番組ではなくても、
身内で盛り上がる話とかを
思い出してほしいんですが、
大抵の人は、
自分にとって卑近なことに
興味がありますよね。
自分と関係のある話、
もっといえば、
自分の話ですね。
だから、人との会話で
割と盛り上がるのが、
身内の話です。
家族がこうだとか、
友達がどうだとか、
同僚のあの人がどうだとか、
なので、必然的に
「笑い」のテーマも
そこに集中しがちなんです。
「人生は」とか
「人類は」とか
「歴史は」とか、
こういったテーマは
割とお笑いに不向きな
テーマです。
コントであれ、
漫才であれ、
フリートークであれ、
まず、こちらに
興味を持ってもらわなければ、
話しがはじまりせんから、
どんなネタでも、
身近な題材が選ばれがちです。
コントでは
誰もが行ったことのあるような
場所が舞台に選定され、
漫才では、
みんなが興味を持っている
時事ネタが定番です。
テレビやラジオの
フリートークも大概が、
その人の体験したことや
身内の話が多いですよね。
でも、こういう話題は
「普遍性」が高いようで、
実はそれほど「普遍性」が
高いものではないんです。
今は誰にとっても
身近なものかもしれませんが、
10年、20年、
あるいは100年も経ってしまえば、
「普遍性」が
薄くなってしまうでしょう。
その証拠に、
お笑い芸人の過去のネタや
過去の番組が再放送されるのは
稀なことです。
(ドリフが唯一の例外か)
これは、
旬が過ぎてしまっているからです。
昔を知っている人には、
懐かしい思いと
過去の楽しさが
蘇ってくるかもしれませんが、
多くの人には
需要がないものなんですね。
一方、同じお笑いでも
落語や舞台の喜劇は違います。
同じネタを何度もやるのが
普通ですし、
なんだったら、
長い歴史の積み重ねが
あるからこそ、
それらの作品は
歴史に名を残す
「名作」としての
重みが出てくるのです。
噺家のはじまりは、
元禄(1688~1704)
からあるそうですし、
寄席の成立は、
寛政(1789~1801)
だそうです。
シェイクスピアの
戯曲などは、16~17世紀に
発表されたものです。
落語にしても、
シェイクスピアの戯曲にしても、
何百年もの間、
多少は時代によって
アレンジを変えているものも
あるのかもしれませんが、
基本的には同じネタで
公演されているんです。
時代を経ても、
ここまで古びないものは
「芸術」と言わずして
なんと言うのでしょうか。
つまり、これらの作品には、
時代を経ても、変わらない
普遍的な要素が入っていて、
それが多くの観客を
惹きつけるわけです。
私がお笑いでやろう
と思っていたのは、
こっちの方でした。
今生きている時代には、
あまり支持されないかも
しれないけど、
時代が経っても、
楽しめる作品が作れると
いいなぁと思っていたんですよね。
たぶん、お笑いを目指していた
人間の中では、
稀な方だと思います。
おこがましい言い方ですが、
「お笑い」を「芸術」の域に
持って行きたかったからです。
ちなみに、商業的に成功するのは、
やはり「娯楽性」の高い方です。
普遍的なものよりも、
その時に旬の題材を取り上げた
作品の方が
多くの人に支持されます。
でも、作品にとっては
どうなのでしょうね。
ただ「消費」されるのが
いいことなのか……。
長くなったので、
他の二つの項目は、
別の記事にします。
サポートしていただけるなら、いただいた資金は記事を書くために使わせていただきます。
