【無料回】クラファン大失敗と話題になている高野連の決算から高野連の現状を考えてみた
最近は口を開けば「寒暖差」という言葉を使っています。
そうです、かっこいいと思っています。
さて、今回はいつもとは違って高校野球の運営組織である高野連の決算について取り上げようかと思います。
というのも高野連が行ったクラファンが爆死しているというのが話題となっていました、そんな中でクラファンによる資金集めが必要な状況だという事でしょうし、現状がどうなっているのか気になりましたので取り上げてみます。
ちなみに高野連の正式名称は「公益財団法人日本高等学校野球連盟」という名称です。
「公益財団法人って聞いたことあるけど何だかよくわからん!!」
というかたも多いでしょうから、まずは公益財団法人についてざっくり説明しておきます。
法人は基本的に営利法人と非営利法人に分けられます。
いつも私が決算を読んでいる株式会社は営利法人で利益を追求することを目的とした会社です。
私が働いていて仕事を頑張って10億円利益を出せたら「ヤッター!!」と会社全体で喜びます。
一方非営利法人とは利益の追求を目的としない会社です、それこそ公益財団法人には公益とついている事からも分かる通りで目的は公(おおやけ)の利益です。
つまり高野連でいえば高校野球が普及して、野球を安全に、楽しくプレーできる環境作れたらいいよね的な目的で動いているわけです。
なので私が高野連で働いていて仕事を頑張って10億円の利益を出すと「利益出す事頑張りすぎじゃね?」ってむしろ怒られます。
利益をだして再投資したり、内部留保をためたり、配当したりとするんじゃなく、そのお金をそれこそ野球用具の提供や支援なんかに使って野球の普及に努めて行こうぜ的な目的で活動をしているわけです。
そういった事もあって公益財団法人は利益追求ではなく活動自体に公共性があるため、税制などの優遇措置がある反面、過剰な利益を出すことは制度として禁止されています。
高校野球の甲子園の入場料なんかは人気にも関わらず非常に安いですが、それはそもそもの目的が利益を出そうぜじゃないという事もあるわけです。
そういった事もあって、実は高校野球だけではなく例えばオーケストラなど文化的な活動を公益財団法人や公共社団法人など非営利目的の法人として運営してきたところは、利益をあまり出せず内部留保を貯めておけない仕組みになっているので、コロナで大打撃を受けて活動の継続が苦しくなっているところが数多くあります。
そもそも非営利法人という仕組み自体が、コロナのような本当に突発的な不確実性に対しては弱い仕組みになっているんですね。
なのでコロナを経て不確実性に対応し、長期的な活動継続のためにも非営利法人から営利法人への移行を進めている組織なども出始めているようです。
ちなみに高野連は、もちろん上場企業などではないので、通常であれば詳細な決算内容というのは分からないわけですが、公共財団法人という公共性から優遇措置が取られているという事もあり、決算情報の開示義務が設けられていますので行政庁に開示請求をすると詳細な決算情報を見る事ができます。
高野連の場合はそもそもホームページで開示していますので今回はそれを見ていきます。
ですが決算を見る前にそもそも高野連について少し知っていきましょう。

まず、組織として高野連は日本学生野球協会という学生野球全体を取り仕切る組織の下部組織となっていて、一方で高野連の下に都道府県の高野連が存在する形になっています。
また、どういった活動をしているのかというと


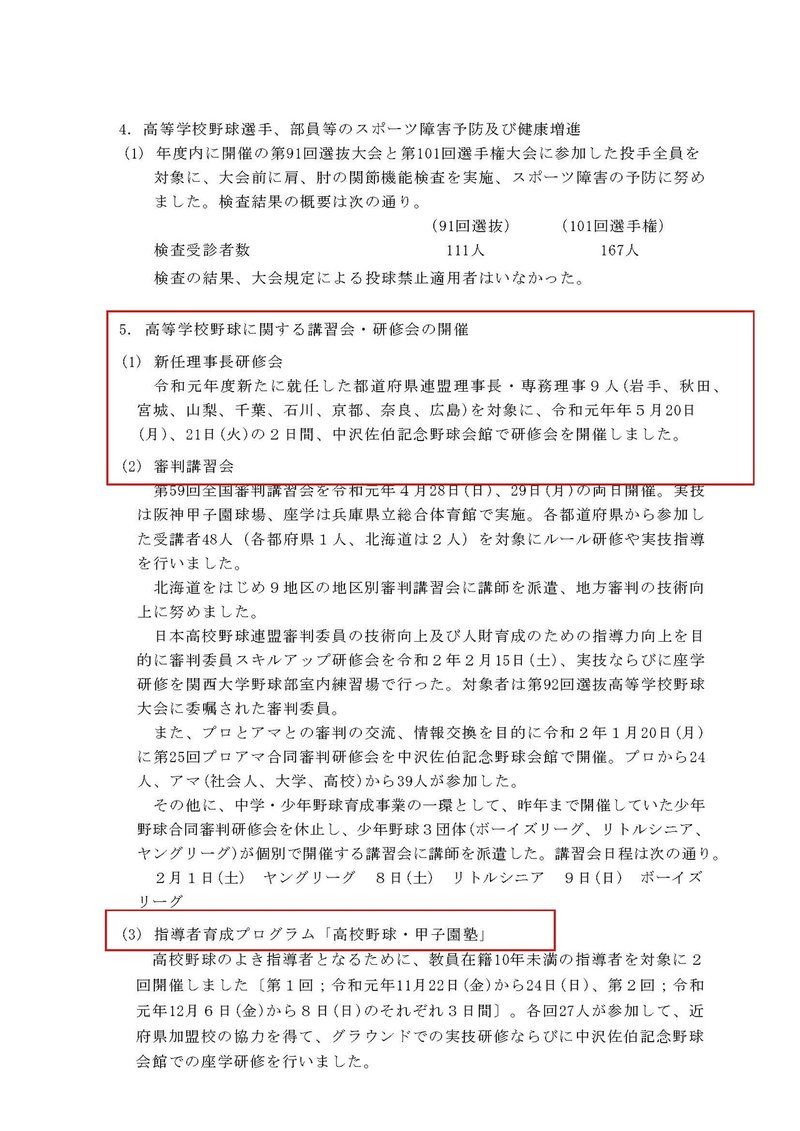

コロナ前の2019年度の事業報告によると、高校野球を普及、監督、指導するために、評議会の開催や各種委員会の開催、高野連の下部組織である都道府県の高野連会議を開催など、基本的には会議を定期的に行って高校野球の指導、監督、普及を行っているようです。
もちろん主要な事業としては大会運営があり、夏と春の甲子園、神宮大会、国体の運営なども行っています。
ちなみに地方大会も高野連が運営し、各都道府県の高野連はその協力を行う形になっているようです。
その他にも高校野球関連の調査や、審判や指導者の講習会やなども行ったとしています。
それではそろそろ高野連の現状について見ていきましょう。
クラファンが必要な財務状況なようですから、まずは財務状況がどうなっているのか見ていきます。

まずは手元資金ですが、現預金は1700万円減って800万円ほどしかない事が分かります。
2020年の2月末の段階でも2500万円ほどしか持っていませんから先ほども書いたように、手元資金を残せる仕組みになっていないんですね。
一方で、特定資産として各種基金は多額で計9.4億円ほどとなっています。
例えば選手権大会準備基金が1.2億円ほどあります、大会開催のためには手元資金がほぼゼロの状態からの開催はできませんし、一定金額を基金として残していっているようです。
他にも例えば選手権大会記念事業基金が1億円など、大会の記念事業の基金も多額となっています。
記念事業としてどういった活動を行っているのかは詳しくは分かりませんが、必ずしも必要なものでは無いでしょうから財務的にはこういった記念事業基金を運営費に回すという事は出来そうです。
また、基金など特定資産の全体の金額としては、コロナ前が14.7億円だった所から9.4億円ほどへ5.3億円ほど減少しています。
コロナ禍での1年間での減少額が5.3億円と1/3ほどの資産を失ってしまったようで、非常に苦しい状況です。
とはいえ非常に苦しいですが今年ぐらいまではどうにかなりそうではありますね。
大会や記念事業の基金として実質的な内部留保をためてきたので、何とかなっているようです。

一方で負債に関しては流動負債が3800万円となっています、事業内容としても大会の運営以外で特段のコストはかからないですから負債は少ないです。
ただ、大会運営となると一気に多額の資金が必要となるでしょうから、甲子園開催前後は資金の移動は大きくなりそうです。
続いて2020年3月~2021年2月の収支を見ていきましょう。

売上(経常収益)を見てみると11.4億円→9600万円と91.6%減と大半を失っています、その要因は何なのかというと入場料収入が9.8億円減少したためです。
実は高野連はコロナ以前では売上の86%と大半を入場料収入が占める形になっていたので、無観客や大会中止で売上がほぼなくなっています。
そして朝日新聞や毎日新聞などからスポンサー料、協賛金などは無いようです。
調べてみたところどうやら、朝日新聞や毎日新聞というのは甲子園の協賛企業ではなく共同開催の企業となっていて、主催者側だったようです。
個人的には全く知りませんでしたから驚きです。
そういった新聞社は人的な支援や金銭的な負担もしているのでしょうが、甲子園の広告効果はどう考えてもそれより高いでしょうから、共同開催ではなく適切なスポンサー料や広告料をもらえば資金的な問題は解決できそうです。
高校の部活動という事で広告費やスポンサー料は取らないという事で運営しているんでしょうが、朝日系列のテレ朝は「熱闘甲子園」などの番組を作って広告費を得ていますし、甲子園の出場選手はメーカーから用具提供を受けて広告塔となっています。
実質的には甲子園は広告の場となっているので、運営側もきちんと広告費やスポンサー料を取って資金的な問題を解決するのが、早いのではないでしょうか。

ちなみにコスト面では、事業費用は10.1億円→5.9億円と多くの大会が中止となる中で4割減となっています。
費用の内訳を見てみると人件費面では、給与は5500万円ほどとなっており、人員数が分からないので何とも言えませんが、年に数万人規模のイベントを複数回開催すると考えると総額としては少額です。
というのも高野連というのは基本的にはボランティアで動いている組織のようで、特に多くは教員がボランティアで参加する形になっているようです。
なので基本的な組織運営では、一部の常勤の方のコストしかかからないという事ですね。
一方でコロナ以前では業務委託費が1.9億円、販売手数料が6300万円、臨時雇賃金が2100万円といった形で外注費が多額です。
甲子園などの大規模な大会運営はボランティアの他に外注で運営されていたという事ですね。
また、旅費交通費が7984万円から2237万円へと大きく減っています、高校野球の審判はボランティアで交通費支給という話を聞きますから、大会がなくなると交通費が大幅に減ると考えられます。
そして大半の支出は減る中で増加した支出としては、支払助成金が1.48億円→2.27億円へと増加しています。
都道府県の高野連はそもそも甲子園の入場料収入もないですし、そもそもが全国高野連からの助成金の収入に頼っていたことが考えられます。
そこにコロナでさらに運営が苦しくなり、支援額が増加したという事でしょう。

そんな中で最終的には、計5.2億円ほどの赤字となってしまったようです。
同様の状況は今も続いているでしょうし、甲子園の開催中止となるよりも無観客開催の方がコストがかかるでしょうから、都道府県組織の支援の資金を含め組織運営はこれ以上に苦しい状況だと考えられます。
という事で、高野連は売上の9割弱が入場料収入だったという事で、甲子園の中止、無観客開催の中で収入源を失っています。
大会や記念事業の基金として、公益財団法人ながらも実質的な内部留保をためておいたことで今年くらいは乗り切れそうではありますが、地方の高野連の支援が増えている事や、入場料収入がない中で無観客開催の方が中止より赤字が増加しているであろう現状を考えると、苦しい状況にいる事は間違いなさそうです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

