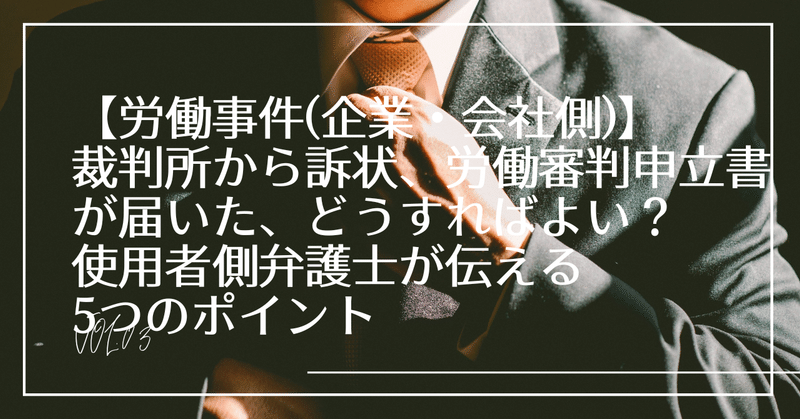
【労働事件(企業・会社側)】裁判所から訴状、労働審判申立書が届いた、どうする?〜使用者側弁護士が伝える5つの確認ポイント〜(24/3/29)
(※2024年3月29日に更新されました)
こんにちは、使用者側弁護士として活動している、弁護士飯島(第一東京弁護士会)です。
経営者や会社担当者の皆様、次の経験はありませんか?
・ある日、裁判所から訴状が届いた
・どうやら、退職した元従業員が当社を訴えたようである
・しかし、これまで、訴訟などの裁判手続を経験したことがないため、どうように初動対応をすれば良いかわからず困っている
このページでは、使用者側弁護士が、企業(会社)が裁判所から訴状や労働審判申立書を受領した場合に、最初に確認すべき5つのポイントを解説します。
最後までお読みいただくと、特に、初めて労働事件を抱えることになった企業(会社)が、慌てずに初動対応をすることができるようになります。
それでは中身に入っていきましょう。
第1 確認すべき5つのポイント
1 企業側での労働事件の始まり
労働者が裁判所に訴訟提起などをした場合、裁判所から企業に訴状や、裁判所作成の書類が郵便(特別送達)で送達されます。
企業がこれを受けとったら、すぐに同封された書類を確認しましょう(放置は厳禁です)。
ここでは、会社側(通常は訴えられた側の)弁護士の立場から、確認すべき5つのポイントをご説明します。
2 5つの確認ポイント
まず次の点を確認します。
①どの裁判所が管轄しているか
②第1回期日はいつか
③第1回期日の場所(法廷)はどこか
④答弁書の提出期限はいつか
⑤事件は、訴訟、労働審判、仮処分のどれか
(どのような主張をしているか)
では、何を見て確認すればよいでしょうか?
通常、裁判所から届く書類には、「第1回口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状」という書類があります。
ここには、①裁判所(支部の場合は支部名)、係属部(たとえば、東京地裁民事X部Y係)、②第1回期日の日時及び③場所(法廷の番号)、④答弁書提出期限が記載されています。
この書面でこれらを確認することができます。
また、⑤の訴訟か否かは、同封されている、労働者作成の書面のタイトルが、
「訴状」となっていれば訴訟、
「労働審判手続申立書」となっていれば労働審判、
「仮処分命令申立書」となっていれば仮処分であることがわかります。
また、事件番号が令和X年(ワ)となっていれば訴訟、令和X年(労)となっていれば労働審判であることが確認できます。
3 なぜ訴訟か労働審判かを確認することが重要か?
私が企業から、「裁判所から書類が届きました。労働者から「訴えられた」みたいです。」と言われた場合、次のようなことを言います。
・「労働者からの書面には、訴状と書いてありますか、それとも、労働審判申立書と書いてありますか?」
なぜかというと、訴訟か、労働審判かでは、準備できる期間が決定的に違うからです。
次で詳しく説明します。
4 訴訟か労働審判かの確認が重要な理由
⑴ 訴訟の場合
訴訟の場合、実務上、答弁書に労働者の請求を争うことを明記した上で、詳細の主張は、第2回期日までに行うという記載とすることが認められています。
なお、準備可能であれば、答弁書の段階から積極的に主張反論していくことも効果的です。
そして、事前に答弁書を提出することを前提に、第1回口頭弁論期日を欠席することも認められています。
この場合、欠席しても答弁書に記載された主張がなされた扱いになります。
これを「陳述擬制」といいます。
その後、企業は、第2回期日までに、詳細の反論を記載した準備書面や証拠を提出することになります。
第2回期日以降は、出頭する必要がありますが、企業が弁護士に委任している場合、企業担当者の方の出頭は必ずしも必要ありません。
⑵ 労働審判手続の場合
ア 労働審判手続とは何か
これに対して、労働者側は労働審判手続を選択することもできます。
どの手続を選択するかは訴える側の労働者にあります。
労働審判手続は労働審判官(裁判官)1名と労働審判員2名で労働審判委員会を構成します。
そして労働審判員会は事案の実情に即した上で、まずは話し合いでの解決を目指します。
労働審判員とは、「労働関係に関する専門的んな知識経験を有する者」(労働審判法1条)をいいます。
訴訟と異なり、この方が審理に加わることが特徴的です。
労働審判手続の詳細を知りたい場合、裁判所のHP(こちら)を確認してください。
また、訴訟とは異なる特徴的な点は、労働審判委員会(主に裁判官)が当事者から直接事情を聴取する方法で審理を進めていくことです。
裁判官が双方当事者が同席している場で直接質問をしていくイメージです。
そのため、企業側も事情をよく知る方や責任者が出頭する必要があります。
この第1回期日の出頭の要否が訴訟とは大きく異なる点です。
イ 労働審判手続は第1回期日が勝負であること
労働審判に関する法律には、次の定めがあります。
(迅速な手続)
第十五条 労働審判委員会は、速やかに、当事者の陳述を聴いて争点及び証拠の整理をしなければならない。
2 労働審判手続においては、特別の事情がある場合を除き、三回以内の期日において、審理を終結しなければならない。
労働審判規則
(労働審判手続の期日における手続等・法第十五条)
第二十一条 労働審判委員会は、第一回期日において、当事者の陳述を聴いて争点及び証拠の整理をし、第一回期日において行うことが可能な証拠調べを実施する。
2 労働審判官は、第一回期日において審理を終結できる場合又は第一回期日において法第二十四条第一項の規定により労働審判事件を終了させる場合を除き、次回期日を指定し、当該期日に行う手続及び当該期日までに準備すべきことを当事者との間で確認するものとする。
(主張及び証拠の提出の時期)
第二十七条 当事者は、やむを得ない事由がある場合を除き、労働審判手続の第二回の期日が終了するまでに、主張及び証拠書類の提出を終えなければならない。
すなわち、労働審判手続は、3回以内の期日で審理を終結することを予定している制度です(労働審判法15条)。
また、やむを得ない事由がある場合を除いて、第2回期日が終了するまでに、当事者は主張及び証拠書類の提出を終えなければならないとされています(労働審判規則27条)。
もっとも、実務では、第1回期日で労働審判委員会の心証(どちらの主張が認められるか)が固まるケースが多いです。
つまり、""第1回期日で勝負が決まる""ことを意味します。
また、第1回期日の所要時間は、概ね2時間程度であることが多いです。
そのため、多くの事件では、第1回期日の後半(権利関係の審理が終了した後)から調停成立に向けた話し合いを行い、その期日でまとまれば終了します。
持ち帰って調停案を検討する必要がある場合は、第2回期日が指定され、第2回期日では、調停成立に向けた話し合いを続けるというイメージです。
したがって、労働審判手続の場合、訴訟のように「追って主張する」ことは許されておらず、第1回期日までに、""フルスケール""の主張反論をする必要があります。
ウ 労働審判手続の場合には準備期間が短いこと
ところで、労働審判の場合、申立てがされた日から40日以内の日に第1回の期日を指定するというルールがあります。
また、答弁書の提出期限は、通常、期日の1週間前〜10日前に設定されることが多いです。
そして、裁判所から書類が届くまでのタイムラグがあることも加味すると、企業が裁判所から書類を受け取ったタイミングから答弁書提出期限まで、数週間しかないということも珍しくありません。
このタイミングから、依頼する弁護士を探した上で、必要な事実関係やヒアリングを行うとなった場合、すぐに準備を始めないと期限までに間に合わないおそれがあります(しかもフルスケールです)。
そのため、裁判所から書類が届いたら、すぐに対応を開始しなければなりません。
5 労働者の主張と証拠の確認
第1回期日及び答弁書提出期限などを確認した後は、労働者の主張と証拠を確認します。
この点、裁判では、ある法律効果が発生・消滅するための要件となる具体的事実が認定できるかを審理します。
この事実のことを「要件事実」といい、訴訟類型ごとに何を主張立証すべきかがあらかじめ決まっています。
たとえば、労働者側がその企業との労働契約が存続していることの確認(地位確認)を求める訴訟を提起した場合、これを争う企業としては、退職合意の事実を主張することが反論方法の一つになります。
この場合、企業としては、たとえば、企業からの退職勧奨に対して、労働者がこれに応じたという事実を主張立証することになり、その証拠として、労働者が署名・押印した退職合意書や退職届を提出することが考えられます。
このような話であれば、まだシンプルですが、企業がした解雇の有効性が争われる場合には、労働者は企業が解雇権を濫用したことを主張立証します。
これに対して、企業は、その解雇権が濫用されていないことを主張立証します。
このように、具体的な事実を「評価」しないと要件が充足しているか判断できない要件のことを、「規範的要件」といいます。
たとえば、解雇権の濫用があったと認められた場合、解雇が無効になりますが、どのような事実が解雇権濫用と評価される事実(「評価根拠事実」)となるか、または、評価されない事実(「評価障害事実」)となるかは、専門家でないと整理は難しいと思います。
特に、労働事件では規範的要件が争点となる類型が多いです。
これらの観点から、企業側としては、労働者側の主張は何か、これを裏付けるものとして提出されている証拠は何かを確認した上で、主張反論を組み立てていくことになります。
たとえば、労働者側が主張立証責任を負っている要件事実について、企業側が反証することによって、労働者の主張立証は成功していないことを主張していきます。
第2 方針の決定
1 労働者の主張を争うか
労働者の主張を確認した後は、大きな話として、労働者の結論部分の主張を争うか否かを検討します。
しかし、通常は、企業側にも言い分があるため、基本的に争うことになると思います。
そうではないと、裁判にまでいかないと思います。
2 労働者の主張を争う場合の検討手順
そこで、労働者が主張している事実のうち、事実として認められる部分と、認められない部分を確認します。
事実として認められない部分については、企業側の主張(認識)を明らかにするとともに、その主張(認識)を裏付ける証拠を提出する必要があります。
このように、労働者の主張する事実関係に対し、企業側の主張(認識)を明らかにすることを「認否」といいます。
具体的には、答弁書など企業側で作成する書面に、労働者の主張に対する認否を記載した上で、企業の言い分(主張反論)などを記載していくことになります。
ところで、裁判所は、一般的に、証言といった主観的な証拠よりも、当時作成された客観的な証拠(簡単にいうと紙で提出できる証拠)の信用性を高く評価します。
そのため、弁護士からも、企業の言い分を裏付ける客観的な証拠があるかを軸に考えることが多いため、打ち合わせの際には、客観的証拠をはじめ、時系列表(5W1H)、組織図を共有できるとスムーズだと思います。
単に、「暴言があった」とか「パワハラがあった」とか「あの社員は問題だ」とかの抽象的な主張ではなく、なぜそのように言えるかの具体的なエピソードを明らかにする必要があります。
なお、あくまで問題となるのは、「事実」であるところ、過去の事実関係を把握している方の協力を得られなければ、弁護士として主張を組み立ていくことはできません。
そのため、""良い答弁書""を作成するためには、企業担当者の協力(事実関係や証拠関係の共有)が不可欠です。
わかりやすくいうと、弁護士が当時の状況を""追体験""できるようにすることが重要です。
企業担当者が全ての事実関係を共有していないと、弁護士として予想外の反論を相手方弁護士からされることにより、不利な展開になってしまいます。
3 和解の可能性などの戦略立案
⑴ 訴訟の場合
訴訟の場合、企業側の反論に対して、労働者側がそれに対する反論と主張の補充、これに対して企業側がさらに反論・・・を繰り返し、双方の主張が出尽くすまで行います。
この過程で裁判官が争点整理をすることにより、主要な争点が絞られていきます。
これらの途中で和解協議が行われることがありますが、和解が難しければ、証人尋問を実施した後に判決になります。
和解協議のタイミングは、序盤・中盤・終盤(証人尋問前・証人尋問後)であり、裁判官から適宜和解の意向を確認されることも多いですし、双方当事者の一方から和解の提案をすることもあります。
⑵ 労働審判の場合
他方で、労働審判の場合、第1回期日が勝負になりますので、第1回期日までに、フルスケールの主張をした上で、和解に向けた戦略も検討しておく必要があります。
通常、第1回期日の後半(権利関係の審理が終了した後)に、労働審判委員会が評議をした後(一旦当事者は退席します)、労働審判委員会が双方に対して、和解の意向を確認しながら進めていきます。
和解の意向の確認方法は、労働審判委員会と一方当事者が個別に行う方法で進められることが多いです。
企業としては、労働審判委員会の心証も踏まえ、和解の意向の有無・内容を伝えることになります。
労働審判委員会が評議をしている時間や、一方当事者が労働審判委員会と個別に協議している時間、他方当事者は部屋の外の廊下や控え室などで待機します。
この時間を使って、弁護士が企業担当者との間で最終的な和解方針を協議することも多くあります。
和解が成立すれば終了しますが、どうしても折り合いが付かず、和解が難しいとなった場合、原則、労働審判委員会が労働審判を言い渡すことにより終了します。
その後、当事者の一方が異議申立てをした場合、労働審判の効力は失われて訴訟に移行します。
他方、双方当事者が一定期間に異議申立てをしない場合、労働審判の内容が確定します。
第3 会社側としてすべき対応のまとめ
弁護士と協力して進めてく場合の手順は、次のとおりになると思います。
1 顧問弁護士がいる場合の対応
すぐに報告・相談しましょう。
➡︎委任の有無(弁護士から見ると受任の可否)を検討しましょう。
➡︎(委任する場合)委任契約を締結した上で・委任状を作成してもらいましょう。
➡︎弁護士と企業担当者で協力して、答弁書を作成・提出してもらいましょう。
もともと顧問弁護士がいて、すでに相談していた案件が訴訟等に移行した事案であれば、すでに答弁書作成のための情報共有はある程度していることになります。
この場合、その続きを本格的に行うことになります。
ところで、実務を経験して思うことは、細かい法解釈が争われるような事案はほんの一握りであり、大半の事件は、""事実関係の有無(法適用の場面)""が勝負のポイントになるということです。
そのため前述したとおり事実関係の整理と、裏付け証拠がとても重要になります。
2 顧問弁護士など委任する弁護士がいない場合の対応
顧問弁護士がいない場合、弁護士に委任するのか、委任するとしてどの弁護士に依頼するかを早急に検討の上、依頼できる弁護士を探します。
ただし、通常、企業が弁護士の協力を得ずに上記の対応を行うことは難しいと思います。
労働審判手続の場合、すでに説明したとおり、準備期間が非常にタイトですので、弁護士を探している間に、気がついたら残り時間がないということにならないよう、速やかに動かれた方が良いでしょう。
弁護士にも労働事件を扱うスタンス(労働者側、使用者側、双方)や、それぞれのタイプが異なりますので、企業にあった弁護士に依頼できるのがベストです。
3 まとめ
以上、訴状などが届いた場合の確認ポイントやその後の進め方のポイントを説明しました。
訴えられてしまった以上、企業として認められない請求だったとしても、これに反論していかないと敗訴してしまいます。
初動で出遅れてしまうと、挽回が難しくなってしまうことは、おわかりいただけたと思います。
企業担当者のみなさま、納得行く訴訟追行ができるよう、応援しています。
経営労働相談のお申込みはこちら。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
