ジャック・ラカンの精神分析理論を参考に生きることになぜ不安がつきまとうのか考えた。
生きることは「不安タスティック」である。これはみうらじゅんさんの考えた造語で、不安だからこそさまざまな可能性が秘めているというポジティブな意味が込められている。
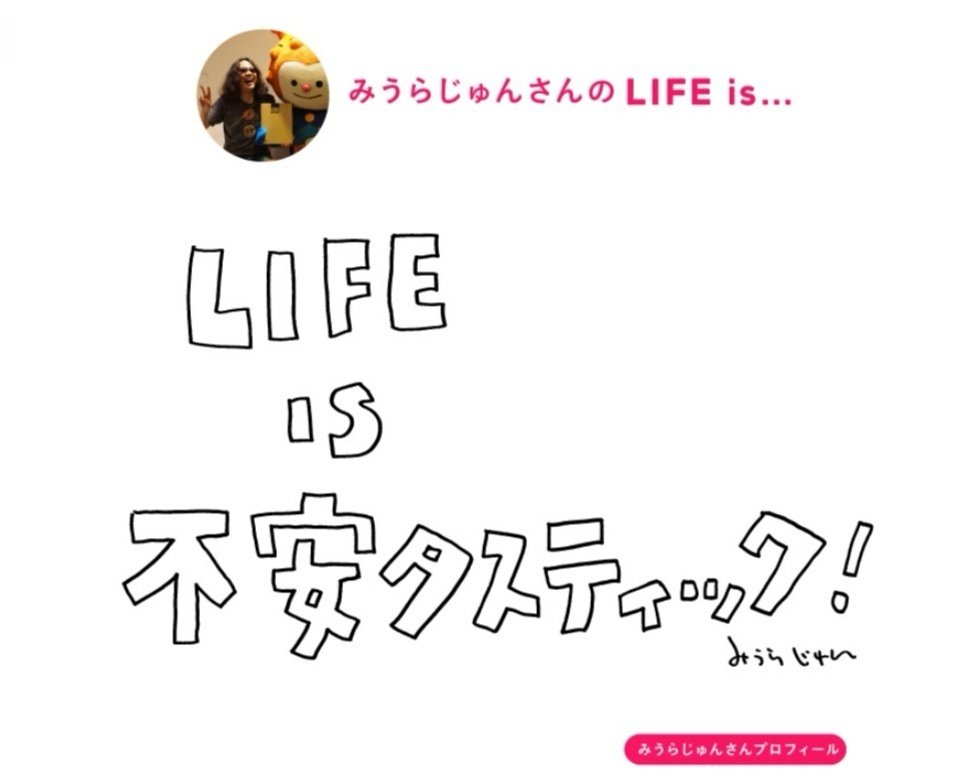
確かに生きることには不安や孤独感がつきまとう。人はそれを埋め合わせる為に、忙しく働いたり、趣味に没頭したり、恋人や家族と過ごしたりすると言ってもいいくらいだ。
でも、どんなに活動的に動き回っていても、ふと独りになると、不安がジリジリと忍び寄ってくる。生きることにつきまとうこの寄る辺なさはいったいどこから来るのだろう?
今回は哲学者であり精神分析家のジャック・ラカンの入門書「疾風怒濤精神分析入門」を参考に、生きることにつきまとう根源的な不安について自分なりに解説してみようと思います。少し長くなりますがご容赦を。

まず、前提から。ジャック・ラカンは人間の心的次元(精神)を「想像界」「象徴界」「現実界」とうい三つの枠組みに分類している。それぞれの領域は。
「想像界」
イメージの領域。人は絵画や映像、人の表情、空模様など様々な事象から「さわやかだな」「不穏だな」「優しそうだな」などイメージを捉えることができ、同時にその様々なイメージを統一的に把握することも可能。
例えば自分の身体からは「頭が痛いな」「お腹がへったな」「肩が凝るな」など複数の器官がバラバラにイメージを送ってきますが、人はそうしたイメージ全ての総体として、これが自分の身体だとイメージできるのです。
では、どうやって把握するのか、科学的には身体中の神経を脳がまとめて…となりますが。ラカンは精神分析的知見から原初的な身体の統一には視覚的なイメージが必要で、その為の装置が鏡だと唱えます。
つまり、身体の機能が働くためには、自分の身体を鏡に映し、統一的なものとして把握する契機が必要だということです。この契機を「鏡像段階」と言います。
「象徴界」
言語の領域。人は言語を使って世界を認識しています。ここでポイントなのは記号と言語の違いです。
例えば犬に「お手!」「ハウス!」と指示を出す場合には意味は一つだけです。こうしたコマンドの内容が唯一である場合は記号だと言えます。
一方言語はシチュエーションや単語の組み合わせの違いによって様々に意味が変わります。
本当に嫌いな人に「馬鹿」と言うのと恋人どうしでじゃれあっている時に「馬鹿」と言うのが違うように。人間の言語は単体では確定された意味を持たず、何かとの関係の中でしか意味を持つことが出来ません。こうした言語を「シニフィアン」と呼びます。
シニフィアンは他のシニフィアンと結び付くことで様々な意味を作り出します。例えば「猿」「木」「落ちる」という単語を繋げることで、「その道のプロでも失敗することがある」という意味になるのです。
記号の持つ意味は常にたった一つで、それは直接この世界(現実)をリアルに捉えることと同義です。しかし、人間はそれ単体では意味を持たないシニフィアンをわざわざ使って世界を認識しています。
つまり、人間が認識している「現実」というものは、物理的な世界とそのまま結びついているわけではないのです。VRゴーグルを使って仮想空間に入るように、人は言語(シニフィアン)を使ってバーチャルに世界を認識しているのです。
ちなみに、前項の「想像界」で人はイメージで世界を捉えることができる。と書きましたが、お気づきの通り、人はイメージを受けとる際に言語のフィルターを通さなければならない。つまり、想像界は象徴界によってコントロールされている、と言えるわけです。
さて、人間は最大の特徴であるこの言語によって文学や思想=「文化」を生み出すことに成功しました。日本最古の歴史書である「古事記」は日本人に「日本文化」をもたらしたのです。
また言語が成り立つためには「文法」が必要なように。文化を作り、民族や国家を成立させる為には「法律や規則、慣習」が不可欠です。そうした決まり事をまとめて〈法〉と呼びます。
つまり、象徴界では「言語=文化=法」という等式が見られるのです。
「現実界」
イメージと言語以外の領域。人は世界を言語とイメージで認識していますが、そこからはみ出す領域のことを「現実界」と言います。
精神分析は自由連想法、つまり好きに言葉をしゃべってもらうことで無意識に沈んだ「言葉」に刺激を与えるものなので、言語以外の領域があるとしたらお手上げだ、という意味で現実界は「不可能な領域、象徴界に空いた穴」とも呼ばれています。
と言われても…?ですよね。ここで「欲動」という言葉が出てきます。例えば「お腹が空いたからご飯が食べたい」と思うのは「欲望」です。これはシニフィアン(言語)化されていますよね。
一方で言語化できないが「人をその満足へ向かって駆り立てるような根源的な力」があり、これを「欲動」と呼ぶのです。
「欲動」の中でも代表的なのは「死の欲動」と呼ばれているものです。
ミュージシャンのXjapanのYOSHIKIが「破滅に向かって」というタイトルでライブをしました。ライブではギターやドラムを壊すなどのパフォーマンスをして、ある種の破滅的な世界観を演出したのです。
このように理由を言語化することが難しい、死に至るような危険なことを時に人は求めることがあります。スカイダイビングなどの危険な行為も戦争などの悲惨な殺し合いも究極的には「死の欲動」に突き動かされていると言えるのです。
しかし、それでも人が滅んでいないのは「死の欲動」に対して人を愛することに繋がる「生の欲動」があるからです。
この「欲動の満足」を目指すことを「享楽」と呼びラカンは「人間の最終目標は享楽を得ることである」つまり言語の〈法〉=「象徴界」の壁をぶち破ることだが、「死の欲動」のような危険な領域に入るのを言語の〈法〉「象徴界」が同時に防いでもいる。と言うのです。
ふぅ…長くなりましたが、ここまでが、前提です。人の心的次元(精神)は「想像界」「象徴界」「現実界」の三つに分類されています。では本題。
生きることには何故不安がつきまとうのか。
人はこの世に産まれた時、暖かな母の胎内から引き剥がされて世界に放り出されるのが不安で泣くのだ。と誰かが言いました。確かに生きることには常に不安や孤独感がつきまといますが、それは何故なのでしょう?
人は言語とイメージで世界を認識していると説明しました。ですが、産まれたばかりの赤ちゃんは言語も知らず、世界をバラバラのイメージで捉えています。
お腹が空いたら泣いてお乳を飲むことはできますが、何が起こっているかは分かりません。自分の口も手も誰がお乳をくれているのかも分からないのです。つまり、赤ちゃんには「私」という「自我」がないのです。
「想像界」の説明で人は様々なイメージを統一的に認識することができると書きました。その為には自分を対象化する契機が必要で、ラカンはその契機を赤ちゃんが「鏡」に自分の姿を映すという体験に求めました。
赤ちゃんは自分の姿が映った鏡を見て喜びを示すそうで、この段階を「鏡像段階」と呼びます。このような反応を示すのは人間だけで動物は無反応か敵と勘違いするそうです。
しかし、「鏡」に映った自分は本当の自分ではありません。左右反転していますし、鏡が歪んでいることだってあります。究極的には本当の自分の姿を人は見ることは出来ないのです。
つまり、鏡に映るのは自分と思われる他の何かである。つまり他者に他ならないことを示唆しています。つまり、自我は他者を通してしか成立しえないものなのです。
これは光学的に映る鏡だけに限った現象ではありません。大好きな俳優やミュージシャンの格好を真似したりするのも、そこになりたい自分を投影するからで。それは自分の理想という鏡に映った他者なのです。
私たちは「自分があって他者が発見される」と考えがちですが、鏡像段階の知見を踏まえれば、まずは他者(鏡像)があって自分(自我)が生まれるのです。
なるほど、他者がいるから自我ができる、ということは「これが私」という自我はつねに他者から借りてきているとも言える=本当の私など存在しないのだ!ということになってしまいます。
ですから「鏡像段階」だけでは私と他者の線引きが曖昧になり、最終的には自我の奪い合いになってしまいます。鏡に映った自分のような何かに乗っ取られるような恐怖を感じてしまうのです。
そこでもう一人の〈他者〉が自我の奪い合いを止めるために登場します。〈他者〉は他者と違い超越的な存在です。子供にとっての大人、大人にとっての王様や神様などの「お上」にあたるもので、〈法〉をもたらす存在です。
「象徴界」で「言語=文化=法」と書いたことかわかるように。言語の世界に入るとは根源的な〈他者〉との経験のことなのです。言語がしゃべれない赤ちゃんにとって〈他者〉とは母親に他なりません。母親によって言語の世界に導いてもらい「これがあなたよ」と保証してもらうことで初めて自我を獲得することができるのです。
整理します。人は鏡に映った自分のような何か=他者から自己イメージを作り上げるが、それだけでは鏡に映る他者と自我の奪い合いになる。それを止め「これがあなたよ」と教えてくれる存在〈他者〉が必要だ。赤ちゃんにとっては母親がその役目を果たす。ということになります。
しかし、母親は常にそばにいてくれる訳ではありません。赤ちゃんにとってはアンコントローラブルな存在なのです。つまり人間は「何を考えているか分からない異質な存在=〈他者〉に生殺与奪の権を握られている」という根源的に不穏な状況に生まれ落ちざるを得ないのです。
ちなみにここで言う「母親」とは象徴的な意味で、実際の母親に限りません。その人にとって「これがあなたよ」と言ってくれる存在を指しています。
例えば人々がSNSでいいね!を求めることも同じです。インフルエンサーに憧れるのはそこに鏡に映った理想の自分=他者がいるからで、いいね!を求めるのは自我を確立するために「これがあなたよ」と〈他者〉に言って欲しいからに他なりません。しかし当然ながら〈他者〉はコントロールできないゆえに、常に不安がつきまとうのです。
長くなりましたが、これがジャック・ラカンの精神分析理論を通して僕が理解した(と思われる)人が生きることに不安がつきまとう理由です(ラカンに詳しい人違ってたらごめん)。
僕たちはこの世に生まれ落ちた時から、自らがコントロールできない〈他者〉によってしか、自我を維持していくことができない。という宿命を背負っているのです。だからこそ常に不安や孤独感、寄る辺無い気持ちを抱きながら「不安タスティック」に生きていくしかないのです。
でもそれはみうらじゅんさんが言うように、決してネガティブなことばかりではありません。人は不安だからこそ行動するし、新しい事にチャレンジする。その原動力にもなるはずです。
生きることは「不安タスティック」その宿命を受け入れて皆が前へ進めるよう祈りつつ今日はこのへんで。
長文読んで頂きありがとうございました。じゃまた!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
