
『学び』って? vol.420
本日はこちらのイベントに登壇させていただきます。
私は教師の視点から「学び」であったり、勉強するのはなんのため?ということについて考えさせていただきます。
勉強は嫌な響き、学びがいい
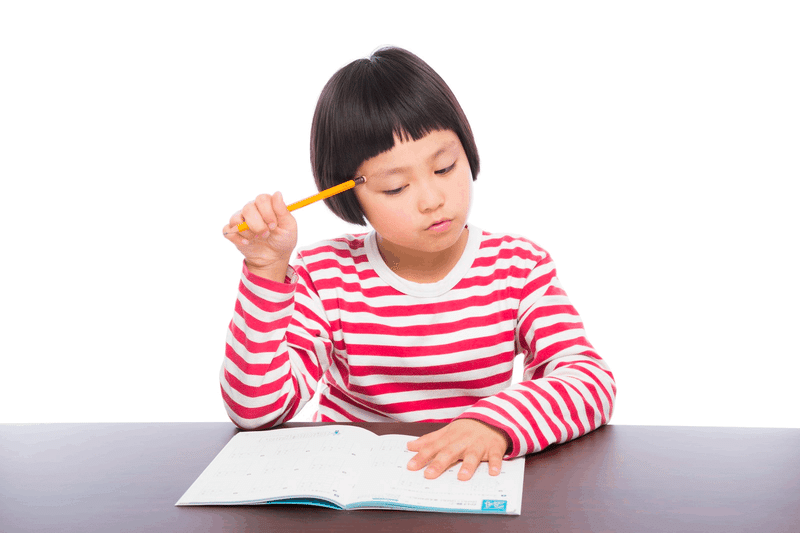
そもそも私は勉強という響きが好きになりません。
勉めることを強いると書いて勉強です。
強制力の働くような若干後ろ向きのような言葉ヅラが好きではないのでしょう。
勉強というのは贅沢だとよく言われます。
確かに発展途上国のような環境に比べれば、ほとんど全ての人が字が書けて読めて話ができる。
これは幸せのことなのかもしれません。
しかし、それを学ぶのは果たして勉強というのでしょうか?
日常生活の中で必要だからこそ手に入れたい力、自ずとこれに対して全ての人が前向きになるのは当たり前なのではないでしょうか?
特に自分で学びたいという意識がある人については。
なので、私の中では学びたくないものが勉強、強制的にさせられるのが勉強、やりたくないけどやらなければいけないものが勉強であって、その逆の知りたいもの、主体的にやるものやりたくてやるものは学びと位置付けています。
では、いわゆる学校で勉強をさせられるのはなぜなのでしょうか?
その前に勉強に対する大人の意識を見てみたいと思います。
大人は勉強しない
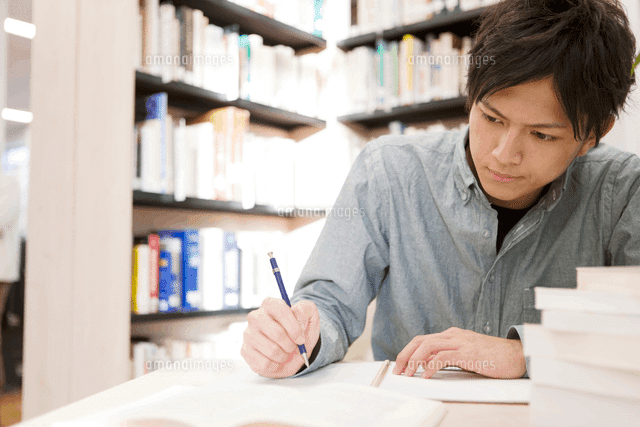
総務省が行った「平成28年社会生活基本調査」で、仕事をしている社会人の週当たりの学習時間は42分と出ています。
週当たりに42分ということは、1日あたりは6分です。
1日にたったの6分しか勉強していないのです。
あれだけ、10何年間も与えられた勉強を必要だからと言わんばかりに強いる大人がたったのこれしか勉強していないのです。
それは、子どもも勉強が嫌になるはずです。
勉強の意味がわからなくなるはずです。
大人ですら、その価値を理解していないということですから。
つまり、勉強というものはもうすでに高尚なものとすることはできず、できれば避けて通りたいという認識が浸透しきっているのは無理のないことなのです。
では、勉強するのはなんのためなのでしょうか?
勉強を学びに近づけるのが学校であり授業

私は勉強をするのは大人のエゴであると思っています。
そもそも勉強は必要のないものであって、学びこそ必要なものだと考えているからです。
では、子どもに学んでもらうにはどうすれば良いのか。
それは、学校の中の勉強という認識で蔓延っているものを、授業などを通して学びへと進化させることが大事になってくるのです。
学ぶことが楽しい、知りたい、やりたい、という本質的欲求を呼び起こし、そこをくすぐる。
これこそが教師の仕事であり、学校の役割だと感じているのです。
その上で語りましょう、なぜその学びが必要なのか。
学びは人生を豊かにする

ただ一言、これに尽きます。
学ぶことで新たな知識を手に入れ、実生活に役立ててそこから見える世界が変化していく。
私はラーメンが好きなので、ラーメンに例えて話せるでしょう。
これは、他の記事を読むか、本日のイベントに参加してみてください。
学ぶことで人と繋がり、新しい視点が生まれ、より生活が彩り鮮やかになる。
それは止まることを知らず、どんどんと新しい渦を巻き起こしていく。
これが学ぶ意味であり、勉強ではなく学びが必要と唱える私の意見です。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
