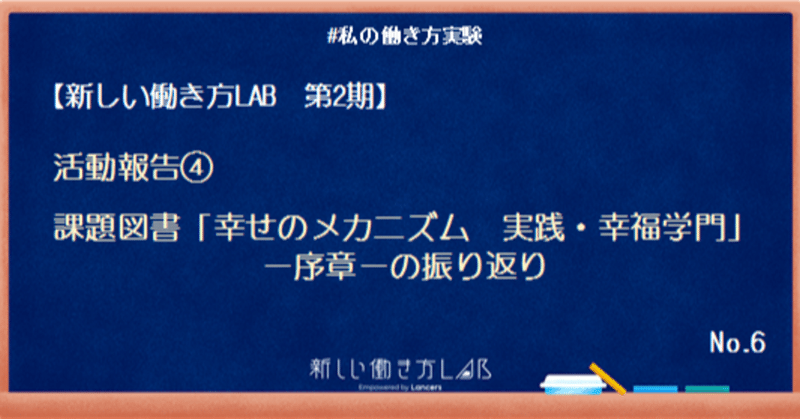
【幸福学】活動報告④:課題図書「幸せのメカニズム 実践・幸福学入門」ー序章ーの振り返り
本記事は、ランサーズ新しい働き方LABの「研究員制度」の活動の一環として、私個人が行う「働き方実験」についてまとめたものです。
「指定企画:幸福学」の課題図書は次の3冊。
・幸せのメカニズム 実践・幸福学入門 前野隆司[著]
・幸せな職場の経営学 「働きたくてたまらないチーム」の作り方 前野隆司[著]
・ウェルビーイング 前野隆司・前野マドカ[著]
「幸せのメカニズム 実践・幸福学入門」序章を振り返る
今回は課題図書のひとつ「幸せのメカニズム 実践・幸福学入門」前野隆司[著]を読んでの振り返りを行っていきます。序章の内容についてです。
本を読むときに、初見で気になるところに赤線を引っ張りながら読みました。私が気になったを箇所を自分の言葉に落とし込み、まとめていきたいと思います。
初見で気になった内容
・幸せは多様。しかし、だれもが共有できる基本的なメカニズムがある。
一人一人の幸せは異なるけれども、万国共通の幸せのイメージがあるはず。世界中のみんなが幸せのイメージを共有でき、めざすべき幸せが明らかになったら、回り道せずに幸せにたどり着けるだろう。
・他人との比較による幸せは長続きしない。
人は他人との比較によって幸せと感じる傾向があるが、他人との比較による幸せは長続きしない幸せ。
ひとりひとりみんな違う。それぞれの個性、良さを生かして自分なりの幸せを見つけるためにも幸せの基本メカニズムを理解することが大切。
・幸福学は認知科学や心理学を援用した科学的な学問。
その人自身の主観的な幸福を測定する。主観的幸福に影響する因子を分析し、それぞれの指標ごとに数値化する。客観的幸福ではなく、主観的幸福。多様な人のそれぞれの考え方がある中で、誰もが幸せになるためのメカニズムを明らかにする。
・幸福はダイエットに似ている。痩せるメカニズムの理解が大切なように、幸せのメカニズムを理解することが大切。
幸せをめざすためには幸せの基本的なメカニズムを理解することが大切。
間違った方法で幸せになろうとすると不幸になる。
一部の幸せだけをめざすと長続きしない。
そのうち幸せになると甘く見ていたら不幸が積み重なる。
幸せなんて人それぞれ、すべての人に共通の幸せのメカニズムなんて存在しないと放っておくと幸せになれない。
序章を読んでの感想
序章を読んで「幸福はダイエットに似ている」という一文で、早速「私は幸せになれないかもしれない」と不安になりました。
というのも、痩せるメカニズムは理解していても、ここ最近、ダイエットに成功したためしがないからです。
幸せの基本的なメカニズムを理解しても、私は実践できないのではないか、ダイエットのように三日坊主で終わってしまうのではないか、と思ったのです。
目標に向かってストイックに毎日の課題をこなす、徹底して自己管理ができる、そんな人が幸せになれる人であって、私のようにズボラでだらしのない人間は一生幸せになれないのではないか、そんな不安がよぎりました。
その後、不安を抱えながら読み進めます。
第1章以降はまた別記事でまとめていきたいと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
