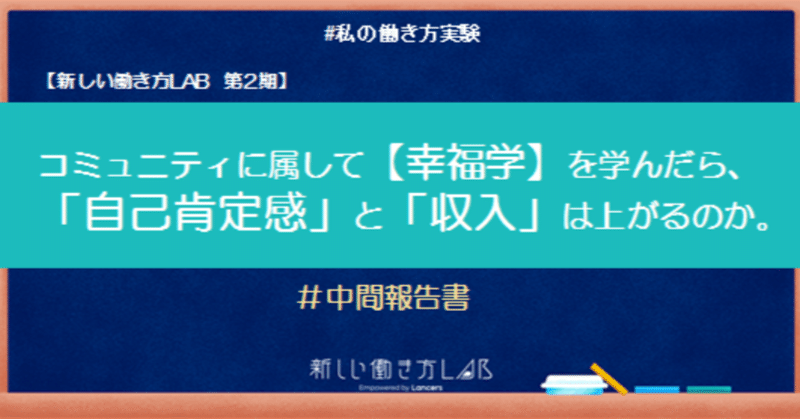
コミュニティに属して【幸福学】を学んだら「自己肯定感」と「収入」は上がるのか。#私の働き方実験 #中間報告書
本記事は、ランサーズ新しい働き方LABの「研究員制度」の活動の一環として、私個人が行う「働き方実験」についてまとめたものです。
「『私は幸せ』と言えるようになりたい」と参加した【幸福学】。
正直なところ、【実験計画書】の段階では「幸せ」と「仕事」をどう結びつければよいか、いまいちよくわからない状態でスタートを切りました。
指定企画の【幸福学】の活動に取り組み、新しい働き方LAB研究員の方々の活動を目にする中で、検証したいことがより明確になってきました。
そこで、「中間報告」を機に、実験テーマ・目的をより具体的に変更して活動していきたいと思います。
◆実験テーマ
コミュニティに属して【幸福学】を学んだら、自己肯定感と収入は上がるのか。
◆実験目的
コミュニケーションが苦手な扶養内ライターが、コミュニティに参加して【幸福学】を学んだら、すこぶる低い自己肯定感と収入が上がるかを検証したい。
◆実験テーマ変更に至った背景

【幸福学】の幸福度診断・ハピネスチャレンジへの取り組みや、新しい働き方LAB内での関わりを通して、私の場合は「自己肯定感の低さ」が「幸せ」に近づけない理由だと考えるようになりました。
幸福度を上げるには感謝と人とのつながりが大切だといいますが、私は、人とつながるためのコミュニケーションに対して苦手意識を持っています。
けれども、新しい働き方LAB内で人と関わったからこそ、自分を一歩引いた場所からみることができ、人に掛けられたことばを素直に受け止められるようになってきました。
そうすると、自分のやるべきことが見え出して「せっかくだからやってみよう」という気持ちになってきたのです。
人に声を掛けられずに諦めてきたことも「やってみたい」を優先すると、自分に少し自信が持てるようになるのでは?と思いました。
もうひとつ、「自己肯定感」とともに引っ掛かっているのが「収入」です。家庭の事情で最低でも今よりも2倍の収入をめざしたい。
あたLABで刺激を受け、8月から新しい仕事にチャンレンジしはじめました。これをきっかけに収入が上がるのかも検証していきたいと思います。
◆改めて検証したいと思ったこと
幸福度を高めるための4つの因子を意識して行動したら「自己肯定感」と「収入」が上がり、幸せに近づけるのか。
自分の幸福度を高めると考える4つの因子に基づく行動
・今よりも少しだけ勇気を出して「やってみよう」を増やす
・人からもらった言葉は素直に「ありがとう」と受け止める
・自分は自分「ありのままに」自分のペースを大切にする
・「なんとかなる」でとにかく一歩を踏み出してみる
◆行ってきた研究活動

■「幸福学」の全体プロジェクト
①ハピネスチャレンジ
すべて参加。考えさせられるお題が多く、自分と向き合うきっかけになった。ほかの人の考えに心動かされることも。後半のグループワークは緊張しぱなっしだと思いますが、皆さんのお話を聞きたいので参加します。
②課題図書3冊
完了。幸福度が高まる行動を実践しても上手くいかないことがあり、具体的な方法を求めて「7日間で『幸せになる』授業」を読んだ。
③幸福度診断
④幸福度を高めるための生活習慣をslackでシェア
■マイハピネスプロジェクト
①カレンダーマーキング法
自分の1日を前向きに振り返る
②幸福度診断
1か月ごとに受け、診断サイトの振り返りで次の1か月を過ごすヒントを得る
③幸福度を高めるための活動
・コワーキングスペースや図書館の活用で仕事の効率化を図る
・興味のあるイベントやウェビナーに参加
・新しい仕事への挑戦
・4年後、子どもが中学生になって外で働けるようになったら、学校の中から学習支援に関わる仕事に携わるのを目標に、通信大で特別支援教育、心理学関連で6単位取得。
・子どもの療育を通して得た生活や学習における工夫をシェアするための記録。
◆ここまでの振り返りと気づき

■6~7月:とにかく「参加」を意識した6月。
新しい場に参加できる喜び、初めての人と話すことに刺激を受ける日々にワクワクして幸福度が少し上がる。
■8月:何をするにも後ろ向きにしか考えられない8月。
夏休みとともに完全夜型生活になって心身ともに不調。幸福度が下がる。
人からもらう温かいことばも受け入れられず、「ライター」と堂々と名乗れない、なにも行動できない自分が情けなくなる。
自分と向き合う診断ツールに取り組むが、結果を見てさらに落ち込む。
↓
中間地点を目前に早く幸せに近づかなければ!と前野教授の「7日間で『幸せになる』授業」を読む。自分が幸せに近づけないのは「自己肯定感の低さ」だと改めて気づかされる。
↓
新しい仕事が始まり「コピーライティング」に触れたのをきっかけに、岩崎俊一氏の「人は『幸福』という『北極星』をめざして生きている」をはじめ数々の名言に出会う。ライターとしてのモチベーションが上がる。
■9月:自分を一歩外側から見ることができ、前を向いた9月。
ウェビナーにはまる。「宇宙兄弟 今いる仲間でうまくいく チームの話」を聞き、あたLABに所属できていることへの感謝、自分の適性・立ち位置でできることをすればよいという安心を得る。
↓
幸福学メンバーのももさんの「幸福度診断×コーチング」を受ける。自分を一歩外側からみることで気持ちが落ち着き、やるべきことが明確になる。
「夢を叶えるために、一歩踏み出せたんですね」「絶対にやらなければならないことに9割力を注いでも、残りの1割は夢を叶えるためのことに注げば、それが仕事や未来につながるかもしれない」ということばで前を向く。
◆今後の活動予定&挑戦したいこと

4年後、再び外で働けるようになったときのために、仕事を軸として今できることを積み重ねていきたいと思います。
・「10/22(土)日本作業科学研究会第25回学術大会in長野 What is Well-Being ?〜作業の視点で幸福を考える〜」前野教授の基調講演(特別コラボ講演)『幸福学×作業科学』とワークショップにオンライン参加予定。
・「無意識の力を伸ばす8つの講義」を読んで幸福度を高められる方法をたくさん試す。
・月収入2倍をめざして効率のよい仕事のためにパッケージ出品に挑戦。
・LD・発達障害の子ども、保護者に向けたサイトのコンテンツづくり
・10月~2月の授業で、心理学関連6単位+女性のキャリア教育1単位を取得。目標は2023年度に学位認定試験で保健衛生学の学位取得。2024年度に認定心理士取得をめざす。
・長期休み以外で平日2時間、週1日の条件で子どもの学習支援に関わることのできる学校の情報収集。
◆まとめ

研究を始めて、仕事・生活で次のような変化が起こりました。
・クライアントに対して仕事を行うだけではなく、自分が携わった仕事の先にいる「人」のことを考えて仕事ができるようになった。
・実生活の中で人に優しくできるようになった。
・子どもに関しての相談先を思い切って増やし、学校にも状況をシェアするようにしたら、先生方からもいろいろと提案してくださるようになった。
【幸福学】では自分に向き合うことが多く、周りとの差を感じてモヤモヤが止まりませんでしたが、人に話す、聴いてもらうことで抜け出せた感じがします。
ゆっくりとしか前に進めないけれども、自分の心が許す限り、できそうなことからやっていきたいと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
