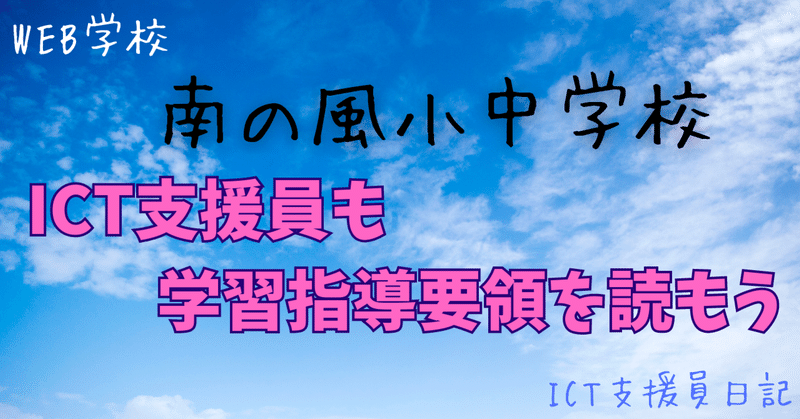
ICT支援員も学習指導要領を読もう
前回、これからのICT支援員に必要な技量として、教科においてICTの活用を先生方と協議し、提案していく力だと書いた。

では、先生方は授業を作るにあたって、何をもとに組み立てているかというと、それはずばり学習指導要領である。
といっても、ここが微妙なところで、昔は多くの先生が、教科書の指導書というものを参考にしながら授業を組み立てていった。もう今はそんな先生は少なくなっているのでばらしてもいいと思うけど、指導書に書かれていた板書例をそのまま黒板に写して授業をする先生も少なからずいた。
まあ、この指導書というのは、よくできていて、当然、学習指導要領をもとに作られているので、下手に自分で教科書を見ながら授業を組み立てていくよりも、すっと簡単に授業が組み立てられる。また、当然教科書の指導書なので、これをある意味忠実に授業再現出来たら単元の目指すものも達成できるというわけだ。実際には、そう簡単にはいかないけど。
しかし、この指導書値段がかなり高く、また、最近は授業の組み立てが変わってきているので、あまり使われなくなってきているのではないだろうか。どうなんだろうか。

そこで、学習指導要領である。
文部科学省のホームページでは次のように書かれている。
学習指導要領とは何か?
全国のどの地域で教育を受けても、一定の水準の教育を受けられるようにするため、文部科学省では、学校教育法等に基づき、各学校で教育課程(カリキュラム)を編成する際の基準を定めています。これを「学習指導要領」といいます。
「学習指導要領」では、小学校、中学校、高等学校等ごとに、それぞれの教科等の目標や大まかな教育内容を定めています。また、これとは別に、学校教育法施行規則で、例えば小・中学校の教科等の年間の標準授業時数等が定められています。 各学校では、この「学習指導要領」や年間の標準授業時数等を踏まえ、地域や学校の実態に応じて、教育課程(カリキュラム)を編成しています。
つまり、この学習指導要領があることで、教師は何を教えればいいか、また、教えなければならないかがわかるし、これによって、全国どこでも同じ内容が教えられて、国民の学力の平均化を図ることができるわけだ。
全国どこでも小学校の授業時間は45分だし、国語は6年生なら175時間授業があり、その175時間を通してどのような力を付けさせたいのかを確認しながら授業を組み立てることができる。
実際には、年間指導計画というものを作成し、例えば、1学期にはここまでの内容をどのくらいの時間で教えるかを計画する。
そして、最終的には1時間ごとの指導案を作成し、その時間で教えるべき内容、どういう方法でそれを達成させるのか、達成したかどうかをどういう方法で確認するのか等毎時間準備しながら授業を行っていく。
結構大変な作業だ。

ICT支援員が先生方と授業を一緒につくっていこうとした場合、やはりある程度、授業がどいういう意図で、どういう風に組み立てられているのかを知っていることは強みになってくると思う。
この学習指導要領、やたら内容が多いので、小学校の全教科、中学校の全教科を見るのはちょっと無理な話だけど、ネットを探すと、その要約みたいなのもでてくるので、ぜひ参考にしたらどうだろうか。学習指導要領を知っているということだけでも、先生方と情報を共有しやすくなるのではないだろうか。
自分も、かつては自分の教えていた教科は当然よく見ていたが、他教科となると研究授業の時に見たぐらいで全然説得力はないんだけど。ICT支援員になってからの方がずっとみているような気がするな。これからも勉強だ。
来年度に向けて、この春休みにちょっと見ておこうかな(続く)。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
