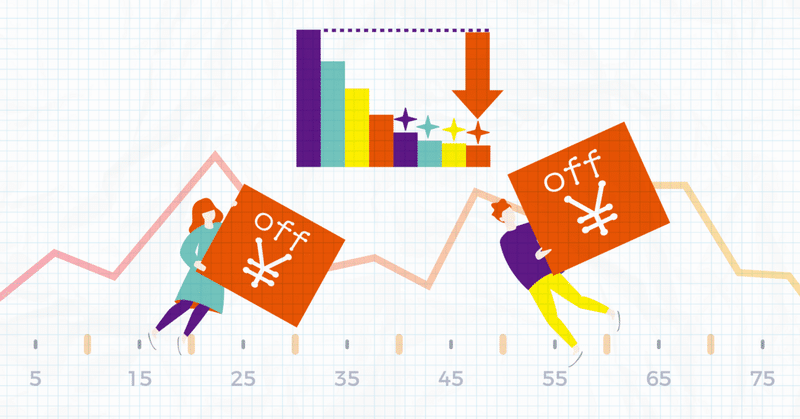
マルクスの価格論は労働価値説を擁護する
資本主義社会では、労働生産物は、「価値」として現象する商品形態を取らなくてはならない。
しかし、商品の価値は、商品自体を眺めていても絶対に見えてこない。なぜなら、価値は幻のような性質を有するからだ。そこで、見えざる価値を表すために、価格がつけられる。
ここでは、商品の価値を表示する貨幣の機能の一つ、価格に注目したい。
商品は、まず何よりも自己の価値を貨幣によって表現しなくてはならない。
貨幣で表現された商品の価値(貨幣商品と商品の交換比率)は、何はともあれ、商品の「価格」である。たとえば、1kgの小麦の価値は「1kgの小麦=7.5gの金」のような交換比率、すなわち「価格」として表現される。あるいは、金の750mgに「円」という貨幣名が与えられる場合には「1kgの小麦=10円」という価格で表現される。
ここでは、貨幣である金が商品の「価値尺度」として機能している。
価格における「価値」とは、感覚で捉えることはできず、表象することはできない商品の社会的属性が、金という自然的属性に転形することによって感覚的に捉えることができる。
つまり、表象することのできる自然的事物のある量に転形されているのだ。
このように、価値という商品の社会的属性を、自然物のある量に転形することで、商品の価値表現の材料として機能すること、これこそがマルクスの「価値尺度」だと考えられる。
価格には、ある量の金という自然的属性を内包するけれども、前述の価値尺度の質的内容を踏まえると、価格においては、この自然的事物が表象されているだけにすぎず、ここに現物があるわけではないことがまず言える。商品の値札にある金は想像された金でしかないのであって、現物の金ではない。しかし、そこで想像されているのは実在的な金、現物の金である。
すなわち、あらゆる商品の共同事業によって商品世界から排除されて、一般的等価形態に強制配置されて、貨幣形態として現象する実在的な「金」である。
貨幣である金は唯一、諸商品と対立しているからこそ(すると等価形態は自然的な現物形態で商品の価値を表示する価値体となっている)、それをイメージすることができる。要するに、価格を構成する価値尺度としての貨幣は、イメージされた表象的・観念的な貨幣であるけれども、そのイメージが指示しているのは「実在の貨幣商品」に他ならない。例えば、うまいぼう1本=金7.5gという価格における「金7.5g」は、もちろん単なる表象でしかないけれど、実在の金を指している。
一般的な諸商品は、自己の価値を、価格で表象される金量で表現して、お互いに比較し合う。そこでは、それらのさまざまな金量を計量して同一の名前で言い表すために、ある金量を価格の「度量標準」として固定する必要が生じる。
ところで、マルクスが言うには、金は、それらが貨幣になる前に、ポンドやグラムといった重量に基づく度量単位で表示されていた。こうした度量単位は、さらに下位の補助単位、例えばオンスやミリグラムに分割されて、これらの単位が一つの度量標準、度量システムを生成する。
価格で表象される金量を計量するための度量標準、つまり「価格の度量標準」として機能するのは、歴史的には、上記にあるような重量に基づく度量システムだった。しかし往々にして社会習慣的に、貨幣商品の重量を表示する貨幣名は、重量に基づく度量システムから分離して、重量名とは別のものになる。(もとの重量名がそのまま貨幣名になるパターンもあるという)
価格の度量標準は価格である観念的な金量を測量するためだけではなく、貨幣である実在の金そのものを計量するためにも用いられる。したがって、「貨幣の度量標準」である。言ってしまえば、それは金量を測定する尺度である。
商品の価格で表象される金であれ、貨幣である現物の金であれ、とにもかくにも、金量を言い表すために金の諸量が度量システムとして機能している時、金は、計算貨幣として機能していると言える。
はじめは、さまざまな貨幣名が習慣的に用いられるけれど、貨幣名は商品世界で普く通用する必要があるため(近代)、「価格の度量標準」および「貨幣の度量標準」は、国家の力によって、つまり国家が制定する法律によって確定する。例えば、調べてみると日本では貨幣法が1897年に制定されて、貨幣名を「円」と決定して「750mgの金=1円」と定めた。
以上から、商品の価格とは、質的には抽象的人間労働の対象化である商品価値を、価値尺度として貨幣である自然的属性を有する金量で表現・表象したものであり、量的には、この金量を価格の度量標準である金量で測量したものである。
価格は価値を表現するものであり、どの商品についても、価値どおりの価格、つまり商品の価値と等しい価値量をもつ金量を表現するのは、商品の価値も金の価値も絶対的な大きさとして把握することができないためである。
したがって、同じ商品でも、さまざまな価格を持つことができるという。
商品の売り手がそれで売りたいという言い値も、買い手がそれで買いたいという付け値も、売り手と買い手のあいだで一致した「決まり値」「売り値」も、量的には異なった価格であるとしても、質的には、すべての商品の価値を貨幣である金量で表現した価格となる。また商品の価値量が変わらないのにもかかわらず、たえず変動する価格は、量的にどのように変化しようとも、質的には常にその「商品の価格」となる。このように商品の価格は、その特質からして、商品の価値を常に正確に表現するものではないと、マルクスは論じる。
前述により、価値と価格が量的に一致しない可能性、つまり価格が価値から乖離する可能性は「価格形態」自体の中に潜む。
しかし、このような乖離の可能性は価格形態の欠陥ではなく、むしろ無政府的な私的生産でしかありえない商品生産が社会的生産として成り立つための、ひとつの重要な要因だと言える。
価格が価値から分離して上昇もしくは下落すると、遅かれ早かれ、今度は価格を逆の方向に変動させることになる。実は、需給関係の変化に応じて絶えず変動する価格は、実はそれが価値から乖離することによって、逆に商品の需給関係を調整することになっている。
そのような価格の変動は価値によって制約された変化である。価格の価値をめぐる変動が、結果的に、社会的需要に合致した商品の供給をもたらすよう作用する。これによって初めて労働がすべての私的労働として無政府的に行われる商品の生産規模が、絶えず変転する社会的な欲求に適合させられる。
このように価値から乖離する価格の本性からすると、ごくわずかな価値しか持たないもの、あるいは全く価値を持たないものが、高い価格で売買されていることに説明がつく。つまり、およそ労働の生産物ではないものが価格を持ち、商品として売買されることができるという。それは、たとえば良心、名誉(いいね数とか、トロフィーとか)、関係(レンタル彼女(彼氏)とか)、金儲けのチャンス(金融商品)など、現代社会で殊更見られる商品が挙げられる。
現代社会では、抽象的人間労働が注入されていない商品が私たちの消費の中に含まれている。しかし、マルクスからすると、それは価格という性質上「擬似的・擬態的に成り立つ商品」であって、おびただしい商品の上に、また膨大な擬態的商品が乗っている様相であろう。
そういうわけで、価値=価格だとは、誰も言っていないのである。
価値論の意義は「労働」から近代社会の動態構造を把握することができるのである。無数の擬態商品が命がけの飛躍を果たす現在の社会であっても、本質的に「労働」がなければ、成り立たない。毎日私たちは食べ物を必要としているし、服や住宅を必要としている。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
