
科学的証拠
こんにちは。いつもお越しくださる方も、初めての方もご訪問ありがとうございます。
今回はwikipedia英語版「科学的証拠」の記事を翻訳をします。
翻訳のプロではありませんので、誤訳などがあるかもしれません。正確さよりも一般の日本語ネイティブがあまり知られていない海外情報などの全体の流れを掴めるようになること、これを第一の優先課題としていますのでこの点ご理解いただけますと幸いです。翻訳はDeepLやGoogle翻訳などを活用しています。
翻訳において、思想や宗教について扱っている場合がありますが、私自身の思想信条とは全く関係がないということは予め述べておきます。あくまで資料としての価値を優先して翻訳しているだけです。
科学的証拠
科学的証拠は、科学的理論や仮説を支持または反論するために役立つ証拠だが、科学者は理論を実際の問題に適用する場合など、他の方法でも証拠を使用する。このような証拠は、経験的証拠であり、科学的方法に従って解釈できることが期待される。科学的証拠の基準は研究分野によって異なるが、科学的証拠の強さは一般的に統計分析の結果と科学的統制の強さに基づいている。
推論の原則
観察と仮説の関係に関する人の仮定や信念は、その人が観察を証拠とするかどうかに影響する。このような仮定や信念は、人が観察結果を証拠としてどのように利用するかにも影響する。例えば、地球が動いていないように見えることは、地動説的宇宙論の証拠とされるかもしれない。しかし、天動説を支持する十分な証拠が提示され、明らかに運動していないことが説明されると、最初の観測は証拠として強く否定される。
理性的な観察者が異なる背景信念を持っている場合、同じ科学的証拠から異なる結論を導き出すことがある。例えば、フロギストン理論に取り組んでいたプリーストリーは、フロギストンを用いた酸化水銀の分解に関する観察結果を説明した。対照的に、元素理論を発展させたラヴォアジエは、同じ観察結果を酸素を参照して説明した。観測と仮説の間に因果関係があるからといって、その観測が証拠として採用されるわけではなく、むしろ因果関係は、観測を証拠として立証しようとする人によって提供されるのである。

一般に酸素の発見者とされる
フランスの化学者アントワーヌ・ラヴォアジエ
フロギストン説を打破し、「近代化学の父」と称せられた
背景信念の効果を特徴づけるより正式な方法は、ベイズ推定である。ベイズ推論では、信念はその確信度を示すパーセンテージで表される。人は最初の確率(事前確率)から始め、証拠を観察した後にベイズの定理を使ってその確率を更新する。その結果、同じ事象を観察する2人の独立した観察者は、その事前値(結論にも関連する以前の観察結果)が異なれば、合理的に異なる結論に到達する。しかし、2人が互いにコミュニケーションすることが許されていれば、2人は合意に至る(オウマンの一致定理による)。
※ベイズ推定・・・ベイズ確率の考えに基づき、観測事象から推定したい事柄を確率的な意味で推論すること。
どのような観察が証拠であるかの決定における背景信念の重要性は、三段論法などの演繹的推論を用いて説明することができる。どちらかの命題が真として受け入れられなければ、結論も受け入れられない。
科学的証拠の有用性
カール・R・ポパーなどの哲学者は、科学的証拠が中心的な役割を果たす科学的方法について、影響力のある理論を提供してきた。要約すると、ポパーは科学者が創造的に理論を展開し、その理論を証拠や既知の事実に照らして検証することで反証される可能性があると説いている。ポパーの理論は、証拠が理論と矛盾する事実を立証することで、理論が間違っていることを証明できるという非対称性を提示している。対照的に、証拠は理論の正しさを証明することはできない。なぜなら、まだ発見されていない他の証拠が、理論と矛盾する可能性があるからである。

カール・ライムント・ポパー
哲学的見解と科学的見解
20世紀には、多くの哲学者が証拠の記述と仮説の論理的関係を研究したのに対し、科学者は統計的推論に用いられるデータがどのように生成されるかに焦点を当てる傾向があった。 しかし、哲学者のデボラ・メイヨーによれば、20世紀末には哲学者たちは、「仮説演繹主義、ベイズ主義、具体化主義のいずれであっても、このような証拠の論理的説明では見落とされたり、誤って説明されたりする科学的実践の重要な特徴がある」ことを理解するようになっていたという。
観察が証拠と見なされるかどうかを決定するために、20世紀には様々な哲学的アプローチがあった。1950年代、ルドルフ・カルナップはこのようなアプローチを3つのカテゴリーに区別することを推奨した。分類的(証拠が仮説を確認するかどうか)、比較的(証拠が代替仮説よりも第一仮説を支持するかどうか)、定量的(証拠が仮説を支持する度合い)。ピーター・アヒンスタインが編集した1983年のアンソロジーでは、カール・ヘンペル(確証の論理について)、R・B・ブレイスウェイト(科学的システムの構造について)、ノーウッド・ラッセル・ハンソン(発見の論理について)、ネルソン・グッドマン(グリューで有名な、投影理論について)、ルドルフ・カルナップ(確証的証拠の概念について)、ウェスリー・C・サーモン(確証と関連性について)、クラーク・グリモア(関連する証拠について)など、科学的証拠に関する著名な哲学者による簡潔なプレゼンテーションが掲載されている。1990年、ウィリアム・ベクテルは、生物学者が証拠の手順や信頼性に関する論争を解決するために使用する4つの要素(データの明確性、他の研究者による再現性、代替的な方法によって得られた結果との整合性、もっともらしいメカニズム理論との整合性)を提示した。

ルドルフ・カルナップ

イギリスの哲学者リチャード・ビーヴァン・ブレイストウェスト
アメリカの科学哲学者ノーウッド・ラッセル・ハンソン

アメリカの科学哲学者ウェスリー・チャールズ・サーモン
アメリカの哲学者クラーク・グリモア

2001年、アヒンシュタインは『証拠の書』と題したこのテーマに関する自著を出版し、その中で他のトピックの中で、証拠の4つの概念を区別した。認識論的状況証拠(与えられた認識論的状況に関連する証拠)、主観的証拠(特定の時間に特定の人物によって証拠とみなされる)、検証的証拠(仮説が真実であると信じる十分な理由)、潜在的証拠(仮説が高い確率であると信じる十分な理由)。アヒンシュタインは、他のいかなる種類の証拠も少なくとも潜在的証拠でなければならないので、彼の証拠概念はすべて潜在的証拠という観点から定義した。彼は、科学者は主に検証的証拠を求めるが、他の証拠概念も使用すると主張し、それらは独特の確率概念に依存しているとした。アヒンシュタインは、この確率概念を、ベイズ主義、カルナップ主義、頻出主義などの以前の確率論的証拠理論と対比した。

単純性は、科学理論に対する一般的な哲学的基準の一つである。強力なチャーチ=チューリングのテーゼの哲学的仮定に基づき、証拠を評価するための数学的基準が推測されている。この基準は、証拠の最も単純な包括的記述が最も正しい可能性が高いというオッカムの剃刀の考え方に似ている。「理想原理では、仮説に関連する事前確率はアルゴリズム的な普遍確率で与えられるべきであり、モデルの対数普遍確率と、モデルを与えられたデータの確率の対数の和は最小化されるべきである」と正式に述べられている。しかし、一部の哲学者(リチャード・ボイド、マリオ・ブンゲ、ジョン・D・ノートン、エリオット・ソーバーなど)は、科学における単純さの役割について懐疑的あるいはデフレ的な見方を採用し、その重要性が強調されすぎていると様々な方法で主張している。
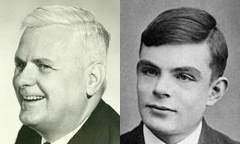
イギリスの数学者・暗号研究者・計算機科学者・哲学者アラン・チューリング
※ 計算可能性理論において、チャーチ=チューリングのテーゼは、計算可能な関数の性質に関するテーゼである。自然数上の関数がチューリング機械によって計算可能である場合に限り、有効な方法によって計算することができると述べている。

アルゼンチン生まれのカナダの哲学者・物理学者マリオ・ブンゲ
オーストラリアの物理哲学者ジョン・D・ノートン
アメリカの生物哲学者・科学哲学者エリオット・ソーバー
科学の本質としての仮説検証の重視は、科学者にも哲学者にも浸透している。しかし、哲学者たちは、新たな証拠を突きつけて仮説を検証することは、科学者が証拠を利用するすべての方法を説明するものではないと指摘している。例えば、ガイガーとマースデンが薄い金箔を通してアルファ粒子を散乱させたとき、その結果得られたデータによって、彼らの実験アドバイザーであったアーネスト・ラザフォードは、初めて原子核の質量と大きさを非常に正確に計算することができた。ラザフォードは、既存の仮説を検証するためだけでなく、新しい原子モデルを開発するためにデータを利用した。このように証拠を利用して新しい仮説を生み出すことを、(C・S・パースに倣って)アブダクションと呼ぶことがある。社会科学の方法論者であるドナルド・T・キャンベルは、そのキャリアを通じて仮説検証を重視してきたが、その後、科学の本質は「実験それ自体」ではなく、「もっともらしい対立仮説」の反復的な競争であるとますます強調するようになった。他の科学者や哲学者は、データや仮説を利用する際に、疑問や問題が中心的な役割を果たすことを強調してきた。

イギリスの物理学者アーネスト・マースデン
ニュージーランド出身のイギリスの物理学者アーネスト・ラザフォード
※ガイガー=マースデン実験(ラザフォード金箔実験とも呼ばれる)は、科学者たちが、すべての原子にはその正電荷と質量のほとんどが集中する原子核があることを学んだ画期的な一連の実験である。彼らは、アルファ粒子ビームが薄い金属箔に当たったときにどのように散乱するかを測定した結果、このことを突き止めたのである。実験は1908年から1913年にかけて、マンチェスター大学の物理学研究所でアーネスト・ラザフォードの指導の下、ハンス・ガイガーとアーネスト・マースデンによって行われた。

アメリカの社会科学者ドナルド・トーマス・キャンベル
科学的証明の概念
「科学的証明」という言葉は一般的なメディアでよく使われるが、多くの科学者や哲学者は、無謬の証明など実際には存在しないと主張してきた。例えば、カール・ポパーはかつて次のように書いている。「我々が生きている世界についての情報を我々に提供できるのは経験科学だけであり、「証明」というのが、ある理論の真理を一度きりで永遠に立証する論証を意味するのであれば、証明は起こらない」。アルベルト・アインシュタインは言った。

科学理論家はうらやましいものではない。自然は、より正確には実験は、彼の研究を容赦なく、そしてあまり友好的に判断しないからだ。自然は決して理論に「イエス」とは言わない。最も好意的な場合は「たぶん」と言い、大多数の場合は単に「ノー」と言う。実験が理論に同意すれば、それは後者にとって「たぶん」を意味し、同意しなければ「ノー」を意味する。おそらくどの理論も、いつかは「ノー」を経験するだろう。
しかし、無謬の証明という理想とは対照的に、実際には、ある調査において使用される証明の基準に従って、理論は証明されていると言えるかもしれない。この限定的な意味において、証明とは、科学的共同体の基準に従って調査と批判的評価のプロセスを経て、理論が高度に受け入れられることである。
関連記事
最後に
最後までお付き合いいただきありがとうございました。もし記事を読んで面白かったなと思った方はスキをクリックしていただけますと励みになります。
今度も引き続き読んでみたいなと感じましたらフォローも是非お願いします。何かご感想・ご要望などありましたら気軽にコメントお願いいたします。
Twitterの方も興味がありましたら覗いてみてください。https://twitter.com/Fant_Mch
筆者の大まかな思想信条は以下のリンクにまとめています。https://note.com/ia_wake/menu/117366
今回はここまでになります。またのご訪問をお待ちしております。
それでは良い一日をお過ごしください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
