
『侍戦隊シンケンジャー』論考第三幕〜小林靖子と「肉親の情愛」から見る精神的孤独〜
1回目・2回目に続く『侍戦隊シンケンジャー』論考、今回はその3回目であるが、今回は小林靖子脚本を語る上での1つの主題論とでもいうべき「肉親の情愛」について語る。
もっとも、このテーマ自体は今回初めて語るものではなく、以前に小林靖子脚本における1つの共通項というか特徴的なるものとして「捻れた肉親愛」と精神的孤独が挙げられるのだ。
よくファンが口にする「時代劇趣味」「主人公を曇らせる」などといった安易な言葉では片付けられない衝撃・驚きたるものが彼女が残した作品の中には多々見受けられる。
それは自身でも語るように「脚本家」ではなく「脚本士」であると自称することから来る作家としての孤独から来ているものではないだろうか。
以前に小林靖子脚本に見受けられる「作家としての孤独」と「登場人物が抱える肉親愛(ブロマンス)」について大雑把に語ったが、では「シンケンジャー」において肉親愛がいかにして表現されているのか?
今回は主に本作で語られている侍たちの孤独がいかにして表現されているのか?に関して、いわゆる「影武者」ネタとはまた別事項のものとして考察して行こうという試みである。
小林靖子が自らを「脚本士」と称することからわかる作家としての孤独

まず「シンケンジャー」における「捻れた肉親愛」を語る前に改めて小林靖子という脚本士が持つ作家としての孤独と異端性に関して改めてここで述懐しておかなければなるまい。
作家や脚本家は自分の表現したいことや自分にしか書けないものを持っているイメージがあるのですが、私はそういうタイプではないんですね。だから自分のことを作家とも脚本家とも思っていないんです。強いて言えば“脚本士”。作品やキャラクターの魅力を映像的にどう伝えるべきかを考えて、これまで培ってきたシナリオライティングの技術を駆使してそれを実現する。そこに自分らしさは必要ないというか、全く意識していないですね。
再度の引用であるが、確かに彼女が初メインで手掛けた『星獣戦隊ギンガマン』(1998)から『烈車戦隊トッキュウジャー』(2014)までに手掛けた5つのメインライター作品並びにサブライターとして参加した作品における個性は後にも先にも例がない。
「ギンガマン」の第一章「伝説の刃」を最初に見た時、我々は心より待ち望んだ「平成戦隊のニュースタンダード像」の登場に歓喜するのみならず、その喜びの中にもある種の驚き・衝撃・戸惑いといった負の感情も同時に襲われる奇妙な感覚に陥った。
その理由は彼女が手掛けて実際の映像として出来上がったドラマが『秘密戦隊ゴレンジャー』(1975)の上原正三・曽田博久をはじめとする既存の脚本家・作家のいずれにも似ていなかったからであり、しかも彼女の精神的継承者も存在しない。
以前も述べたが、例えば上原正三は幼少期の沖縄での戦争体験が彼自身の作風の源泉になっていることが明らかであるし、また金城哲夫や市川森一などの同期の存在が彼に大きな影響を与えていることは60〜70年代の彼が手掛けた作品を見れば一目瞭然だ。
曽田博久も例えば学生運動の活動家だったという経験が彼の作風に活かされており、また『科学忍者隊ガッチャマン』の松浦健郎・鳥海尽三辺りに師事したり、浦沢義雄師匠に関しても鈴木清順と大和屋竺などの天才作家に師事して作風を確立している。
クリエーションとは「匠」の世界であり、かつての映画業界がそうであったように昔はそのような徒弟制度に近い丁稚奉公の制度があって、巨匠とでもいうべき作家に師事して作風を確立するものだが、小林靖子にはそういう「師匠」というべき人がいない。
『特捜ロボジャンパーソン』(1993)で異例のデビューを果たした彼女だが、その作風はやはり誰かに教わったというより彼女自身の徹底した脚本構造の研究と模倣を繰り返した結果として出来上がったものであり、ある意味では「二次創作作家」といえるだろう。
しかし、彼女は確かに育ててくれた存在として堀プロデューサーや長石多可男監督・鷺山京子などがいたが、この人たちは「師匠」というよりも「同僚」に近く、彼女の作風に直接の影響を与えたという風には考えにくい。
また、昔の脚本家・作家には例えば作風の源泉となるトラウマや幼少期の体験から思想が出来上がることが多いのだが、小林靖子自身の過去については「時代劇や刑事ドラマなどの男児向けの作品が好きだった」ことしか語られていないのである。
いうならば庵野秀明らと同じ「オタク第一世代」というべき、テレビ文化の黎明期を原体験として育っていること以外特筆すべきことはなく、そういう意味で彼女の脚本は明らかに既存の脚本家の系譜にはなくどこか淡白な印象があるのだ。
つまり小林靖子という脚本士は既存のスーパー戦隊シリーズのどの作家にも作風が似ておらず、また彼女自身の技法の継承者もいないという点において「孤独」であり「突然変異」とでもいうべき人ではなかろうか。
強いて言えば、同じ女流作家の香村純子は小林靖子への憧憬・尊敬の念を公言しており作風も幾許か意識して寄せているが、どこまで行こうとやはりエピゴーネン(亜流)の領域を抜け出ないため「後継者」とは言い難い。
事によると、決して大袈裟でも過大評価でもなく、小林靖子こそがスーパー戦隊シリーズの脚本においては最後の「作家」というべき存在であったかもしれない事実はいまだに戦隊ファンが理解・共有しうる事実だろう。
少なくとも彼女の後に東映特撮やスーパー戦隊シリーズにおいてその作家性が受け手の間で語られ、それが一時代を築き上げ後世にも影響を与え続けるほどの作家性を持つ人は存在していないのだから。
ましてやテレビ文化がもはやメディアとしての影響力を喪失し凋落・衰退している現状においては彼女のような突然変異の天才が生まれる文化的風土すらないのだからなおさらのことである。
まずはこの事実を決して楽観的にではなく悲観的に受け止めた上で「シンケンジャー」という作品において語られる「肉親愛(ブロマンス)」について考えていくことが肝要であろう。
「肉親愛(ブロマンス)」に対する冷徹かつ皮肉的な視線
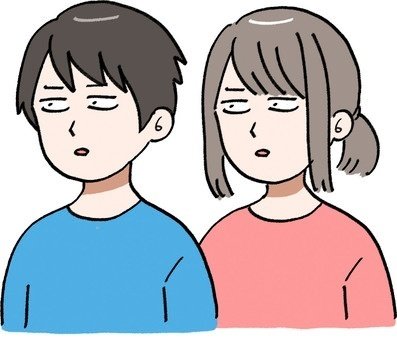
初メインとなる『星獣戦隊ギンガマン』(1998)の頃からそうだが、小林靖子は「肉親愛(ブロマンス)」に関して極めて冷徹かつ皮肉的な視線を持っており、それは「別離」「反発」で表現されることが多い。
例えば「ギンガマン」第一章において彼女は劇中最強の戦士として描かれているカリスマの象徴であるヒュウガをいきなりゼイハブの手によって地の底に沈めて死なせ、弟のリョウマに炎の戦士・ギンガレッドを継承させていることがそれだ。
一見麗しい兄弟愛を描いているようで、実際はむしろ逆でありリョウマが炎の戦士・ギンガレッドとして成長するためにはヒュウガの存在はとんでもなく邪魔であり、リョウマを成長させるために一度兄弟を死別させる。
この後に出てくる青山親子に関しても、やはり息子の勇太が父親の晴彦に対して煙たがったり突っ込んだりする描写が多く、彼自身はむしろリョウマを憧れの存在として慕うことが多い。
それは彼女自身の作家性が世に知られることとなった『未来戦隊タイムレンジャー』(2000)においてもそうであり、典型的なのは年間を通した縦軸の1つである浅見親子の確執であろう。
竜也にとっては頭ごなしに家名を受け継がせようとする父・浅見会長の存在がとんでもなく邪魔であり、自分が自分であるというアイデンティティーを確立するためにトゥモローリサーチという零細の会社を設立した。
また、彼と後半〜終盤において淡い恋愛関係を演じることになるユウリに関しては肉親を幼少期に喪失した天涯孤独の身であり、その元凶となったドルネロへの復讐を糧に刑事として動いている。
更にシオンも故郷の星を亡くしている天涯孤独の身であるし、アヤセ・ドモン・滝沢直人の3人に関してもその背景に肉親の存在は一切なく、肉親愛(ブロマンス)は劇中でむしろ崩壊したまま話が進む。
それは例えば井上敏樹が描くシェイク・スピアや太宰治のような悲観的なロマンスというよりももっと冷めていて、むしろハワード・ホークスや上述の北野武に近い皮肉的な俯瞰の視線といえるであろう。
小林靖子という脚本士にとって肉親の存在は主役の登場人物の成長や行動を妨げる障害物・足枷でしかなく、決して有り難がるような存在ではなく「親子であっても独立した存在」として描かれている。
だからリョウマとヒュウガの炎の兄弟にしろブルブラックとクランツの黒騎士兄弟にしろ、そして浅見親子にしろユウリ一家にしろ小林脚本における家族や家庭には「一家団欒」の空気は全く感じられない。
それは「親をないがしろにしてもいい」という性悪説などではなく、むしろ彼女自身が描いていく中で自然に出てきた無意識の選択であり、それは「シンケンジャー」においても通底している要素である。
『侍戦隊シンケンジャー』(2009)の侍たちにもいわゆる「肉親」と呼ぶべき存在は出てくることがあるが、「ギンガマン」「タイムレンジャー」とは異なり主人公の丈瑠や幼馴染の源太、そして終盤の薫姫には肉親がいない。
その代わりに歌舞伎役者の池波流ノ介、保母さんとして働きながら「普通のお嫁さん」に憧れている白石茉子、擦れた現役高校生の谷千明、そして病弱な姉の代理で侍をやっている花織ことはに肉親が出てくる。
「ギンガマン」「タイムレンジャー」とは逆で主人公となる赤の戦士ではなく脇にいる家臣たちの方に肉親がいるというのが本作の特殊なところだが、そこでもやはり肉親の存在は邪魔でしかない。
少なくとも「シンケンジャー」において肉親の存在が彼らの成長を後押ししてくれるようなことなど一回もないのである。
「シンケンジャー」における親子話は本当に「いい話」なのか?

「シンケンジャー」の感想を見て回ると、本筋とは別の部分である「家臣たちの肉親」が出てくる話に感動したという声が多いのだが、私自身はこれらの感想や論調に対して奇妙な違和感が拭えずにいる。
例えば第一幕の過去回想では丈瑠の父が「今日からお前がシンケンレッドだ!」と強迫観念気味に丈瑠の呪縛となり、また、流ノ介の父親も堅苦しく真面目な親として流ノ介に侍としての心構えを説く。
ここだけを見れば肉親愛が幾分肯定的に描かれているようだが、それ自体は第二幕の千明と龍之介の「いい加減な親らしいな」「当たってるだけに腹立つんですけど!」とそれが原因で衝突している。
それどころか流ノ介は当初親からの教えを律儀に守ろうとして空回りしており殿も含めた他の侍たちから煙たがられているが、その流ノ介自身が最終的に第七幕で肉親愛(ブロマンス)を強く否定している。
「あの殿なら命を預けて一緒に戦える。そう決めたのは自分です!親じゃない」(第七幕『舵木一本釣』より)
そう、物語序盤の早い段階で他ならぬ流ノ介の口から「親の洗脳」であることがはっきりと否定されており、流ノ介が侍・家臣として戦うのはあくまでも丈瑠の人間性に対する信頼・信用であることが描かれた。
これは決して流ノ介だけに固有のルールなのではなく、第二十一幕の谷親子も第三十四幕の白石親子も、そして第四十一幕の花織姉妹においてもこのルールは適用されており、やはり肉親愛は肯定的に描かれない。
家臣たちがそれぞれ口にする肉親への思いがはっきりとされる心情語とでもいうべきセリフをここで引用してみよう。
「姐さん。強くなると、もっと強いのが見えるんだな。親父の剣、ずっと見てたのにさ、強さはわかってなかった」(第二十一幕『親子熊』より)
「私、侍はやめない。お父さん達の事を恨んでるわけじゃないし、後悔もしてないから。ただ、あの時、ただ……」(第二十一幕『親子熊』より)
「でもうち、お姉ちゃんの代わりが出来てへん。殿様や、みんなが優しくしてくれるのに、甘えてたんです」(第二十一幕『親子熊』より)
ここには一見、家臣たちの肉親に対する歪んだ情愛が彼ら自身の内情として肯定されているようだが、その時の彼ら自身の表情やそれを映し出すカメラの照明は決して明るくはなくむしろ若干の暗さや影を伴っている。
特に第三十四幕の茉子と第四十一幕のことはのセリフは典型だが、茉子は肉親に対する不平不満が激昂という形で噴出しており、ことはに至ってはそれが雑念として彼女の心を蝕む毒にまでなっているようだ。
それにもかかわらず、例えば三十四幕の茉子と茉子母の抱擁のシーンに関して、以下のような見解を述べている人までいる。
つまりは、茉子の特徴的な面はすべて、母親のネガティヴな影響だったということです。逆に、茉子の侍としての凛とした様子は、深く傷付くまで戦い抜いた母親の侍魂を受け継いでこそのものであり、これは伊藤かずえさんが醸し出す雰囲気が、多くを語っているように思います。真に重要なのは、最後に挙げたポジティヴな事項であり、本エピソードの収穫はここにこそあると断言出来るでしょう。
本当にそうか?
確かに最後の母娘の抱擁と笑顔だけを見れば白石家の情愛が例外的に肯定されているようであり、最終幕では「しばらく両親と暮らしてまた戻ってくる」とも口にしているが、ここで大事なのは茉子が「侍であることをやめない」「また戻ってくる」という点だ。
茉子は確かに幼少期のトラウマから満たされない空虚な内面を弱った人に抱きついたりお嫁さんに憧れたりすることで満たそうとする、いわゆる「アダルトチルドレン」の側面があったが、そのことと茉子自身の「侍としての覚悟」は全く相関性がない。
何より親子の情愛が純粋に肯定されているというポジティブな解釈をするには長石監督が撮ったこのシーンは照明があまりにも暗く重苦しい影がのしかかっており、この後茉子はむしろ流ノ介と同じように侍としての純度が高まっていく。
実際、彼女からその後最終幕まで肉親への思いが出たことなど一回もないし、流ノ介も千明もことはも肉親への思いを振り切った後はむしろ殿との主従関係を最優先としており、それは肉親愛(ブロマンス)とは全く別のものである。
「肉親愛(ブロマンス)」とは「継承」であると同時に「呪縛」でもある
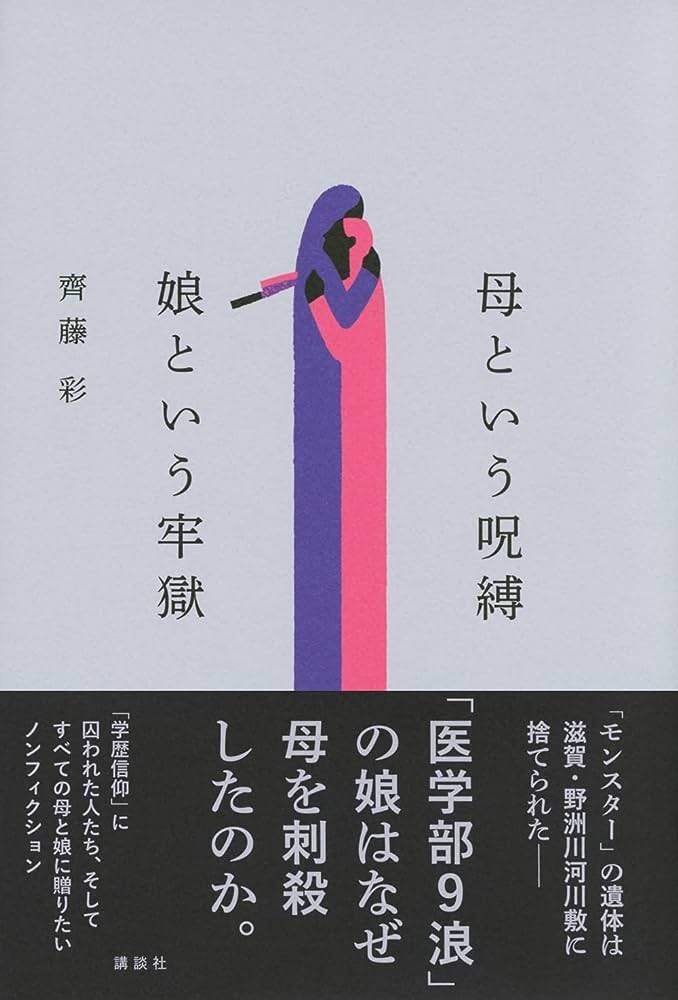
このように見ていくと、「シンケンジャー」において改めて誰の目にも明らかになったこととして、小林靖子にとって「肉親愛(ブロマンス)」とは「継承」であると同時に「呪縛」でもあるという1つの主題が浮き彫りとなるだろう。
「ギンガマン」でも例えばヒュウガからリョウマへ戦士としての薫陶が継承されたようでいて、実はそれ自体がリョウマを雁字搦めにする「呪縛」にもなっており、モークや黒騎士ブルブラックからもそれが弱さであることを指摘された。
そして実際にリョウマは兄ヒュウガから星獣剣を継承することでギンガレッドの資格は受け継いだが、そこから一人前の戦士へ成長したのはむしろヒュウガが引き剥がされた4クール目からであり、ヒュウガと離れることでむしろ成長する。
それは「シンケンジャー」においても例外ではなく、侍たちも親から思想や技術面を「継承」はしているが、同時にそれが「呪縛」にもなっており、あくまでも彼らが成長していくのはむしろ親からの解放を果たした時だ。
「覚えてますよ……どんなに小さくても、絶対に忘れない。例え、牛折神から引き離しても、受け継いだ想いからは引き離せない」(第三十三幕「猛牛大王」より)
榊家の祖父に対して丈瑠が改めて口にしているこの言葉こそがある意味では「シンケンジャー」も含めた小林靖子の家族観なのかもしれない。
そうなのである、物理的に引き剥がせたとしても継承した潜在意識に深くめり込んでいる「親の想い」からは決して逃れることができないという厄介さが重くのしかかる。
だからこそ、そこに対していかに折り合いをつけながら戦士としての成長を描いていくのかというのが小林脚本の1つの特徴だが、これは相当にドライな目線を持たなければできないことだ。
そしてこの「想いの継承」とは同時に「呪縛」であるというのは本作を最高傑作と評するファン・信者がその根拠として挙げる終盤の「影武者」においても例外ではない。
本稿で語ったものをベースに次回は終盤の「影武者」をめぐる一連の騒動がどのようなものであったかを考えていこう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
