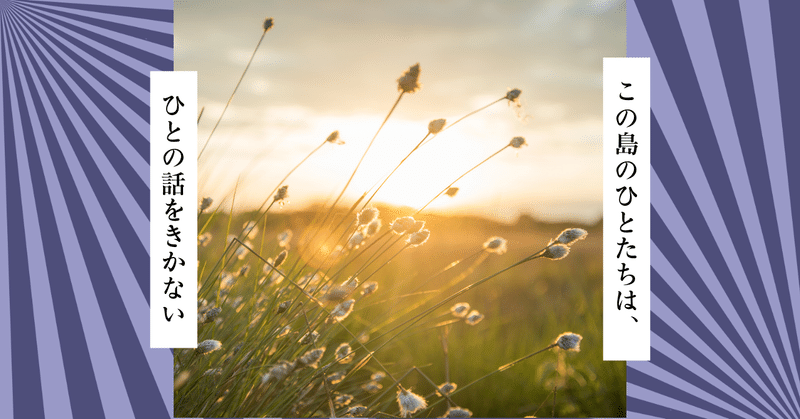
自殺希少地域の本についてのメモ
自殺に関しての研究の多くは自殺の原因が何か、どのような人が自殺に至るのかを明らかにすることが多かった。この本は他とは違い、自殺をする人が少ない地域(自殺希少地域)を研究の対象としている。
精神科医の森川すいめいさんが自殺希少地域を旅し、感じたことをまとめてある本。
一つ目の地域は徳島県海部町(現:海陽町)
序章
●自殺希少地域は癒しの空間ではない
宿のお菓子は賞味期限切れ。宿の人は賞味期限を気にする人もいるんだなという反応。家からお菓子を持ってきてくれる。
→小さなことは気にしない。自分と他人は違って考え方も違うことを認識。押し付けもしないし、否定もしない。
●自殺の対策は予防と防止
①防止はビルの屋上に高いフェンス。地下鉄にはホームドア。効果がわかりやすく評価しやすい。
②予防に関しては、自殺に至る原因は無数にあり、細分化する必要がある。全てを取り除くことは難しい。いじめ、過去のトラウマ、疎外感等。その内容もそう感じるまでの過程も人によって違う。
→自殺希少地域には、『自殺予防因子』があるかもしれない。
第一章 助かるまで助ける
●街にベンチを置くと座る人が出てくる。ちょっとしたコミュニティが出来る。
●日本と福祉国家の違い
①日本
・バリアフリー先進国。みんなが同じように生活できるようにハード面にお金をかけている。車いすでも生活しやすい道路、段差のない施設等。
・孫が遊びに来て嬉しいのに一緒に買い物に行かないお年寄り。人の集まる街のスピード感についていけない。自分の歩く速度や、レジでお金を払う速度では迷惑をかけてしまうから。
・介護施設に入りたくないお年寄り。介護施設は姥捨山だと考える。
→できない人が悪い。自己責任。息苦しい。引け目を感じる。寛容さがない。
②福祉国家のフィンランド
日本ほどバリアフリーが進んでいない。車いすの人がガタガタの道を通る。スピードは遅いし場所を取るけど、助けが必要な人は他の人がその都度助ける。
→引け目を感じることは無い。みんな違うことを受け入れている。助け合い。
第二章 組織で助ける
●行政は人が生きやすくなるためにある。この目的を達成する手段として、効率化やコスト削減がある。今は効率化やコスト削減自体が目的となることが多く、人が生きやすくなるためといった元の目的が忘れられることが多い。
●2種類の組織
①問題を起こらないようにする組織
学校、会社、役所等ほとんどの組織が当てはまる。問題を起こさせないためにルールが多い。機動性がない。問題が起こった後の解決能力が低い。だれの責任か、どこに穴があったのかそういう話に大部分が割かれる。
②問題は起こる前提の組織(問題が起こったときに対処する組織)
ルールが最小限。自由で機動性がある。問題が起こった後解決に向けての話し合いになる。責任の押し付け合いなどではなく、再発防止など前向きな話になる。
この2タイプのバランスが大事。日本は前者に寄りすぎている。
●これからは今ある問題解決のためのNPOが多く出てくることが地域に大切になってくる。存続を目的としてはいけない。
運営は様々なところからの助成金や寄付になってくる。そのためにはコンセプトに共感してもらう必要がある。プレゼンできることが大事。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
