
マーティン・ジェイ『うつむく眼』新装版の刊行にあたり「訳者あとがき」を公開!
マーティン・ジェイ著/亀井大輔・神田大輔・青柳雅文・佐藤勇一・小林琢自・田邉正俊訳『うつむく眼──二〇世紀フランス思想における視覚の失墜』新装版の刊行にあたり、訳者を代表して亀井大輔氏が執筆された「訳者あとがき」の一部を公開いたします。
古代ギリシア以来、最も高貴な感覚と見なされてきた視覚は、現代フランス思想によっていかにその権威を剥奪されたのか。本書は百花繚乱のフランス思想に通底する「反・視覚中心主義」を指摘した記念碑的大著です。
*本稿は、『うつむく眼』の初版(2017年12月)に収録された「訳者あとがき」に、新装版への「追記」(2024年4月)を加えたものであり、あとがきの内容は初版刊行時のものです。
訳者あとがき
本書は、Martin Jay, Downcast Eyes : The Denigration of Vision in Twentieth-Century French Thought, University of California Press, 1993の全訳である。
著者マーティン・ジェイは一九四四年五月四日アメリカ、ニューヨーク州生まれ。一九六五年に同州のユニオン・カレッジにて学士号を取得、一九七一年にハーヴァード大学にて博士号を取得した。博士論文は後に『弁証法的想像力』(一九七三年)として刊行される。その後も『マルクス主義と全体性』(一九八四年)、『アドルノ』(同年)、『永遠の亡命者たち』(一九八五年)などの著作を発表し、アメリカを代表する思想史家として世界的な名声を得た。現在もカリフォルニア大学バークレー校教授を務めている。著書には他に『世紀末社会主義』(一九八八年)、『力の場』(一九九三年)、『文化の意味論』(一九九八年)、『暴力の屈折』(二〇〇三年)、『経験の歌』(二〇〇五年・未訳)、『嘘をつくことの美徳』(二〇一〇年・未訳)、『境界からの試論』(二〇一一年・未訳)などがある。
ジェイについては日本でもすでに多くの翻訳が刊行されており、その経歴を詳しく紹介する必要もないほどである。とはいえ、ジェイと言えばやはりフランクフルト学派研究で知られており、それ以外の方面における業績が見えにくくなっていた感がある。本書は、ジェイが一九九〇年代に成し遂げた、ヨーロッパ思想史の領域におけるもうひとつの代表作であり、フランス現代思想を中心に、西洋における視覚の運命をたどった記念碑的な大著である。本書の刊行によって、思想史家ジェイの全貌がようやく姿を現し出したと言っても過言ではない。
本書で著者は、古代ギリシア以来のヨーロッパの思想や文化に「視覚」をもっとも高貴な感覚とみなす傾向がある、ということから語り始める。そして、とりわけ近代になって視覚は中心の座を占めたが、そうした視覚中心主義も次第に危機に陥り、二〇世紀フランスにおけるさまざまな思想にいたっては反対に、総じて視覚に対する嫌悪や批判や攻撃がみられる、つまり反視覚中心主義が広まっている、ということを大胆かつ丹念な筆致で描き出している。
ヨーロッパ思想における視覚の重要性についてはこれまでも論じられてきたが、現代フランス思想の全体に反視覚中心主義が染み込んでいることを論じたのは本書の慧眼だろう。むろん、本書の狙いは百花繚乱のフランス思想を一括りにして片付けることではない。視覚をめぐる隠れた次元を明るみに出すことによって、ヨーロッパ思想史の長いスパンのなかで二〇世紀フランス思想に新たな光を投げかけることや、それをつうじて現代の意味を根底から考察することも意図されていよう。
本書の圧倒的な量については一目瞭然であるが、古典から最新の研究書まで膨大な文献の渉猟、西洋の歴史全体を見渡す透徹した視野、歴史物語的な論述の巧みさなど、本書の魅力は尽きない。視覚論の基本文献としてすでに確固とした評価を得ている本書であるが、全体を通覧的に読みとおしても、読者の興味関心に従ってどの章から読み進めても、あらためてその面白さを実感することができるはずである。
本書の狙いと方法論についての詳細は、序論で著者が明確に提示しているので、そちらをお読みいただきたい。ここでは本論の議論の流れを紹介するために、各章の内容についてざっと大筋を示しておく。
第1章では、まず古代のギリシアにおいて、視覚がもっとも優位に置かれていたこととその含意が、複数の文献を手がかりに明らかにされる。一言で「視覚」といっても単純ではなく、身体の眼による視覚と、精神の眼による視覚の双方があいまって、西洋の視覚中心主義を形成してきたことも述べられる。続いて、中世とルネサンスがいかに近代の視覚中心主義を準備したかが語られる。そして、近代の支配的な視覚体制となった「デカルト的遠近法主義」の由来が、デカルトの『屈折光学』を詳しく見ていくことで考察される。
第2章では、啓蒙時代に入っても視覚中心主義が依然として続いていくなかで、次第に視覚の優位が動揺していく様子が描かれる。まずはスタロバンスキーを案内役に、一八世紀フランスのさまざまな側面が観察される。ルイ一四世の治世、コルネイユとラシーヌの演劇、モンテスキューとルソー、フランス革命、ディドロとモリヌークス問題といった諸点である。次いで、一九世紀における視覚をめぐる変動が、パリの都市風景の急速な変化と、カメラの発明という視点から描写される。
第3章では、二〇世紀に入り第一次世界大戦直後までの時代に生じた視覚の優位から廃位への反転が、芸術、文学、哲学それぞれの事例に即して語られる。まず、印象主義以降の視覚芸術の歴史がたどられ、マルセル・デュシャンの反網膜主義の諸作品が詳しく論じられる。次に、フランス文学の歴史が主題となり、ボードレール、マラルメ、そしてとりわけプルーストの『失われた時を求めて』に焦点が当てられる。最後に、ベルクソンの哲学がフランス哲学における視覚中心主義批判の皮切りとなったことが、『時間と自由』『物質と記憶』などの主要著作の読解をつうじて示される。
第4章では、第一次世界大戦後、視覚中心主義批判はより激しくなったことが描かれる。このことは、ジョルジュ・バタイユとシュルレアリストによる眼へのこだわりによって示される。バタイユについては、その戦時体験、盲目の父との関係、『眼球譚』、『太陽肛門』や他の多くの論考がたどられる。とりわけ「不定形」「迷宮」といったイメージは、バタイユ以後の反視覚的な思想においても執拗に繰り返されるものとなる。シュルレアリストについては、ブルトンとバタイユの反目、幻視的啓示としての眼、夢のイメージ、シュルレアリスム写真や映画(とくに『アンダルシアの犬』)などが論じられる。
第5章では、まずドイツの哲学者フッサールとハイデガーの視覚をめぐる態度について論じられた後、彼らをフランスに導入したジャン=ポール・サルトルとモーリス・メルロ=ポンティが対照的に語られる。サルトルは、自伝的な要素、小説『嘔吐』での触覚重視、さらには『存在と無』での相互敵対的な「眼差し」の理論によって、視覚中心主義への強烈な批判者と位置づけられる。それに対してメルロ=ポンティの知覚の現象学は、視覚の高貴さを回復する試みとみなされるが、それでもそのなかには反視覚中心的な要素が含まれていることが論じられる。
第6章では、まずフロイトの精神分析が視覚に対してどのような態度をとっていたかについて述べられた後、ジャック・ラカンの鏡像段階の理論、続いて眼と眼差しの分裂と絡み合いが論じられる。鏡で自己の身体を見ることは一種の「誤認」である、という鏡像段階論は、ルイ・アルチュセールによってマルクス主義へと橋渡しされ、彼はイデオロギーがこの誤認によって成立すると論じた。こうして一九六〇・七〇年代のマルクス主義に反視覚中心的な感情が広がった。最後に、アルチュセールが幼少時に眼を特権化していたという自伝での告白が、一九八〇年代でも反視覚中心主義の力が続いたことの例示として紹介される。
第7章では、現代社会に対する視覚中心主義の弊害を、監視の社会もしくはスペクタクルの社会として告発した人物であるミシェル・フーコーとギー・ドゥボールが論じられる。フーコーについては、初期の現象学時代から『狂気の歴史』、ルーセル論、『言葉と物』にいたる視覚への注目がたどられた後、『監獄の誕生』での一望監視の眼差しの権力にかんする考察が繰り広げられる。ドゥボールをめぐっては、シチュアシオニスト・インターナショナルの成立過程や活動内容から、著書『スペクタクルの社会』、活動の終焉までが見届けられる。
第8章では、文化批評家のロラン・バルトと、映画理論家のクリスチャン・メッツならびに映画批評誌『カイエ・デュ・シネマ』の執筆者たちが取り上げられる。まず、バルトと視覚をめぐる議論が、とりわけ『明るい部屋』での写真論を中心に、自伝的テクスト『ロラン・バルト』の解釈も挟みながら展開される。次いで、フランスの映画批評・映画理論の歴史をたどりつつ、一九六〇年代末に生じた新たな論調として、映画を「装置」として捉えるボードリーやメッツの映画理論が考察される。その議論は視覚中心主義批判が頂点を迎えた瞬間だとみなされる。
第9章では、ジャック・デリダの脱構築と、その影響を受けたフレンチ・フェミニズムのリュス・イリガライにおける視覚とのかかわりが考察される。両者はともに反視覚中心主義をさらに燃え上がらせた。デリダの場合、視覚を他の感覚や言語と絡み合わせて複雑にしていくその手つきが、絵画や写真を論じたテクストを中心にたどられる。イリガライは視覚中心主義とファルス中心主義の結びつきを明らかにした人物として取り上げられ、ジェンダーと言語の関係への注目、ラカンの鏡像段階論との対決、プラトンの解釈などが論究される。
第10章は、ポストモダニズムが主題であるが、それがユダヤ教への接近という視点から論じられる。取り上げられるのは、エマニュエル・レヴィナスとジャン=フランソワ・リオタールである。レヴィナスについては、友人ブランショとの親和性、その倫理における聴覚や触覚の役割などが論じられる。リオタールについては、『言説、形象』での視覚論、ユダヤ的な偶像忌避にかんする論考、ポストモダンの崇高論などが検討され、最後に彼が携わった展示会「非物質的なもの」のなかに、現代社会のポストモダン的状況に残された視覚の可能性が探し求められる。
最後に結論では、本論の成果が確認され、かつての地位を奪われた視覚の行方に思いが馳せられる。ジェイによれば、視覚は反視覚中心主義の攻撃をくぐり抜けて、かろうじて生き延びているということである。─では本書の刊行から二五年が経過した現在、視覚の行方はどうなっているのだろうか。映像技術、コンピューター、インターネット、人工知能の発展が目まぐるしい現代、われわれの「視覚」は否応なく激しい変動にさらされ続けている。では現代の思想や言説において、視覚はどのような地位にあるのだろうか。これを考えるのは、われわれ読者に与えられた課題であろう。
日本語で読める関連文献についても補足的に述べておこう。第1章については、ジェイの論考「近代性における複数の「視の制度」」と合わせて読めば、近代とは何かについてのジェイの考えがより理解できる。これは一九八八年の視覚をめぐるシンポジウムで発表された論考であり、その記録がハル・フォスター編『視覚論』(平凡社ライブラリー)に収録されている。
また、論文集『力の場』(法政大学出版局)には、同論考(「近代の視覚体制」と改題)とともに、他の関連論文が三編収録されている。「解釈学の興隆と視覚中心主義の危機」「イデオロギーと視覚中心主義」「モダニズムと形式からの後退」である。ジェイはこれらの諸論を本書のプロジェクトの副産物と呼んでいる。その後も、ジェイは『暴力の屈折』(岩波書店)などで視覚論をさらに展開している。
本書で論じられる思想家には、刊行時には存命中だった人物もいる。そのひとりジャック・デリダは、『デリダ、脱構築を語る』(岩波書店)などで本書に言及して、その議論に応答していることも付け加えておく。
〔中略〕
ジェイは本書を、気球に乗って二〇世紀フランス思想の言説を上空から見渡す旅にたとえている。私たち訳者も、翻訳の作業をつうじて、その醍醐味を追体験することができた。思わぬ長旅になってしまったが、ようやく旅を終えたいまは、多くの読者のかたにも、この魅力的で発見に満ちた知的遊覧飛行を楽しんでいただきたいと願う一心である。哲学や思想史、現代思想に関心をもつかたに、またそれにとどまらず、文学や芸術、表象文化論や映像メディア論など、さまざまな方向から「視覚」に関心をもつ多くのかたに、幅広く本書が届くことを願っている。本訳書が、文化と視覚をめぐる新たな発見、考察、議論のためのささやかな一助となれば、訳者としては望外の喜びである。
二〇一七年一一月
追 記
新装版の刊行にあたり、誤訳や誤植の若干の修正、原註で参照されている文献の日本語訳の書誌情報のアップデート等をおこなった。
近年の動向をご紹介したい。マーティン・ジェイ氏は本訳書刊行後も精力的に著作を刊行している。最近の著書は以下のとおりである。Splinters in Your Eye: Frankfurt School Provocations, Verso, 2020 (『眼のなかの塵──フランクフルト学派の挑発』);Genesis and Validity: The Theory and Practice of Intellectual History, University of Pennsylvania Press, 2021 (『発生と妥当──知的歴史の理論と実践』);Immanent Critiques: The Frankfurt School Under Pressure, Verso, 2023 (『内在的批判──圧力下にあるフランクフルト学派』).
日本語訳としては、マーティン・ジェイ+日暮雅夫編『アメリカ批判理論──新自由主義への応答』(晃洋書房、二〇二一年)、加國尚志+亀井大輔編『視覚と間文化性』(法政大学出版局、二〇二三年)が刊行された。後者の論集は、『うつむく眼』の翻訳刊行をきっかけにして企画されたものであり、本書の日本編とも言うべきジェイ氏の論考「融合する地平?──日本における『うつむく眼』」を収録している。本訳書と併せてご覧いただければ幸いである。
二〇二四年四月八日

マーティン・ジェイ 著
亀井大輔・神田大輔・青柳雅文・佐藤勇一・小林琢自・田邉正俊 訳
『うつむく眼──二〇世紀フランス思想における視覚の失墜』
叢書ウニベルシタス1073/四六判上製/798頁/定価(本体6,600円+税)
ISBN 978-4-588-14084-6
2024年5月10日刊行
詳しくは以下よりどうぞ。
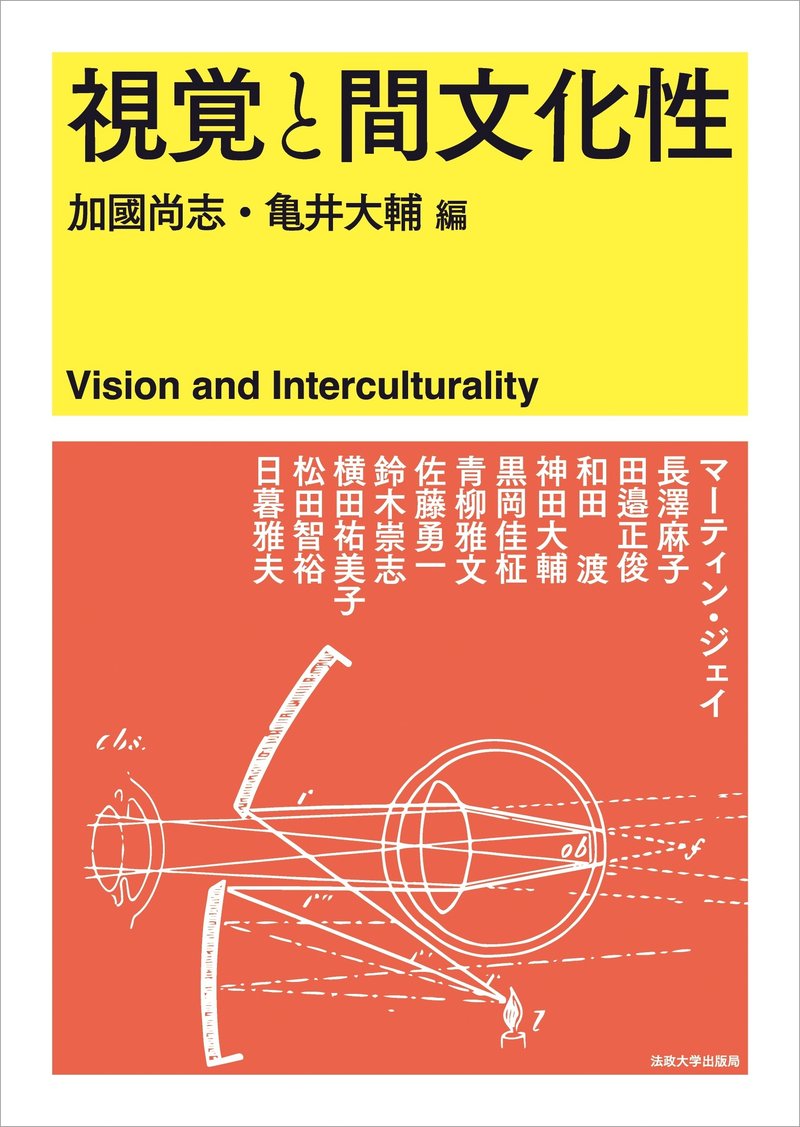
好評既刊
加國尚志・亀井大輔 編
視覚と間文化性
A5判上製/342頁/定価(本体4,500円+税)
ISBN 978-4-588-15133-0
2023年4月刊行
『うつむく眼』の日本編であるジェイ氏の論考「融合する地平?──日本における『うつむく眼』」(神田大輔訳)を収録。詳しくは以下よりどうぞ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
