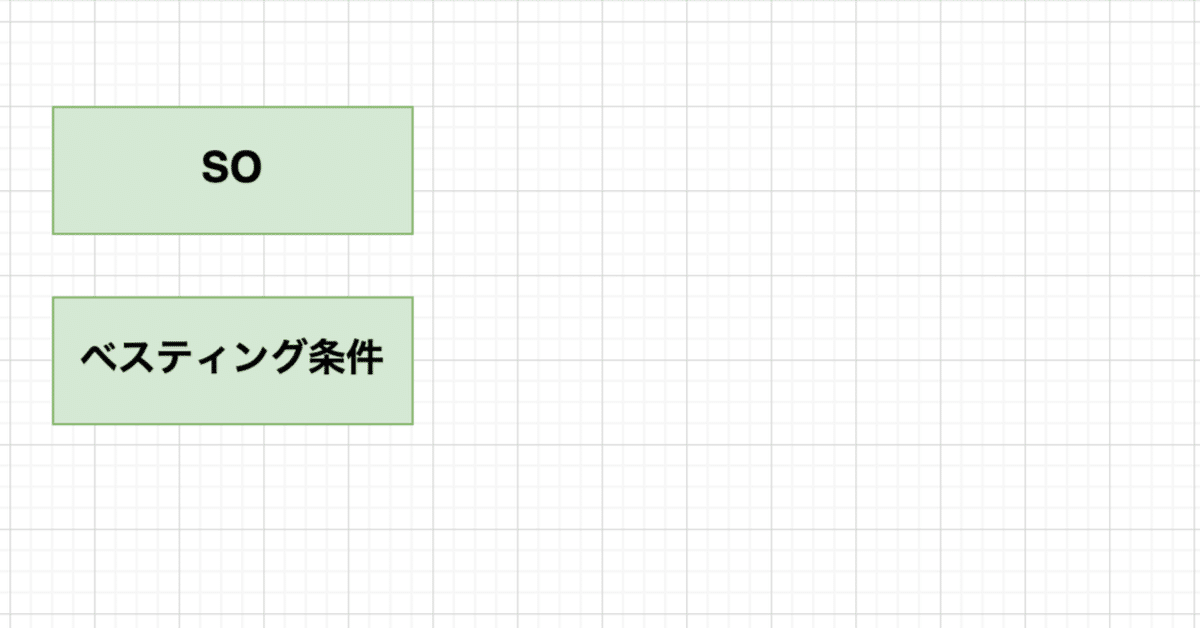
SOのべスティング条件の整理_上場日・入社日・割当日
#0_前提
日本の未上場スタートアップが、税制適格ストック・オプションを用いる場面を前提とする。
税制適格ストック・オプションにはほとんど全てのケースで、行使条件の一つとして会社の上場が設定される(税制適格要件の一つである株式保管委託要件との関係で事実上必要となるため。株式保管委託要件について詳しくは以下noteを参照。)。
この「行使条件としてほぼ必ず上場条件が設定される」という日本独特の事情が、日本のスタートアップのべスティング条件の考え方を独特なものにしている。
べスティング条件には様々なパターンがあるものの、その包括的な整理を示す試みはこれまであまり行われてきていないと認識している。
そのためこの記事では、日本のスタートアップが用いるべスティング条件について、一定の整理・全体像の提示を行うことを試みる。
#1_べスティング条件とは
スタートアップではメンバーに対するインセンティブ付与のために、ストック・オプション(SO)が用いられる。
SOには様々な条件があるが、そのうちの一つが、べスティング条件である。
べスティング(Vesting)とは、権利を確定させることを意味し、具体的には、一定の期間経過に従って、対象者に付与されたSOを徐々に行使可能にしていくことを意味する。
べスティング条件の主なプロパティは、以下である。

この中でも、期間の起算点がべスティング条件設計の大きな分かれ目である。
そのパターンとしては主に、上場日、入社日、割当日があるのでそれぞれ解説する。
#2_上場日起算べスティング
上場日起算べスティングのイメージ
べスティング期間の起算点を上場日に設定するタイプのべスティング条件である。
具体的な在り方としては、例えば、
上場から1年後に50%のSOが権利確定し(=行使可能になり)、
さらに上場から2年後のタイミングで残り50%のSOが権利確定する(=行使可能になる)

という形があり得る。
これは、べスティング条件の各プロパティを、以下のとおり設定することを意味する。
期間の起算点:上場日
期間の終点:起算点から2年後
SOの確定タイミング:上場から1年経過時点で50%、期間終点で50%
すなわち上記の具体例では、
上場してすぐはまだSO行使ができず、
上場から1年後時点で保有SOの50%が行使可能になり、
上場から2年後時点で残り50%のSOも行使可能になる(=全部のSOが行使可能になる)
ことになる。
上場日起算べスティングの主眼
全てのSOを行使できるまで、上記の例では最低でも上場から2年かかることになる。
上場日起算べスティングの主眼は、「上場してすぐSO全部を行使させず、それによりメンバーをリテインする」ことにある。
スタートアップの上場は一つの非常に大きな目標の達成であることに疑いはなく、メンバーに「燃え尽き症候群」的反応が生じることがある。
上場したらSOを行使して経済的利益を得て、すぐに退職してしまうかもしれない。
そこで、上場日起算べスティングを設定し、メンバーをリテインすることが意図される。
その前提として、「SOは退職した場合全部失効する」という設計がセットになる。退職してもSOが失効しないのであれば、上場日起算べスティングを設定してもメンバーをリテインすることはできないからである。
#3_入社日起算べスティング
入社日起算べスティングのイメージ
べスティング期間の起算点を入社日に設定するタイプのべスティング条件である。
具体的な在り方としては、例えば、
【入社日起算べスティング_具体例】
入社日から1年後時点に25%のSOが権利確定し、
入社日から2年後時点に追加で25%(累積50%)、
入社日から3年後時点に追加で25%(累積75%)、
入社日から4年後時点に追加で25%(累積100%)

という形があり得る。
これは、USでスタンダードとされている「4-years vesting with a 1-year cliff」を模したものである(USではより細かく月次でべスティングする例が多いようだが、日本ではあまりそのような例は見ない。)。
これは、べスティング条件の各プロパティを以下のとおり設定することであるとも表現できる。
期間の起算点:入社日
期間の終点:起算点から4年後
SOの確定タイミング:入社日から1年後に25%、その後1年ごとに25%ずつ確定
税制適格SOの各ドキュメント雛形キット「KIQS」も、入社日起算べスティングを盛り込んでいると認識している。
その基本的な主眼は、会社への貢献度(在籍期間で近似)とべスティング量を連動させることにある。
在籍期間が長いほど会社への貢献があったものとして、会社に多く貢献したメンバーにより多くのSOをべスティングする、という発想である。
なお、ここで気をつけなければならないことは、「べスティングされていても、会社が上場していなければ結局そのSOを行使することはできない」ということだ。
べスティングはSOの行使を可能にするものだが、実際に行使するためにはあくまで他の行使条件も満たしていることが前提となる。
そして、#0_前提で記載したとおり、日本では税制適格SOの行使条件として、ほぼ必ず上場条件が設定される。
その帰結として、べスティングされていても、上場していなければ結局SOを行使できないのである。
そうするとここで大きな論点が生じる。
「上場前にメンバーが退職した場合、入社日起算べスティングによりべスティング済みのSOを失効させるかどうか」という問題だ。
上場前において退職するメンバーは、既にべスティング済みのSOであっても行使することができない状態に置かれている。
このべスティング済みではあるがすぐに行使できない状態のSOを退職時に持ち出せるようにするか否かによって、入社日起算べスティングの設計は以下の2パターンに分類される。
パターン1_入社日起算べスティング(退職時全部失効)
このパターンは、メンバーが退職する際に、べスティング済みのSOもそうでないSOも全部失効させる、というものだ。
これまで、日本のスタートアップでは退職時にSOを全部失効させることが一般的だった。
このパターンは、そうしたこれまでの一般的な設計に沿うものである。
どのような場面が、入社日起算べスティング(退職時全部失効)にフィットするか。
先ほど述べたとおり、べスティングしたとしても、上場していなければ結局SOは行使できない。
そうすると、べスティング期間終点より後に上場が起きる場合は、入社日起算べスティング(退職時全部失効)を設定する意味がない。

上図のとおり、べスティング期間終点より後に上場した場合、入社日起算べスティングを設定したか否かにかかわらず、「上場までは全部のSOが行使できず、上場後は全部のSOが行使できる。退職したら全部のSOが失効する。」という全く同じ状態になるからだ。
入社日起算べスティングを設定する意義があるのは、べスティング期間中に上場が起きる場面に限られる。
下図のとおり、べスティング期間中に上場が起きた場合、メンバーは、べスティング済みのSOのみ行使でき、べスティング未了のSOは行使できないため、より多くのSOのべスティングを受けるために引き続き会社で働く、というインセンティブが生まれる。

まとめると、入社日起算べスティング(退職時全部失効)の意義は、「べスティング期間中に上場が起きた場合に、引き続きメンバーをそれまでの在籍期間に応じてリテインする」ことにある。
上場後のリテインを目的とする、という意味では、#1で解説した上場日起算べスティングと近い。
その違いは、「在籍期間にかかわらず、上場後一定期間を確実にリテインする(上場後べスティング)」か、「上場時点の在籍期間が短いメンバーのみ上場後もリテインする(入社日起算べスティング(退職時全部失効))」かの違いであると表現できる。
パターン2_入社日起算べスティング(退職時持ち出し可)
このパターンは、メンバーが会社を退職する際に、べスティング済みのSOを持ち出すこと(=保有し続けること)を認める、というものだ。
その背後には、「べスティング済みのSOは、それまでの貢献(=在籍)への対価として権利確定させているのであるから、退職したとしても保有し続けけられるべきである」という発想がある。

上図のとおり、上場前に行使できない点は変わらないが、退職した場合も、べスティング済みのSOを保有し続けることができる。
これまで日本のスタートアップでは退職時にSOが全部失効するという設計にすることが一般的だった。
しかし近年、退職時に一定割合のSOを保有し続けられるようにする設計を取るスタートアップが見られるようになってきた。
例えば株式会社カウシェは、退職後にも保有し続けられるSO制度についてプレス・リリースを行っている。
退職時に一定のSOの持ち出しを認めることの会社側としてのメリットとしては、
上場までどの程度期間を要するか全く目処が立たない状況等において、「上場まで長期間在籍し続けることが難しいメンバー」に対しても、貢献に対してSOで報いることができ、採用競争力の強化に繋がりうる(ダイバーシティや働き方の多様化の文脈にもつながる)
立ち上げ初期に入社し会社へ貢献したメンバーについて、会社の成長・ステージ変化と共にスキルセット・志向のミスマッチが生じたが、SOの失効を避けるために退職せず居残り続ける、という事態(本来メンバー・会社双方にとって不利益な事態である。)の発生を避けることができる
こと等が挙げられ、今後もこのような設計を取るスタートアップは増えていくのではないかと予想している。
入社日起算べスティング(退職時持ち出し可)の留意点
入社日起算べスティング(退職時持ち出し可)は、入社してすぐのメンバーにSOを付与する際にはマッチしやすい。
もっとも、入社からしばらく経っているメンバーにSOを付与する際には、留意が必要である。
例えば、極端な例では、すでに入社から4年が経過しているメンバーに、入社日起算べスティング(4-years vesting with 1-year cliff)で退職時持ち出し可のSOを渡すと、SO付与と同時にべスティングが完了しているため、そのメンバーは即座に退職しても100%のSOを保持し続けることができることになる。
これをよしとする考え方も否定はされないと思われるものの、SOのようなインセンティブ報酬は本来、会社の価値向上のために"将来に向かって"努力するインセンティブを与える目的のものである。
即座に退職しても100%のSOを持ち出せるのであれば、このようなインセンティブ効果は働きにくくなってしまう。
したがって、入社日起算べスティングは、入社から一定期間経過しているメンバーに付与する際には本当にインセンティブ効果が働くか、在籍期間とべスティング条件を照らして慎重に検討する必要がある。
他方で、次に述べる割当日起算べスティングであれば、将来に向かって努力するインセンティブ効果を持たせるという発想により親和的であり、入社日べスティングより幅広い場面にフィットしやすい、より汎用的な設計であると考えている。
#4_割当日起算べスティング
割当日起算べスティングのイメージ
べスティング期間の起算点をSOの割当日に設定するタイプのべスティング条件である。
具体的な在り方としては、例えば、
【割当日起算べスティング_具体例】
割当日から1年後時点に25%のSOが権利確定し、
割当日から2年後時点に追加で25%(累積50%)、
割当日から3年後時点に追加で25%(累積75%)、
割当日から4年後時点に追加で25%(累積100%)

という形があり得る。
これは、USで一般的とされている「4 years vesting with 1 year cliff」を模したものであり、上記#3の入社日起算べスティングと、起算点が異なるだけである。
また、割当日起算べスティングも、入社日起算べスティングと同様に、退職時にべスティング済みのSOの持ち出しを認めるか否かにより、
パターン1_割当日べスティング(退職時全部失効)
パターン2_割当日べスティング(退職時持ち出し可)
の2つに分類でき、その背後の発想も基本的に上記の入社日起算べスティングのものと同様である。
割当日起算べスティングと入社日起算べスティングの違い
割当日起算べスティングが入社日起算べスティングと異なるのは、「割当日から一定期間従業員をリテインすることでインセンティブ効果を確実に生む」ことができる、という点である。
例えば入社から4年が経過しているメンバーに対してSOを付与する際、
入社日起算べスティングでは、即座に退職しても100%のSOを持ち出せるためインセンティブ効果は生まれにくいが、
割当日起算べスティングでは、即座に退職した場合SOは持ち出せず、べスティング期間分在籍し続けるインセンティブ効果を生むことができる。
もっとも、割当日起算べスティングにおいても留意すべき点があり、それは「SO付与時点で既に長く在籍しているメンバーと、そうでないメンバーの間の公平性をどう確保するか」という問題である。
入社したばかりのメンバーと、すでに5年働いているメンバーがいたとして、2人の割当日起算べスティングのべスティング終点を同じとしてしまうと、すでに5年働いているメンバーにとっては不公平感は拭えない。
そのため、「SO付与時点で既に長く在籍しているメンバーについては、そうでない社員よりべスティングスケジュールを早める」ことで公平性を確保するとよい。
例えば、一般のメンバーのべスティングスケジュールを4-years vesting with 1-year cliffとするなら、そうでない社員は、2-years vesting with 1-year cliffとすることが一例として考えられる。
USのストックオプションに関する文献(Stephen R. Poland and Lisa A. Bucki, "Founder's Pocket Guide: Stock Options and Equity Compensation"(1×1Media, 2018) p31)でも、長く会社に在籍しているメンバーに対してはべスティングスケジュールを短くすることが提案されている。
※割当日起算べスティングの狙いである、割当日から一定期間在籍し続けるインセンティブ効果の発生は、厳密には入社日起算べスティングであっても、べスティング期間を伸長することにより達成することが不可能ではない。しかし、狙った期間のインセンティブ効果を発生させるために個々のメンバーの入社日を勘案した計算・条件設定が必要になり徒に煩雑であり、やはり「割当日から一定期間在籍し続けるインセンティブ効果の発生」という目的達成の手段としてはあまり合理的でないと考えている。
#5_まとめ
以上を総合すると、べスティング条件設計の最初の大きな分岐は、実は「退職したメンバーが、一定のSOを保有し続けることを認めるか」という点にあることがわかる。
退職後の保有を認めないなら、次の選択肢は、(1)上場日起算べスティングを設定する、(2)入社日起算べスティングを設定する、(3)割当日起算べスティングを設定する、(4)そもそもべスティングを設定しない、のいずれかになる。
それぞれの効果・留意点をまとめると以下のとおりである。

退職後の保有を認めるなら、次の選択肢は、(1)入社日起算べスティングにするか、(2)割当日起算べスティングにするか、ということになる。
それぞれの効果・留意点をまとめると以下のようになる。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
