
文章が上手く書けない人必見!−前編−

⑴ はじめに
みなさんは、文章を書くことは得意ですか?それとも苦手でしょうか?
圧倒的に、文章を書くことが苦手な人が多いのではないでしょうか。
私も文章が書けない、苦手な人を沢山見てきました。その中で何が大切か。どこに注意したら文章が書けるようになるのかなど、コツを書いていきます。
今回の記事は長くなると思いますので、前編、後編に分けて投稿したいと思います。
前編の今回は、
①文章を書くことは難しいのか。
②文章構成ってどうするの?
③エピソードの考え方について。
までを取り上げたいと思います。
本格的に文章を書き上げていく部分に関しては、後編で取り上げます。
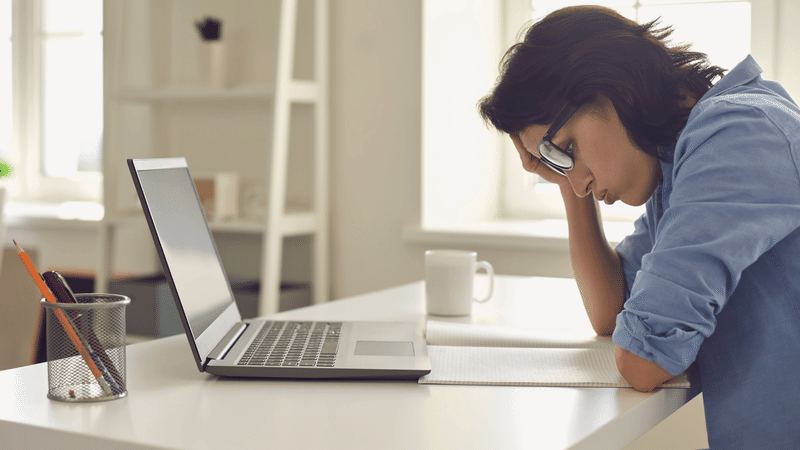
⑵ 文章を書くことは難しい?
文章を書くことが苦手な人によく言われるのが、
①書き出しがわからない。
②何を書けばいいかわからない。
③どうやって広げればいいのかがわからない。
④どうまとめると、わかりやすいのかがわからない。
⑤最終的に自分が何を伝えたいのかがわからない。
など、文章に対する「抵抗感」が伺えるお話しをよく耳にします。
意識の持ち方として「文章を書かなければならない」という気持ちが強いと書きにくいと思います。
「誰かと会話をする」ように文章も書いてみる意識をしてみるだけでも、少し心持ちが変わると思いませんか?文章であっても「誰かに何かを伝える」という部分では一緒。
書き言葉になるだけで、少し難しい何を書けばいいのかわからないと感じる人もいるみたいですが、大丈夫。心配ありませんので、書く練習をしてみましょう。

⑶ 文章構成ってどうするの?
そもそも文章構成ってどうするの?と思われる方もいらっしゃると思います。文章を考える上で、意識してもらいたいのが下記の2点。
自分がこの文章を、
①誰に向けたものとして書くのか。
②何を伝えたいのか。
という部分。
例えば、お客様に向けたものなのか、社内に向けたものなのか、社外に向けたものなのか…という部分を考えるだけでも、言葉の選び方や、言葉の硬さって変わると思いませんか?まずはこの部分を意識してみてください。
後は、自分が書く文章で「どのような内容を伝えたいのか」を考えて書くこと。自分が考えていることや、相手に理解してもらいたいことなどを整理した上で伝えたいことを考えてみてください。
また、実際に書き始めようとすると書けない…という人も多いかと思いますので、まずは箇条書きで大丈夫です。何を伝えたいのかを考えること。その後に、それを強調するエピソードであったり根拠や理論付けできる部分を増やしていくイメージです。
例えば、自己PRと職務経歴書の「活かせる経験、知識」の部分を書きたいとします。自己PRは文字通り自分をアピールする文章なので、「強み」について書いていければいいですよね。
言い換えれば、自己分析したものを使って文章を考えます。活かせる経験、知識の部分も同様です。ここで以前、記事でも書いた自己分析が大切になってきます。
自分について知らなければ、自分がどのような人か説明できないですよね。今日は筆者のストレングス・ファインダーの結果を元に考えていきましょう。
👇筆者のストレングス・ファインダーの結果はこちら👇

ストレングス・ファインダーや自己分析の結果を元に
①自分の強みを書き出す。
筆者の場合「競争性」「達成欲」「収集心」「学習欲」「社交性」です。
②「競争性」「達成欲」「収集心」「学習欲」「社交性」でのエピソードを
それぞれ考えてみる。※いくつか組み合わせても大丈夫です。
③強みとしてアピールできそうなものを考えてみる。
④何を書くか、取捨選択する。
⑤文章を書き始める。
簡単にまとめると、考え方はこのような感じです。
👇自己分析についての記事について知りたい方はこちら👇

⑷ エピソードについて考えてみる。
次に、肉付けしていくエピソードについて考えてみます。
最初は一旦、強みごとに分けて考えてみましょう。それぞれの強みに対するエピソードを箇条書きで書き出してみます。
①競争性
・自分のクラスでデッサンコンクール(学年対抗)があり、
他学年に負けないように、自分の手を3分間で軽めのデッサン。
毎朝SHR(朝の短時間ホームルーム)で取り組ませた。
・声かけの段階で、他学年に負けるな!勝つぞ!
・美術科の教員にデッサンを見せ、花丸のついたものをグラフで
視覚化し、学期ごとに競争させた。
・競争させることで、やる気だけでなく技術力もUPさせることができた。
②達成欲
・毎日スキあらばデッサンに取り組ませていたので、
デッサンコンクールでは2年連続トップ10以内8名以上だった。
・1位も2年連続で受賞。歴代最高得点97点/100点も叩き出す。
・一致団結してクラスでトップ10を取るという意味では達成。
・食堂の壁に絵を描く依頼をクラスにもらい自クラスのみで描き切る。
・毎日朝から定時まで働いてから大学院に3年通った。
・無事、教育学修士ももらう。
・教員免許も第一種免許状から専修免許に上げた。
③収集心と④学習欲
・ICT導入の時に先に導入している学校へアポを取って見学に行き
授業見学と情報交換をした。
・知らないことを知ることが好きなので、美術の勉強をするために
美術館に行くようになる。
・大学院で心理学の勉強もしつつ、大学で習っていた日本語教育に
ついても情報収集。
・公認、臨床心理士の勉強をする。
・労務の知識も身につけたいので情報収集
⑤社交性
・いろんなところに研修会に出かけたり、シンポジウムなどにも
足を運びいろんな人の話を聞く。
・いろんな立場の人とお話ししてみる。
・旅行などでいろんな場所に出かけて、その場所の人と仲良くなる。
簡単にエピソードとして書いてみると上記のような感じです。
上記で出したエピソードを元に今度は文章を組み立てていく作業。何を書くかではなくて、どんな経験をしてきたか、その上で何を伝えたいかを大切にしてみましょう。
話せるけど、文章は書けないのではなくて、どこが必要な部分がわからなくなっているだけなのかなと思います。端的に話すならどの部分が必要かを考えてみると、案外短くまとめられるはずです。
⑸ まとめ
「文章を書くこと」に対しての抵抗感というものは少なからずある人が多いと思います。しかし誰に伝えるのか、何を伝えるのかを考えた上で、書きたい情報を整理していくことができればスムーズに文章を書き上げる事も可能です。
最初から文章を書き上げなければならないと思っていると、なかなか書き上がらないことも多いと思います。
だからこそ、
①誰に何を伝えたいのかを考える。
②伝えるために、どのようなエピソードを持っているのかを考える。
③文章を書く上で、どのエピソードを使うかを取捨選択をする。
④その上で文章を書こうとするのではなく、まずは文章の流れを箇条書きに
してみる。
⑤上記を行った上で文章を書き始める。
を意識してもらえると、抵抗なく書いていくことができます。
そして最初から文章にしようと思わないこと。箇条書きで書きたいことを出してみること、またその上でストーリーを自分の中に作ってみて文章を書き始めてみるとサラッと書けるようになっていくと思います。
今回は前編ということで、文章構成をどうするかについてお伝えしてきました。次回は、後編ということで具体例をあげながらどのように文章を書いていくかお伝えできればと思います。
👇そして最後に重要なお知らせがあります!👇
この度HR Academy by TECO Desinでは、第2期が来週から開始するということで第2期お申込みで「AI×労務」をテーマにした無料講座をプレゼント🎁
また受講資料もお渡しします!是非この機会にチェックをお願いします!
👇テコデザインオンライン説明会の詳細はこちら👇
HR Academy by TECO Designでは、LINE公式のお友だちを募集しています。人事労務分野で働いてみたい方、HR Academy by TECO Designの取り組みについて気になる方は、LINE公式👇も是非ご覧ください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
