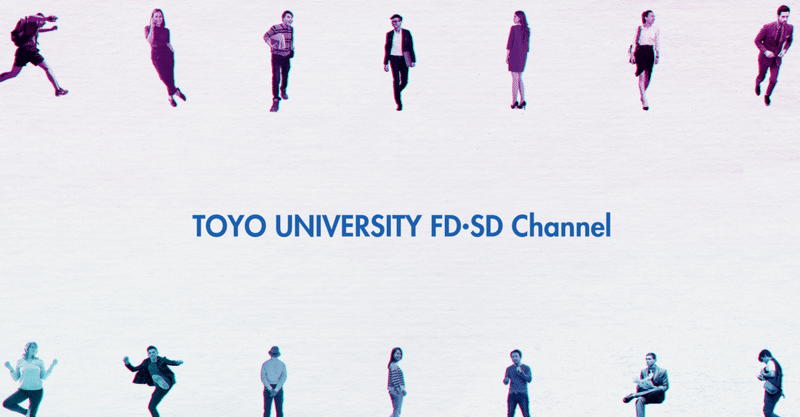
情報は抱え込むより、はき出す方が吉?東洋大学のFD・SD活動のオープンさが、とても今日的でステキだという話。
ノウハウや情報を秘匿せず、誰であれ聞かれれば、わりかしオープンに答えてくれるのは、大学業界ならではの美徳です。「ほとんど0円大学」では、年2回ほど大学の広報担当者を対象に勉強会を開催しており、そこで大学の方々に事例紹介をしてもらうのですが、みなさんけっこうぶっちゃけた話をしてくれるんですね。毎回、興味深く拝聴しながら、この美徳を実感しています。今回、見つけた東洋大学の取り組みは、聞かれたら教えるどころか、大事なノウハウを能動的に社会に発信するという、ノウハウのバーゲンセール的な取り組みです。こういうことができる視野の広さ、時代の捉え方というのは、だいぶ先進的でステキです。
取り組みのタイトルは「東洋大学FD・SDチャンネル」。FDというのはFaculty Developmentの略で、SDというのはStaff Developmentの略。前者は、授業やカリキュラムを改善、向上させる活動を指し、後者は職員の能力、資質アップのための活動を指します。これらFD・SDの情報を学内に伝えるついで(?)に、一部、学外にも公開してしまおうというのが本取り組みです。授業内容の向上や職員のレベルアップのためのノウハウというのは、大学にとって根幹に関わる情報であり、まさに虎の巻です。これを無料で、しかも内容がよくわかるよう動画にまでして世に発信する。どうした?大丈夫か?と思うほどの、大判振る舞いです。
でも、おそらくですが、こういう思い切った情報発信を他に先駆けて行うということは、長期的に見て、非常にプラスに働くように思います。理由は二つぐらいあって、一つは、SNSを中心に情報がすぐ出回ってしまう世の中なので、情報を内部に留めておくことが難しくなってきているから。もう一つは、情報を出すことによって、より多くの情報が集まる環境を生み出せる可能性があり、そういった環境のほうが、効率的・効果的にものごとを発展させることができるから。……まぁ二つ書いてみましたが、理由として大きいのは圧倒的に二つ目ですね。一つ目、どっちでもいいです。
大学業界は、業界としてオープンであり、オンライン授業への対応など、共通した悩みをたくさん持っています。また、世の中が競争より共創を好むように変わってきており、コロナはこれに拍車をかけたように感じます。
大学業界の特殊性や時代の空気を考えると、悩みの解決のためにノウハウを共有し、ともに考えられる場を、率先して情報提供することで主体的に作りだしていく、という行動は、これからの時代にすごくマッチしています。人や情報が集まる場には、さらに多くの人や情報が集まります。こういったよき循環の中枢にいられれば、いち大学だけでは決して得られない膨大な知見を手に入れられるはずです。
情報収集や情報発信を直線として捉えるのではなく、循環だと考え、それをどう育てていくかという視点で取り組んでいくと面白い、といった話を、以前、noteに書いたことがあります。このときは、広報活動を想定して書いたのですが、今回の東洋大のFD・SD活動にも当てはまるところがあるように感じました。いやでも、繰り返しになりますがFD・SD活動でこういった情報発信を行うのはそれでもすごいです。これら情報は一部ノウハウも含まれているどころか、すべてがノウハウです。だけどこれくらい思い切った投資をしてこそ、他者を巻き込むきっかけになりえるのかもしれませんね。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
